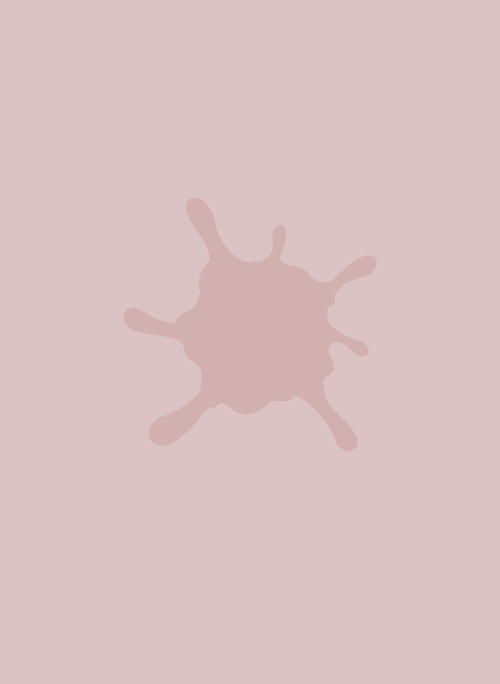「はい、敦子です」
敦子はよく通る声で電話に出た。
「敦子!? 敦子なの…!?」
通話の内容は、耳をそばだてなくても分った。
先輩の切り裂けそうな声は、この場に届いていた。
「あ、ぁ、ぁ、敦子ぉ…助けて…っ」
森先輩の声は、やっと安息を掴んだような
真理を探し当てた数学者のような声をあげた。
「大丈夫、先輩。敦子はずっと先輩の傍にいるよ」
敦子は言って息を飲んだ。
「私の声、聞こえてるんだよね? ドアを、開けて? 潤もいるの、先輩を助けに、応援に来てくれた人もいるの」
「ドア?暗くてなにも見えない、でも、あぁ、よかった、敦子の声…聞けて安心した…!」
先輩の錯乱した様子に、敦子以外、誰も動けず、口を動かすこともできない。
ただ、敦子のケータイに視線が集まるだけ。
「ねぇ敦子、充が電話に、出てくれないの……ありえないよね、こういう時は、や、やっぱり後輩しか頼れない、敦子、だけだよ」
敦子の頬を伝って涙が落ちていく。
「敦子大好きだよ……早くここから出て、県大会のミーツしなきゃね」
敦子は無言で俺のハンカチでその涙をぬぐった。
「助けて、ここは、暗くて狭くて、閉ざされてるの……ッひっ! やっ…やだ!何するの、やめて!やめてよ」
敦子との会話で落ち着いたかと思った会話が急に荒れた。
「え? 先輩? 誰かいるの?」
「また、もう、いいでしょ、誰なの、やめてよ、やめ」
ゴキン、とひどく鈍い音がした。
「え?」
敦子がビクっとしてケータイを耳から離した。
敦子はよく通る声で電話に出た。
「敦子!? 敦子なの…!?」
通話の内容は、耳をそばだてなくても分った。
先輩の切り裂けそうな声は、この場に届いていた。
「あ、ぁ、ぁ、敦子ぉ…助けて…っ」
森先輩の声は、やっと安息を掴んだような
真理を探し当てた数学者のような声をあげた。
「大丈夫、先輩。敦子はずっと先輩の傍にいるよ」
敦子は言って息を飲んだ。
「私の声、聞こえてるんだよね? ドアを、開けて? 潤もいるの、先輩を助けに、応援に来てくれた人もいるの」
「ドア?暗くてなにも見えない、でも、あぁ、よかった、敦子の声…聞けて安心した…!」
先輩の錯乱した様子に、敦子以外、誰も動けず、口を動かすこともできない。
ただ、敦子のケータイに視線が集まるだけ。
「ねぇ敦子、充が電話に、出てくれないの……ありえないよね、こういう時は、や、やっぱり後輩しか頼れない、敦子、だけだよ」
敦子の頬を伝って涙が落ちていく。
「敦子大好きだよ……早くここから出て、県大会のミーツしなきゃね」
敦子は無言で俺のハンカチでその涙をぬぐった。
「助けて、ここは、暗くて狭くて、閉ざされてるの……ッひっ! やっ…やだ!何するの、やめて!やめてよ」
敦子との会話で落ち着いたかと思った会話が急に荒れた。
「え? 先輩? 誰かいるの?」
「また、もう、いいでしょ、誰なの、やめてよ、やめ」
ゴキン、とひどく鈍い音がした。
「え?」
敦子がビクっとしてケータイを耳から離した。