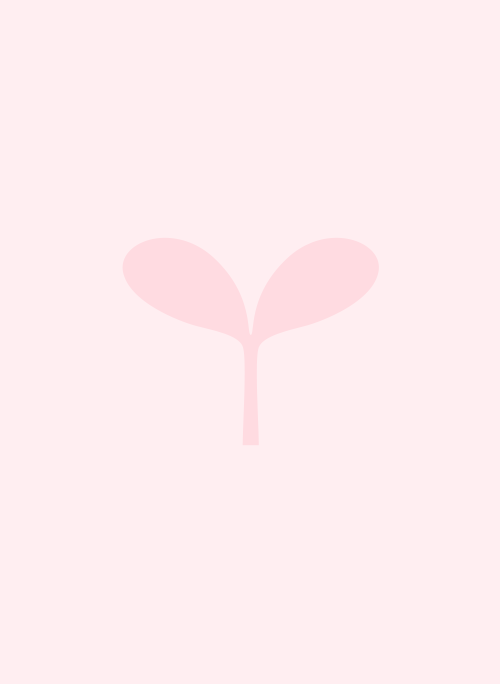実家の玄関を出てから約三時間。
僕はリュックを背負い、楽器を入れたシャイニーケースを右手に持った。空音寮のある町の駅で電車を降りた。
そして駅から十分程歩くと空音寮という看板が見えてきた。明日からまた学校が始まるのだ。
僕は一週間ぶりに寮の玄関を開けた。荷物を持ったまま食堂に向かうと、数人の寮生と寮母さんが楽しそうに談笑している。
「ただいま帰りました。寮母さん、明日からまたご飯お願いします」
「お帰りなさい。やっぱり長期休暇中はみんながいなくて寂しいわ。でもまた今日から賑やかになるわ」
寮母さんの歳は知らないけれど、おそらく兵庫のお婆ちゃんと同じくらいだろう。と、いう事は七十歳前後なのだろうか。寮母さん専用の背もたれのない丸椅子にちょこんと座り、僕たち寮生の顔を嬉しそうに眺めている。
数年前、寮母さんのご主人は亡くなったと聞いているけれど、亡くなった理由は知らない。
「じゃあ僕、明日の授業の準備があるので部屋に行きますね」
「おう、じゃあな」
「おう、また明日」
「お休みなさい。ゆっくり休んでね」
寮生たちの元気な声と寮母さんの暖かい声が笑顔と共に僕に届けられた。
「うん。また明日」
そう言って部屋の鍵をリュックから取り出した。そして食堂の南側の扉にその鍵を挿し込み九十度右へと回す。南棟へ繋がる廊下を歩き二階にある自分の部屋へと歩を進めていった。
この寮は食堂と寮母さんの部屋が隣り合わせで一つの建物になっている。そして食堂の南側と北側に二階建ての寮が一つずつ建てられているのだ。寮母さんの話によると、三年程前までは北棟が男子寮で南棟が女子寮だったらしい。その為、食堂から各棟へ繋がる扉にも鍵付きの扉が付いているのだろう。
僕の住んでいる南棟は女子寮だったのだ。なぜこの寮が二棟とも男子寮になったのか。その理由など考えた事もなかったけれど、今、ふと気になった。
僕は部屋に入るなり、大の字でベッドへ寝転んだ。このベッド、数年前までは綺麗な先輩が寝ていたのだろうか。そんな不謹慎な事を考えていると、本棚の日記が目に入った。
「日記付き……か」
声にならない声を漏らす。
日記付きとアピールし、寮生を募集した真意はなんなのだろう。僕は本棚に近づき日記を手に取る。そして再びページをめくる。やはりそこには何も書かれていない。
日記を抱え首を傾げながらベッドに横たわる。しばらく日記の表紙を眺めた後立ち上がり、カーテンを閉め灯りを消した。そして日記を抱えたままで眠りに就いた。
* * *
「こんばんは。どこに行ってたの?」
「どこって? さっきまで寮の食堂にいたよ」
「そうじゃなくて、一週間もどこに行ってたの? って訊いてるんだよ」
「え? あ、ゴールデンウィーク中の事? それなら家族で山中湖畔のオートキャンプ場に……。ねえ? 君、名前は?」
少女は笑顔のまま、すうっと姿を消していった。
* * *
「ん……? まっぶしっ……!」
昨日寝る前、閉めたはずのカーテンの隙間から柔らかな陽射しが僕の瞼を刺激している。枕元のスマホに手を伸ばし時間を確認する。
『9:10』
あれ? 今日は一限から授業のはずである。え?
僕は目をしっかと開き、再びスマホの時間を確認した。
『9:11』
「わっ! 寝坊した!」
寮から大学まではどんなに急いでもドアツードアで三十分はかかる。今から行っても出席扱いにはならないのだ。諦めの早さには自信のある僕はすんなり諦めた。二限からにしよう。
こんな性格だから栞里ちゃんにも手が届かなかったのだろう。
僕はヨタヨタしながら食堂へ向かった。寮の朝食は四枚切りの分厚いトーストに珈琲や紅茶。グリーンサラダにヨーグルト。そして何故か烏龍茶が常に用意してある。ヨーグルト以外はおかわりし放題である。
僕は分厚いトーストにバターを塗る。そしてトーストの角を口元に運んだ。
「ん?」
夢……見たよな。うん、確かに見た。少女と何かの話をした気がする。また逢えたんだ。
僕は食べかけたトーストをお皿に戻し、慌てて席を立つ。新しい珈琲を入れたポットを持つ寮母さんに、「すぐ戻ります」と伝え部屋へと戻っていった。
あの少女は僕に何かを伝えようとしているのだろうか。そうじゃなければこれほど頻繁に同じ少女の夢をみるはずがない。
たかが夢の中の話。けれど……。
再び少女に逢えた喜びもある。けれど、少女が僕に逢いにくる真意はなんなのだろう。そうだ、少女との会話を思い出さなければ。どんな話をしていたのだろう。思い出せ。
僕はベッドに座りながら考えた。少女の顔はなんとなく思い出す事ができた。花柄のワンピースを身に纏い、長い黒髪がさらりと風になびいていた。小さな顔に大きな瞳。
何を話した? 少女はなんと言った?
頭を掻きむしり必死に考えた。しかし、答えは見つからなかった。
僕は天井を見るともなく見る。
「くそっ!」
諦めの早い僕は肩を落としながら食堂へと戻っていった。
朝食を終えトレイを「返却口」と書かれた場所へ運ぶとキッチンの奥から寮母さんがこちらを見ていた。
「いっぱい食べた? ゴールデンウィークはどこか旅行でも行ったのかい?」
「ご馳走さまでした。家族で山中湖畔でキャンプしてたんです。楽器も持っていって母とサックス二重奏してたら沢山の人が集まってきていっぱい拍手してもらいました」
「そうだったのかい。それは楽しかった……」
僕は寮母さんの話が終わるのを遮り大きな声を出す。
「それだ! 寮母さん、それだ!」
「どれ?」
「それです!」
「だからどれ?」
寮母さんはぼかんと口を開き、何かを探すかのようにきょろきょろと辺りを見渡した。
僕は部屋へ戻るとメモできる紙を探した。けれど、適当な紙が見つからす学校用の鞄を開きルーズリーフを取り出した。
音楽で使う五線譜の付いたルーズリーフである。
ペンケースから取り出した2Bの鉛筆でメモをとる。
――なにをしてたの?
――山中湖畔でキャンプをしてた。
確かこんな会話をしたはずである。このメモがこれから先、役に立つのかどうかは分からないけれど、とにかく書いてみた。そうだ、明日の朝からこのルーズリーフと鉛筆を枕元に置き、起きたらすぐにメモをとる事にしよう。
忘れてしまう前に……。
僕は寮を出て大学へと向かっていった。僅かな希望を胸に抱きながら……。
僕はリュックを背負い、楽器を入れたシャイニーケースを右手に持った。空音寮のある町の駅で電車を降りた。
そして駅から十分程歩くと空音寮という看板が見えてきた。明日からまた学校が始まるのだ。
僕は一週間ぶりに寮の玄関を開けた。荷物を持ったまま食堂に向かうと、数人の寮生と寮母さんが楽しそうに談笑している。
「ただいま帰りました。寮母さん、明日からまたご飯お願いします」
「お帰りなさい。やっぱり長期休暇中はみんながいなくて寂しいわ。でもまた今日から賑やかになるわ」
寮母さんの歳は知らないけれど、おそらく兵庫のお婆ちゃんと同じくらいだろう。と、いう事は七十歳前後なのだろうか。寮母さん専用の背もたれのない丸椅子にちょこんと座り、僕たち寮生の顔を嬉しそうに眺めている。
数年前、寮母さんのご主人は亡くなったと聞いているけれど、亡くなった理由は知らない。
「じゃあ僕、明日の授業の準備があるので部屋に行きますね」
「おう、じゃあな」
「おう、また明日」
「お休みなさい。ゆっくり休んでね」
寮生たちの元気な声と寮母さんの暖かい声が笑顔と共に僕に届けられた。
「うん。また明日」
そう言って部屋の鍵をリュックから取り出した。そして食堂の南側の扉にその鍵を挿し込み九十度右へと回す。南棟へ繋がる廊下を歩き二階にある自分の部屋へと歩を進めていった。
この寮は食堂と寮母さんの部屋が隣り合わせで一つの建物になっている。そして食堂の南側と北側に二階建ての寮が一つずつ建てられているのだ。寮母さんの話によると、三年程前までは北棟が男子寮で南棟が女子寮だったらしい。その為、食堂から各棟へ繋がる扉にも鍵付きの扉が付いているのだろう。
僕の住んでいる南棟は女子寮だったのだ。なぜこの寮が二棟とも男子寮になったのか。その理由など考えた事もなかったけれど、今、ふと気になった。
僕は部屋に入るなり、大の字でベッドへ寝転んだ。このベッド、数年前までは綺麗な先輩が寝ていたのだろうか。そんな不謹慎な事を考えていると、本棚の日記が目に入った。
「日記付き……か」
声にならない声を漏らす。
日記付きとアピールし、寮生を募集した真意はなんなのだろう。僕は本棚に近づき日記を手に取る。そして再びページをめくる。やはりそこには何も書かれていない。
日記を抱え首を傾げながらベッドに横たわる。しばらく日記の表紙を眺めた後立ち上がり、カーテンを閉め灯りを消した。そして日記を抱えたままで眠りに就いた。
* * *
「こんばんは。どこに行ってたの?」
「どこって? さっきまで寮の食堂にいたよ」
「そうじゃなくて、一週間もどこに行ってたの? って訊いてるんだよ」
「え? あ、ゴールデンウィーク中の事? それなら家族で山中湖畔のオートキャンプ場に……。ねえ? 君、名前は?」
少女は笑顔のまま、すうっと姿を消していった。
* * *
「ん……? まっぶしっ……!」
昨日寝る前、閉めたはずのカーテンの隙間から柔らかな陽射しが僕の瞼を刺激している。枕元のスマホに手を伸ばし時間を確認する。
『9:10』
あれ? 今日は一限から授業のはずである。え?
僕は目をしっかと開き、再びスマホの時間を確認した。
『9:11』
「わっ! 寝坊した!」
寮から大学まではどんなに急いでもドアツードアで三十分はかかる。今から行っても出席扱いにはならないのだ。諦めの早さには自信のある僕はすんなり諦めた。二限からにしよう。
こんな性格だから栞里ちゃんにも手が届かなかったのだろう。
僕はヨタヨタしながら食堂へ向かった。寮の朝食は四枚切りの分厚いトーストに珈琲や紅茶。グリーンサラダにヨーグルト。そして何故か烏龍茶が常に用意してある。ヨーグルト以外はおかわりし放題である。
僕は分厚いトーストにバターを塗る。そしてトーストの角を口元に運んだ。
「ん?」
夢……見たよな。うん、確かに見た。少女と何かの話をした気がする。また逢えたんだ。
僕は食べかけたトーストをお皿に戻し、慌てて席を立つ。新しい珈琲を入れたポットを持つ寮母さんに、「すぐ戻ります」と伝え部屋へと戻っていった。
あの少女は僕に何かを伝えようとしているのだろうか。そうじゃなければこれほど頻繁に同じ少女の夢をみるはずがない。
たかが夢の中の話。けれど……。
再び少女に逢えた喜びもある。けれど、少女が僕に逢いにくる真意はなんなのだろう。そうだ、少女との会話を思い出さなければ。どんな話をしていたのだろう。思い出せ。
僕はベッドに座りながら考えた。少女の顔はなんとなく思い出す事ができた。花柄のワンピースを身に纏い、長い黒髪がさらりと風になびいていた。小さな顔に大きな瞳。
何を話した? 少女はなんと言った?
頭を掻きむしり必死に考えた。しかし、答えは見つからなかった。
僕は天井を見るともなく見る。
「くそっ!」
諦めの早い僕は肩を落としながら食堂へと戻っていった。
朝食を終えトレイを「返却口」と書かれた場所へ運ぶとキッチンの奥から寮母さんがこちらを見ていた。
「いっぱい食べた? ゴールデンウィークはどこか旅行でも行ったのかい?」
「ご馳走さまでした。家族で山中湖畔でキャンプしてたんです。楽器も持っていって母とサックス二重奏してたら沢山の人が集まってきていっぱい拍手してもらいました」
「そうだったのかい。それは楽しかった……」
僕は寮母さんの話が終わるのを遮り大きな声を出す。
「それだ! 寮母さん、それだ!」
「どれ?」
「それです!」
「だからどれ?」
寮母さんはぼかんと口を開き、何かを探すかのようにきょろきょろと辺りを見渡した。
僕は部屋へ戻るとメモできる紙を探した。けれど、適当な紙が見つからす学校用の鞄を開きルーズリーフを取り出した。
音楽で使う五線譜の付いたルーズリーフである。
ペンケースから取り出した2Bの鉛筆でメモをとる。
――なにをしてたの?
――山中湖畔でキャンプをしてた。
確かこんな会話をしたはずである。このメモがこれから先、役に立つのかどうかは分からないけれど、とにかく書いてみた。そうだ、明日の朝からこのルーズリーフと鉛筆を枕元に置き、起きたらすぐにメモをとる事にしよう。
忘れてしまう前に……。
僕は寮を出て大学へと向かっていった。僅かな希望を胸に抱きながら……。