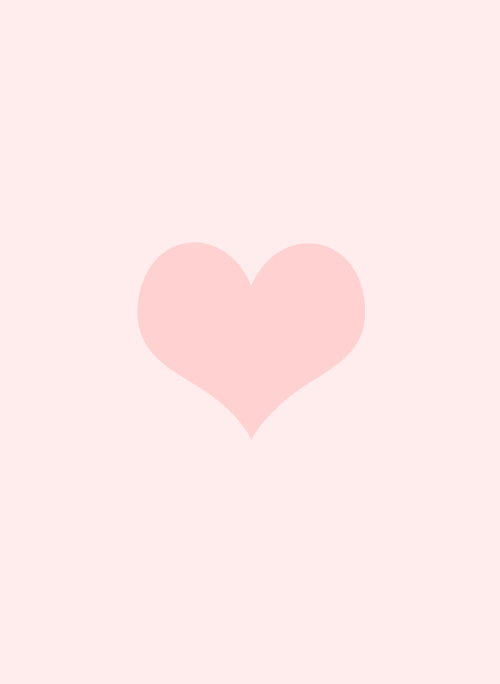初日を迎える時の気持ちは、何時も複雑な感情が入り混じったものになる。
前日迄の興行が特に印象深いものであったりすれば尚更の事だ。
通り過ぎた十日間の熱が、まだ自分の身体の中で余熱として燻っているところへ、新たな熱が加わる。
冷めて欲しく無い……
そんな気持ちと、新たな出会いへの期待……
余熱を消し去ってくれるには、新たな出会いが、より熱を帯びたものでなければならない。
余熱の燻りが余りにも鮮烈過ぎたりすると、それを消し去ってくれるには余程の舞台に出会わなければ残り続けてしまうものだ。
姿月(しづき)との一年振りの仕事は、余りにも鮮烈過ぎた。
そのせいだったのか、僕は初日の一回目の照明を終えると、無意識のうちに彼女へ電話を掛けていた。
今日から和歌山の劇場の筈だ。
三回……
五回……
七回……
十回以上鳴らしたかも知れない。
諦めて切ろうとした時、彼女とやっと繋がった。
「お疲れ様です」
意味も無く電話を掛けてしまった事を少しばかり後悔しながら、彼女の天真爛漫な何時もの声を待っていた。
ほんの少し、本当に僅かばかりの沈黙を感じた。
「そっちの初日はどうですか?」
もとからこれといった用事があって掛けた電話では無かったから、彼女の沈黙に慌ててそんな事を聞いた。
「……アタシ、飛んだの」
返って来た返事は、意外な言葉であった。
そして、その後に続いたのは彼女の涙混じりの声だった。
前日迄の興行が特に印象深いものであったりすれば尚更の事だ。
通り過ぎた十日間の熱が、まだ自分の身体の中で余熱として燻っているところへ、新たな熱が加わる。
冷めて欲しく無い……
そんな気持ちと、新たな出会いへの期待……
余熱を消し去ってくれるには、新たな出会いが、より熱を帯びたものでなければならない。
余熱の燻りが余りにも鮮烈過ぎたりすると、それを消し去ってくれるには余程の舞台に出会わなければ残り続けてしまうものだ。
姿月(しづき)との一年振りの仕事は、余りにも鮮烈過ぎた。
そのせいだったのか、僕は初日の一回目の照明を終えると、無意識のうちに彼女へ電話を掛けていた。
今日から和歌山の劇場の筈だ。
三回……
五回……
七回……
十回以上鳴らしたかも知れない。
諦めて切ろうとした時、彼女とやっと繋がった。
「お疲れ様です」
意味も無く電話を掛けてしまった事を少しばかり後悔しながら、彼女の天真爛漫な何時もの声を待っていた。
ほんの少し、本当に僅かばかりの沈黙を感じた。
「そっちの初日はどうですか?」
もとからこれといった用事があって掛けた電話では無かったから、彼女の沈黙に慌ててそんな事を聞いた。
「……アタシ、飛んだの」
返って来た返事は、意外な言葉であった。
そして、その後に続いたのは彼女の涙混じりの声だった。