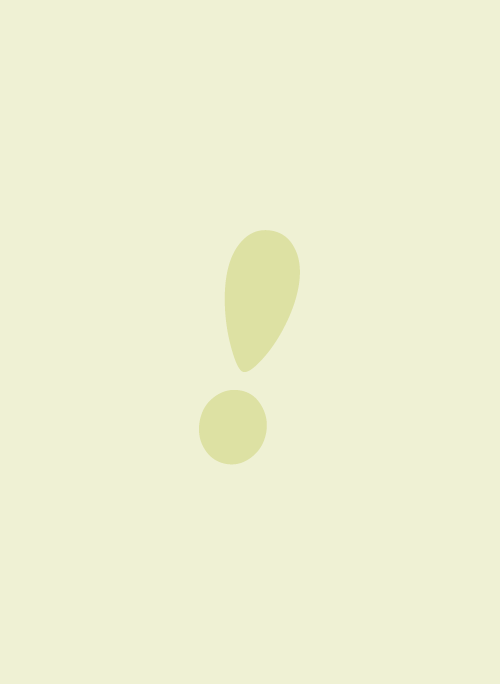私の名は、ナタリー・マルグリット・ロムニエル。
ごく普通の17歳だ。
この学院に入学して、2年ほど。
もう2年生になった。
今までは、平凡で幸せな日々だったのに・・・
ごく普通の17歳だ。
この学院に入学して、2年ほど。
もう2年生になった。
今までは、平凡で幸せな日々だったのに・・・
「アレン・・・」
隣を歩く恋人、アレン・ヘンリー・ジョーンズに呼びかける。
「うん?」
「・・・なんでもない」
「何だよ・・・」
「ううん、すごい普通で幸せだな、って」
学校から寮までの帰り道を一緒に歩くのが、付き合い始めてから、ずっと変わらない私たちの習慣。
隣を歩く恋人、アレン・ヘンリー・ジョーンズに呼びかける。
「うん?」
「・・・なんでもない」
「何だよ・・・」
「ううん、すごい普通で幸せだな、って」
学校から寮までの帰り道を一緒に歩くのが、付き合い始めてから、ずっと変わらない私たちの習慣。
そして・・・これも。
女子寮まで送ってもらい、人影のない場所で口づけを交わすのも、私たちの習慣だ。
照れたみたいな、優しい口づけ。
変わらない私たちの習慣。
「ん・・・っ」
「・・・おやすみなさい」
「あぁ。じゃあな」
そうやって、言葉を交わすことも。
こうやってごく自然に出た言葉さえ、叶うと信じられない。
アレンも、私も・・・
いや、この学院の生徒みんなが・・・
女子寮まで送ってもらい、人影のない場所で口づけを交わすのも、私たちの習慣だ。
照れたみたいな、優しい口づけ。
変わらない私たちの習慣。
「ん・・・っ」
「・・・おやすみなさい」
「あぁ。じゃあな」
そうやって、言葉を交わすことも。
こうやってごく自然に出た言葉さえ、叶うと信じられない。
アレンも、私も・・・
いや、この学院の生徒みんなが・・・
「お帰りー」
部屋に入ると、一足先に帰ってきていたルームメイトが勉強をしていた。
「ただいま。パトリシア、早かったのね」
「うん。ナタリーは、今日もアレンと?」
「もー、毎日同じコト訊かないでよぉー」
彼女は、パトリシア・フローラ・バークス。
栗色の髪に、水色の目がかわいい美少女だ。
部屋に入ると、一足先に帰ってきていたルームメイトが勉強をしていた。
「ただいま。パトリシア、早かったのね」
「うん。ナタリーは、今日もアレンと?」
「もー、毎日同じコト訊かないでよぉー」
彼女は、パトリシア・フローラ・バークス。
栗色の髪に、水色の目がかわいい美少女だ。
「パトリシアも、ロルフが送ってくれたんでしょ?」
「もちろんよ」
パトリシアも恋人がいる。
ロルフ・ハインリヒ・ウィンスブルッグだ。
バスケが得意で、クラブではエースだとか。
アレンも、テニス部で一番の強さ。
誇らしい恋人だ。
「もちろんよ」
パトリシアも恋人がいる。
ロルフ・ハインリヒ・ウィンスブルッグだ。
バスケが得意で、クラブではエースだとか。
アレンも、テニス部で一番の強さ。
誇らしい恋人だ。
私とパトリシアは、同じ新聞部。
それに、アレンとロルフもルームメイトだから、よく一緒に出かけたりする。
去年は、それぞれ、クラスメイトでもあった。
アレンとロルフは、先生たちの手を焼かせるコンビ。
まぁ、ロルフがやらかして、アレンが巻き込まれるパターンが多かったみたいだけど。
私たち4人は、とても仲良しだ。
それに、アレンとロルフもルームメイトだから、よく一緒に出かけたりする。
去年は、それぞれ、クラスメイトでもあった。
アレンとロルフは、先生たちの手を焼かせるコンビ。
まぁ、ロルフがやらかして、アレンが巻き込まれるパターンが多かったみたいだけど。
私たち4人は、とても仲良しだ。
でも・・・迫り来る戦争の影におびえていた。
アレンとパトリシアの故郷が、私たちの国と戦争を始めようとしていたからだ。
また、ロルフのふるさとも、中立を保とうとしていながら、対立を深めていった。
『明日』が叶う保証はどこにもない。
『明日』を生きている保証はどこにもない。
今夜にも襲撃されるかもしれない国境近辺には、いつだってその不安がある。
アレンとパトリシアの故郷が、私たちの国と戦争を始めようとしていたからだ。
また、ロルフのふるさとも、中立を保とうとしていながら、対立を深めていった。
『明日』が叶う保証はどこにもない。
『明日』を生きている保証はどこにもない。
今夜にも襲撃されるかもしれない国境近辺には、いつだってその不安がある。
パトリシアの机の上に、新聞が置いてあった。
【緊迫する政情。戦争間近か】
眉をひそめたくなるような文字。
「これからどうなるんだろうね・・・」
「分かんないよ・・・」
私は、紅茶を飲みながら、うつむく。
パトリシアとおそろいのティーカップは、アレンとロルフが見立ててくれた。
進級祝いにと渡されたプレゼントだ。
かわいい花柄で、私もパトリシアも愛用している。
カップのぬくもりを手に包みながら、ため息をついた。
戦いたくない。
死にたくない。
何より・・・みんなと離れたくない。
そう思っていたのに・・・
【緊迫する政情。戦争間近か】
眉をひそめたくなるような文字。
「これからどうなるんだろうね・・・」
「分かんないよ・・・」
私は、紅茶を飲みながら、うつむく。
パトリシアとおそろいのティーカップは、アレンとロルフが見立ててくれた。
進級祝いにと渡されたプレゼントだ。
かわいい花柄で、私もパトリシアも愛用している。
カップのぬくもりを手に包みながら、ため息をついた。
戦いたくない。
死にたくない。
何より・・・みんなと離れたくない。
そう思っていたのに・・・
「遅かったな、アレン」
「あぁ」
自室に戻ると、ルームメイトのロルフが煙草を弄んでいた。
「おい、煙草はオーギュスト先生に止められてるだろ」
「吸わないさ。いつまでもつか分からねえけどな」
「ったく・・・」
去年のクラスメイトであるロルフは、俺とはまた別の国からこの学校へやってきた留学生だ。
ルームメイトの発表がされたときは、正直、困惑した。
ロルフの少しばかり軽薄な空気感は、俺にはないものだったから。
実際のところ、第一印象だけでなく、ロルフは軽い奴だった。
煙草も、酒も、女遊びも、学年内で有名なレベル。
真面目なだけが取り柄の俺は、少々不安だった。
でも、今なら分かる。
去年の担任のキャロライン・ロイドバーグ先生は、正しい決断をした。
俺は、ロルフぐらい軽やかな相手がルームメイトでなかったら、会話もろくに出来なかっただろう。
同室の俺が過ごしやすい程度に空気を崩し、同室の俺が困らない程度に遊ぶ。
ロルフは、そういう芸当がいとも簡単にできる奴だ。
感謝している。
「そーいやさ」
「ん?」
「まーた、ナタリーとは進展なしか?」
「・・・そういうお前は、パトリシアと手も繋いでないだろ」
からかってくるロルフに言い返す。
平和で、穏やかな日常。
・・・ちゃんとキスはしてるからな。
心の中で、反論を付け加える。
「あぁ」
自室に戻ると、ルームメイトのロルフが煙草を弄んでいた。
「おい、煙草はオーギュスト先生に止められてるだろ」
「吸わないさ。いつまでもつか分からねえけどな」
「ったく・・・」
去年のクラスメイトであるロルフは、俺とはまた別の国からこの学校へやってきた留学生だ。
ルームメイトの発表がされたときは、正直、困惑した。
ロルフの少しばかり軽薄な空気感は、俺にはないものだったから。
実際のところ、第一印象だけでなく、ロルフは軽い奴だった。
煙草も、酒も、女遊びも、学年内で有名なレベル。
真面目なだけが取り柄の俺は、少々不安だった。
でも、今なら分かる。
去年の担任のキャロライン・ロイドバーグ先生は、正しい決断をした。
俺は、ロルフぐらい軽やかな相手がルームメイトでなかったら、会話もろくに出来なかっただろう。
同室の俺が過ごしやすい程度に空気を崩し、同室の俺が困らない程度に遊ぶ。
ロルフは、そういう芸当がいとも簡単にできる奴だ。
感謝している。
「そーいやさ」
「ん?」
「まーた、ナタリーとは進展なしか?」
「・・・そういうお前は、パトリシアと手も繋いでないだろ」
からかってくるロルフに言い返す。
平和で、穏やかな日常。
・・・ちゃんとキスはしてるからな。
心の中で、反論を付け加える。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…