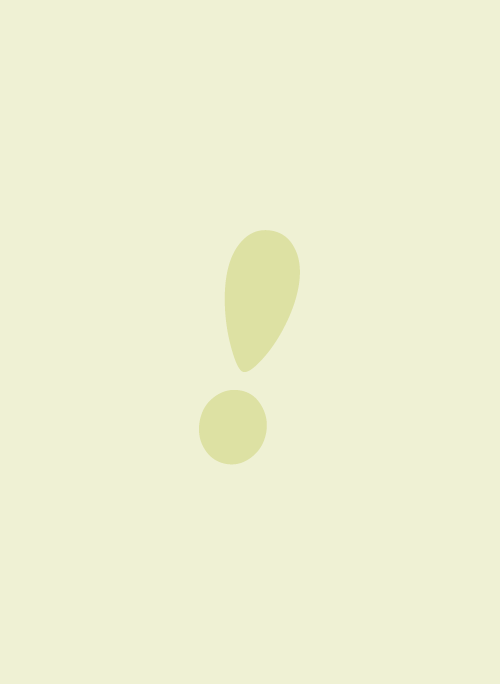その朝は、らしくないくらい早めに登校し、クラスメイトのエレノアとイチャついていた。
華やかな女子生徒を象徴するような太めのリボンに指を絡ませ、距離感をゼロにしていく。
俺が指を動かすたびに、エレノアがくすぐったげに笑う。
赤みがかった金色の髪が揺れて、可愛らしい。
「やぁだ、ロルフったら」
「いいだろ?」
「もぉ、パトリシアが可哀想よ」
「エレノアにだって、マイケルがいるだろ?」
俺と同じバスケ部のマイケルと交際中のエレノアだが、同郷ということもあってそれなりに親しくしている。
エレノアの白いあごに手を触れ、単なる級友では許されないであろう口づけを交わそうとしたとき・・・
激しい衝撃音で、身体がふらついた。
甘ったれた空気が吹っ飛ぶ。
「やだ、何・・・!?」
しがみついてくるエレノアを支えながら、校舎の窓から外を見る。
「・・・何だ、あれ」
華やかな女子生徒を象徴するような太めのリボンに指を絡ませ、距離感をゼロにしていく。
俺が指を動かすたびに、エレノアがくすぐったげに笑う。
赤みがかった金色の髪が揺れて、可愛らしい。
「やぁだ、ロルフったら」
「いいだろ?」
「もぉ、パトリシアが可哀想よ」
「エレノアにだって、マイケルがいるだろ?」
俺と同じバスケ部のマイケルと交際中のエレノアだが、同郷ということもあってそれなりに親しくしている。
エレノアの白いあごに手を触れ、単なる級友では許されないであろう口づけを交わそうとしたとき・・・
激しい衝撃音で、身体がふらついた。
甘ったれた空気が吹っ飛ぶ。
「やだ、何・・・!?」
しがみついてくるエレノアを支えながら、校舎の窓から外を見る。
「・・・何だ、あれ」
学生寮から火が上がっている。
そして、北の国境地帯には、アレンの故郷の国旗が掲げられていた。
「戦争・・ってことか・・・?」
国旗の下に備えられた大砲や兵士たちを見る限り、それ以外の選択はないだろう。
そして、北の国境地帯には、アレンの故郷の国旗が掲げられていた。
「戦争・・ってことか・・・?」
国旗の下に備えられた大砲や兵士たちを見る限り、それ以外の選択はないだろう。
恐れていた事態がついに訪れた。
おそらく・・・アレンやパトリシアの国、ナタリーの国、そして俺の故郷の3カ国が戦うことになる。
それは・・・最も悲しむべき状況。
おそらく・・・アレンやパトリシアの国、ナタリーの国、そして俺の故郷の3カ国が戦うことになる。
それは・・・最も悲しむべき状況。
「悪い、エレノア、先に逃げててくれ」
「え、でも、逃げるって・・・」
「たぶん、校舎の中でいい」
さっきから怒鳴ってる先生たちの声がそう言ってる。
「俺、行かねぇと」
「え、でも、逃げるって・・・」
「たぶん、校舎の中でいい」
さっきから怒鳴ってる先生たちの声がそう言ってる。
「俺、行かねぇと」
行かなければいけない場所がある。
守らなければいけない人がいる。
きっとその人は・・・今、登校している最中で。
いつも通り、友達と笑いあっているはずで。
毎日のように、軽やかに微笑んでいるはずで。
守らなければいけない人がいる。
きっとその人は・・・今、登校している最中で。
いつも通り、友達と笑いあっているはずで。
毎日のように、軽やかに微笑んでいるはずで。
「分かった。気をつけてね」
エレノアがうなずく。
俺は、階段を駆け下りた。
エレノアと逢い引きしていた2階の廊下から、全速力で校庭まで走り抜ける。
きっと・・・いるはずなんだ・・・
エレノアがうなずく。
俺は、階段を駆け下りた。
エレノアと逢い引きしていた2階の廊下から、全速力で校庭まで走り抜ける。
きっと・・・いるはずなんだ・・・
神様・・・
どうか・・・
彼女が無事でありますように・・・
「ロルフ!」
名前を呼ばれて、そちらを見ると、ルームメイトが走っていた。
そりゃもう、死に物狂いの形相で。
なりふり構ってない。
アレンは、とても走るのが速い。
その達者な足で、体育大会ではいつも花形だ。
バスケで鍛えているはずの俺でも、ついていくのが精いっぱい。
だが、今は、髪の乱れとか、そういうことは頭から消して、ただひたすら走る。
アレンもきっと、目指す方向は同じだろう。
「まだ・・・学校来てないよな?」
誰のことかは、言わずもがなだ。
「そのはずだ」
「まずいことになってなきゃいいんだが」
唇をかむアレンに、自分が重なる。
同じ気持ちだ。
俺が抱えてる不安と同じ気持ちだ。
名前を呼ばれて、そちらを見ると、ルームメイトが走っていた。
そりゃもう、死に物狂いの形相で。
なりふり構ってない。
アレンは、とても走るのが速い。
その達者な足で、体育大会ではいつも花形だ。
バスケで鍛えているはずの俺でも、ついていくのが精いっぱい。
だが、今は、髪の乱れとか、そういうことは頭から消して、ただひたすら走る。
アレンもきっと、目指す方向は同じだろう。
「まだ・・・学校来てないよな?」
誰のことかは、言わずもがなだ。
「そのはずだ」
「まずいことになってなきゃいいんだが」
唇をかむアレンに、自分が重なる。
同じ気持ちだ。
俺が抱えてる不安と同じ気持ちだ。
「あれ・・・ん、アレン、・・・アレンッ!」
甘やかな声が響いた。
わずかにかすれ、震えた声。
その声は、校舎の入り口からだった。
ほっと安堵する。
逃げていたのだ。
助かっていたのだ。
「なた・・・ナタリー・・・!」
アレンも、声を震わせる。
クールを気取って、いつも感情を気取らせないアレンが、ナタリーのこととなると、ひどく感情的になる。
あの小柄な少女は、それほどの大きな存在なのだ。
甘やかな声が響いた。
わずかにかすれ、震えた声。
その声は、校舎の入り口からだった。
ほっと安堵する。
逃げていたのだ。
助かっていたのだ。
「なた・・・ナタリー・・・!」
アレンも、声を震わせる。
クールを気取って、いつも感情を気取らせないアレンが、ナタリーのこととなると、ひどく感情的になる。
あの小柄な少女は、それほどの大きな存在なのだ。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…