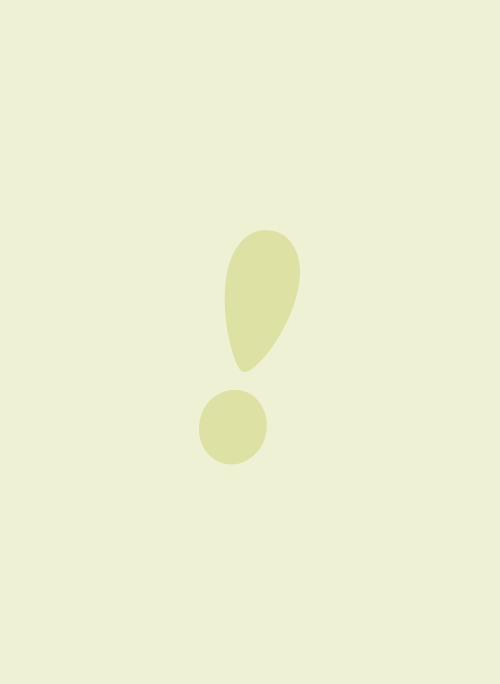ひどく静かに時間は過ぎていった。
まるで、痛みなんて感じていないかのようで、自分がひどく恨めしかった。
愛する人がこの世を去っても、日は昇る。
身体は空腹を訴える。
そういう自分を嫌いだと思った。
援軍は、いたって温厚に俺たち留学生を扱った。
3カ国間で取り決められたしばらくの休戦の間に、荷物をまとめるように指示し、俺たちはそれに従った。
加えて、彼らは、死んだ生徒の家族たちに手紙を書くよう、俺たちに言った。
死の通達は出来るが、最後の様子や遺した言葉を伝えることは出来ないから、と。
それぞれの墓標と、住所とを照らし合わせながら、俺たちは遺族に手紙を書いた。
まるで、痛みなんて感じていないかのようで、自分がひどく恨めしかった。
愛する人がこの世を去っても、日は昇る。
身体は空腹を訴える。
そういう自分を嫌いだと思った。
援軍は、いたって温厚に俺たち留学生を扱った。
3カ国間で取り決められたしばらくの休戦の間に、荷物をまとめるように指示し、俺たちはそれに従った。
加えて、彼らは、死んだ生徒の家族たちに手紙を書くよう、俺たちに言った。
死の通達は出来るが、最後の様子や遺した言葉を伝えることは出来ないから、と。
それぞれの墓標と、住所とを照らし合わせながら、俺たちは遺族に手紙を書いた。
俺も、一人ずつ手紙を書いた。
テニス部の仲間や、クラスメイト。
周りで命を落とした多くの仲間のために。
そんな中で、戦死したオリバーの家族へ手紙を書くことになった。
オリバーは、同郷の仲間で、ナタリーと2年間同じクラスでもあった。
美術部の数少ない男子生徒だったオリバーは、数学が得意で、いつも教科担任のヴェラ・ストラウド先生に褒められていたらしい。
他の教科でも成績優秀で、ナタリーと仲がよかった。
数学が分からないときは、オリバーに教えてもらうのよ、と笑っていたナタリーを思い出した。
天国で、一緒に勉強でもしているのかもしれない。
少し・・・妬ける。
テニス部の仲間や、クラスメイト。
周りで命を落とした多くの仲間のために。
そんな中で、戦死したオリバーの家族へ手紙を書くことになった。
オリバーは、同郷の仲間で、ナタリーと2年間同じクラスでもあった。
美術部の数少ない男子生徒だったオリバーは、数学が得意で、いつも教科担任のヴェラ・ストラウド先生に褒められていたらしい。
他の教科でも成績優秀で、ナタリーと仲がよかった。
数学が分からないときは、オリバーに教えてもらうのよ、と笑っていたナタリーを思い出した。
天国で、一緒に勉強でもしているのかもしれない。
少し・・・妬ける。
ペンを取る。
簡潔な挨拶。
そして、自分の名前。
そして・・・・・・
『今回は、ひどく残念な報せをしなくてはなりません』
書きたくない。
報せたくない。
嘘だったらどんなにいいだろう・・・
『オリバーは、このたびの戦闘で命を落としました』
簡潔な挨拶。
そして、自分の名前。
そして・・・・・・
『今回は、ひどく残念な報せをしなくてはなりません』
書きたくない。
報せたくない。
嘘だったらどんなにいいだろう・・・
『オリバーは、このたびの戦闘で命を落としました』
『オリバーは、勇敢に戦い、敵を恐れずに・・・』
書きかけ、便箋を破った。
敵って何だ?
同じ国の兵は、敵だったのか?
本当に?
・・・本当に?
書きかけ、便箋を破った。
敵って何だ?
同じ国の兵は、敵だったのか?
本当に?
・・・本当に?
「アレン?」
「・・・あぁ、パトリシアか」
声をかけてきたのはパトリシアだったが、その後ろには、ロルフやダニエル、アグネスたちがいた。
彼女の姿だけが・・・ない。
「今から寮が開放されるそうよ」
「寮が?」
「戦闘が休止したから。荷物もまとめなきゃいけないし」
「・・・そうだな。ちょっと待っててくれ。俺も行く」
「えぇ」
便箋は、ポケットにしまった。
「・・・あぁ、パトリシアか」
声をかけてきたのはパトリシアだったが、その後ろには、ロルフやダニエル、アグネスたちがいた。
彼女の姿だけが・・・ない。
「今から寮が開放されるそうよ」
「寮が?」
「戦闘が休止したから。荷物もまとめなきゃいけないし」
「・・・そうだな。ちょっと待っててくれ。俺も行く」
「えぇ」
便箋は、ポケットにしまった。
校門を出る。
パトリシアが、眩しい日差しに目を細めた。
しばらくぶりの外。
しばらくぶりの自分の部屋。
銃の跡が残り、血痕もあるが、それ以外は、平穏を感じさせるままだ。
いつも通りの部屋。
ロルフの机と背中合わせになるように置かれた机。
その横の本棚。
読書は嫌いじゃないから、それなりの量の本が置いてある。
ロルフは、本じゃなくて煙草や酒を隠すように使ってたけど。
教科書。
ノート。
制服。
時計。
勉強道具や日用品を、静かにカバンの中に詰めていく。
机の引き出しを開ける。
たいしたものは入っていない。
故郷の家族からの手紙。
美術部のナターシャが描いてくれた俺の似顔絵。
ショパンのレコード。
・・・俺は、ショパンが好きだった。
でも、ナタリーは、クララ・シューマンが好きで。
あぁ、モーツァルトも嫌いじゃないと言っていた。
・・・考えるな。
もう、考えたくない。
もう、覚えていたくない。
忘れたい。
なかったことにしたい。
・・・でも。
パトリシアが、眩しい日差しに目を細めた。
しばらくぶりの外。
しばらくぶりの自分の部屋。
銃の跡が残り、血痕もあるが、それ以外は、平穏を感じさせるままだ。
いつも通りの部屋。
ロルフの机と背中合わせになるように置かれた机。
その横の本棚。
読書は嫌いじゃないから、それなりの量の本が置いてある。
ロルフは、本じゃなくて煙草や酒を隠すように使ってたけど。
教科書。
ノート。
制服。
時計。
勉強道具や日用品を、静かにカバンの中に詰めていく。
机の引き出しを開ける。
たいしたものは入っていない。
故郷の家族からの手紙。
美術部のナターシャが描いてくれた俺の似顔絵。
ショパンのレコード。
・・・俺は、ショパンが好きだった。
でも、ナタリーは、クララ・シューマンが好きで。
あぁ、モーツァルトも嫌いじゃないと言っていた。
・・・考えるな。
もう、考えたくない。
もう、覚えていたくない。
忘れたい。
なかったことにしたい。
・・・でも。
本当は・・・違う。
ずっと覚えていたい。
彼女の全てを捨てたくない。
でも、覚えているのはつらすぎる。
そう・・・そういうことなのだ。
俺は、強くないから。
弱いから。
彼女がいることでしか強くなれなかったから。
だから、彼女は逝く間際、俺に何かを遺そうとはしなかった。
忘れないでほしい、も。
逝きたくない、も。
何も残さずに逝ってしまった。
そういう俺を知っていたから。
なのに、俺は気付けなかった・・・
何一つ・・・
後悔がこみ上げた。
すると・・・
ずっと覚えていたい。
彼女の全てを捨てたくない。
でも、覚えているのはつらすぎる。
そう・・・そういうことなのだ。
俺は、強くないから。
弱いから。
彼女がいることでしか強くなれなかったから。
だから、彼女は逝く間際、俺に何かを遺そうとはしなかった。
忘れないでほしい、も。
逝きたくない、も。
何も残さずに逝ってしまった。
そういう俺を知っていたから。
なのに、俺は気付けなかった・・・
何一つ・・・
後悔がこみ上げた。
すると・・・
引き出しの中をあさっていた手に、やわらかい布の感触があった。
「・・・・・・?」
取り出すと、青いリボンだった。
俺たちの学院では、男子生徒はネクタイ、女子生徒はリボンを、それぞれシャツの首もとにつけることが決められている。
女子生徒のリボンは、いろいろと種類があり、どのリボンをつけるかで学校内での立ち位置が何となく分かる。
太めのや、柄が入っているものは、華やかな女子生徒。
まぁ、ロルフと仲がいいタイプの子たちだ。
紐ぐらい細く、無地のものは、真面目な女子生徒。
先生に気に入られるような子たち。
新聞部の生徒は、その中間くらいの太さのを愛用している。
ことに、ナタリーは、その青い瞳によく似合う濃紺のタータンチェック柄を。
でも、教師陣の指導が厳しくなる体育祭前後は、全体的に細めの無地が人気になる。
ナタリーも例に漏れず、いつもより少し細いリボンを身につけていた。
体育祭が終わって、何か思い出に交換しようかと俺が言うと、ナタリーは、ポケットからこのリボンを取り出した。
そして、俺も、自分のネクタイを差し出したのだ。
そんな思い出すら・・・
こんなにも鮮やかだ。
忘れられるわけがない。
「・・・・・・?」
取り出すと、青いリボンだった。
俺たちの学院では、男子生徒はネクタイ、女子生徒はリボンを、それぞれシャツの首もとにつけることが決められている。
女子生徒のリボンは、いろいろと種類があり、どのリボンをつけるかで学校内での立ち位置が何となく分かる。
太めのや、柄が入っているものは、華やかな女子生徒。
まぁ、ロルフと仲がいいタイプの子たちだ。
紐ぐらい細く、無地のものは、真面目な女子生徒。
先生に気に入られるような子たち。
新聞部の生徒は、その中間くらいの太さのを愛用している。
ことに、ナタリーは、その青い瞳によく似合う濃紺のタータンチェック柄を。
でも、教師陣の指導が厳しくなる体育祭前後は、全体的に細めの無地が人気になる。
ナタリーも例に漏れず、いつもより少し細いリボンを身につけていた。
体育祭が終わって、何か思い出に交換しようかと俺が言うと、ナタリーは、ポケットからこのリボンを取り出した。
そして、俺も、自分のネクタイを差し出したのだ。
そんな思い出すら・・・
こんなにも鮮やかだ。
忘れられるわけがない。
涙がこぼれた。
守り切れなかった。
愛し抜けなかった。
悔しい。
苦しい。
切ない。
悲しい。
言い尽くせない思いが、あふれ出てくる。
「・・・アレン」
同じく部屋を片付けていたロルフが、俺の横にしゃがみ込んだ。
守り切れなかった。
愛し抜けなかった。
悔しい。
苦しい。
切ない。
悲しい。
言い尽くせない思いが、あふれ出てくる。
「・・・アレン」
同じく部屋を片付けていたロルフが、俺の横にしゃがみ込んだ。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
この作品をシェア
君の生きた証~love in war~
を読み込んでいます