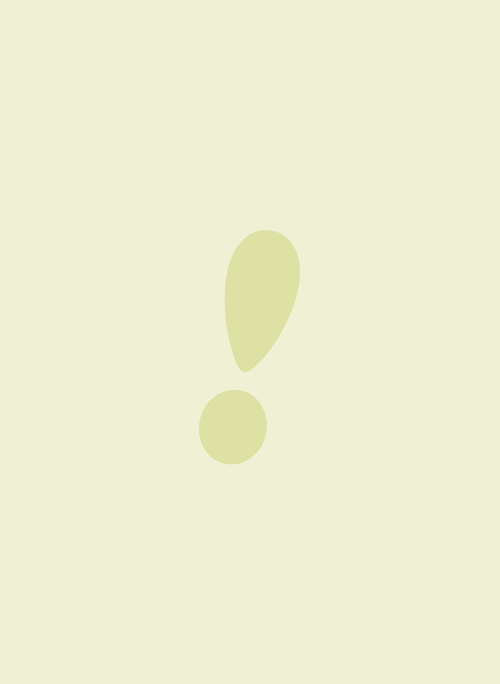だけど、あぁ・・・
やっぱりたくさんたくさん刻まれているのは、あなたの思い出なのね。
アレン。
泣いたり、
怒ったり、
からかったり、
沈んだり、
すねたり、
嫉妬したり、
でも、何よりたくさんの笑顔をくれた。
何一つ忘れてはいないわ。
キスするときの右側に顔を傾ける仕草も。
甘いものが苦手なことも。
そう、いつもコーヒーはブラックだった。
ショパンが好きで。
女っぽい趣味かな、と苦笑していたっけ。
私を気遣うように、クララ・シューマンのレコードを買っていたこともあった。
ケンカしたとき謝るのは、いつも私から。
私に原因があるときも、そうじゃないときも。
そういうところは頑固だったわ。
一度決めた意志は、絶対に曲げない。
そんなアレンを見れて、ちょっと嬉しかった。
朝のテニスの練習は、いつだって8時の鐘が鳴るまで。
ぎりぎりまで練習して、ヘンリー先生に怒られることも少なくなかったっけ。
テニスラケットを片手でくるくる回しながら、歩く姿は、ちょっと子供っぽかった。
先生たちの評価は、一貫して『真面目』。
勉強もコツコツこなして、テニスにも懸命に打ち込む、心優しい、いい生徒だと。
そんなお堅い恋人なんておもしろくないでしょ?と、誰かが言っていた。
そんなことないわ。
一瞬たりとて、そんなこと思わなかったわ。
いつだって、誇らしい大好きな恋人だった。
アレン・・・
ありがとう。
私、幸せだった。
これが最後なのね・・・
これで、全て終わりなのね・・・
みんな、大好きよ・・・
どうか元気で・・・
さよなら・・・
私は、意識が遠のいていくのを感じた。
ずっとずっと、遙かな遠いところへ・・・
私は消えていった。
やっぱりたくさんたくさん刻まれているのは、あなたの思い出なのね。
アレン。
泣いたり、
怒ったり、
からかったり、
沈んだり、
すねたり、
嫉妬したり、
でも、何よりたくさんの笑顔をくれた。
何一つ忘れてはいないわ。
キスするときの右側に顔を傾ける仕草も。
甘いものが苦手なことも。
そう、いつもコーヒーはブラックだった。
ショパンが好きで。
女っぽい趣味かな、と苦笑していたっけ。
私を気遣うように、クララ・シューマンのレコードを買っていたこともあった。
ケンカしたとき謝るのは、いつも私から。
私に原因があるときも、そうじゃないときも。
そういうところは頑固だったわ。
一度決めた意志は、絶対に曲げない。
そんなアレンを見れて、ちょっと嬉しかった。
朝のテニスの練習は、いつだって8時の鐘が鳴るまで。
ぎりぎりまで練習して、ヘンリー先生に怒られることも少なくなかったっけ。
テニスラケットを片手でくるくる回しながら、歩く姿は、ちょっと子供っぽかった。
先生たちの評価は、一貫して『真面目』。
勉強もコツコツこなして、テニスにも懸命に打ち込む、心優しい、いい生徒だと。
そんなお堅い恋人なんておもしろくないでしょ?と、誰かが言っていた。
そんなことないわ。
一瞬たりとて、そんなこと思わなかったわ。
いつだって、誇らしい大好きな恋人だった。
アレン・・・
ありがとう。
私、幸せだった。
これが最後なのね・・・
これで、全て終わりなのね・・・
みんな、大好きよ・・・
どうか元気で・・・
さよなら・・・
私は、意識が遠のいていくのを感じた。
ずっとずっと、遙かな遠いところへ・・・
私は消えていった。
視界の端に、銃が映った。
とっさに身構えたが、はっとした。
俺じゃなくて、ロルフでもなくて・・・
違う、狙っているのは・・・
「ナタリー、伏せろ!」
必死の声は、しかし遅すぎた。
とっさに身構えたが、はっとした。
俺じゃなくて、ロルフでもなくて・・・
違う、狙っているのは・・・
「ナタリー、伏せろ!」
必死の声は、しかし遅すぎた。
あぁ・・・悪夢だ。
いつか見た夢の続きだ・・・
揺らぐ意識の中でそう思った。
「ナタリー!おい!」
名前を呼んでも、彼女は目を開けない。
「嘘だろ・・・なぁ、ナタリー!」
いつか見た夢の続きだ・・・
揺らぐ意識の中でそう思った。
「ナタリー!おい!」
名前を呼んでも、彼女は目を開けない。
「嘘だろ・・・なぁ、ナタリー!」
「アレン!」
ロルフが叫んだ。
「ここは俺が何としても食い止める!お前はナタリーを連れて行け!パトリシアもだ!」
「でも、お前は!」
「・・・はっ」
薄く笑った表情が、全てを肯定している。
「何とかするさ、さぁ、ほら、急げ!」
ロルフが叫んだ。
「ここは俺が何としても食い止める!お前はナタリーを連れて行け!パトリシアもだ!」
「でも、お前は!」
「・・・はっ」
薄く笑った表情が、全てを肯定している。
「何とかするさ、さぁ、ほら、急げ!」
「頼んだぞ、アレン」
ロルフが静かな目で懇願した。
「守ってくれ」
誰をとは言わない。
それが、ロルフの誠実さなのだ。
「・・・分かった」
俺は、ナタリーを抱きかかえ、走り出した。
ロルフが静かな目で懇願した。
「守ってくれ」
誰をとは言わない。
それが、ロルフの誠実さなのだ。
「・・・分かった」
俺は、ナタリーを抱きかかえ、走り出した。
昨日の夜、腕の中にあったぬくもりだ。
愛したぬくもりだ。
俺の背中につめを立てたぬくもりだ。
神様、
命って、こんなに軽かったっけ・・・?
彼女の血液が俺の制服ににじんでいく。
そのなめらかな温度すら、悲しい。
彼女の体温が溶けていくような気がして・・・
だめだ・・・
まだ逝ってはだめだ・・・
愛したぬくもりだ。
俺の背中につめを立てたぬくもりだ。
神様、
命って、こんなに軽かったっけ・・・?
彼女の血液が俺の制服ににじんでいく。
そのなめらかな温度すら、悲しい。
彼女の体温が溶けていくような気がして・・・
だめだ・・・
まだ逝ってはだめだ・・・
「きゃああああああああ!」
「ナタリー!」
「アレン、どうしたの!?」
周囲の悲鳴なんて聞いちゃいられない。
「キャロライン先生!ベッドどこですか!?」
元担任で、ラテン語教諭のキャロライン・ロイドバーグ先生に向かって叫んだ。
「ここに寝かせなさい、アレン!アグネス、急いで薬と包帯を持っていらっしゃい!」
「はい!」
今にも泣きそうなアグネスが駆けていく。
「先生!俺、B型です!彼女と、ナタリーと同じだから!」
「アレン、落ち着きなさい!」
「お願いです、俺の血・・・!」
「そんな・・・あなたこそ血まみれよ、今、採血したらあなたの命が危なくなるわ!」
「それでも・・・!それでも、かまいません!」
神様・・・
俺は死んでもいいから・・・
どうか、彼女を・・・
「ナタリー!」
「アレン、どうしたの!?」
周囲の悲鳴なんて聞いちゃいられない。
「キャロライン先生!ベッドどこですか!?」
元担任で、ラテン語教諭のキャロライン・ロイドバーグ先生に向かって叫んだ。
「ここに寝かせなさい、アレン!アグネス、急いで薬と包帯を持っていらっしゃい!」
「はい!」
今にも泣きそうなアグネスが駆けていく。
「先生!俺、B型です!彼女と、ナタリーと同じだから!」
「アレン、落ち着きなさい!」
「お願いです、俺の血・・・!」
「そんな・・・あなたこそ血まみれよ、今、採血したらあなたの命が危なくなるわ!」
「それでも・・・!それでも、かまいません!」
神様・・・
俺は死んでもいいから・・・
どうか、彼女を・・・
「・・・っ」
「ナタリー!?」
ナタリーが、薄く目を開き、口を動かす。
「え・・・」
聞こえない。
聞こえないよ、ナタリー・・・
何を・・・伝えようとしてる・・・?
口元に耳を寄せる。
「あれ・・・、い・・・て・・・」
「え・・・?」
「ナタリー!?」
ナタリーが、薄く目を開き、口を動かす。
「え・・・」
聞こえない。
聞こえないよ、ナタリー・・・
何を・・・伝えようとしてる・・・?
口元に耳を寄せる。
「あれ・・・、い・・・て・・・」
「え・・・?」
「あ・・・れん・・・は・・・い・・・き・・・て・・・」
「お・・・俺・・・?」
こくんと、ナタリーがうなずく。
そして、絶え絶えな息で、言葉を繋いでいく。
「あの・・・ね・・・マ・・・ルゴ・・・の夫は・・・アンリだったけど・・・」
「お・・・俺・・・?」
こくんと、ナタリーがうなずく。
そして、絶え絶えな息で、言葉を繋いでいく。
「あの・・・ね・・・マ・・・ルゴ・・・の夫は・・・アンリだったけど・・・」
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…