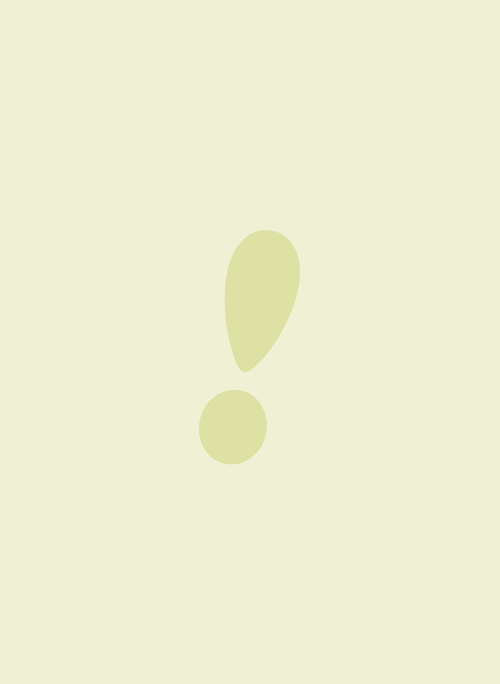こんな静かなキス、初めてだった。
いつも、くだらない冗談や遊びみたいにキスしてたから。
それに、こんなに異性の存在を心地よく、愛おしく思えたのも初めてだった。
アレンと部屋で交わしていた会話を不意に思い出す。
『ロルフ、もう無駄にエレノアをいちゃつくのはやめろ』
制服を脱ぎながら、ため息をつくアレン。
『パトリシアが泣くだろ』
『へぇ、お前はそういうのないのかよ』
『・・・そういうのって』
『女遊びは、男の本能だろ。あ、ナタリーが扇情的過ぎて、他の女にはそういうこと思わないとか?』
『・・・俺たちは、お前が思ってるほど大人じゃねぇよ』
アレンは、少し困った様子でそう言っていた。
『相手がそばにいるだけで、心が安らぐ。キスするだけで、世界の全てが愛おしく思える。そんな恋が、あるんだよ』
そのときは、もう2人はキスまで進んだのかとぼんやり嫉妬しただけだった。
だが、今なら。
体を重ねて抱き合うことでなくても、相手を大切にするすべを俺は知っている。
いつも、くだらない冗談や遊びみたいにキスしてたから。
それに、こんなに異性の存在を心地よく、愛おしく思えたのも初めてだった。
アレンと部屋で交わしていた会話を不意に思い出す。
『ロルフ、もう無駄にエレノアをいちゃつくのはやめろ』
制服を脱ぎながら、ため息をつくアレン。
『パトリシアが泣くだろ』
『へぇ、お前はそういうのないのかよ』
『・・・そういうのって』
『女遊びは、男の本能だろ。あ、ナタリーが扇情的過ぎて、他の女にはそういうこと思わないとか?』
『・・・俺たちは、お前が思ってるほど大人じゃねぇよ』
アレンは、少し困った様子でそう言っていた。
『相手がそばにいるだけで、心が安らぐ。キスするだけで、世界の全てが愛おしく思える。そんな恋が、あるんだよ』
そのときは、もう2人はキスまで進んだのかとぼんやり嫉妬しただけだった。
だが、今なら。
体を重ねて抱き合うことでなくても、相手を大切にするすべを俺は知っている。
静かに静かに、唇が触れ合い、心臓の音だけがやけにうるさく感じられる。
パトリシアの鼻先にうっすら浮いたそばかすがぞくぞくするほどあでやかだ。
愛している、と呟いてみる。
彼女が遠くならないように。
自分が壊れてしまわないように。
パトリシアの鼻先にうっすら浮いたそばかすがぞくぞくするほどあでやかだ。
愛している、と呟いてみる。
彼女が遠くならないように。
自分が壊れてしまわないように。
「・・・生きてくれ」
腕の中のパトリシアをより強く抱きしめる。
細い体つきの彼女にとっては、痛いくらいだろうと分かっていながら。
「俺が死んだとしても、どうか、パトリシアだけは生きてくれ」
細い体つきの彼女にとっては、痛いくらいだろうと分かっていながら。
「俺が死んだとしても、どうか、パトリシアだけは生きてくれ」
背中に回された腕が、優しく俺の体を包む。
パトリシアの細い腕が、まるで聖母のようだ。
「・・・生きるわ」
だからあなたも、と声が絞られる。
「あなたも生きて・・・」
叶うなら、私のために。
どうか、生きて。
声にならない声をパトリシアが吐き出す。
さっきまで目の前に広がっていた苦い夜の色が、ひどく甘やかに映った。
そうか・・・
そうだよな・・・
生きなきゃ・・・いけないよなぁ。
遠くなった友に向かって語りかけた。
少しだけ、遠いはずの生が近づいた気がした。
パトリシアの細い腕が、まるで聖母のようだ。
「・・・生きるわ」
だからあなたも、と声が絞られる。
「あなたも生きて・・・」
叶うなら、私のために。
どうか、生きて。
声にならない声をパトリシアが吐き出す。
さっきまで目の前に広がっていた苦い夜の色が、ひどく甘やかに映った。
そうか・・・
そうだよな・・・
生きなきゃ・・・いけないよなぁ。
遠くなった友に向かって語りかけた。
少しだけ、遠いはずの生が近づいた気がした。
「あふ・・・ぁ」
目が覚めた。
寒い。
本能的に、そばにあったあたたかいものに身体を寄せた。
「ん~~~~・・・ん?」
何となく違和感。
目をこすると・・・
「おはよ」
目が覚めた。
寒い。
本能的に、そばにあったあたたかいものに身体を寄せた。
「ん~~~~・・・ん?」
何となく違和感。
目をこすると・・・
「おはよ」
「わ、わわわわわっ、ああああ、あれん!」
「・・・傷つくなぁ、その反応」
「あ、ああああ、っと、失礼しました」
そっか・・・私・・・
自分の全てを変えたんだ。
「じゃ改めて」
軽くついばむように口づけられた。
「おはよ、ナタリー」
「・・・傷つくなぁ、その反応」
「あ、ああああ、っと、失礼しました」
そっか・・・私・・・
自分の全てを変えたんだ。
「じゃ改めて」
軽くついばむように口づけられた。
「おはよ、ナタリー」
でも、やっぱり恥ずかしい・・・
「服着るから。・・・見ないでね?」
「何を今さら。昨日の夜は・・・」
「もう!怒るよ!」
「はいはい、こっち向いてますよ」
ちょっとふてくされたように、アレンがそっぽを向いた。
だって・・・恥ずかしいじゃん・・・
「服着るから。・・・見ないでね?」
「何を今さら。昨日の夜は・・・」
「もう!怒るよ!」
「はいはい、こっち向いてますよ」
ちょっとふてくされたように、アレンがそっぽを向いた。
だって・・・恥ずかしいじゃん・・・
屋根裏の窓から差し込む朝日が眩しい。
あぁ・・・こんなに世界って綺麗だったっけ?
あぁ・・・こんなに世界って綺麗だったっけ?
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…