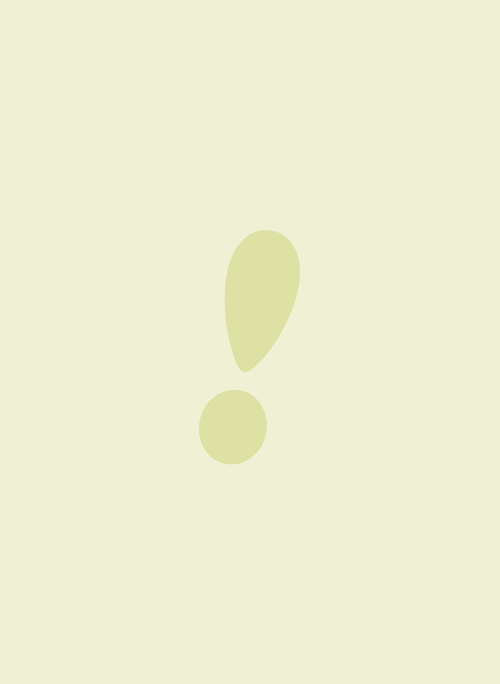アレンは、深いため息をつくと、私にキスを落とした。
気怠い熱が身体に響く。
大人びたキスの振動にさえ敏感になってしまうほどに。
一つになれたのだという実感が身体の中心からわき上がってくる。
アレンが好きだと思った。
ずっとこの幸福が続けばいいと思った。
甘い幸福に浸りながら、私はかつてないほど深い眠りへと落ちていった。
気怠い熱が身体に響く。
大人びたキスの振動にさえ敏感になってしまうほどに。
一つになれたのだという実感が身体の中心からわき上がってくる。
アレンが好きだと思った。
ずっとこの幸福が続けばいいと思った。
甘い幸福に浸りながら、私はかつてないほど深い眠りへと落ちていった。
気怠い熱が身体に残っている。
疲れたのだろうか。
傍らで眠るナタリーは、軽い寝息を立てている。
白い柔肌に、そっと触れてみる。
「ん・・・」
少し開いた口元は、キスでも求めているかのようだ。
寒いのか、身体をすり寄せてくるナタリーが愛おしかった。
悲しいほど、狂おしいほど、愛しかった。
疲れたのだろうか。
傍らで眠るナタリーは、軽い寝息を立てている。
白い柔肌に、そっと触れてみる。
「ん・・・」
少し開いた口元は、キスでも求めているかのようだ。
寒いのか、身体をすり寄せてくるナタリーが愛おしかった。
悲しいほど、狂おしいほど、愛しかった。
屋根裏は冷える。
彼女の上に、上着を掛けた。
抱かれたばかりとは思えないほどのあどけない寝顔に、軽く指を寄せる。
赤く火照った頬だけが情事の名残を見せていた。
「・・・マルゴ王妃、か」
誰が言い出したのか分からない。
でも、とびきりぴったりの二つ名。
男好きの王妃の名にふさわしく、彼女のベッドでの振る舞いは妖艶だった。
甘い吐息。
背中に刻まれるつめ。
震える腰つき。
その全てがなまめかしく、ぞくぞくした。
思い出すだけで、ぐらりと身体がふらつきそうになるほどに。
いや、実際、思い返すだけで、腰が浮く。
男とは、そういうものだ。
・・・自分でも腹が立つけれど。
星が不気味なほど明るい。
彼女の上に、上着を掛けた。
抱かれたばかりとは思えないほどのあどけない寝顔に、軽く指を寄せる。
赤く火照った頬だけが情事の名残を見せていた。
「・・・マルゴ王妃、か」
誰が言い出したのか分からない。
でも、とびきりぴったりの二つ名。
男好きの王妃の名にふさわしく、彼女のベッドでの振る舞いは妖艶だった。
甘い吐息。
背中に刻まれるつめ。
震える腰つき。
その全てがなまめかしく、ぞくぞくした。
思い出すだけで、ぐらりと身体がふらつきそうになるほどに。
いや、実際、思い返すだけで、腰が浮く。
男とは、そういうものだ。
・・・自分でも腹が立つけれど。
星が不気味なほど明るい。
愛している。
全てを捨ててでも守りたい恋だ。
家族や、故郷や、友人たち全てをなげうってでも。
それほど・・・深い愛だ。
全てを捨ててでも守りたい恋だ。
家族や、故郷や、友人たち全てをなげうってでも。
それほど・・・深い愛だ。
だが、叶わないかもしれない。
国に帰れば、もうここへは戻れないかもしれない。
ナタリーに会うことも出来なくなるかもしれない。
否、と頭を振る。
悪い考えを振り払うように。
・・・愛すると決めただろう?
国に帰れば、もうここへは戻れないかもしれない。
ナタリーに会うことも出来なくなるかもしれない。
否、と頭を振る。
悪い考えを振り払うように。
・・・愛すると決めただろう?
何があっても、彼女を守り抜こう。
腕の中のぬくもりに、そう誓った。
愛する人の白い肌を、闇の中の光が照らしていた。
腕の中のぬくもりに、そう誓った。
愛する人の白い肌を、闇の中の光が照らしていた。
目の前にいるぬくもりに触れたいと心から思った。
ロルフが愛おしかった。
愛していた。
苦しいほど、好きだと思った。
ずっと、偽られてきた愛なのだとしても。
ロルフが愛おしかった。
愛していた。
苦しいほど、好きだと思った。
ずっと、偽られてきた愛なのだとしても。
ロルフは知っていたのかもしれない。
ナタリーが彼に振り向かないことも。
アレンがどれほど真っ直ぐにナタリーを想っているかも。
そして、私がロルフを深く深く慕っていることにも。
知っていてあれほど卑怯なことをしたのかと罵りたかった。
逝った仲間たちに顔向けできないほど、ひどいことを・・・と。
そう言えたら、どんなに楽だっただろう?
ナタリーが彼に振り向かないことも。
アレンがどれほど真っ直ぐにナタリーを想っているかも。
そして、私がロルフを深く深く慕っていることにも。
知っていてあれほど卑怯なことをしたのかと罵りたかった。
逝った仲間たちに顔向けできないほど、ひどいことを・・・と。
そう言えたら、どんなに楽だっただろう?
彼は・・・むごすぎる現実から逃れたくて、夢を見た。
叶わない恋さえ叶うような幻を見た。
自分でない相手を愛している人さえ、腕の中に抱ける、と。
そういう夢を見させるのだ。
あのナタリーという少女は。
憎らしい、でも・・・限りなく愛おしい私の親友は。
頭がおかしくなるくらいたくさんの仲間を失って、とロルフが呟く。
「目の前で殺されて・・・それでも生きる意味って何なんだろうな」
この苦しみを背負って生きなきゃなんないのか?
苦しすぎる生を全うしなければならないのか?
ロルフの苦しい息づかいがそう問いかける。
答えのない問いかけだ。
答えはあるのかもしれないけど、私には分からない。
叶わない恋さえ叶うような幻を見た。
自分でない相手を愛している人さえ、腕の中に抱ける、と。
そういう夢を見させるのだ。
あのナタリーという少女は。
憎らしい、でも・・・限りなく愛おしい私の親友は。
頭がおかしくなるくらいたくさんの仲間を失って、とロルフが呟く。
「目の前で殺されて・・・それでも生きる意味って何なんだろうな」
この苦しみを背負って生きなきゃなんないのか?
苦しすぎる生を全うしなければならないのか?
ロルフの苦しい息づかいがそう問いかける。
答えのない問いかけだ。
答えはあるのかもしれないけど、私には分からない。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…