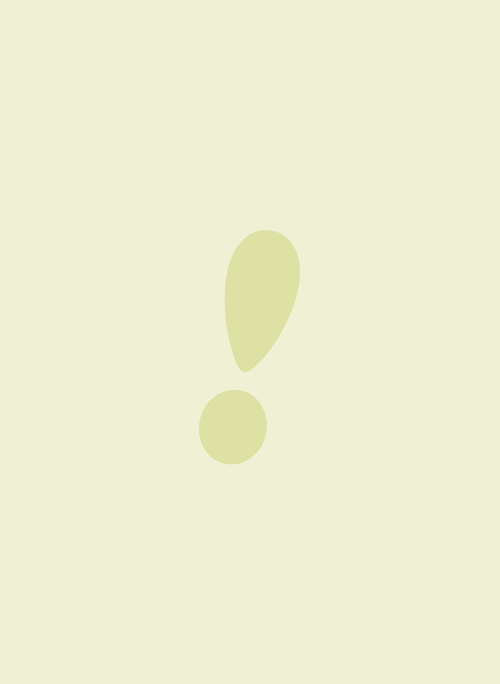「パトリシア」
「うん?」
「好きだよ」
それだけをつぶやいて、、静かに時が過ぎるのだけを待ち続けた。
明日には遠くなる恋人。
腕の中にあるぬくもり。
抱きしめて、抱きしめて、決してもう離れまいと誓う。
ただ静かに夜が更けていく。
「うん?」
「好きだよ」
それだけをつぶやいて、、静かに時が過ぎるのだけを待ち続けた。
明日には遠くなる恋人。
腕の中にあるぬくもり。
抱きしめて、抱きしめて、決してもう離れまいと誓う。
ただ静かに夜が更けていく。
「え・・・ちょっと、アレン・・・?」
何だかいつものアレンじゃないみたいだ。
すごく大人びていて、なんだか・・・
・・・怖い。
何だかいつものアレンじゃないみたいだ。
すごく大人びていて、なんだか・・・
・・・怖い。
顔を傾けて、キスをされる。
向き合うと、アレンの方が顔の位置が高くなるから、自然とそうなる。
いつも通りだ。
優しくて、愛されていることの伝わってくるキス。
・・・そう思っていたら、違った。
深い深いキスが始まった。
向き合うと、アレンの方が顔の位置が高くなるから、自然とそうなる。
いつも通りだ。
優しくて、愛されていることの伝わってくるキス。
・・・そう思っていたら、違った。
深い深いキスが始まった。
アレンは、一度キスをやめた。
屋根裏の天窓から、星明かりが差し込んでいる。
アレンの端整な顔立ちがぼんやりと照らされ、切ないほどの愛しさがあふれ出す。
静かに、アレンが口を開いた。
「・・・俺、死ぬのが怖いんだ」
「ア、レン・・・」
「かっこわりぃだろ?・・・でも、本当なんだ」
アレンが、左目をかすかに歪ませる。
「未練残して死ぬのが怖い。何も思わずに死ぬには、俺はたくさんのものを好きになりすぎたから」
だから、とアレンがささやいた。
「お前くらいは、悔いなく愛させてくれ」
そして・・・わずかにためらった後、アレンは覚悟を決めたようにまたキスをした。
そのキスは、やっぱり顔を傾けるいつもの姿勢で。
でも、やっぱり違っていて。
キスはどんどん激しくなった。
屋根裏の天窓から、星明かりが差し込んでいる。
アレンの端整な顔立ちがぼんやりと照らされ、切ないほどの愛しさがあふれ出す。
静かに、アレンが口を開いた。
「・・・俺、死ぬのが怖いんだ」
「ア、レン・・・」
「かっこわりぃだろ?・・・でも、本当なんだ」
アレンが、左目をかすかに歪ませる。
「未練残して死ぬのが怖い。何も思わずに死ぬには、俺はたくさんのものを好きになりすぎたから」
だから、とアレンがささやいた。
「お前くらいは、悔いなく愛させてくれ」
そして・・・わずかにためらった後、アレンは覚悟を決めたようにまたキスをした。
そのキスは、やっぱり顔を傾けるいつもの姿勢で。
でも、やっぱり違っていて。
キスはどんどん激しくなった。
制服のリボンが緩められていく。
「やだ・・・アレン、こんなところで・・・」
「だめ。めちゃくちゃにしてやる」
「で・・・もっ、ぁ・・・っ」
「ナタリーって、耳弱いのな」
ひたりと耳元に唇を寄せられる。
丁寧でしっとりとした口づけ。
甘い水音に、身体が染められていく。
恥ずかしかったが、それが、より確かな形で結ばれるための行為なのだと私は理解していた。
「ナタリー、好きだよ」
「私も・・・」
好きだ。
アレンが好きだ。
だから、全てを許したい。
全てを分かち合いたい。
全てを与えたい。
全てを・・・
アレンのわずかにぎこちない様子が、少しおかしい。
私は、アレンの長めの茶色い髪に指を絡めた。
身体にキスを落とされ、思わず甘い吐息が漏れる。
優しくて、不器用で、甘やかな扱いだった。
だんだん、怖いという気持ちは薄れていった。
アレンの腕の中は心地よくて、ずっと前から知っていたみたいだった。
怖い、よりも、気持ちいいという感覚が徐々に身を包んでいった。
アレンのキスも、私の体に触れる手つきも、全てが気持ちがよかった。
「やだ・・・アレン、こんなところで・・・」
「だめ。めちゃくちゃにしてやる」
「で・・・もっ、ぁ・・・っ」
「ナタリーって、耳弱いのな」
ひたりと耳元に唇を寄せられる。
丁寧でしっとりとした口づけ。
甘い水音に、身体が染められていく。
恥ずかしかったが、それが、より確かな形で結ばれるための行為なのだと私は理解していた。
「ナタリー、好きだよ」
「私も・・・」
好きだ。
アレンが好きだ。
だから、全てを許したい。
全てを分かち合いたい。
全てを与えたい。
全てを・・・
アレンのわずかにぎこちない様子が、少しおかしい。
私は、アレンの長めの茶色い髪に指を絡めた。
身体にキスを落とされ、思わず甘い吐息が漏れる。
優しくて、不器用で、甘やかな扱いだった。
だんだん、怖いという気持ちは薄れていった。
アレンの腕の中は心地よくて、ずっと前から知っていたみたいだった。
怖い、よりも、気持ちいいという感覚が徐々に身を包んでいった。
アレンのキスも、私の体に触れる手つきも、全てが気持ちがよかった。
「なんか・・・おかしくなっちゃいそう」
「そうさ。本当におかしくなるくらい愛してやる」
アレンらしくない言葉。
アレンらしくない口調。
アレンらしくないキス。
アレンらしくない仕草。
でも、なぜか懐かしい。
遠い昔から、こうなることが分かっていた気さえする。
そう、私は、あなたを愛するために生まれてきた。
あなたに愛されるために生まれてきた。
あなたと共に生きるために、生まれてきた。
「そうさ。本当におかしくなるくらい愛してやる」
アレンらしくない言葉。
アレンらしくない口調。
アレンらしくないキス。
アレンらしくない仕草。
でも、なぜか懐かしい。
遠い昔から、こうなることが分かっていた気さえする。
そう、私は、あなたを愛するために生まれてきた。
あなたに愛されるために生まれてきた。
あなたと共に生きるために、生まれてきた。
身体を押し倒される。
アレンの体重がのしかかる。
重いのに・・・なぜか愛しい。
怖いのに・・・なぜか幸福だ。
アレンの体重がのしかかる。
重いのに・・・なぜか愛しい。
怖いのに・・・なぜか幸福だ。
静かに静かに、アレンは、私を抱いた。
私は、一つ吐息をつき、アレンを受け入れた。
甘い熱がわき上がる。
鼓動が重なる。
荒い息の色さえ、同じになって溶け合っていく。
その行為の中で、私は深い安らぎに包まれていた。
自分の全てがアレンのためにあるような気さえしていた。
身体の奥から貫いてくる甘やかで熱い痛みがひどく愛おしかった。
私の名前を耳元でささやくアレンの背中につめを立てる。
消えてしまわないように。
私がいなくなってしまわないように。
どうしてだろう?
泣きたいほどアレンが愛おしかった。
自分の全てが変わっていく夜の温度さえ、身体に刻みたいと思った。
「力、抜けるか」
「ん・・・っ、や、無理・・・みたい」
「全部、俺に預けて」
アレンの動きが速くなる。
痛みと愛情が溶けていく。
苦しくて、泣きたいくらい愛しい。
私は、一つ吐息をつき、アレンを受け入れた。
甘い熱がわき上がる。
鼓動が重なる。
荒い息の色さえ、同じになって溶け合っていく。
その行為の中で、私は深い安らぎに包まれていた。
自分の全てがアレンのためにあるような気さえしていた。
身体の奥から貫いてくる甘やかで熱い痛みがひどく愛おしかった。
私の名前を耳元でささやくアレンの背中につめを立てる。
消えてしまわないように。
私がいなくなってしまわないように。
どうしてだろう?
泣きたいほどアレンが愛おしかった。
自分の全てが変わっていく夜の温度さえ、身体に刻みたいと思った。
「力、抜けるか」
「ん・・・っ、や、無理・・・みたい」
「全部、俺に預けて」
アレンの動きが速くなる。
痛みと愛情が溶けていく。
苦しくて、泣きたいくらい愛しい。
アレンは、深いため息をつくと、私にキスを落とした。
気怠い熱が身体に響く。
大人びたキスの振動にさえ敏感になってしまうほどに。
一つになれたのだという実感が身体の中心からわき上がってくる。
アレンが好きだと思った。
ずっとこの幸福が続けばいいと思った。
甘い幸福に浸りながら、私はかつてないほど深い眠りへと落ちていった。
気怠い熱が身体に響く。
大人びたキスの振動にさえ敏感になってしまうほどに。
一つになれたのだという実感が身体の中心からわき上がってくる。
アレンが好きだと思った。
ずっとこの幸福が続けばいいと思った。
甘い幸福に浸りながら、私はかつてないほど深い眠りへと落ちていった。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…