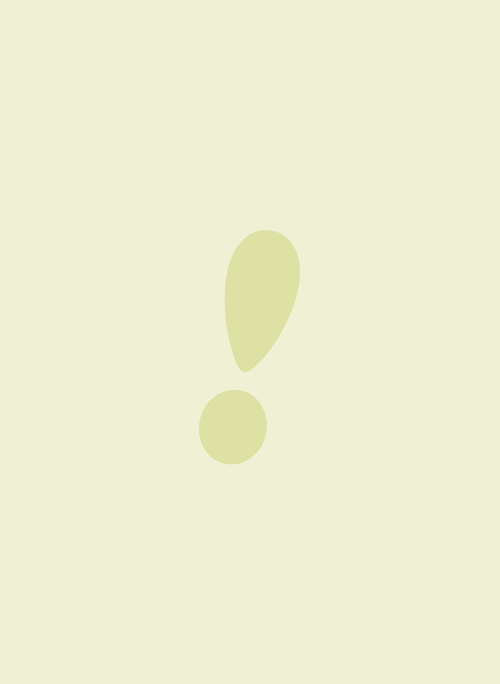「嘘になるわけがないんだ。お前がこんなに本気になってくれたんなら・・・報いるすべは俺にしかない」
力強く抱きしめられる。
「正も誤もねぇよ。・・・これが俺の愛だ」
・・・信じてもいいのだろうか?
信じるべきなのだろうか・・・?
でも、理性が飛んでいく。
怖いくらい、彼に溺れていく。
裏切りも、嘘も偽りも、全て、本当はどうだっていい。
彼さえそばにいてくれるなら。
ようやく、息をできる気がした。
今度こそ、信じぬくと決めた。
この愛を貫いていこうと。
私は、体を包む優しいぬくもりに両手を回した。
力強く抱きしめられる。
「正も誤もねぇよ。・・・これが俺の愛だ」
・・・信じてもいいのだろうか?
信じるべきなのだろうか・・・?
でも、理性が飛んでいく。
怖いくらい、彼に溺れていく。
裏切りも、嘘も偽りも、全て、本当はどうだっていい。
彼さえそばにいてくれるなら。
ようやく、息をできる気がした。
今度こそ、信じぬくと決めた。
この愛を貫いていこうと。
私は、体を包む優しいぬくもりに両手を回した。
「正も誤もねぇよ。・・・これが俺の愛だ」
そう。
友を裏切り、愛する人を傷つけ、恋人を踏みにじってなお、俺は、誰かを愛することにここまで貪欲なのだ。
パトリシアを捨てたくないと、そう思ってしまう。
愛されたいと、愛したいと、そう望んでしまう。
どれほど不実なことか、よく分かっているのに。
でも、この腕の中の少女は、守り抜きたい全てなのだ。
そう。
友を裏切り、愛する人を傷つけ、恋人を踏みにじってなお、俺は、誰かを愛することにここまで貪欲なのだ。
パトリシアを捨てたくないと、そう思ってしまう。
愛されたいと、愛したいと、そう望んでしまう。
どれほど不実なことか、よく分かっているのに。
でも、この腕の中の少女は、守り抜きたい全てなのだ。
「話を・・・聞いてくれるか?」
誰にもずっと言えなかった話だ。
アレンも、ナタリーも知らない。
「俺の17年間の話だ」
誰にもずっと言えなかった話だ。
アレンも、ナタリーも知らない。
「俺の17年間の話だ」
ウィンスブルッグ家の長男として生を受け、育てられた。
下には2人の妹。
家を守ることは、自分が生まれた時から決まっていた運命だった。
跡取りとして恥ずかしくない生き方を強制された。
教育も、交友関係も。
そんな束縛から逃れようと、留学を決めた。
そして・・・彼女に出会った。
でも、彼女は選んではくれなかった。
下には2人の妹。
家を守ることは、自分が生まれた時から決まっていた運命だった。
跡取りとして恥ずかしくない生き方を強制された。
教育も、交友関係も。
そんな束縛から逃れようと、留学を決めた。
そして・・・彼女に出会った。
でも、彼女は選んではくれなかった。
「けど・・・君は」
この美しい瞳は。
「俺を愛してくれた」
甘えだとわかっている。
利己的な愛だと知っている。
それでも。
「パトリシアを守るために生きることは・・・もう許されないか?」
この美しい瞳は。
「俺を愛してくれた」
甘えだとわかっている。
利己的な愛だと知っている。
それでも。
「パトリシアを守るために生きることは・・・もう許されないか?」
水色の瞳がみるみるうちに潤む。
パトリシアは、俺の腕の中で、ただうなずいた。
何度も何度も、首を縦に振った。
故郷へ帰ることすら叶わなかった仲間がいる。
遺体すら戻らなかった仲間がいる。
最後の言葉すら残せなかった仲間がいる。
彼らが叶えられなかった幸せを、叶えたい。
真実にしたい。
どれほど、それが難しいことだとしても。
パトリシアは、俺の腕の中で、ただうなずいた。
何度も何度も、首を縦に振った。
故郷へ帰ることすら叶わなかった仲間がいる。
遺体すら戻らなかった仲間がいる。
最後の言葉すら残せなかった仲間がいる。
彼らが叶えられなかった幸せを、叶えたい。
真実にしたい。
どれほど、それが難しいことだとしても。
やり直せるなんて思わない。
時間は元には戻らない。
でも、未来なら・・・
きっと幸福に生きられる。
時間は元には戻らない。
でも、未来なら・・・
きっと幸福に生きられる。
静かに夜が更けていく。
数え切れない悲しみをのせて。
明日には、俺はここにはいない。
そばで微笑むパトリシアはいない。
ナタリーもアレンも。
もう何もなくしたくないのに・・・
でも、遠い未来なら。
一緒に生きられるはずだ。
アレンもナタリーも、パトリシアも俺も、みんなで一緒に幸せになる運命が、叶うはずだ。
俺は、その幸福を信じたいと思った。
数え切れない悲しみをのせて。
明日には、俺はここにはいない。
そばで微笑むパトリシアはいない。
ナタリーもアレンも。
もう何もなくしたくないのに・・・
でも、遠い未来なら。
一緒に生きられるはずだ。
アレンもナタリーも、パトリシアも俺も、みんなで一緒に幸せになる運命が、叶うはずだ。
俺は、その幸福を信じたいと思った。
「パトリシア」
「うん?」
「好きだよ」
それだけをつぶやいて、、静かに時が過ぎるのだけを待ち続けた。
明日には遠くなる恋人。
腕の中にあるぬくもり。
抱きしめて、抱きしめて、決してもう離れまいと誓う。
ただ静かに夜が更けていく。
「うん?」
「好きだよ」
それだけをつぶやいて、、静かに時が過ぎるのだけを待ち続けた。
明日には遠くなる恋人。
腕の中にあるぬくもり。
抱きしめて、抱きしめて、決してもう離れまいと誓う。
ただ静かに夜が更けていく。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…