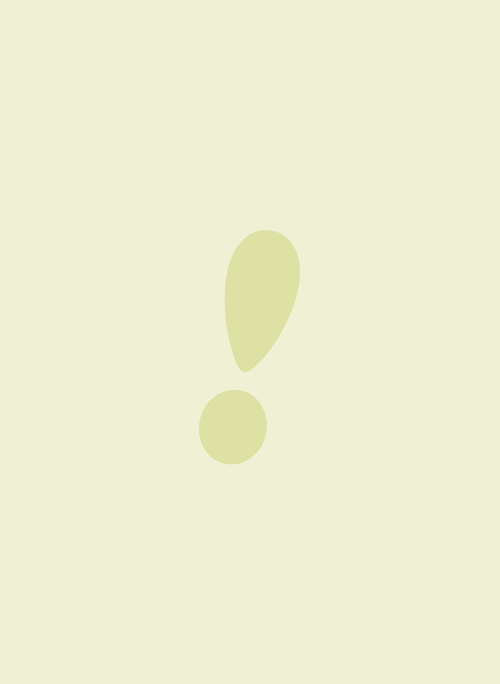「好きだよ」
そう口にしながら、俺はナタリーの身体を横たえた。
ずっと抑えてきた。
俺は、あんまりナタリーのことが好きだから、一度彼女に触れてしまったら、めちゃくちゃにしてしまいそうで怖かったから。
だけど、それは、ロルフに奪っていいと判断させるためではなかった。
彼女を奪われるためではなかった。
全てかき消してやる。
ロルフにキスされたことなんて、すぐに忘れさせてやる。
そのくらい激しいキスをしたかった。
ほの暗い星が、ナタリーの髪を薄く照らしていた。
そう口にしながら、俺はナタリーの身体を横たえた。
ずっと抑えてきた。
俺は、あんまりナタリーのことが好きだから、一度彼女に触れてしまったら、めちゃくちゃにしてしまいそうで怖かったから。
だけど、それは、ロルフに奪っていいと判断させるためではなかった。
彼女を奪われるためではなかった。
全てかき消してやる。
ロルフにキスされたことなんて、すぐに忘れさせてやる。
そのくらい激しいキスをしたかった。
ほの暗い星が、ナタリーの髪を薄く照らしていた。
涙が止まらない。
嗚咽を必死に抑えようとするが、叶わない。
神様・・・
いっそ、この命が消えてしまえばいいのに。
いっそ・・・私なんか、このまま消えてしまえたらいいのに。
嗚咽を必死に抑えようとするが、叶わない。
神様・・・
いっそ、この命が消えてしまえばいいのに。
いっそ・・・私なんか、このまま消えてしまえたらいいのに。
愛されていると思っていた。
両親ともに健在で、姉と弟がいて、幸福な家庭を絵に描いたように幸せだった。
愛されることが当然だった。
愛することは自然なことだった。
だから、同じ教室で共に学ぶ中で、ごく自然にロルフに恋をした。
軽薄な雰囲気も、魅力的だった。
自分にないものばかり持っているロルフは、素敵だと思った。
付き合おうといわれた時は、本当に嬉しかった。
華やかな女の子たちを虜にするあのはしばみ色の瞳が、自分に向けられるのだというだけで、胸が高鳴った。
両親ともに健在で、姉と弟がいて、幸福な家庭を絵に描いたように幸せだった。
愛されることが当然だった。
愛することは自然なことだった。
だから、同じ教室で共に学ぶ中で、ごく自然にロルフに恋をした。
軽薄な雰囲気も、魅力的だった。
自分にないものばかり持っているロルフは、素敵だと思った。
付き合おうといわれた時は、本当に嬉しかった。
華やかな女の子たちを虜にするあのはしばみ色の瞳が、自分に向けられるのだというだけで、胸が高鳴った。
でも、それは、全て嘘だった。
私は、利用されていただけ。
私が彼を愛しただけ。
私が知らないふりをしていただけ。
気づいていたのに、愛されているふりを通しただけ。
恋は、ここまで人を愚かにさせる。
私は、利用されていただけ。
私が彼を愛しただけ。
私が知らないふりをしていただけ。
気づいていたのに、愛されているふりを通しただけ。
恋は、ここまで人を愚かにさせる。
恋は、ひどく厄介だ。
ときに拙く、ときに儚く、ときに切なく、ときに狂おしい。
優しさをくれることも、悲しみを与えることも、星の数ほどある。
それが恋だ。
好きという感情は、ときに扱いづらい。
自在に扱うことすらままならないことだってある。
どれだけ傷ついただろう?
どれだけ苦しんだだろう?
あぁ・・・なのに、私は・・・
まだあの人の笑顔を嫌いになれてない。
ときに拙く、ときに儚く、ときに切なく、ときに狂おしい。
優しさをくれることも、悲しみを与えることも、星の数ほどある。
それが恋だ。
好きという感情は、ときに扱いづらい。
自在に扱うことすらままならないことだってある。
どれだけ傷ついただろう?
どれだけ苦しんだだろう?
あぁ・・・なのに、私は・・・
まだあの人の笑顔を嫌いになれてない。
まだ・・・まだ、好きだ。
好きで、好きで、仕方ない。
怖いくらい、全てが消えてくれない。
まだ、鮮明だ。
ぞっとするほど鮮やかだ。
息が苦しくなる。
好きで、好きで、仕方ない。
怖いくらい、全てが消えてくれない。
まだ、鮮明だ。
ぞっとするほど鮮やかだ。
息が苦しくなる。
私は、ロルフを愛した。
自分の全てを懸けて。
そのことを、うまく後悔できない。
彼を、うまく嫌いになれない。
悔しいけど、苦しいけど、一生背負っていきたいと思ってしまう。
消えてほしくないと、そう思ってしまう。
自分の全てを懸けて。
そのことを、うまく後悔できない。
彼を、うまく嫌いになれない。
悔しいけど、苦しいけど、一生背負っていきたいと思ってしまう。
消えてほしくないと、そう思ってしまう。
「ロル・・・フ・・・」
足が止まった場所にしゃがみ込み、顔を覆う。
ただ、ただ悲しい。
寒い。
体の芯まで冷えていく。
思わず、腕をさすった。
すると・・・
「・・・バ、カ野郎」
低い囁きとともに、ふわりとした感触が肩を包んだ。
足が止まった場所にしゃがみ込み、顔を覆う。
ただ、ただ悲しい。
寒い。
体の芯まで冷えていく。
思わず、腕をさすった。
すると・・・
「・・・バ、カ野郎」
低い囁きとともに、ふわりとした感触が肩を包んだ。
「バカ野郎、寒いなら、寒いって言えよ」
低く息を切らせながら、ロルフが私の目を覗き込む。
「背負うなら、俺も一緒だよ」
低く息を切らせながら、ロルフが私の目を覗き込む。
「背負うなら、俺も一緒だよ」
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…