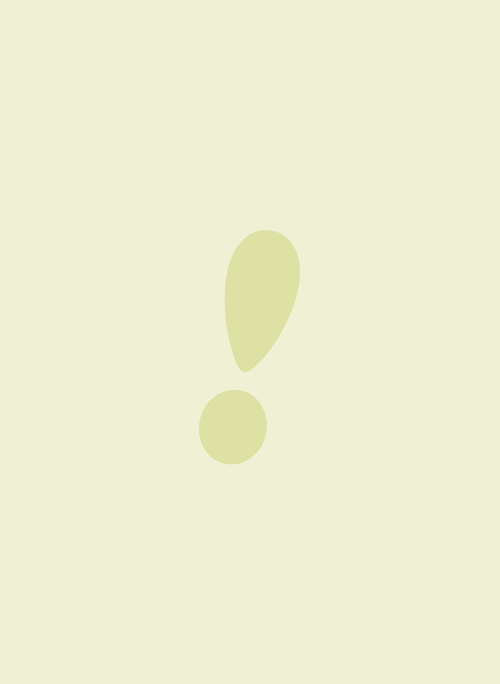柔らかい栗毛。
水色の視線。
思い出すだけで、胸に痛みが走った。
馴れ合いで受け入れたはずの恋。
彼女に少しでも近づきたくて、妥協した恋。
心のどこかに罪悪感が刻まれるような悲しい恋。
それを・・・・・・俺は、踏みにじったのだ。
水色の視線。
思い出すだけで、胸に痛みが走った。
馴れ合いで受け入れたはずの恋。
彼女に少しでも近づきたくて、妥協した恋。
心のどこかに罪悪感が刻まれるような悲しい恋。
それを・・・・・・俺は、踏みにじったのだ。
後悔して、何かが変わるわけじゃない。
過去は、決して形を変えない。
だけど・・・・・・俺は、間違っていた。
その事実だけが深く胸に刺さる。
過去は、決して形を変えない。
だけど・・・・・・俺は、間違っていた。
その事実だけが深く胸に刺さる。
叶わない想いに胸を焦がし。
愛する人のそばで微笑む友を憎み。
歪んだ感情を偽りの恋人に向け。
それでもそばにいてくれたのは、パトリシアだった。
愛する人のそばで微笑む友を憎み。
歪んだ感情を偽りの恋人に向け。
それでもそばにいてくれたのは、パトリシアだった。
なのに、俺は、それを踏みにじり、穢した。
懺悔は、ただ、彼女を傷つける悪意だった。
真実は、ただ、悲しみを深くする罪だった。
あぁ、もう本当に正しいものなんて、存在するのかすらわからない。
懺悔は、ただ、彼女を傷つける悪意だった。
真実は、ただ、悲しみを深くする罪だった。
あぁ、もう本当に正しいものなんて、存在するのかすらわからない。
どこで道をたがえた?
どこで俺は間違った?
誰も答えてはくれない。
でも、過ちなら・・・正せはしないか?
繰り返すことなく、正すことは叶わないか?
もう、どうだっていい。
この本能のまま、俺は、脳裏に刻まれた笑顔をつかみたくて駆け出した。
どこで俺は間違った?
誰も答えてはくれない。
でも、過ちなら・・・正せはしないか?
繰り返すことなく、正すことは叶わないか?
もう、どうだっていい。
この本能のまま、俺は、脳裏に刻まれた笑顔をつかみたくて駆け出した。
私たちは、深い沈黙に包まれていた。
どういう言葉を発すればいいのか、私にもアレンにも分からなかったからだ。
「・・・寒いな」
どういう言葉を発すればいいのか、私にもアレンにも分からなかったからだ。
「・・・寒いな」
「えぇ・・・」
「・・・屋根裏に行くか?」
アレンが私の傍らでそっとつぶやく。
「・・・うん」
「・・・屋根裏に行くか?」
アレンが私の傍らでそっとつぶやく。
「・・・うん」
屋根裏は、私たちの隠れ家だった。
付き合い始めた当初、人前でしゃべるのすら恥ずかしがった私のために、アレンが教えてくれた。
『テニス部の一番手にだけ引き継がれるんだ』
アレンはそう言った。
『じゃあ、ティムも知ってるの?』
『あいつはあいつでちゃんと持ってるさ』
アレンはいたずらっぽく笑った。
『昼休み、ロゼッティとティムの姿が見えないって、ヘレン先生が心配してるの知らないのか?』
付き合い始めた当初、人前でしゃべるのすら恥ずかしがった私のために、アレンが教えてくれた。
『テニス部の一番手にだけ引き継がれるんだ』
アレンはそう言った。
『じゃあ、ティムも知ってるの?』
『あいつはあいつでちゃんと持ってるさ』
アレンはいたずらっぽく笑った。
『昼休み、ロゼッティとティムの姿が見えないって、ヘレン先生が心配してるの知らないのか?』
「わ・・・久しぶりだね」
「そうだな・・・」
物陰の階段を上り、秘密の隠れ家に着いた。
最近は訪れることもなかったが、懐かしさに思わず頬が緩む。
まるで、戦争のことなど考えもしなかったあの頃のようだ。
「座れよ」
「そうだな・・・」
物陰の階段を上り、秘密の隠れ家に着いた。
最近は訪れることもなかったが、懐かしさに思わず頬が緩む。
まるで、戦争のことなど考えもしなかったあの頃のようだ。
「座れよ」
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…