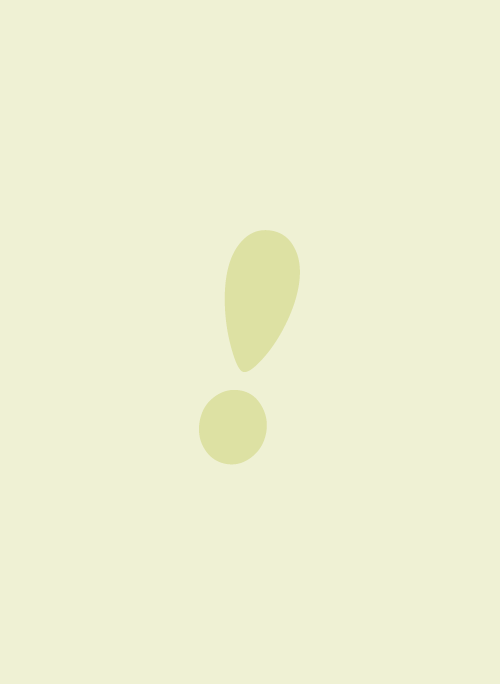頭の中が真っ白だった。
やわらかで、でも、苦いキス。
煙草の味だろうか。
苦くて、大人びた味だった。
生々しいほどの温度が唇から全身に広がった。
やわらかで、でも、苦いキス。
煙草の味だろうか。
苦くて、大人びた味だった。
生々しいほどの温度が唇から全身に広がった。
ロルフが・・・私を好き・・・?
ずっと前から・・・?
そんな・・・
じゃあ、あの日々は嘘になるの?
4人で一緒に街へ出かけ、カフェでお茶を飲んだあの日々は・・・全て嘘なの?
4人で休み時間に廊下ではしゃいだ記憶は・・・全てまやかしなの?
ねぇ・・・
ずっと前から・・・?
そんな・・・
じゃあ、あの日々は嘘になるの?
4人で一緒に街へ出かけ、カフェでお茶を飲んだあの日々は・・・全て嘘なの?
4人で休み時間に廊下ではしゃいだ記憶は・・・全てまやかしなの?
ねぇ・・・
「それ・・・どういう意味・・・?」
もう一つの衝撃が、ぐわんと耳の奥で揺れている。
「アレンの親が・・・私たちに銃を向けた・・・?」
もう一つの衝撃が、ぐわんと耳の奥で揺れている。
「アレンの親が・・・私たちに銃を向けた・・・?」
「あぁ、そうさ。アレンの父親は敵国の将軍だ。それも対外敵特別隊を編成した張本人」
「たいがいてき・・・とくべつたい・・・」
「国外の敵と戦う部隊だ・・・今も、すぐ壁の外で軍を指揮してる」
「そんな・・・」
アレンは何も言わなかった。
家のこと、故郷のこと、家族のこと・・・
それは・・・隠していたからなの・・・?
「たいがいてき・・・とくべつたい・・・」
「国外の敵と戦う部隊だ・・・今も、すぐ壁の外で軍を指揮してる」
「そんな・・・」
アレンは何も言わなかった。
家のこと、故郷のこと、家族のこと・・・
それは・・・隠していたからなの・・・?
「遺体回収の時・・・死にかけた兵士がいた」
「兵士・・・」
「敵軍の若い兵士だった。そいつを見てた壮年の男がいた」
ロルフのはしばみ色の目が遠くを見つめるように揺らぐ。
「兵士は、その男を指さして、『ジョーンズ司令万歳』と」
「ジョーンズ・・・」
「男は、茶色の短髪で、鋭い緑の目をしてた・・・」
「それは・・・」
「アレンと同じだ」
「兵士・・・」
「敵軍の若い兵士だった。そいつを見てた壮年の男がいた」
ロルフのはしばみ色の目が遠くを見つめるように揺らぐ。
「兵士は、その男を指さして、『ジョーンズ司令万歳』と」
「ジョーンズ・・・」
「男は、茶色の短髪で、鋭い緑の目をしてた・・・」
「それは・・・」
「アレンと同じだ」
私は、アレンの姿を思い出していた。
少し長めの濃い茶色の髪。
切れ長だが、目尻の下がった優しい緑色の瞳。
すっと通った鼻梁。
細い輪郭線。
へらりと笑う口元。
薄い唇のその温度さえ・・・今は、なぜか記憶から遠のいている。
少し長めの濃い茶色の髪。
切れ長だが、目尻の下がった優しい緑色の瞳。
すっと通った鼻梁。
細い輪郭線。
へらりと笑う口元。
薄い唇のその温度さえ・・・今は、なぜか記憶から遠のいている。
「ジョーンズなんて・・・よくある名前よ」
分かっているのに。
冗談でこんなことを言うロルフじゃないと知っているのに。
「アレンと同じ容貌で、同じ名で、同じ国の人間だぞ」
「あの人は何も言ってないわ」
それでも・・・
分かっているのに。
冗談でこんなことを言うロルフじゃないと知っているのに。
「アレンと同じ容貌で、同じ名で、同じ国の人間だぞ」
「あの人は何も言ってないわ」
それでも・・・
私はアレンを愛しているのだ。
「友人を大勢殺したのはあいつの父親だぞ」
「アレンではないわ」
「俺たちに銃を向けたのはあいつの家だ」
「アレン自身ではないわ」
「いい加減にしろ!」
ロルフが私の身体を壁に押しつけた。
ロルフの体重が身体にのしかかる。
「なぁ・・・死んでいったヤツらの思いはどうなるんだ・・・?」
「アレンではないわ」
「俺たちに銃を向けたのはあいつの家だ」
「アレン自身ではないわ」
「いい加減にしろ!」
ロルフが私の身体を壁に押しつけた。
ロルフの体重が身体にのしかかる。
「なぁ・・・死んでいったヤツらの思いはどうなるんだ・・・?」
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…