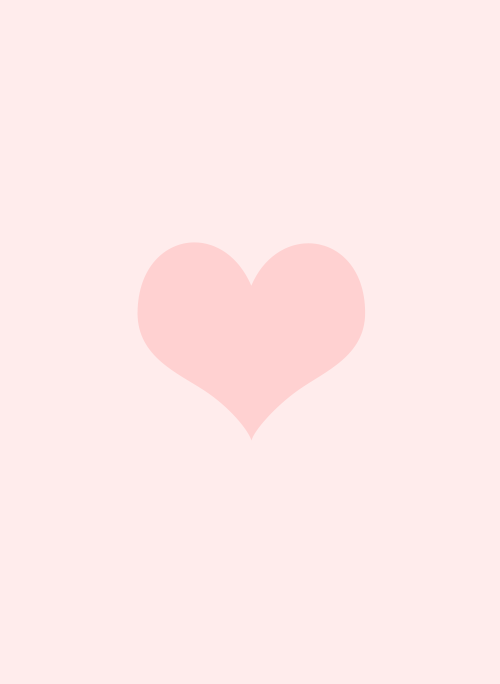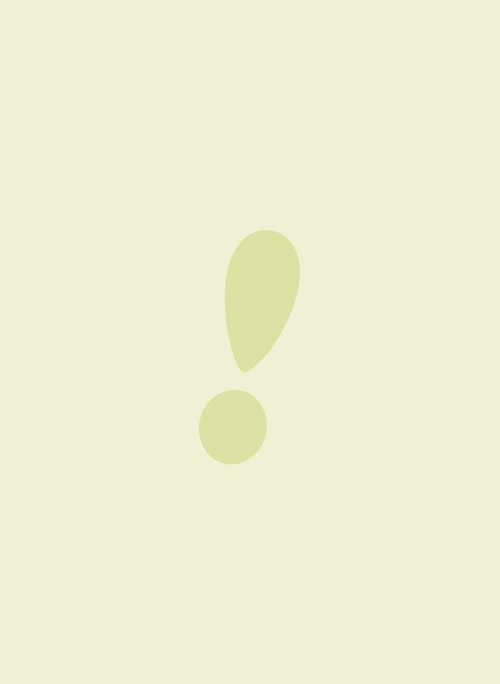「おい、アレン、しっかりしろ」
ヘンリー先生も声をかけるが、目を開けない。
「疲れてたんだろうな」
「無理もないよ、昨日から働きづめだった」
「囮だって買って出て・・・」
周囲からも同情の声が上がった。
もう戦いの熱は冷め、静かな絶望だけがその場で共有する全てになっていた。
「上で休ませます」
ふいに、ロルフが言った。
「ここじゃ、ベッドも足りてないし、ケガしてるわけじゃないなら・・・」
ヘンリー先生も声をかけるが、目を開けない。
「疲れてたんだろうな」
「無理もないよ、昨日から働きづめだった」
「囮だって買って出て・・・」
周囲からも同情の声が上がった。
もう戦いの熱は冷め、静かな絶望だけがその場で共有する全てになっていた。
「上で休ませます」
ふいに、ロルフが言った。
「ここじゃ、ベッドも足りてないし、ケガしてるわけじゃないなら・・・」
冷静な判断だと思った。
「そうだな・・・静かなところで休ませてやれ」
「はい」
淡々とした表情で、ロルフがアレンの腕を抱える。
横には、半泣きのナタリーが付き添った。
「う・・・ぐ・・・ひぐ・・・っ」
「泣くなよ、ナタリー」
「ひぅ・・・っ、だって・・・っ」
いつも気丈なナタリーが泣きじゃくっているのに、いつもおちゃらけているロルフが、ただ静かな目をしていた。
「そうだな・・・静かなところで休ませてやれ」
「はい」
淡々とした表情で、ロルフがアレンの腕を抱える。
横には、半泣きのナタリーが付き添った。
「う・・・ぐ・・・ひぐ・・・っ」
「泣くなよ、ナタリー」
「ひぅ・・・っ、だって・・・っ」
いつも気丈なナタリーが泣きじゃくっているのに、いつもおちゃらけているロルフが、ただ静かな目をしていた。
その静けさで、ふいに胸が苦しくなる。
この人は行ってしまう。
明日になれば、もう離れなければならない。
それぞれ違う国を故郷と呼ぶのだから仕方がないと諦めきれる程度の想いではなかった。
自分の持つもの全てを捨ててでも、愛し抜きたい人だった。
この人は行ってしまう。
明日になれば、もう離れなければならない。
それぞれ違う国を故郷と呼ぶのだから仕方がないと諦めきれる程度の想いではなかった。
自分の持つもの全てを捨ててでも、愛し抜きたい人だった。
ただ、その後ろ姿を目に焼き付けようと思った。
あの人が誰を想っていてもいいから、と。
今、生きていてさえくれればいいから、と。
儚い思いを刻みつけるように、私はロルフの背中を脳裏に写した。
あの人が誰を想っていてもいいから、と。
今、生きていてさえくれればいいから、と。
儚い思いを刻みつけるように、私はロルフの背中を脳裏に写した。
2階までアレンを運ぶ。
細身なヤツだと思っていたが、抱えた身体は意外と筋肉質だった。
軍人の息子なだけある。
その傍らですすり泣くナタリーに目をやった。
泣かせるなよな、とアレンに語りかける。
恋人を泣かせる罪は重いんだぜ、と。
細身なヤツだと思っていたが、抱えた身体は意外と筋肉質だった。
軍人の息子なだけある。
その傍らですすり泣くナタリーに目をやった。
泣かせるなよな、とアレンに語りかける。
恋人を泣かせる罪は重いんだぜ、と。
アレンの身体をベッドに横たえてから、息をついた。
「はぁ・・・」
自分も疲れていたのだ、と自覚した。
神経を麻痺させて戦ってきた代償が、体中を痛めつけてくる。
「大丈夫?ロルフ・・・」
「はぁ・・・」
自分も疲れていたのだ、と自覚した。
神経を麻痺させて戦ってきた代償が、体中を痛めつけてくる。
「大丈夫?ロルフ・・・」
「ごめんなさいね、無理させて・・・」
「いや・・・ナタリーも疲れてるだろ、少し休めよ」
「えぇ・・・そうね・・・」
薔薇色の頬が、いつになく青い。
疲れか、不安か、それとも死へのおびえか・・・
ナタリーがアレンを見る目は、ひどく静謐だった。
「いや・・・ナタリーも疲れてるだろ、少し休めよ」
「えぇ・・・そうね・・・」
薔薇色の頬が、いつになく青い。
疲れか、不安か、それとも死へのおびえか・・・
ナタリーがアレンを見る目は、ひどく静謐だった。
「外の空気吸おうぜ」
「えぇ・・・」
死んだように眠るアレンを気にしつつも、ナタリーは立ち上がった。
肩を並べて、廊下を歩き出す。
『あの子かわいくないか?』
『どの子?』
『ほら、奥の金髪!』
『あぁ、新聞部の・・・』
『アレン、知ってんのか?』
『有名だよ。頭がよくて、すごくいい文章を書くから』
『へぇ』
『ナタリー・ロムニエルだろ』
「ひでぇもんだな・・・」
大砲を受けた廊下や教室には、アレンと恋心に胸を躍らせた日々の面影はなかった。
「えぇ・・・」
死んだように眠るアレンを気にしつつも、ナタリーは立ち上がった。
肩を並べて、廊下を歩き出す。
『あの子かわいくないか?』
『どの子?』
『ほら、奥の金髪!』
『あぁ、新聞部の・・・』
『アレン、知ってんのか?』
『有名だよ。頭がよくて、すごくいい文章を書くから』
『へぇ』
『ナタリー・ロムニエルだろ』
「ひでぇもんだな・・・」
大砲を受けた廊下や教室には、アレンと恋心に胸を躍らせた日々の面影はなかった。
「そうね・・・」
「生き残ったのは・・・奇跡だよな・・・」
「えぇ・・・」
ナタリーの金色の髪が風に揺れる。
青い眼差しの光る横顔が絶望に陰る。
自覚しているのかそうでないのか。
全てがなまめかしく見える女というのは、少なからずいるものだ。
ある種の男を惹きつけてやまず、ぞくりとするほど妖艶な空気に包まれている。
そして、そういう女に惚れる男も、少なからずいるのだ。
あっけらかんと見せる笑顔。
素朴な癖毛の揺れ。
そんな隙間から、ふとのぞく色気に溺れる男というのも・・・確かにいる。
「叶うなら、みんなと一緒に生きていきたかったわ・・・」
そうつぶやいて、目を伏せる仕草が、ひどく綺麗に映って・・・
そこでなんだか・・・
俺は・・・
理性が限界まで飛んだ。
「生き残ったのは・・・奇跡だよな・・・」
「えぇ・・・」
ナタリーの金色の髪が風に揺れる。
青い眼差しの光る横顔が絶望に陰る。
自覚しているのかそうでないのか。
全てがなまめかしく見える女というのは、少なからずいるものだ。
ある種の男を惹きつけてやまず、ぞくりとするほど妖艶な空気に包まれている。
そして、そういう女に惚れる男も、少なからずいるのだ。
あっけらかんと見せる笑顔。
素朴な癖毛の揺れ。
そんな隙間から、ふとのぞく色気に溺れる男というのも・・・確かにいる。
「叶うなら、みんなと一緒に生きていきたかったわ・・・」
そうつぶやいて、目を伏せる仕草が、ひどく綺麗に映って・・・
そこでなんだか・・・
俺は・・・
理性が限界まで飛んだ。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…