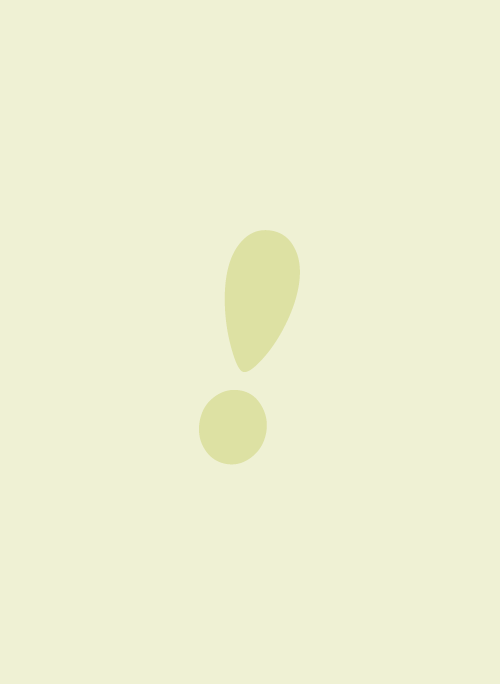「っ・・・!」
「な・・・何・・・っ!?」
大きな爆音が耳をつんざいた。
その音を皮切りに、激しい銃声が続く。
「何よ、これ・・・・・・っ!?」
パトリシアが私にしがみつく。
「国境より敵軍侵入っ!」
「生徒は直ちに避難しなさい!」
先生たちが悲鳴を上げながら、みんなを誘導する。
私たちのいる校庭には、寮から登校中の生徒たちが大勢いた。
「な・・・何・・・っ!?」
大きな爆音が耳をつんざいた。
その音を皮切りに、激しい銃声が続く。
「何よ、これ・・・・・・っ!?」
パトリシアが私にしがみつく。
「国境より敵軍侵入っ!」
「生徒は直ちに避難しなさい!」
先生たちが悲鳴を上げながら、みんなを誘導する。
私たちのいる校庭には、寮から登校中の生徒たちが大勢いた。
「そ・・・んな・・・」
パトリシアが、呆然として膝をつく。
「ミス・バークス!早く逃げなさい!」
顔を引きつらせ叫ぶのは、私たちのクラス担任のヘレン・ウィンストン先生だ。
教師陣の中でも、落ち着いた雰囲気で知られるベテランのヘレン先生が、真っ青な顔をしている。
しかし、パトリシアは、先生の様子など気にもとめず、泣き叫んだ。
「そんな・・・嘘よ・・・」
パトリシアの国の兵たちが、学院に攻め込もうとしていた。
パトリシアが、呆然として膝をつく。
「ミス・バークス!早く逃げなさい!」
顔を引きつらせ叫ぶのは、私たちのクラス担任のヘレン・ウィンストン先生だ。
教師陣の中でも、落ち着いた雰囲気で知られるベテランのヘレン先生が、真っ青な顔をしている。
しかし、パトリシアは、先生の様子など気にもとめず、泣き叫んだ。
「そんな・・・嘘よ・・・」
パトリシアの国の兵たちが、学院に攻め込もうとしていた。
ついに・・・始まったんだ・・・
戦争が・・・
「パトリシア、逃げよう」
私は、必死でパトリシアの手を取る。
校門から、砲弾が撃ち込まれる。
怖い。
怖い。
死にたくない・・・
ただそれだけの思いで走った。
戦争が・・・
「パトリシア、逃げよう」
私は、必死でパトリシアの手を取る。
校門から、砲弾が撃ち込まれる。
怖い。
怖い。
死にたくない・・・
ただそれだけの思いで走った。
ひたすら走って、校舎の中に入ったときには、涙が止まらなかった。
怖くて怖くてたまらなかった。
「はぁ、はぁっ・・・」
「あ、アグネス・・・ノエラ・・・」
「ナ、タリー・・・ィ」
4人で、肩を抱き合って泣いた。
銃弾の隙を走ってきたせいで、顔がすすだらけだった。
怖くて怖くてたまらなかった。
「はぁ、はぁっ・・・」
「あ、アグネス・・・ノエラ・・・」
「ナ、タリー・・・ィ」
4人で、肩を抱き合って泣いた。
銃弾の隙を走ってきたせいで、顔がすすだらけだった。
寮から、わずか数百メートルほどの校舎までの道のり。
校門をくぐった生徒と、わずかに遅かった生徒とで、命が決まった。
強固な校門が閉鎖され、そこから校舎までの範囲は守られたようだが、その外の国境近くは火の海だ。
敵軍は、私たちの寮を乗っ取り、そこから籠城戦に持ち込むことにしたらしい。
校門に入っていたかどうかで、生死の境が決定した・・・。
その恐怖と安堵で、どうしていいか分からず、私たちは泣いていた。
校門をくぐった生徒と、わずかに遅かった生徒とで、命が決まった。
強固な校門が閉鎖され、そこから校舎までの範囲は守られたようだが、その外の国境近くは火の海だ。
敵軍は、私たちの寮を乗っ取り、そこから籠城戦に持ち込むことにしたらしい。
校門に入っていたかどうかで、生死の境が決定した・・・。
その恐怖と安堵で、どうしていいか分からず、私たちは泣いていた。
戦争が・・・始まった・・・
止まらない涙に、足の震え。
ただそれだけが、戦いという悲惨な現実を物語っていた。
止まらない涙に、足の震え。
ただそれだけが、戦いという悲惨な現実を物語っていた。
「あー、寒いなー」
もう一枚シャツを重ねればよかったと後悔する。
いつもより、気温が低い。
身体を温めようと、テニスラケットをひゅんと一振り。
いつも通りの手応えと重み。
低血圧の恋人は、ちゃんと起きられただろうか。
金色の髪に寝癖がつく様子を想像して、顔がにやけた。
かわいいだろうな、と思ってしまうのは、俺だけの秘密だ。
もう一枚シャツを重ねればよかったと後悔する。
いつもより、気温が低い。
身体を温めようと、テニスラケットをひゅんと一振り。
いつも通りの手応えと重み。
低血圧の恋人は、ちゃんと起きられただろうか。
金色の髪に寝癖がつく様子を想像して、顔がにやけた。
かわいいだろうな、と思ってしまうのは、俺だけの秘密だ。
テニスコートでは、毎朝の光景だ。
テニス部のみんなが、練習に励んでいる。
ダブルスでペアを組んでいるティム・ヨハネスバーグが、ちょっと長すぎるあごをなでながら俺に近づいてきた。
「アレン、今朝、北の方で変な音がしなかったか?」
「北の方で?」
「あぁ、なんか・・・爆発みたいな」
「さぁ・・・」
「ま、国境には軍が常駐してるし、大丈夫か」
1人で納得して、ティムがうなずく。
爆発音・・・ね。
テニス部のみんなが、練習に励んでいる。
ダブルスでペアを組んでいるティム・ヨハネスバーグが、ちょっと長すぎるあごをなでながら俺に近づいてきた。
「アレン、今朝、北の方で変な音がしなかったか?」
「北の方で?」
「あぁ、なんか・・・爆発みたいな」
「さぁ・・・」
「ま、国境には軍が常駐してるし、大丈夫か」
1人で納得して、ティムがうなずく。
爆発音・・・ね。
北の方・・・といえば、国境だ。
そして、寮がある。
国境地帯に軍が常駐するようになったのは、ここ数ヶ月でのことだ。
隣国から敵軍が攻めてこないように、と。
しかし、彼らの言う敵軍とは、俺たちの祖国の軍のことだ。
祖国の軍から身を守るために、異国の兵に防衛される皮肉には、思わず苦笑いしてしまう。
そして、寮がある。
国境地帯に軍が常駐するようになったのは、ここ数ヶ月でのことだ。
隣国から敵軍が攻めてこないように、と。
しかし、彼らの言う敵軍とは、俺たちの祖国の軍のことだ。
祖国の軍から身を守るために、異国の兵に防衛される皮肉には、思わず苦笑いしてしまう。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…