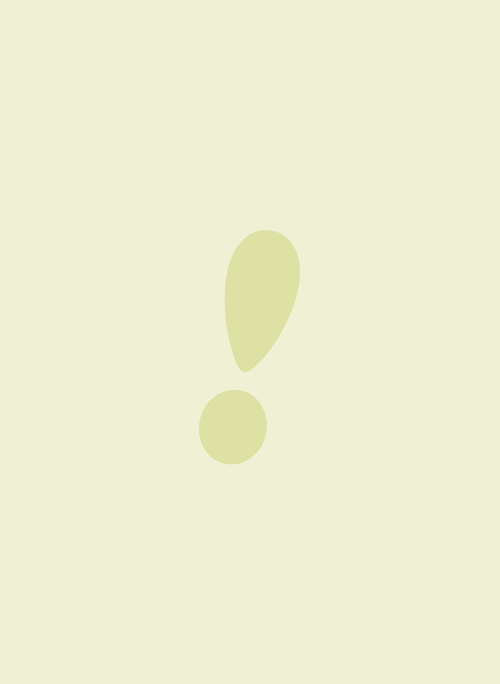しかし、鉄に似た血のにおいで、その思惑はかき消される。
俺は、ただ瀕死の同胞を背負いながら、アレンの陰った表情を気に懸けるだけだった。
俺は、ただ瀕死の同胞を背負いながら、アレンの陰った表情を気に懸けるだけだった。
傷ついた仲間たちに食事を配る。
せめてもの温かいスープと、パンを持って歩いた。
みんな一様に疲れ切っており、体中に刻まれた傷が戦いのすさまじさを物語っていた。
せめてもの温かいスープと、パンを持って歩いた。
みんな一様に疲れ切っており、体中に刻まれた傷が戦いのすさまじさを物語っていた。
体育館に、うめき声が響き渡る。
母を呼ぶ声、部活仲間を呼ぶ声、恋人を呼ぶ声・・・
生きたい、死にたくないと命にすがる声・・・
気が狂いそうな現実だった。
そして、その現実の中、少女が駆け抜けてきた。
母を呼ぶ声、部活仲間を呼ぶ声、恋人を呼ぶ声・・・
生きたい、死にたくないと命にすがる声・・・
気が狂いそうな現実だった。
そして、その現実の中、少女が駆け抜けてきた。
「電報です!電報が軍から届きました!」
新聞部の1年生、アリサ・ホワイトだった。
「明日の夕方までに到着の予定だそうです!」
「何っ!?」
喜びより衝撃が勝った。
新聞部の1年生、アリサ・ホワイトだった。
「明日の夕方までに到着の予定だそうです!」
「何っ!?」
喜びより衝撃が勝った。
「助けが来るのか・・・?」
「軍が救いに来るのか?」
「終わるのか?」
「死ななくてすむのか?」
みんなそれぞれが疑問を吐く。
「俺たちは・・・どうなるんだ・・・?」
「軍が救いに来るのか?」
「終わるのか?」
「死ななくてすむのか?」
みんなそれぞれが疑問を吐く。
「俺たちは・・・どうなるんだ・・・?」
横でつぶやいたのは、ロルフだった。
アリサに歩み寄り、細い肩に手をかける。
「おい、お前・・・」
「は、はい・・・!」
のっぽな上級生に肩をつかまれ、アリサがすくむ。
「電報には、何て書いてある?俺たち・・・俺たち、留学生については何て?」
アリサに歩み寄り、細い肩に手をかける。
「おい、お前・・・」
「は、はい・・・!」
のっぽな上級生に肩をつかまれ、アリサがすくむ。
「電報には、何て書いてある?俺たち・・・俺たち、留学生については何て?」
「落ち着いて、ロルフ。アリサがおびえてるわ」
「パトリシア・・・」
「アリサ、教えて。何て書いてあるの?」
「あ・・・あの・・・」
アリサがおそるおそるという表情で電報を差し出した。
「こ、これです・・・」
「パトリシア・・・」
「アリサ、教えて。何て書いてあるの?」
「あ・・・あの・・・」
アリサがおそるおそるという表情で電報を差し出した。
「こ、これです・・・」
『アスユウガタツク。リュウガクセイクニヘカエス』
「明日夕方着く・・・留学生国へ返す・・・」
ロルフが読み上げた。
「明日、軍がここへ着いた時点で、俺たちは捕虜になって、国元へ戻されるってワケか・・・」
「明日夕方着く・・・留学生国へ返す・・・」
ロルフが読み上げた。
「明日、軍がここへ着いた時点で、俺たちは捕虜になって、国元へ戻されるってワケか・・・」
「冗談じゃねぇや・・・」
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…