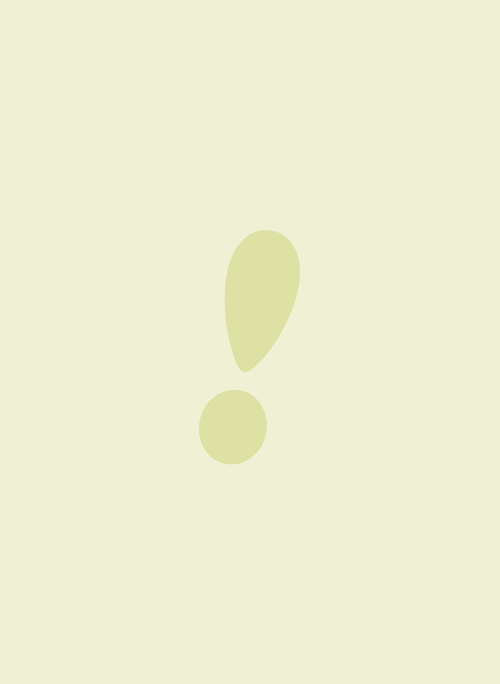見ていて痛ましいほどだった。
どうしてこんなに心が痛むのか分からないけれど、ただ悲しかった。
アレンが泣いているような気がしたから。
どうしてこんなに心が痛むのか分からないけれど、ただ悲しかった。
アレンが泣いているような気がしたから。
「アレン・・・」
「お願いします」
「アレン・ヘンリー・ジョーンズ、顔を上げなさい」
ヘレン先生が静かに言った。
アレンは、素直に顔を上げる。
さらりとした茶色の髪が揺れた。
「はい・・・」
「分かりました。倉庫から銃を出しましょう」
「お願いします」
「アレン・ヘンリー・ジョーンズ、顔を上げなさい」
ヘレン先生が静かに言った。
アレンは、素直に顔を上げる。
さらりとした茶色の髪が揺れた。
「はい・・・」
「分かりました。倉庫から銃を出しましょう」
「ヘレン!」
「分かっているわ、オーギュスト。でも・・・」
ヘレン先生は、オーギュスト先生を見た。
「この子たちの気持ちももっともです」
「分かっているわ、オーギュスト。でも・・・」
ヘレン先生は、オーギュスト先生を見た。
「この子たちの気持ちももっともです」
「大勢の教え子が死んで・・・それでもなお、あの国が憎くないかと問われれば・・・答えは否よ」
ヘレン先生が、ため息をついた。
「ただし、よくお聞きなさい、アレン」
「はい」
「敵軍からの攻撃があってからです」
「え・・・」
「あくまで銃は自己防衛のため。それを忘れないように」
「・・・分かりました」
ヘレン先生が、ため息をついた。
「ただし、よくお聞きなさい、アレン」
「はい」
「敵軍からの攻撃があってからです」
「え・・・」
「あくまで銃は自己防衛のため。それを忘れないように」
「・・・分かりました」
アレンは、わずかに迷いを見せながらもうなずいた。
「おい、エミール、ロルフ、ダニエル、行こうぜ」
アレンが、こちらを見ないまま歩き出す。
いつもは、ナタリーがいれば、何だって一番の優先順位なのに。
「あ、アレン、何を・・・」
「バカ、戦いに備えるぞ」
いつものアレンらしくない声で、背中が遠ざかっていった。
「おい、エミール、ロルフ、ダニエル、行こうぜ」
アレンが、こちらを見ないまま歩き出す。
いつもは、ナタリーがいれば、何だって一番の優先順位なのに。
「あ、アレン、何を・・・」
「バカ、戦いに備えるぞ」
いつものアレンらしくない声で、背中が遠ざかっていった。
「おい、アレン!」
思わず呼びかけた。
「・・・何だ?」
「お前本当に・・・いいのか?」
思わず呼びかけた。
「・・・何だ?」
「お前本当に・・・いいのか?」
だって・・・お前は・・・
「お前が守るべきものは・・・」
いくら迷いなく歩いているように見せたって、本当は違うだろ?
「お前が守るべきものは・・・」
いくら迷いなく歩いているように見せたって、本当は違うだろ?
「あのさ・・・ロルフ」
「何だ?」
「・・・黙っててくれるか?」
倉庫へと足早に向かうアレンが、静かに振り返った。
底知れぬ深い闇がアレンの瞳に浮かんでいる。
こんな目のアレンは初めてだった。
いや、もともとアレンは、厳しい顔つきをしている。
ナタリーには穏やかな眼差ししか向けないが、いつもはきつい目つきだ。
テニスの試合の時しかり。
勉強中しかり。
生真面目な性格を反映したような鋭い緑の目は、いつもぎらついている。
人を殺しそうな顔してる、と言ったのは、クラスメイトだったっけか。
とがり気味の顎や、きりりとした眉が、一層その印象をきつくしている。
ナタリーのクラスメイトであるチャールズは、「目が合っただけで殺されそうだ」とアレンのことを噂していた。
テニスの練習をさぼって、アレンに厳しく怒られた後輩は、いまだにアレンと口をきくのが苦手だという。
俺自身、ルームメイトになったときは、こんな怖い顔をしたヤツと一緒にやっていけるだろうかと本気で不安になった。
そう、根本的な部分で、アレンは殺気立った人間なのだ。
「何だ?」
「・・・黙っててくれるか?」
倉庫へと足早に向かうアレンが、静かに振り返った。
底知れぬ深い闇がアレンの瞳に浮かんでいる。
こんな目のアレンは初めてだった。
いや、もともとアレンは、厳しい顔つきをしている。
ナタリーには穏やかな眼差ししか向けないが、いつもはきつい目つきだ。
テニスの試合の時しかり。
勉強中しかり。
生真面目な性格を反映したような鋭い緑の目は、いつもぎらついている。
人を殺しそうな顔してる、と言ったのは、クラスメイトだったっけか。
とがり気味の顎や、きりりとした眉が、一層その印象をきつくしている。
ナタリーのクラスメイトであるチャールズは、「目が合っただけで殺されそうだ」とアレンのことを噂していた。
テニスの練習をさぼって、アレンに厳しく怒られた後輩は、いまだにアレンと口をきくのが苦手だという。
俺自身、ルームメイトになったときは、こんな怖い顔をしたヤツと一緒にやっていけるだろうかと本気で不安になった。
そう、根本的な部分で、アレンは殺気立った人間なのだ。
その視線を向けられて、鳥肌が立った。
言ってはならない。
触れてはならない。
そういう真実が、この世にはあるのだ。
忘れていた・・・
言ってはならない。
触れてはならない。
そういう真実が、この世にはあるのだ。
忘れていた・・・
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…