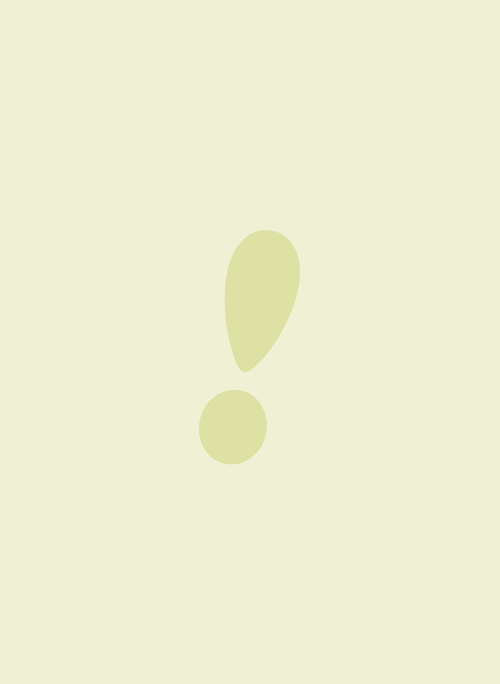俺の守りたいものは、何だ?
俺が守ろうとしているものは何だ?
切れた唇をかみながら、自問する。
答えは出ず、ただ怒りに似た痛みが頬をすべるだけだった。
俺が守ろうとしているものは何だ?
切れた唇をかみながら、自問する。
答えは出ず、ただ怒りに似た痛みが頬をすべるだけだった。
窓ガラスの割れる音で目が覚めた。
何が起こったのか、と思わず身を起こすと隣に寝ているはずのナタリーがいない。
もしかして、また襲撃が・・・?
そう思って身体をこわばらせていると、アグネスが駆け込んできた。
「パトリシア!」
「アグネス・・・、どうしたの?」
「アレンが喧嘩してる!」
「誰と?」
何が起こったのか、と思わず身を起こすと隣に寝ているはずのナタリーがいない。
もしかして、また襲撃が・・・?
そう思って身体をこわばらせていると、アグネスが駆け込んできた。
「パトリシア!」
「アグネス・・・、どうしたの?」
「アレンが喧嘩してる!」
「誰と?」
喧嘩という単語とアレンがうまく結びつかなかった。
アレンは、好き好んで人と喧嘩するようなタイプではない。
たぶん、これは誰に聞いても同じ意見だろう。
テニスに打ち込むときは、血気盛んで、とんでもなく激しいボレーを決めてくるという話だ。
でも、日常生活では、ごくおとなしい生徒。
先生たちの意見も、手のかからない生徒ということで一致しているだろう。
そのアレンが喧嘩をする相手・・・
「エミールとよ!エミール・アンダーソン!」
「エミールと!?」
アレンは、好き好んで人と喧嘩するようなタイプではない。
たぶん、これは誰に聞いても同じ意見だろう。
テニスに打ち込むときは、血気盛んで、とんでもなく激しいボレーを決めてくるという話だ。
でも、日常生活では、ごくおとなしい生徒。
先生たちの意見も、手のかからない生徒ということで一致しているだろう。
そのアレンが喧嘩をする相手・・・
「エミールとよ!エミール・アンダーソン!」
「エミールと!?」
エミールとアレンは、去年同じクラスだった。
部活動も、同じテニス部に所属している。
でも、たしかにそこまで親しいとは言えない。
もっというなら、エミールの恋人であるミラベルは、かつてアレンの交際相手だった。
2人の距離が縮まらないのは、そういう恋愛事情があるからかもしれない。
いろいろと思いを巡らせながら、階段を降りていくと、その現場に行き当たった。
荒い息を吐くエミール、それに、頭から血を流すアレン。
それだけ見れば、何があったかは明白だった。
部活動も、同じテニス部に所属している。
でも、たしかにそこまで親しいとは言えない。
もっというなら、エミールの恋人であるミラベルは、かつてアレンの交際相手だった。
2人の距離が縮まらないのは、そういう恋愛事情があるからかもしれない。
いろいろと思いを巡らせながら、階段を降りていくと、その現場に行き当たった。
荒い息を吐くエミール、それに、頭から血を流すアレン。
それだけ見れば、何があったかは明白だった。
おびえた表情で眉をひそめるナタリー。
寝癖のついた髪のままのロルフ。
そのほか、何人かの生徒が集まってきている。
そして、ヘンリー・リンドグレーン先生が険しい顔つきで状況を見ていた。
寝癖のついた髪のままのロルフ。
そのほか、何人かの生徒が集まってきている。
そして、ヘンリー・リンドグレーン先生が険しい顔つきで状況を見ていた。
「エミール、そのへんにしとけ」
ヘンリー先生は、あくまで淡々としている。
妙に後ろがざわついたと思って振り返ると、先生たちが集まっていた。
「ヘンリー、これは・・・」
「アレン、どうしたの!?」
オーギュスト先生に、ヘレン先生。
ジョゼフ先生も。
それぞれ驚いた顔でアレンを見ている。
無理もない。
アレンは、問題を起こすような生徒ではないからだ。
ヘンリー先生は、あくまで淡々としている。
妙に後ろがざわついたと思って振り返ると、先生たちが集まっていた。
「ヘンリー、これは・・・」
「アレン、どうしたの!?」
オーギュスト先生に、ヘレン先生。
ジョゼフ先生も。
それぞれ驚いた顔でアレンを見ている。
無理もない。
アレンは、問題を起こすような生徒ではないからだ。
「いえ、平気です」
「平気ってあなた・・・」
「本当に大丈夫なんです」
アレンは、首を振った。
しんどそうな表情だった。
「・・・銃の使用許可を出してください」
「平気ってあなた・・・」
「本当に大丈夫なんです」
アレンは、首を振った。
しんどそうな表情だった。
「・・・銃の使用許可を出してください」
「・・・アレン」
横で声を上げたのはロルフだった。
「お前・・・」
「エミールの言う通りかもしれません。・・・俺たちは、かけがえのない友人を殺された」
アレンが唇をかみしめる。
「戦争という大義名分があるにせよ、それは許しがたい行為です」
横で声を上げたのはロルフだった。
「お前・・・」
「エミールの言う通りかもしれません。・・・俺たちは、かけがえのない友人を殺された」
アレンが唇をかみしめる。
「戦争という大義名分があるにせよ、それは許しがたい行為です」
アレンは、穏やかな性格だ。
ナタリーが怒っても、ロルフが不機嫌になっても、いつものんびりと微笑んでいるような。
そのアレンが、武力行使を望むとは。
「それに、自分の命さえ危ういときに、殺人の罪などには気を向けていられません」
どうか、とアレンは先生たちに頭を下げた。
「どうか、銃を出してください」
ナタリーが怒っても、ロルフが不機嫌になっても、いつものんびりと微笑んでいるような。
そのアレンが、武力行使を望むとは。
「それに、自分の命さえ危ういときに、殺人の罪などには気を向けていられません」
どうか、とアレンは先生たちに頭を下げた。
「どうか、銃を出してください」
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…