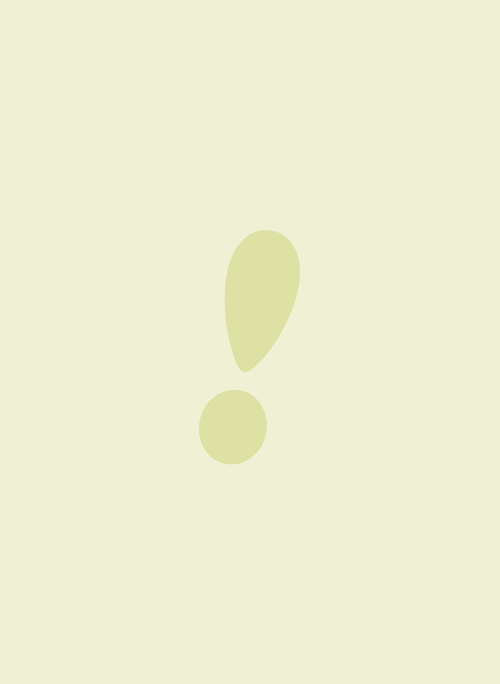そのとき・・・
ガッシャー・・・ンッ!
何かの割れる音がした。
ガッシャー・・・ンッ!
何かの割れる音がした。
口の中に鉄の味を感じた。
手でぬぐってみると、唇を切っていた。
ついでに言うと、頭も痛い。
さっき割れたガラスで切ったかもしれない。
「お前がそんな臆病者だったなんてな、アレン!」
手でぬぐってみると、唇を切っていた。
ついでに言うと、頭も痛い。
さっき割れたガラスで切ったかもしれない。
「お前がそんな臆病者だったなんてな、アレン!」
怒鳴られて、また頭が痛くなった。
「落ち着け、エミール」
「これが落ち着いてられるってのか!」
目の前で激昂しているのは、部活仲間のエミール・アンダーソンだ。
エミールは、俺より小柄で、格闘術の心得もない。
いたずらに拳を振り回してくるだけの攻撃を避けたら、エミールがケガをする危険もあった。
だから、とりあえず殴られてみた。
でも、こんなに憤りの声を上げられるくらいなら、避けて殴り返してもよかったかもしれない。
「落ち着け、エミール」
「これが落ち着いてられるってのか!」
目の前で激昂しているのは、部活仲間のエミール・アンダーソンだ。
エミールは、俺より小柄で、格闘術の心得もない。
いたずらに拳を振り回してくるだけの攻撃を避けたら、エミールがケガをする危険もあった。
だから、とりあえず殴られてみた。
でも、こんなに憤りの声を上げられるくらいなら、避けて殴り返してもよかったかもしれない。
「俺は・・・援軍が来るまで攻撃はしない方がいいと言っただけだ」
「それが臆病って言うんだよ!」
もともとエミールとはそりが合わなかったが・・・
ときは、十数分前にさかのぼる。
「それが臆病って言うんだよ!」
もともとエミールとはそりが合わなかったが・・・
ときは、十数分前にさかのぼる。
「銃の使用許可をください」
エミールがヘンリー先生にそう申し出た。
「エミール・・・」
「それは・・・」
「・・・わけを聞かせろ、エミール」
先生は、あくまで冷静だった。
エミールがヘンリー先生にそう申し出た。
「エミール・・・」
「それは・・・」
「・・・わけを聞かせろ、エミール」
先生は、あくまで冷静だった。
「俺は・・・友達を大勢失いました。あいつらが憎くて、許せないんです」
エミールは、ぎりりとまなじりをつり上げる。
「自分の目の前で友達を殺したヤツらがのうのうとしてるのが我慢できません!」
エミールは、ぎりりとまなじりをつり上げる。
「自分の目の前で友達を殺したヤツらがのうのうとしてるのが我慢できません!」
「なるほどな・・・」
「あ・・・あの・・・」
口を挟むつもりはなかったが、思わず声になってしまった。
「それは、間違ってると思う・・・」
「あ・・・あの・・・」
口を挟むつもりはなかったが、思わず声になってしまった。
「それは、間違ってると思う・・・」
「何だって?」
エミールが、引きつった形相でこちらをにらむ。
「あぁ、アレン、お前はあっちの出身だったなぁ」
「いや・・・違う、そうじゃなくて・・・」
「何が違うんだ」
「俺の家は・・・代々軍人の家系だ」
エミールが、引きつった形相でこちらをにらむ。
「あぁ、アレン、お前はあっちの出身だったなぁ」
「いや・・・違う、そうじゃなくて・・・」
「何が違うんだ」
「俺の家は・・・代々軍人の家系だ」
「・・・それがどうした」
「だから、家には、いつも周辺諸国の地図があった」
「何が言いたいんだ?」
「この国境近くには、3つほど砦がある」
「砦・・・」
「軍が駐在してるはずだ。さすがに、敵軍の侵入は知ってるだろう」
「どういうことだ?」
「もうしばらくすれば、援軍が来るはずだ」
伝えることが、誠実さだと思っていた。
「だから、家には、いつも周辺諸国の地図があった」
「何が言いたいんだ?」
「この国境近くには、3つほど砦がある」
「砦・・・」
「軍が駐在してるはずだ。さすがに、敵軍の侵入は知ってるだろう」
「どういうことだ?」
「もうしばらくすれば、援軍が来るはずだ」
伝えることが、誠実さだと思っていた。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…