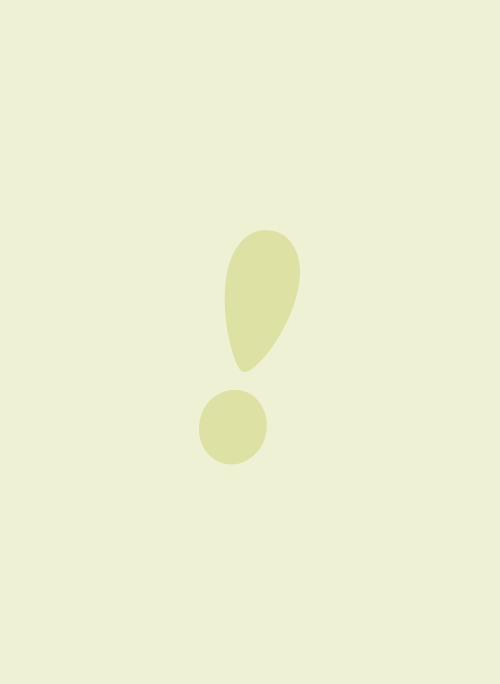アレンやロルフがひどくくたびれた様子で帰ってきたのは、真夜中過ぎだった。
学校の外では、何人もの生徒の遺体が回収されたらしい。
私たちも、校舎内で負傷者の看護に当たっていたが、助かった人は少なかった。
それはもう・・・気が狂いそうなほど。
学校の外では、何人もの生徒の遺体が回収されたらしい。
私たちも、校舎内で負傷者の看護に当たっていたが、助かった人は少なかった。
それはもう・・・気が狂いそうなほど。
日常はもう戻っては来ない。
ミルドレッドが新聞を掲示板に張り出す朝も。
ピーターが学生食堂で誰かのパンを取ろうとする昼休みも。
アンドリューが居眠りして先生に叱られる午後も。
ルドガーとキャサリンが照れくさそうに帰路をともにする夕暮れも。
もう何も帰っては来ない。
ミルドレッドが新聞を掲示板に張り出す朝も。
ピーターが学生食堂で誰かのパンを取ろうとする昼休みも。
アンドリューが居眠りして先生に叱られる午後も。
ルドガーとキャサリンが照れくさそうに帰路をともにする夕暮れも。
もう何も帰っては来ない。
ただただ頭が重かった。
つらく、悲しく、切なかった。
もっと、生きていたかっただろうに。
つらく、悲しく、切なかった。
もっと、生きていたかっただろうに。
実際、死の間際にそう言い残した生徒は少なくなかった。
「もっと生きたいのに」
「死にたくない」
「母さんに会いたい」
「まだやりたいことたくさんあるのに」
胸を締め付けられるほど切なく、苦しい願いだった。
「もっと生きたいのに」
「死にたくない」
「母さんに会いたい」
「まだやりたいことたくさんあるのに」
胸を締め付けられるほど切なく、苦しい願いだった。
「遺体の処理をしなければ・・・ね」
ふいに声がして横を見ると、ヘレン先生だった。
「先生・・・」
「ナタリー、疲れたでしょう。顔が青いわ」
「遺体の処理って・・・」
「今は冬だから何とかなってるけど、遺体の腐敗はいやでも進むわ」
ヘレン先生が眉を寄せる。
友人の死が、また現実味を帯びて心に寄せてくる。
ふいに声がして横を見ると、ヘレン先生だった。
「先生・・・」
「ナタリー、疲れたでしょう。顔が青いわ」
「遺体の処理って・・・」
「今は冬だから何とかなってるけど、遺体の腐敗はいやでも進むわ」
ヘレン先生が眉を寄せる。
友人の死が、また現実味を帯びて心に寄せてくる。
「今日はもう休みなさい。ひどい顔色よ」
「眠れないんです・・・」
「でも、夜のうちに休まなければ・・・」
「普通に眠りに落ちるには、あまりにたくさん人が死にすぎました」
闇でさえ誤魔化せない、深い悲しみ。
「眠れないんです・・・」
「でも、夜のうちに休まなければ・・・」
「普通に眠りに落ちるには、あまりにたくさん人が死にすぎました」
闇でさえ誤魔化せない、深い悲しみ。
早く眠らなければ。
明日にも、敵は攻め入ってくるかもしれない。
覚悟を決めるためにも、疲れを癒やさなければ。
分かっている。
でも、理性で全てを割り切るには、あまりに多くを失いすぎた。
明日にも、敵は攻め入ってくるかもしれない。
覚悟を決めるためにも、疲れを癒やさなければ。
分かっている。
でも、理性で全てを割り切るには、あまりに多くを失いすぎた。
「ナタリー」
背中から呼びかけられ、振り向く。
制服を血に染めたアレンだった。
「アレン・・・」
「先生、遺体を講堂に運び終えました」
「ありがとう、アレン。あなたももう休みなさい。ケガのない生徒は、校舎の中で休むことになったわ」
「分かりました」
あくまで淡々とした態度のアレンだったが、私には分かった。
ひどく疲れている。
背中から呼びかけられ、振り向く。
制服を血に染めたアレンだった。
「アレン・・・」
「先生、遺体を講堂に運び終えました」
「ありがとう、アレン。あなたももう休みなさい。ケガのない生徒は、校舎の中で休むことになったわ」
「分かりました」
あくまで淡々とした態度のアレンだったが、私には分かった。
ひどく疲れている。
テニスの試合で負けたとき。
ロルフと喧嘩して寮に戻りたくないとき。
テストの点数が思わしくなかったとき。
ダニエルのノートにいたずら書きして先生に叱られたとき。
とにかく、つらいこと、嫌なこと、気にくわないことがあったとき、アレンは、ひどく疲れた様子で目尻にしわを寄せる。
ロルフと喧嘩して寮に戻りたくないとき。
テストの点数が思わしくなかったとき。
ダニエルのノートにいたずら書きして先生に叱られたとき。
とにかく、つらいこと、嫌なこと、気にくわないことがあったとき、アレンは、ひどく疲れた様子で目尻にしわを寄せる。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…