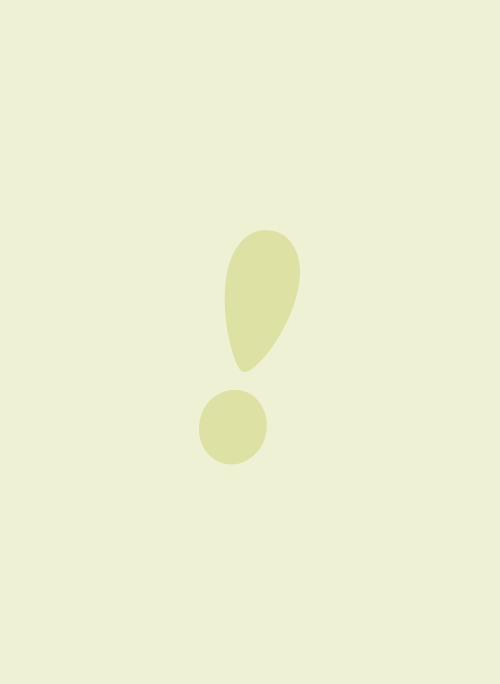敵国の兵士だった。
こちらに攻撃をするうちに、流れ弾にでも当たったのか、血まみれで倒れていた。
俺たちより3、4才ほど年上に見える。
気の強そうな顔をしていた。
「う・・・」
兵士は、うめき声を上げた。
「・・・生きてる?」
こちらに攻撃をするうちに、流れ弾にでも当たったのか、血まみれで倒れていた。
俺たちより3、4才ほど年上に見える。
気の強そうな顔をしていた。
「う・・・」
兵士は、うめき声を上げた。
「・・・生きてる?」
腹部に弾を受け、瀕死のようだ。
味方に害があろうと、気にしないとは・・・
あらためて、敵軍の無情さを思った。
味方に害があろうと、気にしないとは・・・
あらためて、敵軍の無情さを思った。
「・・・っ」
「どうした?何か言い残すか?」
何か言おうと口を開いた彼が、うっすらと目を開き、俺の背後を指さす。
「え・・・?」
「どうした?何か言い残すか?」
何か言おうと口を開いた彼が、うっすらと目を開き、俺の背後を指さす。
「え・・・?」
振り返ると、薄暗い月明かりを背負い、立つ男がいた。
はっとして、身構える。
緊張で心臓の音が高くなる。
これで・・・終わりか?
俺は・・・殺されて・・・死ぬのか?
まだ、まだ・・・俺は・・・
敵軍の幹部だろうか。
この若い兵士を助けに来たのか。
それとも、俺と同じ死体回収の任に就いたのだろうか。
月明かりに、男の顔立ちがくっきりと映える。
茶色の短髪と口ひげに、鋭い緑色の眼光。
いかにも軍人らしい精悍な顔つきの男は、上等そうな軍服を身にまとっていた。
兵士は、彼を指さして、苦しげな息の下からささやいた。
「・・・ンズ司令・・・、万歳・・・」
はっとして、身構える。
緊張で心臓の音が高くなる。
これで・・・終わりか?
俺は・・・殺されて・・・死ぬのか?
まだ、まだ・・・俺は・・・
敵軍の幹部だろうか。
この若い兵士を助けに来たのか。
それとも、俺と同じ死体回収の任に就いたのだろうか。
月明かりに、男の顔立ちがくっきりと映える。
茶色の短髪と口ひげに、鋭い緑色の眼光。
いかにも軍人らしい精悍な顔つきの男は、上等そうな軍服を身にまとっていた。
兵士は、彼を指さして、苦しげな息の下からささやいた。
「・・・ンズ司令・・・、万歳・・・」
俺は、耳を疑った。
「今・・・」
おそるおそる、兵士の口元に耳を近づける。
息も絶え絶えになりながら、兵士は、その男の名らしい言葉をつぶやいた。
「今・・・」
おそるおそる、兵士の口元に耳を近づける。
息も絶え絶えになりながら、兵士は、その男の名らしい言葉をつぶやいた。
今度は、はっきりとその名が聞き取れた。
俺は、信じがたい事実に困惑しながら、また後ろを振り返る。
しかし、さっきの男の姿はなかった・・・
俺は、信じがたい事実に困惑しながら、また後ろを振り返る。
しかし、さっきの男の姿はなかった・・・
アレンやロルフがひどくくたびれた様子で帰ってきたのは、真夜中過ぎだった。
学校の外では、何人もの生徒の遺体が回収されたらしい。
私たちも、校舎内で負傷者の看護に当たっていたが、助かった人は少なかった。
それはもう・・・気が狂いそうなほど。
学校の外では、何人もの生徒の遺体が回収されたらしい。
私たちも、校舎内で負傷者の看護に当たっていたが、助かった人は少なかった。
それはもう・・・気が狂いそうなほど。
日常はもう戻っては来ない。
ミルドレッドが新聞を掲示板に張り出す朝も。
ピーターが学生食堂で誰かのパンを取ろうとする昼休みも。
アンドリューが居眠りして先生に叱られる午後も。
ルドガーとキャサリンが照れくさそうに帰路をともにする夕暮れも。
もう何も帰っては来ない。
ミルドレッドが新聞を掲示板に張り出す朝も。
ピーターが学生食堂で誰かのパンを取ろうとする昼休みも。
アンドリューが居眠りして先生に叱られる午後も。
ルドガーとキャサリンが照れくさそうに帰路をともにする夕暮れも。
もう何も帰っては来ない。
ただただ頭が重かった。
つらく、悲しく、切なかった。
もっと、生きていたかっただろうに。
つらく、悲しく、切なかった。
もっと、生きていたかっただろうに。
この作家の他の作品
表紙を見る
ある街を支配するのは
4つの極道
北の玄武
南の朱雀
東の青龍
西の白虎
4人の組長は全員、高校生
3人に愛された美少女組長の運命は!?
☆
2015 5/9 (sat)完結!
読者様800人!
本棚inされた方
感想ノートに書いてください♪
これからもよろしくお願いします(*^o^*)
表紙を見る
身体を重ねることを
甘く考えてた・・・
命を重ねる行為は
命を作る行為でもあったのに・・・
ごく普通の少女は
愛する人との交わりで
子供を身ごもってしまう
命とは何か
生きるとは何かについて
問いかける物語
☆☆☆
毎日増えていくpv数を見ながら
妊娠・中絶に対する関心の高さを思います
いろいろな人の体験から紡いだ物語です
どうか誰かの糧になりますよう
表紙を見る
キス魔な女子高校生・月野 美玲
「だからっ、み、美玲とキスしたいんだよ!」
・・・真面目な彼氏と?
「俺だけが、ずっとお前の特別だと思ってたんだよ」
・・・強引な幼なじみと?
「殺してやりてぇ」
・・・深すぎる愛に溺れる彼氏の親友と?
「もっと月野のコト知りたい」
・・・好奇心旺盛な秀才のライバルと?
「俺の時間も止まってたってこと」
・・・過去の恋に引きずられた元カレと?
「あなたは江崎先輩より俺を選ぶべきコトが判明しました」
・・・甘えん坊な後輩と?
「溺れさせた責任、取ってくれよ」
・・・クールな体育教師と?
「もういいお兄さんじゃいられない」
・・・完璧な先輩と?
美玲が選ぶ愛のカタチは?
,゜.:。+゜,゜.:。+゜
読者さま10人に!
&pv数も19000を越えました♪
一番のお気に入り作品です^^
pv数も伸びますように・・・(祈)
応援してくださる皆様
ありがとうございます☆
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…