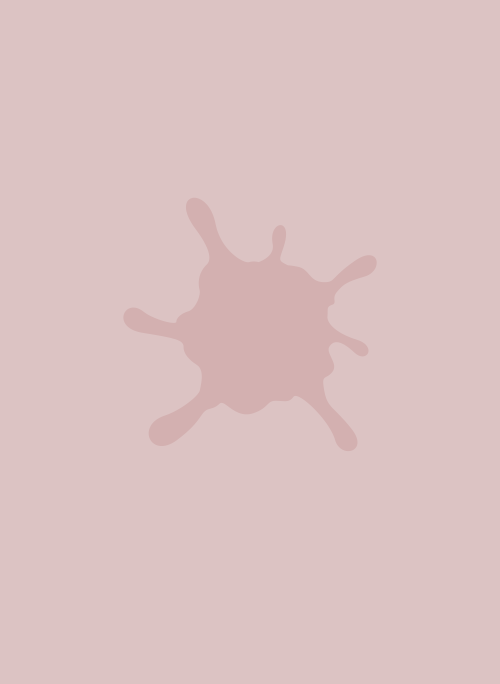例えばそれが偶然であったとしても、皆はそれを奇跡と呼ぶだろう。
例えそれが奇跡であっても、夢想家は運命だったと。
運命だったとしても、当人達は自分達が死力を尽くした必然だと語る。
そして私のような現実家は、これを歴史とした。
彼とその兄弟は決して恵まれた環境に産まれたとは言われない。
またはその逆で恵まれているのだと主張する者も少なからずいた。
私も同じくそう思う。
全てに始まりがあるように、彼の始まりは実に幻想的であったに違いない。
それが尾ひれの付いた伝承や、狂人の誇張された虚言であったとしても、人はそれらを肯定するだろう。
殆んどの者は幼少期に無償の愛を受ける。
彼にとってもそれは当然の権利であっただろう。
愛を送る者によって、環境によって人は変わっていくのだろう。
私の様に長くはない短い一生だからだろうか、個が他に、人が人に対して与える影響は小さくない。
短くはあるが精一杯、それを輝かせる為に生きる人間が時に思いがけない成長を見せる事に、私はいつも驚かされる。
【華國史】第参巻
~星の魔法使いの章~
後書きより
あらゆる境界が霞み程度の壁しか無かった時代、2つの強大な大国が陸を分かつ舞台での物語。
以下は今でも花咲き栄える王国の民に一番愛されている史実。
子供達は皆、寝る前にこの話を聞かせてくれと親にせがむ。
親は子に、子はまたその子に語り継ぐ。
皆は満天の夜空を見上げて思いにふける。
1人の偉大な星の魔法使いの姿を想像しながら……
【華國史】第参巻
~星の魔法使いの章~
幼少期
多くの由来ある星座が滴り落ちそうなまでに見下ろす大地には、黄金色をした淡く光る稲穂がその頭を垂れる。
暦では秋であったが、未だに生ぬるい風が稲穂を揺らし、星の瞬きに合わせて緩く踊っていた。
月こそ雲に隠れてはいたものの、星達が代わりに地面を青白い世界をまだらに映している。
あたかも普段は大きな月明かりのせいで自分達が矮小な存在では無い事を証明するが如く、取り戻そうとしているかの様だった。
はるか遠く一面に広がる稲畑の中央には、ぽつりと緩やかで小高い丘がその顔を覗かせる。
多種多様な菜園がしげる丘の上には、塗り直したばかりの白い壁に、汚れた赤い屋根を乗せた小屋が建っている。
陽は山に吸い込まれ、夜もふけているというのに小屋からは油ランプの包み込む様な光が小屋の隙間から外へと不規則な筋を成していた。
いつもとは雰囲気が違う小屋を、そこに飼われている無数の家畜達が丘下から何事かと見上げている。
小屋の外には長い簡素な作りの木製ベンチが置かれていた。
そこに四人の男達が座っている。
彼らは一つの家族であった。
一人は背の高い子供、もう一人は太った子供。
その父であるがっしりとした体格の男、そして老いて白髭を蓄えた二人の祖父であった。
四人は一言も話さず、ただ黙って星に照らされ揺れ続ける稲畑を眺めていた。
始めに沈黙を破ったのは太った子供であった。
太った少年
「大丈夫かな~?長いな~」
祖父
「大丈夫、こんな穏やかな夜は何も起こらない、大丈夫。
どれ、星に願いをかけておこう」
そういうと祖父は星に祈りの言葉を捧げ、父は両手をしっかりと握り締め頭にやり、神に祈りを捧げた。
しばらくして、女のうめき声と共に小屋の中から幼く、力無い泣き声が起こった。
二人の少年
「生まれた!」
二人の子供は同時に立ち上がり、父は涙を流し、祖父は星に感謝の言葉を送った。
しかしすぐに赤子の声は止み、女性の悲痛な叫び、そして泣き声が聞こえた。
二人の少年は悔しそうに膝を抱え涙をぬぐい、父は声を殺して泣いた。
祖父は髪を振り乱し星に呪いの言葉を吐いている。
だがまた少し間をおいて赤ん坊の泣き声が再度響く。
するとまた女性の叫び声。
小屋の外にいる男達はそれに一々反応しては一喜一憂した。
一体どうなっているんだ?
七回目の後、女性の泣き声は聞こえなかった。
男達は疲れ果て、事の始めと同じ様にベンチに腰掛けて静かに待った。
小屋のドアがそっと開かれ中の灯りが辺りにもれる。
その光に反応した男達が一斉に扉を見た。
太った少年
「おばさん!生まれた?」
「生まれたよ、こんなの初めてだわ」
そう言うなり助産婦らしき女性はその場に座り込んだ。
我先に小屋の中に駆けていく男達。
星はいつもより光輝いてそれを見守っている様だった。
一同を心配させたその男の子はセブンと名付けられた。
生まれた家の三男坊になる。
本来ならば七人兄弟がいるはずだったが、三人兄弟の末っ子として生まれる。
栄養も足りず、医療も進んでいないこの時代では特に珍しい事ではなかった。
それでも生まれた瞬間に七度死に、七度息を吹き替えした事は皆をびっくりさせた。
この農村の大人が子供であった頃から全ての赤子を抱き抱えた助産婦でさえ今回のような例は始めてだと驚いた。
家族の中では一際小さかったセブンはこの先、しっかり育ってくれるんだろうかと皆は不安に思ったが、その心配をよそに当人は兄二人に続いて元気一杯に育っていった。
一家の長男は背が高く、長男には似つかわしくない奔放な性格をしていた。
名前は「トール」
次男は横幅が広く、食いしん坊であった。
名前は「マッチョ」
長男トールはいつも下二人を引き連れ、マッチョは嫌々それに付き合い、セブンはいつも二人に泣かされていた。
二人は不器用ながらも可愛がったつもりであったが、年の差が開いた幼いセブンには村でも特にやんちゃな二人のいたずらに付いていくのが大変だったのだ。
三人の父は非常に仕事熱心で誠実、セブンは生まれて来なかった四人の加護を受けていると信じ込んでいた。
母もまた父に負けずたくましく働き、泣き虫のセブンを溺愛している。
祖父は祖母に先立たれてからは畑仕事をやめ、隠居生活を楽しんでいるようだった。
これがセブンの家族であった。
多くの農家が小屋を構えるこの地方は国の南に位置し、豊かな土壌に恵まれていた為、一次産業が盛んであった。
セブンの家族もまた稲を育て、牛を飼い、少しの野菜を育てている。
セブンはこの村の多くが好きだった。
鼻をくすぐる草の匂い、柔らかい赤土の道、村人みんなが汗を流し仕事をしているこの村を心から愛していたし愛されもしていた。
セブンの発育は平均的速度だったが、家族は皆大きく、そしていつも上の兄弟と一緒にいるので周りからは「チビ」と呼ばれる羽目になる。
だが、セブンはそれも嫌いではなかった。
皆の目は優しく、口元を緩めてチビと言っている。
悪意の無い、むしろ愛のこもったその言葉はセブンにとって、とても心地の良い響きだったのだ。
セブン達三人兄弟は村の子供達から疎まれ、恐れられていた。
長男トールは荒くれ者で、頭が良く、直ぐに悪戯をしてくるし、次男のマッチョは力が強く、お菓子をことごとく奪っていったからだ。
セブンはいつも兄達のせいで周りから苛められそうになったが、良いところで兄二人が飛んで来る。
それにセブン自身いつも兄達に引っ張り回されていたので同年代の中ではそれなりに強かった。
ある時、村の子供達は中々手が出せない三兄弟の悪口で盛り上がり、ある計画を立てた。
彼らは我が物顔の三兄弟をコテンパンにするべく小石を持って道端の草むらで待ち伏せをし奇襲を仕掛けようというものだった。
そうとも知らずいつもの様に三人が陽気に今日は何をするか話しながら青草のしげる一本道を歩いてきた。
そして号令と共に待ちきれなかったとばかりに三兄弟めがけて一斉に石の雨が降らされる。
さあ怒り狂った三人が来るぞと棒切れを構える子供達。
しかしトールの逃げろの一声で三人は意思が通じあったかの様にバラバラに逃げ、行方をくらましてしまった。
子供達は拍子抜けし、三方向に別れて走り去る彼等の誰を追うかを咄嗟に決められずまんまと逃げられてしまった。
夕方まで、三兄弟を村中探したのに見つからず、あの三人がこれで懲りるだろうかと若干不安に思いつつ、各々は家へと仕方なく帰って行った。
心配したのは三兄弟の両親だった。
いつもなら泥だらけになり、お腹を空かせて競争する様に走って帰って来る時間はとっくに過ぎている。
祖父と三人で村を探しに行く途中直ぐに、まとめて兄弟を見つける事が出来た。
三人は一様にたんこぶを作り、シャツはボロボロで怪我だらけだった。
三人は襲撃後バラバラに逃げたが、三人共同じ行動をとっていたと分かり、笑って肩を抱え合いながら歩いてきたのだった。
彼らは三方に逃げた後、夕方まで森に身を潜め、襲撃してきた子供達が家に帰った頃を見計らい、決闘を申し込んで歩いたのだ。
この娯楽の少ない時代、喧嘩は一種の楽しみであり、親は嫌がる自分の子を無理矢理決闘を申し込んできた三兄弟の一人と一対一で戦わせたのだった。
トール
「俺は五件潰した、計10人だ。
しかも年長からやってやったぞ!」
マッチョ
「やるなー兄さん!俺も五件、全部で八人だ」
二人以上にセブンは傷だらけだった。
トール
「セブン、お前は負けたのか?」
セブン
「僕はネズミの前歯を折った」
セブンの小さな手の平には赤い血の付いた歯が一本大事そうに布の上に置かれている。
トール
「俺でも七分三分のネズミのカトルをやっつけたのか?
実はあいつは三人でやっつけようと思ってたんだけど」
セブン
「多分負けたけど、でも泣かしてやったよ。
僕は…僕は泣かなかったけどね」
セブンは目を真っ赤に張らして笑った。
マッチョ
「…ふーん?いつも泣いてるお前が?
じゃあ、お前の勝ちだ!
あの出っ歯結構強いのに…お前すげーな!」
トール
「マッチョ…、そうだな!大将とった奴が一番偉いんだぞ!
良くやったセブン!お前が一番だ!」
立つのもやっとなセブンを兄二人はしっかりと支えてやった。
三人は喜んでいたが、両親にはきつく怒られた。
しかし祖父はセブンにこっそり「宝物が出来たな?」と囁く。
セブンはにっこり笑い出っ歯だったカトルの歯をポケットに詰め込み、本当は泣いてしまった事は内緒にしてしまった。
翌日にはこの喧嘩話が村中の噂になり、大人達をも感心させた。
それからはもう三兄弟に手を出す者はいなくなったのだった。
三兄弟がここまで強かったのは祖父が元軍人であったからというのもあった。
この頃、三人は毎日のように特訓を受けていたと記録されている。
弓、剣、斧、槍、一通りの武器の扱いだけは出来るようになっていた。
この日も小屋の裏では相も変わらず祖父が言うには緩い特訓が続いていた。
トール
「セブンは弱いなー?」
マッチョ
「肉をもっと食え、脂肪はパワーだ」
祖父
「年の差の割には良くやってるだろう?
まあ、チビは根性だけは一人前だな!
うはは」
セブンは遂に泣き出した。
トール
「泣くなよ、今日は旅の魔法使いが広場に来てるってよ」
トールはマッチョを苛める事はあったがセブンは可愛がっている。
マッチョ
「お前まだチビだから魔法見た事ねーだろ?
連れてってやるぞ!」
マッチョはセブンが生まれてから兄貴風を吹かせる事が多かった。
祖父
「お前等も見た事ないじゃろが」
トール
「泣いてたら連れて行ってやんないぞー?」
セブン
「じゃあ泣かない」
マッチョ
「じいちゃん一緒に行くか?」
祖父
「祈りは好きだが魔法は嫌いじゃ、簡単に命を奪うからな」
トール
「それは便利だな」
祖父
「これ!いつも言っとるじゃろが!
騎士の習わしを宣言せい!」
トール
「ハイハイ、血気の勇は自ら望まぬ様に」
マッチョ
「されど弱きを守る為に力を求めよ」
セブン
「我らは正義、そして護国の名誉を求めん!」
祖父
「よしっ、行け!小さき騎士達よ!」
三人は待ってましたと、稽古を終えて商店が集まる広場へと全力で走っていった。
三人が息を切らせて広場に着くと、すでに人だかりで円が出来ていた。
その群衆の中では何か旅の魔法使いが行っているようで歓声が起こっている。
トール
「何だよ、もう始まっちゃてるじゃねーか」
マッチョ
「じいさんのせーだ」
セブン
「全然見えない!」
トールはセブンを肩車してやり、マッチョが群衆を掻き分けた。
ネズミのカトル率いる少年団が最前列に陣取っていたのをトールはひと睨みした。
マッチョ
「どけよ、またうちのチビがお前等の残りの前歯貰いに行くぞ?」
少年達はおずおずと場所を譲りわたし、マッチョの差し出された手にお菓子を渋々乗せていった。
マッチョ
「よおセブン、お前のお陰でお菓子が手に入ったぞ、食うか?」
セブン
「ひょーーー!火の玉だ!」
セブンは今はお菓子どころでは無かった。魔法使いは小さな火の玉でジャグリングをしていたのだ。
火は次第に増え、大きくなり、空中で爆発した。
それと同時に歓声が沸き上がる。
興奮したセブンは肩車してもらっているトールの髪を力一杯に握りしめた。
トール
「いててて」
ピエロの扮装をした魔法使いは次に風を起こし、紙で作った鳥を飛ばして見せた。
セブンは紙の鳥をを捕まえようとする。
トール
「おっいチビっ首がしまって息、息が」
一通り芸が終わり、拍手の中でピエロはお辞儀して回った。
帽子にコインを入れてもらっているようである。
セブンはトールに下ろされ、げんこつを食らったが気にもとめず魔法を出そうとしていた。
マッチョ
「出るわけねーだろ」
セブン
「出たー!」
出た。
しかも小さな人の形をした火が踊っている。
自分でも驚いたセブンは叫んだ。
トール
「何だこりゃ?」
マッチョ
「お前にぴったりのチビ2号だな!」
周りの皆も初めは驚いたが、兄弟がケラケラ笑うのに釣られ、直ぐに笑いだした。
しかし一番驚いているのは旅の魔法使いであった。
尖り靴にブカブカのズボン、継ぎ当てだらけのコート。旅の魔法使いは姿そのまま「ピエロ」と名乗った。
黒く美しい長髪で涙の刺青、ピエロの割には中々の男前であった。
探し物をしている旅の最中で、ぜひセブンの家に泊めて欲しいとの事だった。
セブン
「いいよ」
トール
「お前が決めていいのか?」
マッチョ
「良くねーよ、怪しすぎるだろこの格好」
ピエロ
「怪しく無いよ?」
マッチョ
「怪しい奴は皆そう言うんだよ」
ピエロ
「君、頭良いね」
トール
「まあ聞いてみるだけな、じいちゃん魔法使う奴嫌いだからなー なあセブン?」
セブン
「何を探してんの?」
セブンはトールの皮肉に気づかなかいようだった。
ピエロ
「宝物だよ」
セブンはポケットから血の付いた歯を出した。
セブン
「これ?」
ピエロ
「無邪気な笑顔で怖いの出すなよ、君の?」
セブン
「ネズミの前歯」
セブンはさも誇らしげに見せたが、ピエロは理解出来なかった。
マッチョ
「何故うちに?
泊まる所なら他にもあるだろう?
村長だって旅の話を聞きたがってたのに」
ピエロ
「いちいち鋭いね、君」
トール
「まあいいじゃん、魔法見せて貰えるしよ」
四人はワーワー話しながらセブン達の小屋へと向かった。