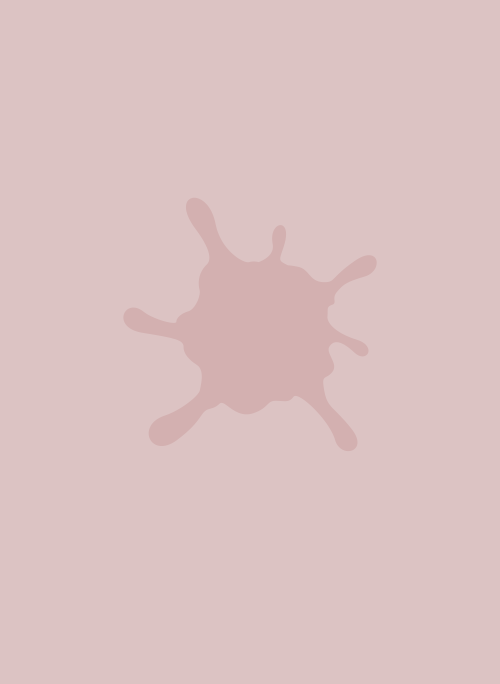華護義勇軍にはアイドル部隊があった。
三日月城塞の中だけでなく北大陸で彼らは暖かく見守られている。
成人男性の腰までの身長で全身を毛で覆われ鼻は常に濡れていた。
二本足で立つ亜人、もしくは亜犬であろうか、コボルト族の戦士達であった。
本人達はいたって真面目で勇敢であるが、訓練に参加する様は周囲の戦意を消失させる。
コボルト
「指令官殿!」
セブン
「どうした?グットマン」
グットマンはコボルト族の隊長であった。
茶色の毛でお腹は白く、革のベルトにサーベルをぶら下げ、背中にはボウガンを背負っていた。
グットマン
「何故我々は後方支援なのですかー?
納得いきません!
我々はこの国を守る為に戦いに来たのです」
セブン
「グフー、コボルトは鼻も目も耳も人より優れているだろう?」
グットマン
「そうです。誰にも負けませーん」
セブン
「それに数も少ない」
グットマン「少数精鋭です!」
セブン
「グフー、そうだ。
だから本来なら最前線に立って貰いたいが、そういう能力は追跡や夜間行軍の際に必要不可欠となる。
悔しいが、今は温存させておかなくてはならないんだ」
グットマン
「はっ成る程!そうでしたか…。
すみません。考えが至らず。
反省しなきゃだなー」
セブン
「だが、働いて貰う時はどの部隊よりもキツくなるぞ?」
グットマン
「望む所です!あと指令官殿の部隊のクロネ殿が我々を見るなり抱きついて来るのをなんとかしていただきたい。
我々は戦士なのです。
大人です。それなのになー…」
セブン
「グフーそれは困ったな~あっちょっとゴミが頭に」
セブンは嘘をつきゴミを取る振りをしてグットマンの頭を撫でた。
グットマンは次第に舌を垂れ、尻尾が左右に動き始める。
そのつぶらな瞳は何を考えているのか分からない。
セブン
「すまない、見間違いだった」
グットマン
「はっすいません、一瞬何も考えていませんでした」
セブン
「グフー(コボルトが可愛すぎて勝手に出てくる鼻息)」
三日月城塞の中だけでなく北大陸で彼らは暖かく見守られている。
成人男性の腰までの身長で全身を毛で覆われ鼻は常に濡れていた。
二本足で立つ亜人、もしくは亜犬であろうか、コボルト族の戦士達であった。
本人達はいたって真面目で勇敢であるが、訓練に参加する様は周囲の戦意を消失させる。
コボルト
「指令官殿!」
セブン
「どうした?グットマン」
グットマンはコボルト族の隊長であった。
茶色の毛でお腹は白く、革のベルトにサーベルをぶら下げ、背中にはボウガンを背負っていた。
グットマン
「何故我々は後方支援なのですかー?
納得いきません!
我々はこの国を守る為に戦いに来たのです」
セブン
「グフー、コボルトは鼻も目も耳も人より優れているだろう?」
グットマン
「そうです。誰にも負けませーん」
セブン
「それに数も少ない」
グットマン「少数精鋭です!」
セブン
「グフー、そうだ。
だから本来なら最前線に立って貰いたいが、そういう能力は追跡や夜間行軍の際に必要不可欠となる。
悔しいが、今は温存させておかなくてはならないんだ」
グットマン
「はっ成る程!そうでしたか…。
すみません。考えが至らず。
反省しなきゃだなー」
セブン
「だが、働いて貰う時はどの部隊よりもキツくなるぞ?」
グットマン
「望む所です!あと指令官殿の部隊のクロネ殿が我々を見るなり抱きついて来るのをなんとかしていただきたい。
我々は戦士なのです。
大人です。それなのになー…」
セブン
「グフーそれは困ったな~あっちょっとゴミが頭に」
セブンは嘘をつきゴミを取る振りをしてグットマンの頭を撫でた。
グットマンは次第に舌を垂れ、尻尾が左右に動き始める。
そのつぶらな瞳は何を考えているのか分からない。
セブン
「すまない、見間違いだった」
グットマン
「はっすいません、一瞬何も考えていませんでした」
セブン
「グフー(コボルトが可愛すぎて勝手に出てくる鼻息)」
昼食を済ませたセブンは何かを探すクロネに出会った。
セブン「クロネ!」
クロネ
「おっセブン、見てよこれリッチの爪を利用して作ったの」
セブン
「ヘーこんなのになったのか」
クロネ
「見た目は小さくなったけど、凄い威力よ。
盾を切り裂けるぐらいなんだから。
所でコボルト見なかった?」
セブン「あっ!」
セブンはグットマンに頼まれていた事を思い出した。
セブン
「クロネ、コボルトに抱きつくのをやめて欲しいんだけど」
クロネ
「なんで?死霊ばっかり相手にしてたから癒されたいのよ。
もしかして焼きもち?」
セブン
「違う!彼らは成人で、勇敢な戦士だ。
本人達も嫌がってるし、クロネだって急に誰かに抱きついてこられたら嫌だろ?」
クロネ
「うーん、良くわかんないから一回やってみて」
セブン「え?何を?」
クロネ
「おっ顔赤くなってるね?
小さい頃はよく大好き~って抱きついてた癖に~」
セブン「クロネ!」
クロネ
「分かったわよ、ごめん」
そういうとクロネは振り替えって去っていった。
去り際にカトリがセブンに向かってやって来てクロネとすれ違った。
カトリ
「クロネ、顔が赤毛色だぞ?熱でもあるのか?
教会騎士団に医者が…」
クロネ「大丈夫」
カトリ
「なんだあいつ?
よおセブン、昼からの事なんだけどってお前顔赤いぞ?
大丈夫か?教会騎士団に医者が…」
セブン「大丈夫」
セブン「クロネ!」
クロネ
「おっセブン、見てよこれリッチの爪を利用して作ったの」
セブン
「ヘーこんなのになったのか」
クロネ
「見た目は小さくなったけど、凄い威力よ。
盾を切り裂けるぐらいなんだから。
所でコボルト見なかった?」
セブン「あっ!」
セブンはグットマンに頼まれていた事を思い出した。
セブン
「クロネ、コボルトに抱きつくのをやめて欲しいんだけど」
クロネ
「なんで?死霊ばっかり相手にしてたから癒されたいのよ。
もしかして焼きもち?」
セブン
「違う!彼らは成人で、勇敢な戦士だ。
本人達も嫌がってるし、クロネだって急に誰かに抱きついてこられたら嫌だろ?」
クロネ
「うーん、良くわかんないから一回やってみて」
セブン「え?何を?」
クロネ
「おっ顔赤くなってるね?
小さい頃はよく大好き~って抱きついてた癖に~」
セブン「クロネ!」
クロネ
「分かったわよ、ごめん」
そういうとクロネは振り替えって去っていった。
去り際にカトリがセブンに向かってやって来てクロネとすれ違った。
カトリ
「クロネ、顔が赤毛色だぞ?熱でもあるのか?
教会騎士団に医者が…」
クロネ「大丈夫」
カトリ
「なんだあいつ?
よおセブン、昼からの事なんだけどってお前顔赤いぞ?
大丈夫か?教会騎士団に医者が…」
セブン「大丈夫」
肝心のセブンの部隊に正式ではないがピエロが加わった事により益々華龍王華隊は三日月城塞の話題となる。
実績のあるウルブスとピエロは言うまでもなかったが、
セブンと共に過ごしていた仲間も実力者であったからだ。
この世界の魔法使いのランクで言えばウルブスとピエロは魔術師で、
残り全員は上級魔法使いであった為である。
潜在能力でいえばセブンはこの時既に魔術師を越えた存在であったとされる。
上級魔法使いと認められるには幾つかの条件があった。
眠りドラゴン城の至る所に配置されていた魔力送りの石碑。
それにはめられた魔力に反応する鉱石で一定以上のレベルを示す事。
さらに上級魔法を習得し、初級魔法を無詠唱で行える事。
使える魔法を十個以上取得している事が条件であった。
魔術師になるとそれに加え新しい魔法の開発が条件に加わり、
尚且つ幾つかの方面である程度の貢献していなければならなかった。
上級魔法使いは全魔法使いの中でもその数を三割も越えていなかった。
必ずしもランクが高い魔法使いが強いという訳ではなかったが、
能力の指数を測る上で重要な役目を担っていた。
選りすぐりの部隊は三日月城塞でも異才を放っている。
カトリは常にセブンのそばに付き、隊長業務を支え、クロネは完成した武器を手にボルト族相手に特訓を重ねていた。
魔方陣を完成させた双子は鳥形の精霊を呼び出し周囲の警戒を怠らなかった。
三日月城塞の多くの者が次第にこの少数の部隊が別格の力を持っている事に気がつき初めていた中、
セブンは思い悩んでいた。
そして彼は寝食を共にしていた仲間にそれを打ち明けたのだ。
セブン
「ここにいる人間は皆優秀で、戦う理由もはっきりしている」
カトリ
「そうだな、教会騎士団は南の宗教狩りに会うだろうし」
クロネ
「ボルト族のみんなはまた差別を受けるしね」
ミニッツ&セコンド
「そんなの義勇軍もだろ?」
セブン
「そう、皆強く、それでいて負けられない思いを秘めているだろう?
なのに何故、西の関所みたいな安全な場所に?
東の兵力として使わないのはおかしくないかな?
義勇軍のエイブルスも言ってたんだ」
ウルブス
「安全な場所は無いという事は先の奇襲で証明されたでしょう?」
セブン
「それでも、もう2ヶ月もたった。
なのに東からの救援や、出撃要請も無い」
ピエロ
「単に統率の無い部隊を集めただけかもよ?」
セブン
「でも今じゃみんな仲良くやってるじゃないか」
カトリ
「集団戦闘訓練も様になってきたしな」
ウルブス
「それが狙いなのかも知れませんな」
ピエロ
「ちょっと違う気もするけどね、案外君達を育てる期間が欲しかったのかもね」
ウルブス
「ピエロの言う事も一理ありますね。
貴方達は既に別格の存在なのですから」
しかしこの後、セブンの心配は悪い方向に解決され、
ウルブスが言った別格の存在という理由が証明される事になる。
実績のあるウルブスとピエロは言うまでもなかったが、
セブンと共に過ごしていた仲間も実力者であったからだ。
この世界の魔法使いのランクで言えばウルブスとピエロは魔術師で、
残り全員は上級魔法使いであった為である。
潜在能力でいえばセブンはこの時既に魔術師を越えた存在であったとされる。
上級魔法使いと認められるには幾つかの条件があった。
眠りドラゴン城の至る所に配置されていた魔力送りの石碑。
それにはめられた魔力に反応する鉱石で一定以上のレベルを示す事。
さらに上級魔法を習得し、初級魔法を無詠唱で行える事。
使える魔法を十個以上取得している事が条件であった。
魔術師になるとそれに加え新しい魔法の開発が条件に加わり、
尚且つ幾つかの方面である程度の貢献していなければならなかった。
上級魔法使いは全魔法使いの中でもその数を三割も越えていなかった。
必ずしもランクが高い魔法使いが強いという訳ではなかったが、
能力の指数を測る上で重要な役目を担っていた。
選りすぐりの部隊は三日月城塞でも異才を放っている。
カトリは常にセブンのそばに付き、隊長業務を支え、クロネは完成した武器を手にボルト族相手に特訓を重ねていた。
魔方陣を完成させた双子は鳥形の精霊を呼び出し周囲の警戒を怠らなかった。
三日月城塞の多くの者が次第にこの少数の部隊が別格の力を持っている事に気がつき初めていた中、
セブンは思い悩んでいた。
そして彼は寝食を共にしていた仲間にそれを打ち明けたのだ。
セブン
「ここにいる人間は皆優秀で、戦う理由もはっきりしている」
カトリ
「そうだな、教会騎士団は南の宗教狩りに会うだろうし」
クロネ
「ボルト族のみんなはまた差別を受けるしね」
ミニッツ&セコンド
「そんなの義勇軍もだろ?」
セブン
「そう、皆強く、それでいて負けられない思いを秘めているだろう?
なのに何故、西の関所みたいな安全な場所に?
東の兵力として使わないのはおかしくないかな?
義勇軍のエイブルスも言ってたんだ」
ウルブス
「安全な場所は無いという事は先の奇襲で証明されたでしょう?」
セブン
「それでも、もう2ヶ月もたった。
なのに東からの救援や、出撃要請も無い」
ピエロ
「単に統率の無い部隊を集めただけかもよ?」
セブン
「でも今じゃみんな仲良くやってるじゃないか」
カトリ
「集団戦闘訓練も様になってきたしな」
ウルブス
「それが狙いなのかも知れませんな」
ピエロ
「ちょっと違う気もするけどね、案外君達を育てる期間が欲しかったのかもね」
ウルブス
「ピエロの言う事も一理ありますね。
貴方達は既に別格の存在なのですから」
しかしこの後、セブンの心配は悪い方向に解決され、
ウルブスが言った別格の存在という理由が証明される事になる。
東の関所では華國を代表する二人の王子が快進撃を見せていた頃、
煌皇国将軍ボーワイルドは煌皇国領最南端の港街に帰港していた。
出撃時兵数は約二万であったが、海峡越えと魔法都市攻略で無事帰還出来たのはおよそ一万であった。
多くの被害を出し、若き将兵達は陰口を叩いたが、
皇帝は港街に自ら出向きこれを称賛する。
「皇帝ブレイランド」
好戦的であり、支配欲が強く、自分の代で大陸統一を成したいと考えを持つ策略家。
第四皇子であったが皇帝の座に上り詰める程の人物であった為に、
今回のボーワイルドが成した奇襲における重大さを認知していたのだ。
ブレイランドは疲れ果てていたボーワイルドが率いる師団にと、
多くの食料と酒を持って出迎えた。
ブレイランド
「よくぞ帰ったボーワイルド!
報告は受けている。
これで敵は北にも兵力を割かねばなるまい!
しかも一番危険な時期での渡峡を成功させるとは、全くもって見事だ。
兵力を奪う事は出来なかったが、国力に大打撃を与える事が出来た。
これで数年すれば奴らの軍事力は落ちるであろう。
そして更にドラゴンをも葬ったと聞いた。
ボーワイルド、お前こそは真の名将よ!
お前にドラゴンスレイヤーの称号と煌陽金帝(コウヨウキンテイ)勲章を与える!
領地を増やし、この宝物を与える。
お前なら使うべき時を知っているだろうからな。
以下、ボーワイルドと共に出撃した兵に青銅勲章と功績に応じ金貨、銀貨を与える。
皆よくやった!」
ボーワイルドはドラゴンを倒したのは自分では無いと言おうとしたが、
回りの熱を冷まさぬよう言葉を飲み込んだ。
最高位の勲章を与えられ更にまた秘宝を与えられたのであった。
帰還した兵は皆自分達の成し遂げた事を皇帝が賛辞した事を誇りに思い、
厳しかった遠征の疲れは報奨への期待とで幾分か軽くなった。
しかしボーワイルドの心はここにあらず、更なる戦いへと向いていた。
それは急を要し、未だボーワイルドは自らが描いた作戦の真っ只中にいたからである。
自分の考えが正しければ華國は山脈の制圧を完了している頃であろうと。
この時またしても華國の動きはボーワイルドの頭の絵の通りに動いていたのっだった。
煌皇国将軍ボーワイルドは煌皇国領最南端の港街に帰港していた。
出撃時兵数は約二万であったが、海峡越えと魔法都市攻略で無事帰還出来たのはおよそ一万であった。
多くの被害を出し、若き将兵達は陰口を叩いたが、
皇帝は港街に自ら出向きこれを称賛する。
「皇帝ブレイランド」
好戦的であり、支配欲が強く、自分の代で大陸統一を成したいと考えを持つ策略家。
第四皇子であったが皇帝の座に上り詰める程の人物であった為に、
今回のボーワイルドが成した奇襲における重大さを認知していたのだ。
ブレイランドは疲れ果てていたボーワイルドが率いる師団にと、
多くの食料と酒を持って出迎えた。
ブレイランド
「よくぞ帰ったボーワイルド!
報告は受けている。
これで敵は北にも兵力を割かねばなるまい!
しかも一番危険な時期での渡峡を成功させるとは、全くもって見事だ。
兵力を奪う事は出来なかったが、国力に大打撃を与える事が出来た。
これで数年すれば奴らの軍事力は落ちるであろう。
そして更にドラゴンをも葬ったと聞いた。
ボーワイルド、お前こそは真の名将よ!
お前にドラゴンスレイヤーの称号と煌陽金帝(コウヨウキンテイ)勲章を与える!
領地を増やし、この宝物を与える。
お前なら使うべき時を知っているだろうからな。
以下、ボーワイルドと共に出撃した兵に青銅勲章と功績に応じ金貨、銀貨を与える。
皆よくやった!」
ボーワイルドはドラゴンを倒したのは自分では無いと言おうとしたが、
回りの熱を冷まさぬよう言葉を飲み込んだ。
最高位の勲章を与えられ更にまた秘宝を与えられたのであった。
帰還した兵は皆自分達の成し遂げた事を皇帝が賛辞した事を誇りに思い、
厳しかった遠征の疲れは報奨への期待とで幾分か軽くなった。
しかしボーワイルドの心はここにあらず、更なる戦いへと向いていた。
それは急を要し、未だボーワイルドは自らが描いた作戦の真っ只中にいたからである。
自分の考えが正しければ華國は山脈の制圧を完了している頃であろうと。
この時またしても華國の動きはボーワイルドの頭の絵の通りに動いていたのっだった。
歴史を動かすのは名将では無い。
時代の流れの中で名将が生まれるだけである。
皇帝ブレイランドの言葉通り将軍ボーワイルドとの今後の方針で意見が食い違う。
皇帝は東よりの侵略者を食い止めつつ再度華國領土内への侵攻を命令する。
ボーワイルドは防衛に徹底するべきであると皇帝に唱えるが、
皇帝はこれを却下する。
ボーワイルド
「魔法都市を陥落させたのはひとえに我が国の魔法使いよりも敵国の方が優位に立っていたからであります。
魔法技術を我々に奪わせないように、城の地下に巨龍を潜ませ、
それを妨害された今。
我々が行うのは東の勢力を叩き、前線にいる華國側の魔法使いどもを削り、
我が国の後身を育てる事こそが得策かと思われます。
さすれば、五年、十年の間に軍事勢力図は大きくこちら側に傾きましょう。
然る後に進行せねば勝算は五分と五分になります」
ブレイランド
「ならん。
そこまで待てぬ。
そなたは今より西の関所の後方に控える軍と合流し、
華國西方の防衛ラインをことごとく踏破せよ」
ボーワイルド
「では東は…」
ブレイランド
「好きにさせておくさ、お前は西より敵の王城へと向かい、華を摘んでこい。
西には大きな兵力は無いとの報告だ。
お前ならば突破するのは容易いであろう?」
ボーワイルド
「東より種が飛んで来ているにも関わらずですか?」
ブレイランド
「煌皇軍五大将軍のうち三将を東に向かわせている。
案ずるな、兵力では我が国の方が上だ」
ボーワイルド
「しかし、北も今回の一件で総力を上げて来るでしょう。
そうなれば…」
ブレイランド
「くどい!
華國王の首を持って来たならば意見を聞いてやる。
ボーワイルド将軍に命ずる。
今より出撃準備に取りかかれ!」
ボーワイルド
「…仰せのままに」
このまま防衛に徹すれば必ず華國を撤退へと向かわせる事が出来ると確信していただけに、
ボーワイルドは悔しくて堪らなかった。
兵力を分散させれば確固に戦う為に死者が多く出る、
更に東には敵の精鋭、危うくなる可能性がある。
長い目で見れば東を攻略し、損害を最小限に抑える事を先決すれば勝てるはずであった。
しかし、ボーワイルドは従うしか無かった。
皇帝の命は絶対であったからだ。
そして、もしここで歯向かえば軍事系統そのものが危うくなる事もあったからである。
ボーワイルドは皇帝の理知を上回る野心が残念でならなかった。
時代の流れの中で名将が生まれるだけである。
皇帝ブレイランドの言葉通り将軍ボーワイルドとの今後の方針で意見が食い違う。
皇帝は東よりの侵略者を食い止めつつ再度華國領土内への侵攻を命令する。
ボーワイルドは防衛に徹底するべきであると皇帝に唱えるが、
皇帝はこれを却下する。
ボーワイルド
「魔法都市を陥落させたのはひとえに我が国の魔法使いよりも敵国の方が優位に立っていたからであります。
魔法技術を我々に奪わせないように、城の地下に巨龍を潜ませ、
それを妨害された今。
我々が行うのは東の勢力を叩き、前線にいる華國側の魔法使いどもを削り、
我が国の後身を育てる事こそが得策かと思われます。
さすれば、五年、十年の間に軍事勢力図は大きくこちら側に傾きましょう。
然る後に進行せねば勝算は五分と五分になります」
ブレイランド
「ならん。
そこまで待てぬ。
そなたは今より西の関所の後方に控える軍と合流し、
華國西方の防衛ラインをことごとく踏破せよ」
ボーワイルド
「では東は…」
ブレイランド
「好きにさせておくさ、お前は西より敵の王城へと向かい、華を摘んでこい。
西には大きな兵力は無いとの報告だ。
お前ならば突破するのは容易いであろう?」
ボーワイルド
「東より種が飛んで来ているにも関わらずですか?」
ブレイランド
「煌皇軍五大将軍のうち三将を東に向かわせている。
案ずるな、兵力では我が国の方が上だ」
ボーワイルド
「しかし、北も今回の一件で総力を上げて来るでしょう。
そうなれば…」
ブレイランド
「くどい!
華國王の首を持って来たならば意見を聞いてやる。
ボーワイルド将軍に命ずる。
今より出撃準備に取りかかれ!」
ボーワイルド
「…仰せのままに」
このまま防衛に徹すれば必ず華國を撤退へと向かわせる事が出来ると確信していただけに、
ボーワイルドは悔しくて堪らなかった。
兵力を分散させれば確固に戦う為に死者が多く出る、
更に東には敵の精鋭、危うくなる可能性がある。
長い目で見れば東を攻略し、損害を最小限に抑える事を先決すれば勝てるはずであった。
しかし、ボーワイルドは従うしか無かった。
皇帝の命は絶対であったからだ。
そして、もしここで歯向かえば軍事系統そのものが危うくなる事もあったからである。
ボーワイルドは皇帝の理知を上回る野心が残念でならなかった。
この時、東の華國勢力一万七千、多くが騎士、戦士、魔法使いで構成された純粋な兵力であった。
率いるのは華國王子リンスとトリートである。
これに対抗する煌皇軍は既存の関所守備兵を含め兵力二万五千、
正規兵は五千足らずであった。
率いるのはボーワイルドと同じ位である将軍三名である。
華國は正規兵を国境に集中させ、民兵や新規兵を大陸、北、西、東へ配備した。
敵の艦隊による奇襲の足止めの為である。
そして日に日に増してゆく志願兵は王城で待機させ、
戦況を読みつつ各所へ援軍に向かわせる手筈であった。
一方、煌皇民兵を含む華國東方勢力包囲網は三将軍に集中させ分割される事になった。
煌皇軍は国内の守備兵を全て北に回したのだ。
西では華國側の正規軍では無いものの実力派の集団が三日月城塞で関所を守っている。
その兵力は若干、千名。
これに向けて煌皇国皇帝が送った兵力、ボーワイルドと更にもう一人の将軍があわせ持つ兵力二万。
東西を合わせ前線兵数を総合的に見れば
「華國軍一万八千」
vs
「煌皇軍四万五千」
その差、二万七千
華國側は約倍以上の兵力差があったのだ。
西側だけで考えれば二十倍である。
いかに煌皇側が民兵が多くとも、その戦力差は一方的であった。
これはボーワイルドの奇襲戦による功績が大きかった。
総力戦となれば五分の戦いが出来たであろうが、
兵力を分散させるしか無いと読んだ煌皇国皇帝が全軍を山脈に向かわせた結果であった。
率いるのは華國王子リンスとトリートである。
これに対抗する煌皇軍は既存の関所守備兵を含め兵力二万五千、
正規兵は五千足らずであった。
率いるのはボーワイルドと同じ位である将軍三名である。
華國は正規兵を国境に集中させ、民兵や新規兵を大陸、北、西、東へ配備した。
敵の艦隊による奇襲の足止めの為である。
そして日に日に増してゆく志願兵は王城で待機させ、
戦況を読みつつ各所へ援軍に向かわせる手筈であった。
一方、煌皇民兵を含む華國東方勢力包囲網は三将軍に集中させ分割される事になった。
煌皇軍は国内の守備兵を全て北に回したのだ。
西では華國側の正規軍では無いものの実力派の集団が三日月城塞で関所を守っている。
その兵力は若干、千名。
これに向けて煌皇国皇帝が送った兵力、ボーワイルドと更にもう一人の将軍があわせ持つ兵力二万。
東西を合わせ前線兵数を総合的に見れば
「華國軍一万八千」
vs
「煌皇軍四万五千」
その差、二万七千
華國側は約倍以上の兵力差があったのだ。
西側だけで考えれば二十倍である。
いかに煌皇側が民兵が多くとも、その戦力差は一方的であった。
これはボーワイルドの奇襲戦による功績が大きかった。
総力戦となれば五分の戦いが出来たであろうが、
兵力を分散させるしか無いと読んだ煌皇国皇帝が全軍を山脈に向かわせた結果であった。
将軍ボーワイルドは出撃命令を受け一週間で軍を再編成し再度艦に乗り込んだ。
煌皇領の海域を走り、海岸に船を停泊させる。
大陸内部へと行軍し、出撃より5日で山脈西の関所前にある城に入城する。
出迎えたのは共に西の関所を破らんとする将軍、フェネックである。
フェネックは騎馬戦を用いた機動戦略が得意であり、
またボーワイルドとの相性が非常に良かった。
ボーワイルド
「てっきりキュバインだと思っていたが」
フェネック
「私ではご不満ですか?」
ボーワイルド
「いや、貴殿は信用を裏切らん。
信頼している」
フェネック
「光栄です。
しかしお疲れ様でした。
大功でしたね」
ボーワイルド
「なに、私がやらねば誰かがやっていたさ」
フェネック
「やれませんよ、最悪の時期に魔の海峡を渡る者なんて」
ボーワイルド
「無茶だったとでも?」
フェネック
「あなた意外ならね。
我が自慢の騎馬隊五千、俊足を誇る歩兵五千。
合わせて一万、あなたの指揮下に入る事をお許し下さい」
ボーワイルド
「五千にまで騎馬を増やしたのか?
大したこと苦労であっただろう」
フェネック
「私財を投げ売りましたよ、命を失えば持っていても意味はありませんから」
ボーワイルド
「私の領土内より貴殿の親族にささやかな援助をさせてくれ」
フェネック
「宜しいんですか?」
ボーワイルド
「領土が増えたのでな、それを守る為にも我々は勝たねばな」
フェネック
「では安心して指示に従います。
貴方と共に戦える事を誇りに思います」
ボーワイルド
「私もだ。
早速作戦会議を開く」
フェネック
「既に人は揃えて待機させてあります」
ボーワイルド
「流石は烈風の称号を持つ男だ」
フェネック
「何でも奮起、名将に続き3つ目の称号を得たそうで?」
ボーワイルド
「情報まで早いとはな、ハッハッハ」
ボーワイルドはこの男が他の将軍よりも話やすかったし使い易くもあった。
若く、聡明であり、素直なフェネックはボーワイルドの考える以上の働きを常に見せた。
ボーワイルドは常にフェネックを褒め称えていたので、
今回の人事となったのであろう。
その為、ボーワイルドに傾倒していたキュバインとは幾分不仲ではあった。
煌皇領の海域を走り、海岸に船を停泊させる。
大陸内部へと行軍し、出撃より5日で山脈西の関所前にある城に入城する。
出迎えたのは共に西の関所を破らんとする将軍、フェネックである。
フェネックは騎馬戦を用いた機動戦略が得意であり、
またボーワイルドとの相性が非常に良かった。
ボーワイルド
「てっきりキュバインだと思っていたが」
フェネック
「私ではご不満ですか?」
ボーワイルド
「いや、貴殿は信用を裏切らん。
信頼している」
フェネック
「光栄です。
しかしお疲れ様でした。
大功でしたね」
ボーワイルド
「なに、私がやらねば誰かがやっていたさ」
フェネック
「やれませんよ、最悪の時期に魔の海峡を渡る者なんて」
ボーワイルド
「無茶だったとでも?」
フェネック
「あなた意外ならね。
我が自慢の騎馬隊五千、俊足を誇る歩兵五千。
合わせて一万、あなたの指揮下に入る事をお許し下さい」
ボーワイルド
「五千にまで騎馬を増やしたのか?
大したこと苦労であっただろう」
フェネック
「私財を投げ売りましたよ、命を失えば持っていても意味はありませんから」
ボーワイルド
「私の領土内より貴殿の親族にささやかな援助をさせてくれ」
フェネック
「宜しいんですか?」
ボーワイルド
「領土が増えたのでな、それを守る為にも我々は勝たねばな」
フェネック
「では安心して指示に従います。
貴方と共に戦える事を誇りに思います」
ボーワイルド
「私もだ。
早速作戦会議を開く」
フェネック
「既に人は揃えて待機させてあります」
ボーワイルド
「流石は烈風の称号を持つ男だ」
フェネック
「何でも奮起、名将に続き3つ目の称号を得たそうで?」
ボーワイルド
「情報まで早いとはな、ハッハッハ」
ボーワイルドはこの男が他の将軍よりも話やすかったし使い易くもあった。
若く、聡明であり、素直なフェネックはボーワイルドの考える以上の働きを常に見せた。
ボーワイルドは常にフェネックを褒め称えていたので、
今回の人事となったのであろう。
その為、ボーワイルドに傾倒していたキュバインとは幾分不仲ではあった。
※以下本文とは関係ありません。
煌皇軍の最高司令官を皇帝とし、五大将軍によって統制されている。
格式としては以下の通りになる。
皇帝
全軍の指揮
将軍
時と場合により率いる兵数が変化
↓
軍団長(将軍が兼任する場合もある)
約五千の兵の指揮
↓
連隊長
約千の兵を指揮
↓
部隊長
約百名を指揮
↓
隊長
約十名を指揮
↓
一般兵
となる。
「煌皇国勲章制度」
戦場で功績を与えられた者には勲章が与えられ、
それは勲章のランクにより税収を一定額免除される物である。
ボーワイルドが受け取った最高位の勲章
「煌陽金帝勲章」はその者から三代に限り、全額免除とされる。
「青銅勲章」はその者一代限り、一割免除となる。
「称号制度」
飛び抜けた才能や、功績を称え皇帝から送られる称号。
ボーワイルドであれば「奮起、名将、ドラゴンスレイヤー(龍殺し)」の3つを持つ。
主に連隊長以上に送られる物であり、
同ランクの将校同士であればこの称号が多い者がより上位に立つという事になる。
【華國外部工作員ジェノスの報告】
煌皇軍の最高司令官を皇帝とし、五大将軍によって統制されている。
格式としては以下の通りになる。
皇帝
全軍の指揮
将軍
時と場合により率いる兵数が変化
↓
軍団長(将軍が兼任する場合もある)
約五千の兵の指揮
↓
連隊長
約千の兵を指揮
↓
部隊長
約百名を指揮
↓
隊長
約十名を指揮
↓
一般兵
となる。
「煌皇国勲章制度」
戦場で功績を与えられた者には勲章が与えられ、
それは勲章のランクにより税収を一定額免除される物である。
ボーワイルドが受け取った最高位の勲章
「煌陽金帝勲章」はその者から三代に限り、全額免除とされる。
「青銅勲章」はその者一代限り、一割免除となる。
「称号制度」
飛び抜けた才能や、功績を称え皇帝から送られる称号。
ボーワイルドであれば「奮起、名将、ドラゴンスレイヤー(龍殺し)」の3つを持つ。
主に連隊長以上に送られる物であり、
同ランクの将校同士であればこの称号が多い者がより上位に立つという事になる。
【華國外部工作員ジェノスの報告】
華國第一王子リンス、第二王子トリートに率いられた一万七千の軍は東の関所を破り、
雄々しく渓谷を越えた。
第一次、第二次南北戦争ではお互いに関所内での戦闘だけであったが、
今回は両軍共に敵領土へ足を踏み入れる事に成功する。
華國軍は関所が破られた場合に敵を待ち受ける避難所としての役目を担う煌皇国の城を包囲していた。
その城は東の渓谷を出た所からでも目視出来る距離にある煌皇側の防衛拠点である。
この城は「重き扉の城」と呼ばれ、戦略の為に作られただけあり、中々優れた機能を備えていた。
正門だけで無く、城内の戸もしっかりと作られ、立て籠るには最適の城であった。
関所で敗退した煌皇兵はこの城に留まり、静かに援軍を待つ。
そこで実質的に軍の全権を握っていたリンスは敵の援軍が来る前に決着をつけるべく一考を案じていた。
彼は突撃兵を編成すると、その陣容の中央に攻城兵器を据えた。
彼は本国よりこの城をねじ伏せる為、密かに運搬していた物であった。
「鈍足の訪問者」
これは大きな丸太が五本組まれ、大きな巨木になっている。
それは横に寝かされ、先端は獅子の顔を模した鉄の装飾がなされていた。
大きな車輪がいくつもつけられた巨大な台車に固定され、
さながら現代の戦車の様相であった。
この兵器には無数の綱が付けられている。
リンスは第一師団の重装騎馬隊百名と共にこの綱を馬に結び、
渓谷の坂と歩兵の押し出す力を利用し引っ張り出した。
一度走り出した鈍足の訪問者は次第に馬に引かれ速度をあげてゆく。
その後ろを攻撃力の高い第一師団の制圧に特化した彼岸花騎士団と魔法部隊の三強が突撃を開始。
城からは異様な兵器と騎馬に向け矢が放たれる。
しかし馬にまで重装甲を施した彼等に跳ね返され続けた。
リンス
「怯むな!我が剣の合図を待て」
リンスはそう言うと剣を引き抜き天に掲げた。
煌皇兵
「奴だ!黒き鎧に金髪!
獅子王子がいるぞ!狙え!」
リンスに向かい多くの弓が一斉に放たれたが鈍足の訪問者に搭乗していた魔法使いによって地面に吸い込まれる様に叩き落とされる。
大風が起こり矢は全てリンスより前に起動を変えられたのだ。
リンス
「ボール!また来るぞ!」
ボールと言うこの風使いは魔法部隊の三強の一つ王華隊の隊員であり、
カトリの父であった。
リンス「今だ!展開せよ!」
リンスが天に立てていた剣を横に振ると城の正門に向かい走っていた騎馬隊が左右二方に別れる。
リンス
「ボール!乗れ!」
一足遅らせたリンスの馬にボールが飛び乗り、
リンスの馬は足を止めた。
左右に展開した騎馬隊が綱を引きつつ矢の雨降る城壁下を駆ける。
後方からは凄まじい音を響かせ鈍足とは思えぬ訪問者がそのまま両脇に引っ張られた力を利用し、
真っ直ぐに門を叩く。
凄まじいノックは立て籠っていた煌皇軍の不安を掻き立て、
それは直ぐに悪夢が現実である事に気づかせた。
煌皇兵の危惧していた通り二重の正門は内側へと破り倒されていた。
それを見たリンスは自軍の方を振り返ると剣を再度天に突き上げた。
リンス
「私に続け!突撃する!」
兵力一万七千と六千、しかも華國側は精鋭揃いである。
正門を破られた煌皇軍の士気は一気に低迷し、
その日1日で重き扉は全て開かれる事になるのであった。
雄々しく渓谷を越えた。
第一次、第二次南北戦争ではお互いに関所内での戦闘だけであったが、
今回は両軍共に敵領土へ足を踏み入れる事に成功する。
華國軍は関所が破られた場合に敵を待ち受ける避難所としての役目を担う煌皇国の城を包囲していた。
その城は東の渓谷を出た所からでも目視出来る距離にある煌皇側の防衛拠点である。
この城は「重き扉の城」と呼ばれ、戦略の為に作られただけあり、中々優れた機能を備えていた。
正門だけで無く、城内の戸もしっかりと作られ、立て籠るには最適の城であった。
関所で敗退した煌皇兵はこの城に留まり、静かに援軍を待つ。
そこで実質的に軍の全権を握っていたリンスは敵の援軍が来る前に決着をつけるべく一考を案じていた。
彼は突撃兵を編成すると、その陣容の中央に攻城兵器を据えた。
彼は本国よりこの城をねじ伏せる為、密かに運搬していた物であった。
「鈍足の訪問者」
これは大きな丸太が五本組まれ、大きな巨木になっている。
それは横に寝かされ、先端は獅子の顔を模した鉄の装飾がなされていた。
大きな車輪がいくつもつけられた巨大な台車に固定され、
さながら現代の戦車の様相であった。
この兵器には無数の綱が付けられている。
リンスは第一師団の重装騎馬隊百名と共にこの綱を馬に結び、
渓谷の坂と歩兵の押し出す力を利用し引っ張り出した。
一度走り出した鈍足の訪問者は次第に馬に引かれ速度をあげてゆく。
その後ろを攻撃力の高い第一師団の制圧に特化した彼岸花騎士団と魔法部隊の三強が突撃を開始。
城からは異様な兵器と騎馬に向け矢が放たれる。
しかし馬にまで重装甲を施した彼等に跳ね返され続けた。
リンス
「怯むな!我が剣の合図を待て」
リンスはそう言うと剣を引き抜き天に掲げた。
煌皇兵
「奴だ!黒き鎧に金髪!
獅子王子がいるぞ!狙え!」
リンスに向かい多くの弓が一斉に放たれたが鈍足の訪問者に搭乗していた魔法使いによって地面に吸い込まれる様に叩き落とされる。
大風が起こり矢は全てリンスより前に起動を変えられたのだ。
リンス
「ボール!また来るぞ!」
ボールと言うこの風使いは魔法部隊の三強の一つ王華隊の隊員であり、
カトリの父であった。
リンス「今だ!展開せよ!」
リンスが天に立てていた剣を横に振ると城の正門に向かい走っていた騎馬隊が左右二方に別れる。
リンス
「ボール!乗れ!」
一足遅らせたリンスの馬にボールが飛び乗り、
リンスの馬は足を止めた。
左右に展開した騎馬隊が綱を引きつつ矢の雨降る城壁下を駆ける。
後方からは凄まじい音を響かせ鈍足とは思えぬ訪問者がそのまま両脇に引っ張られた力を利用し、
真っ直ぐに門を叩く。
凄まじいノックは立て籠っていた煌皇軍の不安を掻き立て、
それは直ぐに悪夢が現実である事に気づかせた。
煌皇兵の危惧していた通り二重の正門は内側へと破り倒されていた。
それを見たリンスは自軍の方を振り返ると剣を再度天に突き上げた。
リンス
「私に続け!突撃する!」
兵力一万七千と六千、しかも華國側は精鋭揃いである。
正門を破られた煌皇軍の士気は一気に低迷し、
その日1日で重き扉は全て開かれる事になるのであった。
この作家の他の作品
表紙を見る
御嶽山噴火を心から悲しく思います。
荒廃した世界に文明復興を掲げた
「人類再編統括本部」
それを担ったのは鉄の道であった
しかし人員不足の為
志を同じくはしているが
軍の問題児ばかりで構成された
独立遊撃装甲列車隊
「火龍の竜騎兵」
癖のある指令官に抜擢された青年は
愚連隊を率い
上層部の思わぬ快進撃を続けた。
装甲列車という閉鎖的な空間で
芽生える友情は
その装甲よりも厚く、固い物だった。
火龍の咆哮は新たな時代への
生まれたばかりの産声であった
長編通快戦争ものです。
表紙を見る
これはある女子高生が過ごした
三年間の記録である。
オカルトという「非」日常
それを楽しむ後輩との出会いが
彼女の世界を変えた。
以下登場順に紹介。
小山友子(エース)
本作の主人公。
霊感の強い女子高生。
高身長ゆえの高体重に悩んでいる。
藤沢真奈美
主人公の友人。
バレー部所属、怖い話が嫌い
谷口相馬(隊長)
オカルト研究部の部長。
自他共に認める苛められっ子。
荒木祐介(ゼロ)
オカルト研究部の部員。
セクハラ発言を好む。実家は米屋
岡田修平
オカルト研究部の顧問。
あらゆる事を気にしない。
表紙を見る
広大な荒野
無法者達は力で法律をねじ曲げる
黄金を求めてさ迷う者もいれば
銃の腕で名を上げようとした者もいた
ギャンブルに命を掛け
酒と女と喧嘩が男の生きざまだった
西部開拓時代。
これはその無秩序だが掟があり
ロマンと夢が溢れた時代。
そんな金の時代を駆け抜けた
誰も名前を知らない
ある1人のガンマンのお話。
独自視点の短編アクション西部劇です
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…