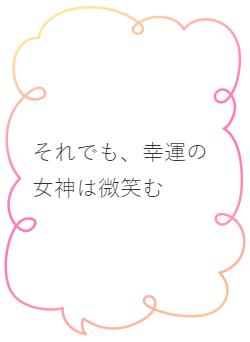むくりと起き上がって、大鍋をまじまじと見つめた。
普通の大鍋だ。銀色の、顔のある、普通の・・・
「そんなに見つめて・・・さては、オイラに惚れたゴンね。」
「ごめんそれすっごい勘違い。」
前言撤回。
やっぱ、顔ある時点で普通じゃない。
しかも、喋ってるし。
なんか頰らしきところを淡い赤に染めてるし。
「照れなくてもいいゴンよぉ〜。」
「照れてない照れてない。
それよりさ、なんであたしがここにいるか知ってる?」
「え?なんでって、わからないゴン?」
「うん。なんか、目が覚めたらここにいて。
あたし、ついさっきまではウィレボにある古びた出店にいたのに。」
大鍋サンは、不思議なモノを見るようにあたしを見た後、納得したように頷いた。
「あぁ、そうだったゴン。君は忘れてたんだったゴンね。」
「へ?忘れてた、って・・・」
あたし、大鍋と喋ったことがあれば、絶対覚えてると思・・・あ。
でも、そういえば3年より前の記憶がないんだったっけ。
そう、納得しかけた時ーー
「いや、ゴン、それは違うカン。
その子は確かにお姫様だけど、あの子じゃないカン。」
キィキィ甲高い声が背後から聞こえてきた。
後ろに首をひねればーーー
顔のある、小物を入れるカンカンがすっくとばかりに、堂々と立っていた。
普通の大鍋だ。銀色の、顔のある、普通の・・・
「そんなに見つめて・・・さては、オイラに惚れたゴンね。」
「ごめんそれすっごい勘違い。」
前言撤回。
やっぱ、顔ある時点で普通じゃない。
しかも、喋ってるし。
なんか頰らしきところを淡い赤に染めてるし。
「照れなくてもいいゴンよぉ〜。」
「照れてない照れてない。
それよりさ、なんであたしがここにいるか知ってる?」
「え?なんでって、わからないゴン?」
「うん。なんか、目が覚めたらここにいて。
あたし、ついさっきまではウィレボにある古びた出店にいたのに。」
大鍋サンは、不思議なモノを見るようにあたしを見た後、納得したように頷いた。
「あぁ、そうだったゴン。君は忘れてたんだったゴンね。」
「へ?忘れてた、って・・・」
あたし、大鍋と喋ったことがあれば、絶対覚えてると思・・・あ。
でも、そういえば3年より前の記憶がないんだったっけ。
そう、納得しかけた時ーー
「いや、ゴン、それは違うカン。
その子は確かにお姫様だけど、あの子じゃないカン。」
キィキィ甲高い声が背後から聞こえてきた。
後ろに首をひねればーーー
顔のある、小物を入れるカンカンがすっくとばかりに、堂々と立っていた。