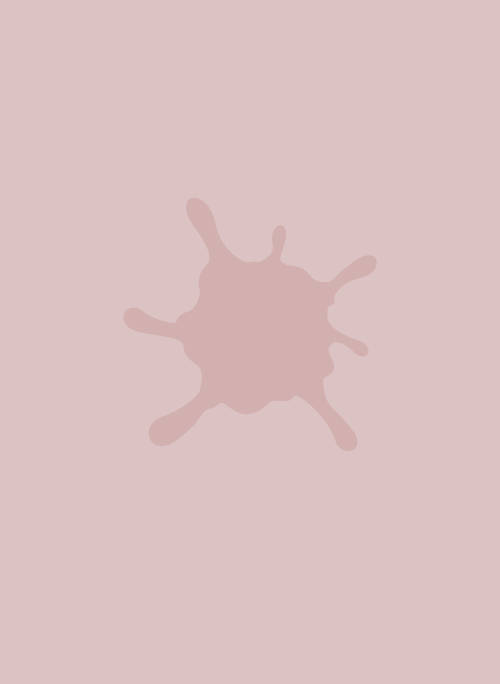4番目を支えてくれたこの右手さえも鬱陶しく感じるのは、やはりこの性格故か。
「俺はよくお気楽って言われるよーんっ。だけどねぇ、
人ってのは気楽で間抜けそうに見えて、案外なに考えてんのか分かったもんじゃあないぜ?」
にやりと笑うクロネコに思わず4番目の頬は赤く染まる。
美形ドチクショウ。
おまけに「まあ、俺、人じゃないんだけどねーんっ!」といつもの二割増しのウザったさ。
ええい、この残念イケメソが。お前が性格変えろやボケ。
「あはは~」とまた優しい笑みを向けるクロネコに、4番目はポツリと呟く。
「人も案外、悪くないかも……」
「え?」
「なっ、なんでもないっ!」
その呟きは聞こえることこそなかったものの、4番目が徐々に変わりつつあることは確かであった。
「俺はよくお気楽って言われるよーんっ。だけどねぇ、
人ってのは気楽で間抜けそうに見えて、案外なに考えてんのか分かったもんじゃあないぜ?」
にやりと笑うクロネコに思わず4番目の頬は赤く染まる。
美形ドチクショウ。
おまけに「まあ、俺、人じゃないんだけどねーんっ!」といつもの二割増しのウザったさ。
ええい、この残念イケメソが。お前が性格変えろやボケ。
「あはは~」とまた優しい笑みを向けるクロネコに、4番目はポツリと呟く。
「人も案外、悪くないかも……」
「え?」
「なっ、なんでもないっ!」
その呟きは聞こえることこそなかったものの、4番目が徐々に変わりつつあることは確かであった。
「……ねぇ、クロネコ…」
「あれ、『さん』付けしてくれないんだ~?ちぇ~」
「クロネコ……さん。あの、あのねっ、僕っ…………
………あ、」
「え?なになに?どうし………」
お互い言葉を続けようとするも、それは唐突に遮られる。
突如として出てきた霧によって。
それは次第に4番目の体を包み込み、どこかへ連れ去ろうとする。
思わず4番目が手をのばすとクロネコもその手を掴もうと手を伸ばすが……
ーすかっ……
「あ……」
その手は掴まれることなく、霧は4番目を包み込んでしまった。
それでも4番目はなにかを伝えようと口を開き、………霧に隠され消えてしまった。
突然の展開に呆けるクロネコ。
その頭の中では霧に消える前の4番目の言葉が何度も再生される。
『僕も、少しずつ変わろうと思う。…………君には【失望】できないや。
ばいばい、クロネコさん』
「………。」
そうしてクロネコはそっと目を閉じ、黒猫の姿となって路地裏を駆けていったのだった。
彼の思いは、本人以外だれも知り得ない…………
*
目を開けば、コーヒーのいい匂いが4番目の鼻をくすぐった。
4番目はカウンターらしきところに座っており、目の前には男の人が。推定27歳だろうか。
褐色の髪を後ろで結い、白シャツにスラックス、深緑の腰エプロン。男性からも僅かにコーヒーの香りがする。
成る程、ここは喫茶店か。
ということは恐らくこの男は店の者。
目の前の男は急に現れた4番目に少し驚いたが、まるで "慣れているかのように" 表情を戻した。
にっこり笑う男に、4番目は無表情。…いや、ボーッとしているのだろうか。
「いらっしゃいませ。ご注文は?」
「………。」
マスターらしき男は愛想よく話しかけてくれるが、4番目は黙ったままだ。
目を開けば、コーヒーのいい匂いが4番目の鼻をくすぐった。
4番目はカウンターらしきところに座っており、目の前には男の人が。推定27歳だろうか。
褐色の髪を後ろで結い、白シャツにスラックス、深緑の腰エプロン。男性からも僅かにコーヒーの香りがする。
成る程、ここは喫茶店か。
ということは恐らくこの男は店の者。
目の前の男は急に現れた4番目に少し驚いたが、まるで "慣れているかのように" 表情を戻した。
にっこり笑う男に、4番目は無表情。…いや、ボーッとしているのだろうか。
「いらっしゃいませ。ご注文は?」
「………。」
マスターらしき男は愛想よく話しかけてくれるが、4番目は黙ったままだ。
「………どうかしたか? 悩みがあるなら、私が聞こう」
だれでも安心するような笑みを向けられ、ようやっと口を開いたかと思えば。
「わす、れた……」
「?」
「僕……さっき、まで、なに、してたっけ……な」
思い出せない。
虚ろな目をしてマスターを見つめる4番目。その様子を黙って見ていたマスターはそっと語りかける。
「思い出せないのなら、無理に思い出さなくてもいい。嫌な思い出なのなら、もし思い出したとき私がそれを『否定』しよう」
そう言うなり4番目の前にカップをおくマスター。
ふんわりと甘い匂いの広がるこの飲み物は、気持ちを落ち着けてくれるオレンジティーだった。
カップを手に取りオレンジティーを口にする4番目。
こくりと、一口飲んでほっと溜め息をつくと、次第に自分を理解できたようで虚ろな目から一点。
大きな目をパチパチさせて、すぐに怪訝な表情となった。
「……『否定』ねぇ…。ああ、なるほど、思い出したよ。
僕は4番目の【失望】。それが名前さ。呼びにくいなら4番目でいいよ」
少しツンとした態度。さきほどの大人しい4番目はどこへやら。
しかしオカシイ。
クロネコと出逢う前の4番目と、なんら変わりないではないか。
「ん~、記憶はまだ曖昧だけど。ま、いっか。いつものことだしね。
どうせ、記憶が消えても支障はない。だって、世界は変わらず愚かなままで、僕をいつだって【失望】させるから」
どうやら記憶が抜けた様子の4番目。
やはり、変わることなど無理なのだろうか?
こくりと、一口飲んでほっと溜め息をつくと、次第に自分を理解できたようで虚ろな目から一点。
大きな目をパチパチさせて、すぐに怪訝な表情となった。
「……『否定』ねぇ…。ああ、なるほど、思い出したよ。
僕は4番目の【失望】。それが名前さ。呼びにくいなら4番目でいいよ」
少しツンとした態度。さきほどの大人しい4番目はどこへやら。
しかしオカシイ。
クロネコと出逢う前の4番目と、なんら変わりないではないか。
「ん~、記憶はまだ曖昧だけど。ま、いっか。いつものことだしね。
どうせ、記憶が消えても支障はない。だって、世界は変わらず愚かなままで、僕をいつだって【失望】させるから」
どうやら記憶が抜けた様子の4番目。
やはり、変わることなど無理なのだろうか?
しかし、マスターは気にすることなく4番目に語りかける。
「なるほど、君はこの世界が嫌いなのだな。……なぜ、そこまで嫌う?」
「なに、理由なんてあんたに教えなきゃなんないの?」
「い、いやっ!別に嫌なら嫌と…………………「他人面する奴らしかいない。愚弄者の塊によって出来た世界だからだよ」
慌てるマスターに4番目はカップを傾けながら淡々と答える。
初めから教えてあげればよかったのに。
「ところで、僕は名前を教えたのに君は何も教えてくれないんだね。さっきから質問ばかり。
ツマンナイ人間しかいない世界に、やっぱり僕は【失望】する」
言いたい放題言うわりに、4番目は気に入ったのかオレンジティーをおかわりする。
「なるほど、君はこの世界が嫌いなのだな。……なぜ、そこまで嫌う?」
「なに、理由なんてあんたに教えなきゃなんないの?」
「い、いやっ!別に嫌なら嫌と…………………「他人面する奴らしかいない。愚弄者の塊によって出来た世界だからだよ」
慌てるマスターに4番目はカップを傾けながら淡々と答える。
初めから教えてあげればよかったのに。
「ところで、僕は名前を教えたのに君は何も教えてくれないんだね。さっきから質問ばかり。
ツマンナイ人間しかいない世界に、やっぱり僕は【失望】する」
言いたい放題言うわりに、4番目は気に入ったのかオレンジティーをおかわりする。
それに少し面喰らったマスターだが、カップを受けとり新しい紅茶を淹れた。
「私の名前は【麻石 聖】(あさいし ひじり)だ。それと、君が人外だからこそ、そして正体を教えてくれたからこそ私も伝えよう。
私は『否定』の魔法使い。他にも私を合わせて10人の魔法使いがいるが、さてね。素性の知れないやつもいるんだよ」
「……ふうん、『否定』ねぇ」
こくりと一口だけ口に含む4番目。
その目は何かを掴んだかのようにギラギラ光っている。
「ところでさあ、ここっていつも客いないの?僕以外誰もいないけど」
「ああ、それは。学園に行っている者や仕事の都合でこの時間帯は来れない者が多くてね」
「へえ、じゃあここで何か起こっても、誰も気づかないのかな」
「え、」
カチャリと音がしたかと思えば。備え付けフォークとバターナイフを持った4番目が、その切っ先をマスターに向けていた。
「君が死んだら、世界は少しでも変わるのかな。それとも、悪くなるのかな」
「なっ……」
「好奇心って大切だもんね。だから、
僕の遊びに付き合ってよ。
【失望】させない程度にさ」
ひゅっと風をきる音と共に鋭いフォークの先がマスターの鼻筋へと投げられた。
近距離だったものの、首を傾けよけたマスター。フォークは後ろにある棚へとサクリと刺さった。
それに「おもしろいねえ」とでも言うかのように4番目は手当たりしだい、次々とフォーク、ナイフ、スプーン。
ついには自身の座っていた椅子までも片手でヒョイと持ち上げ投げつける。
この作家の他の作品
表紙を見る
月夜に浮かんだフタツの光
ヒトツは、紅く
ヒトツは、蒼く
相容れぬ対極の光色が
偶然そこにいただけの少年を巻き込む
その時、確かに世界は震えたのだ
○●--- ---●○
東洋と西洋の若者達が紡ぐ
学園を舞台とした
愉快痛快怪奇ストーリー
○●--- ---●○
【双世のレクイエム】
(そうせいのれくいえむ)
それは
あっては
ならない
ものだった
ほら
世界は今も震(怯)えてる
[THANKS]
梅雨之あめサマ
颯希サマ
素敵な感想ありがとうございます!
これを糧に更新頑張りますね!
表紙を見る
『時間だよ、時間だよ』
探そうか、僕らの世界を
強制的に
泥沼世界へ御招待
*・・・・・・・・・・・・・・・*
『夢』は溢れて
『零』は果てなく
■
夢朶雨と零夏サマのコラボ
第1弾
■
キーワード:夢零コラボ
*・・・・・・・・・・・・・・・*
時計を離しちゃいけないよ
時計を壊しちゃいけないよ
世界は君の赴くままに
表紙を見る
鶴と嘘つきが出会ったのは
愛にさまよい想い焦がれる
二人の擦れ違いユーレイだった
「あんさん、好きな人に会えへんで
寂しくないんかいな」
「君を置いてどこかへ消えてしまった
彼が、憎くないのかい」
問いかけてみれどユーレイは
哀愁を帯びた笑みを浮かべて
ただ一言こう言うだけ
「「それでも、愛してるから」」
たとえ会えなくとも
それこそ死んでしまっても
愛があるなら
▼黒猫彼方サマより▼
【榛名 樒子】
【三隅 和寿】
を、お借りしています
▼鶴と嘘つき▼
【REALLY】
【塩辛い酒よりも、甘ったるいだけの酒が飲みたい。】
に、登場しています
※※注意※※
作中に出ている方言は関西弁ではなく、私オリジナルの【ドナ語】です
悪しからず
[THANKS]
黒猫彼方サマ
レビュー・感想ありがとうございます!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…