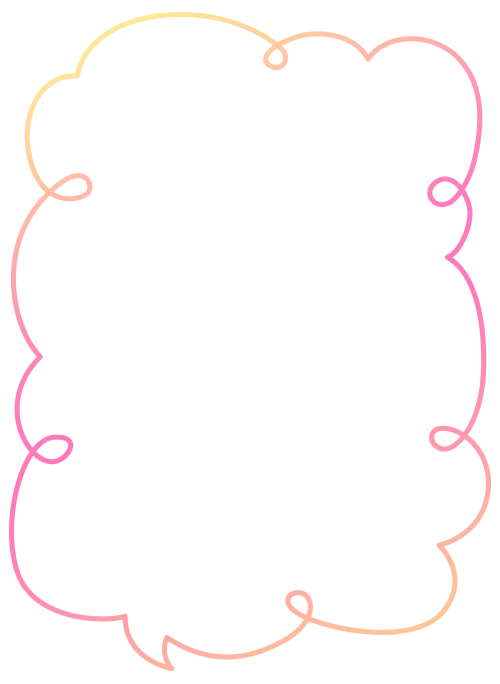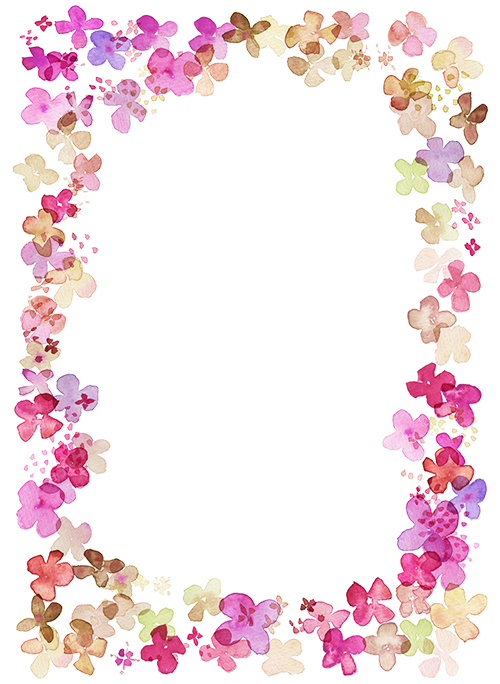「お前、それを言うためにわざわざあんな必死に追いかけてきたのか?」
「うん……。本当にごめ……――」
もう一度謝ろうとした時、目の前の狼谷君が呆れたように笑った。
あっ、まただ。
胸がキュンっと高鳴って痛いくらいに締め付けられる。
保健室で感じた不思議な気持ちが再びわき上がる。
「何度も謝んなよ。それに、人の目とかいちいち気にしてねぇから安心しろ」
「でも……」
「タヌキの絵ももう気にしてねぇし、もう謝んな」
あれって、タヌキじゃなくてウサギなのに……。
心の中でそうポツリと呟いてみる。
「そういうことだから。じゃあな」
狼谷君はそう言うと、あたしに背中を向けて歩き出した。
教室とは反対側に向かって歩いていく狼谷君。
きっと屋上で授業をサボるに違いない。
この学校で屋上を利用しているのは狼谷君ただ一人。
屋上は狼谷君だけのもの。
他の生徒は絶対に屋上へあがってはいけない。
『屋上へ行けば、狼谷にボコられる』
いつしかそんな噂が校内に広がった。
あたしだって今までずっと……そうだと信じて疑わなかった。
狼谷君の外見と噂話だけで、彼のことを全部知った気になっていたから。
とにかく怖くて、悪くて、近付いてはいけない危険人物っていうレッテルを貼っていた。
だけど、本当にそうなのかな……?
狼谷君の背中を目で追いながらふとそんなことを考える。
もっと、知りたい。
狼谷君のことを……もっともっと知ってみたいな。
この日を境に、あたしの心の中にそんな気持ちが芽生え始めた。
「うーーーっ。寒いっ!!」
厳しい寒さに、手を擦り合わせる。
こんな日に限って委員会が長引いてしまった。
まだ6時すぎだというのに、辺りはもう真っ暗。
つま先はもう感覚がないし、スカートから出ている膝のあたりは痛くてたまらない。
一刻も早く家に帰って、コタツに入ってゴロゴロしたい。
「あっ……」
その時、ふとあることに気が付いた。
片手だけ手袋をしていない。
さっきメールの返信の為に右手の手袋をとって、ポケットに入れたんだった。
コートのポケットにあるはずの手袋を震える手で引っ張り出そうとする。
「あれっ?」
だけど、あるはずの手袋がどこにもない。
もしかして、右ポケットじゃなくて左ポケットにいれたんだっけ?
「嘘……。なんで。なんでないの?」
両方のポケットを探してみても、やっぱり右手の手袋だけ見つからない。
もしかしたら、携帯をポケットにしまう時に落としたのかも……。
慌てて振り返って歩いてきた道を引き返す。
あの手袋は去年、愁太がくれたものだった。
『これ、やる』
そう言って少しだけ照れくさそうに差し出したピンク色の手袋。
『いつも指先が冷たいんだよねぇ……。今度温かい手袋でも買おうかな』
いつもあたしの話を話半分にしか聞いてくれていない愁太。
だけど、ちゃんと聞いていてくれたんだ……。
愁太にそんな話をした矢先だったから、すごく嬉しかった。
『幼なじみって言っても、本当はお互いのこと意識してるんじゃないの?』
ってよく友達に言われる。
だけど、あたしも愁太もお互いを異性だと意識したことは一度もない。
確かに気を許せる仲。
友情とも違う関係。
小さい頃から幼なじみとして一緒に育ってきたし、ほとんど家族みたいなもの。
愁太とはおじいちゃんおばあちゃんになっても仲のいい幼なじみでいたい。
手袋をプレゼントされた時、あたしは強くそう思ったんだ。
「どうしよう……。どこに落としちゃったんだろう……」
地面に視線を落として必死になって手袋を探すものの、辺りが暗いこともあってなかなか見つからない。
しばらく歩くと、駅前まで来ていた。
そこは塾帰りに不良達に取り囲まれて散々からかわれた嫌な思い出のある場所。
どうしよう……。
明日の朝、いつもより早く起きて学校に行く前に探そうかな。
だけど、その間にも愁太にもらった手袋は誰かに踏まれているかもしれない。
そう考えると、やっぱり諦めることなんてできなくて。
諦めずに探さなきゃ。
覚悟を決めて一歩を踏み出した時、ポンポンッと誰かに肩を叩かれた。
「ねぇ、さっきから何探してんの~?」
振り返ると、そこには耳にジャラジャラとピアスをつけた派手な男の子が立っていた。
「探し物があるなら、俺、手伝うよ」
「あっ……、ありがとうございます。でも、自分で探すので……」
「そんな遠慮すんなって~。一人で探すより人数多い方が見つけやすいし」
「でも……」
「で、何を探してんの?」
断ろうとしても、一方的に話を進めようとする男の子。
男の子はタバコをくわえながら取り出した携帯をあたしに差し出す。
ディスプレイには電話番号が表示されたいた。
「これ、俺の番号。登録しておいてね」
「えっ?」
「いやいや。そんな露骨に嫌そうな顔されちゃうとショックでかいなぁ~。つーか、そんなに見つめないでよ」
「はいっ?」
全然見つめていないのに……。
「今気付いたけど、キミ、可愛いね~。ていうか、この制服って星陵学園?」
スカートの辺りをジロジロ見ながら首を傾げる男の子。
「あのっ、もう失礼します!!」
やっぱり不良は苦手。
いい人の振りをして近づいてきたのは、ナンパのためだったんだ。
ニコリと笑って歩き出そうとした瞬間。
この作家の他の作品
表紙を見る
傷モノの子爵令嬢アイリーン
×
イケメン冷徹辺境伯エドガー
父の再婚後、絶世の美女と名高きアイリーンは意地悪な継母と義妹に虐げられる日々を送っていた。
実は、彼女の目元にはある事件をキッカケに痛々しい傷ができてしまった。
それ以来「傷モノ」として扱われ、屋敷に軟禁されて過ごしてきた。
ある日、ひょんなことから仮面舞踏会に参加することに。
目元の傷を隠して参加するアイリーンだが、義妹のソニアによって仮面が剥がされてしまう。
すると、なぜか冷徹辺境伯と呼ばれているエドガーが跪まずき、アイリーンに「結婚してください」と求婚する。
抜群の容姿の良さで社交界で人気のあるエドガーだが、実はある重要な秘密を抱えていて……?
傷モノになったアイリーンが冷徹辺境伯のエドガーに
たっぷり愛され甘やかされるお話。
※注意※他サイトにも別名義で投稿しています。
表紙を見る
「第5回noicomiマンガシナリオ大賞」にエントリーしています。
5話分のマンガシナリオです。
一宮愛衣(17)いちみやあい
おしゃれ好きな陽キャギャル。
バッチリメイクにピンクベージュの胸下まである髪の毛を緩く巻いた派手系女子。
見た目は派手だけど恋愛経験なし。誰に対しても分け隔てなく優しい性格。ちょっぴりお節介。
音無綾斗(17)おとなしあやと
寡黙で余計なことは喋らない無気力人間。女子にも素っ気ないが、愛衣にだけは甘い。
少し長い前髪の黒髪。高身長。細身に見えるけど意外と筋肉質な体。隠れイケメンなのを愛衣に見破られている。
勉強、運動共にできる。
恋愛経験なしの初心なギャル×ちょっと訳ありな無気力隠れイケメン
そんな二人のラブストーリー。
表紙を見る
周りのみんなは結婚をゴールだという。
だから、結婚をした。
あとは子供を産んで、育てて……
そうすればきっと固い絆で結ばれる夫婦になれる。
そうすれば、
私は『幸せ』を手に入れることができる。
――はずだった。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…