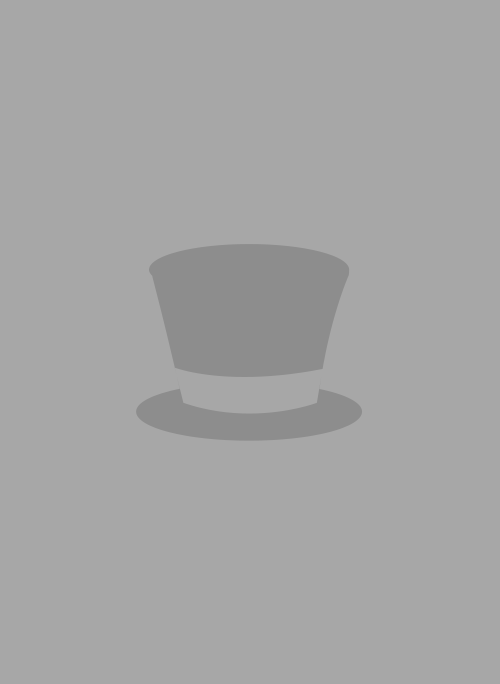【向日葵】
夏が苦手。暑くて、息苦しくて。
星という命に合図を贈る打ち上げ花火も、『冷やし中華はじめました』の癖のある文字も、ブルーの中に繊細な銀細工を散りばめたような海も、どれも魅力を感じない。
夏の外出はなるべく控えたい。私の肌は白くて弱いから、日焼け止めクリームを丁寧に塗らないとヒリヒリ、ピリピリ痛んでお風呂にも入れなくなる。日傘は邪魔になるから持ちたくない。
行くなら、静かで涼しい映画館か美術館、屋内がいい。
そんな私が、向日葵に恋をした。
背の高いあなたは、お日さまの光を浴びて、背を高く伸ばしている向日葵のよう。
星という命に合図を贈る打ち上げ花火も、『冷やし中華はじめました』の癖のある文字も、ブルーの中に繊細な銀細工を散りばめたような海も、どれも魅力を感じない。
夏の外出はなるべく控えたい。私の肌は白くて弱いから、日焼け止めクリームを丁寧に塗らないとヒリヒリ、ピリピリ痛んでお風呂にも入れなくなる。日傘は邪魔になるから持ちたくない。
行くなら、静かで涼しい映画館か美術館、屋内がいい。
そんな私が、向日葵に恋をした。
背の高いあなたは、お日さまの光を浴びて、背を高く伸ばしている向日葵のよう。
神宮外苑の花火をあなたと見たくて、橘商店街の角にあるお店であなたと冷やし中華を食べたくて、実家のある伊豆の海をあなたと泳ぎたくて。
ショッピングモールで色艶ある紫の浴衣と、清楚な淡いピンクの水着と、赤いリボンがついた麦わら帽子を買いました。
向日葵の隣で一緒に咲きたいと思ううちに、苦手な夏さえも好きになっていたのです。
今年の夏はあなたと乱反射したい。朝日が窓に反射する始発電車のように。
見上げたら、少し背を屈めてくれたあなた。
つま先立ちをしたら届きそうな距離に、今、あなたはいます。
【向日葵*END】
ショッピングモールで色艶ある紫の浴衣と、清楚な淡いピンクの水着と、赤いリボンがついた麦わら帽子を買いました。
向日葵の隣で一緒に咲きたいと思ううちに、苦手な夏さえも好きになっていたのです。
今年の夏はあなたと乱反射したい。朝日が窓に反射する始発電車のように。
見上げたら、少し背を屈めてくれたあなた。
つま先立ちをしたら届きそうな距離に、今、あなたはいます。
【向日葵*END】
【映る裸のダイアモンド】
雑居ビルの五階にある居酒屋。駅から離れた路地裏という立地条件なのに店内は仕事帰りのサラリーマンで賑わっている。
その生ぬるい籠った空気の中で烏龍茶を飲んでいる私と目の前に座っている君。
君は右手で生ビールの入ったジョッキを持ち、左手でケータイをいじっている。
ねえ、君から誘ったんでしょ。
仕事帰りに一杯やりたいって。
私が呑めないのも知らずに。
しかもこの辺りで一番安い居酒屋指定で。この立地条件でも繁盛している理由はその安さにある。
その生ぬるい籠った空気の中で烏龍茶を飲んでいる私と目の前に座っている君。
君は右手で生ビールの入ったジョッキを持ち、左手でケータイをいじっている。
ねえ、君から誘ったんでしょ。
仕事帰りに一杯やりたいって。
私が呑めないのも知らずに。
しかもこの辺りで一番安い居酒屋指定で。この立地条件でも繁盛している理由はその安さにある。
女性を連れて二人きりで呑むなら、洒落たバーとか、おつまみがおいしい店、せめて女性が入りやすい居酒屋を選んでほしい。
ほら、周りを見渡してみて。
女性は店員さんしかいないでしょ。
私ひとり、この席で浮いてる。いくら男っぽくてなにも気にしないような私でもさすがに居づらい……。
正直、このからあげもおいしくない。
君の味覚がこれをおいしいと感じるのなら、私と君の味覚は生ビールと烏龍茶くらいの差がある。
花嫁修行なんてしていないけど、私が作るからあげの方が遥かにおいしいと思う。もしここで揚げられるなら、厨房に立たせてほしい。
君にどちらがおいしいか判定してほしい。
その結果によって私と君の味覚という相性がわかるだろう。この相性は身体の相性よりも重大だったりする。
ほら、周りを見渡してみて。
女性は店員さんしかいないでしょ。
私ひとり、この席で浮いてる。いくら男っぽくてなにも気にしないような私でもさすがに居づらい……。
正直、このからあげもおいしくない。
君の味覚がこれをおいしいと感じるのなら、私と君の味覚は生ビールと烏龍茶くらいの差がある。
花嫁修行なんてしていないけど、私が作るからあげの方が遥かにおいしいと思う。もしここで揚げられるなら、厨房に立たせてほしい。
君にどちらがおいしいか判定してほしい。
その結果によって私と君の味覚という相性がわかるだろう。この相性は身体の相性よりも重大だったりする。
私、ここになにをするために来たの? これで一緒にいる意味があるの?
会話くらいしてよ。
あなたが得意な政治家に対する批判や、経済の事。そんなに堅苦しくなく、昨日、アイドルの前田未来が結婚したとか、そんな他愛無い事でもいい。
なんでもいいから、とケータイを見ているその目に訴えてみる。
やっと君がジョッキを置いた。
今度は空いた右手で枝豆をポコポコと口の中に押し出し、左手は相変わらずケータイをいじっている。
これなら、お一人様で焼き肉屋へ行った方がいい。網にタンやカルビを好きなだけ乗せて、自分の好きな焼き加減で食べられる。
二十代の頃はお一人様に抵抗があったけど、三十を過ぎて独り身だと、お一人様に慣れてくる。いつしかお一人様がラクだとさえ思うようになってきた。
会話くらいしてよ。
あなたが得意な政治家に対する批判や、経済の事。そんなに堅苦しくなく、昨日、アイドルの前田未来が結婚したとか、そんな他愛無い事でもいい。
なんでもいいから、とケータイを見ているその目に訴えてみる。
やっと君がジョッキを置いた。
今度は空いた右手で枝豆をポコポコと口の中に押し出し、左手は相変わらずケータイをいじっている。
これなら、お一人様で焼き肉屋へ行った方がいい。網にタンやカルビを好きなだけ乗せて、自分の好きな焼き加減で食べられる。
二十代の頃はお一人様に抵抗があったけど、三十を過ぎて独り身だと、お一人様に慣れてくる。いつしかお一人様がラクだとさえ思うようになってきた。
「あたし、一人でご飯を食べられないんですっ」
なんて言う内巻きカールの桃色アイドル系女子にちょっとイラっとくる。
私なんて、一人牛丼、一人ラーメン、一人回転寿司、一人焼き肉。どれだってなんて事はない。
お一人様は食べ終わったらすぐに店を出るから回転率も早いし、店にとってはありがたい客だろう。まさにお一人『様』だ。
威勢よくそう言えるけど、ほんのちょっと侘しい。ぽつんと一人佇んだ時の女としての切ない侘しさ。お一人様がラクなんて本当は臆病な言い逃れ。
人は人を必要としているのだから。
そろそろ、枝豆にも飽きたんじゃない? なにか話しません?
今、私は女としての切ない侘しさ限界五秒前。
四、三、二、一。
もう!!
私は枝豆以下って事?
ケータイ以下って事?
そんなに退屈なら、ケータイをいじるくらい退屈なら、私といてもつまらないなら誘わないでよ。
誘われると嬉しくてどんな場所にだって着いていく私が惨めじゃない……。
ケータイよりも私を見てほしい。
お互い毎日が忙しい中で、刻々と時間は過ぎていく。気づけば出勤時間で、気づけば残業。終われば深夜。同じ職場で同じ空間にいてもプライベートとは違う。職場は職場。浮わついた気持ちでお金はもらえない。
首を縦に振るだけでNOとは言えない日々。
歳を重ねれば重ねるほど、一年があっという間に感じる。
だから、こうして二人でいる時間を無駄にしたくない。
今、どうしても聞きたい事がひとつだけあるの。
『ねえ、誰とメールしてるの?』
そう言おうとした瞬間、君が「なに?」と無警戒な上目遣いで私を見た。
すっきりとした切れ長の額縁。その中にある茶色いダークな瞳が浮かび上がるように明かりを取り込んでいる。
仕事中とは違う警戒心が一切無い君のその瞳。
じっと見つめられると、なにも言えなくなる。考えていた言葉も、時には魂さえも吸い取られてしまう。
………────。
それは無警戒な君の瞳の中に私がいるから。
君の瞳に映る私はまるで別人のように美しい。
すっきりとした切れ長の額縁。その中にある茶色いダークな瞳が浮かび上がるように明かりを取り込んでいる。
仕事中とは違う警戒心が一切無い君のその瞳。
じっと見つめられると、なにも言えなくなる。考えていた言葉も、時には魂さえも吸い取られてしまう。
………────。
それは無警戒な君の瞳の中に私がいるから。
君の瞳に映る私はまるで別人のように美しい。
この作家の他の作品
表紙を見る
名探偵、赤沼光一
またもや殺人事件を解決へと導く
2017年11月23日*完結*
レビュー
ありがとうございました
月乃ミラ様
高山様
表紙を見る
『重なり合う、ふたつの傷』
子供の頃は泣けなかった
でも今は泣ける
あなたと出逢ったから
その涙は希望の涙か
それとも別れの涙か
今を生きている
あなたへ贈ります
玉置梨織(たまきりお)15歳
天野蒼太(あまのそうた)15歳
神田ルミ(かんだるみ)15歳
桜井零士(さくらいれいじ)19歳
「オレ、好きだな、君の声。鼻にかかったじゃれた声」
コンプレックスだった自分の声を好きになった瞬間。
*2014年9月9日完結*
どうぞよろしくお願いします
レビュー
ありがとうございました
mira!様
高山様
さいマサ様
小田真紗美様
シュレディンガーの猫様
こみあな様
表紙を見る
瀬名優人×小松結月
+友情出演 吉沢愛子
あの、国民的コーンスナックが
東京で買えなくなる。
残るは、あと一袋。
さてどうなる、
コーンスナックと恋の行方。
イケメンを超越した王子様。
私は瀬名先輩のことが、
好きで好きで、
どうしようもなくなりました。
2017年6月6日*完結*
レビュー
ありがとうございました
高山様
月乃ミラ様
小田真紗美様
英 蝶 眠様
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…