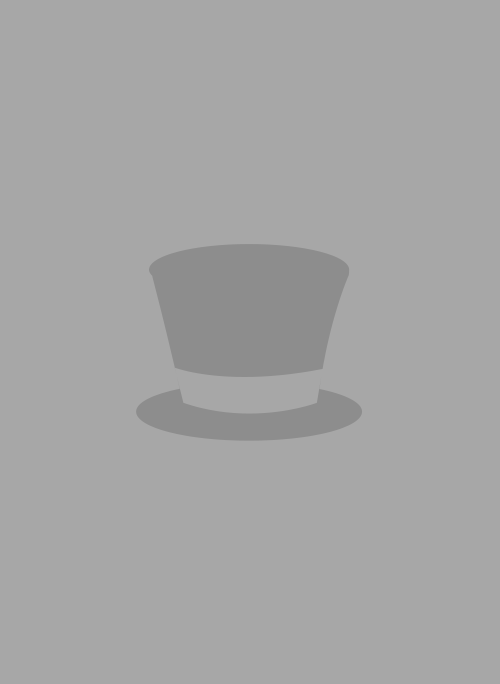だから、下北沢のレトロなカフェで春樹と同じカフェオレを飲んだ。
那須高原にある洋食屋さんで、春樹と同じオムライスを食べた。窓の外に広がる山々や新緑を眺めながら。
普通のカフェオレとオムライスでも特別なカフェオレとオムライスに思えた。
私が春樹をテレビで見て「好き」と言うと、冬樹は「バカじゃねーの」とケラケラ高い音域で笑う。
そういう時だけ、私の心をレントゲンで写し診て、アイドルなんてテレビや雑誌の中にしかいない存在だと、夢なんて幻だと、六畳のフローリングという冷たい現実を突きつける。
冬樹だけではなく、きっとみんな笑うだろう。春樹は私より一回り以上年下のアイドルだから。
でも、今言ったよね。
「僕がしてあげるよ」って。
硬直したまま春樹を見ると、
「なんて、嘘」
と、アイドルチックに大人をからかうように笑った。
「嘘でもいい」
気づくと吐息のようにそう囁いて春樹の手を強く掴んでいた。
「これから、映画の撮影なんだ」
現実的な答え。迷惑なファンだと思われているだろう。
「そっか。ごめん……。つぐみさんとの映画、楽しみにしてます」
そう言って緩く離した私の手を今度は春樹が掴んだ。
「撮影が終わってアイドルの仮面を外したら、二人で……行こう」
「なんて、嘘」
と、アイドルチックに大人をからかうように笑った。
「嘘でもいい」
気づくと吐息のようにそう囁いて春樹の手を強く掴んでいた。
「これから、映画の撮影なんだ」
現実的な答え。迷惑なファンだと思われているだろう。
「そっか。ごめん……。つぐみさんとの映画、楽しみにしてます」
そう言って緩く離した私の手を今度は春樹が掴んだ。
「撮影が終わってアイドルの仮面を外したら、二人で……行こう」
私は玲奈でも京子でも有紀でも絵理でも敦子でもない。篠原つぐみでもない。そうなる必要もない。
私の名前は吉高麻子。私は私のままでいいんだ。誰かと比べる必要なんてない。
世間体の中で動いていた普通という人生の長針が止まった。
そして私の子宮を突いていた槍が光輝く人生の短針へと変わり動き始めた。
まだ間に合うよ、と猛スピードで。
お腹や腰が痛くて面倒だと思いながらも付き合ってきた生理に意味を見つけた。
毎月子宮から落ちるその血液のように私の目から涙がぽとりぽとりと落ちた……。
私、女なんだ。
【普通という人生の長針*END】
【重なる鼓動】
法学部の隼人と付き合い始めて二ヶ月が過ぎた。知識が豊富で私の知らない事を沢山知っている爽やかな好青年。
友達に紹介され、知的で美的なその姿に一目惚れしてしまった。
片想いだと毎夜胸を焦がしていたら、隼人に告白された。
「美里ちゃん、僕の彼女になってもらえませんか?」
「はいっ……」
両想いって素晴らしい。
心は晴天。
どんな時でも傍に居たいほど大好き。……でも、着いていけない事がひとつだけある。
それはマラソン。
映画館や図書館が似合う草食系のインドア派で文学部の私と趣味が合いそうに見えたのは錯覚? 初デートは博物館で『地球の構造と宇宙の成り立ち』だったのに。
隼人は毎朝五時に起きてクラシック音楽を聴きながら多摩川の土手を走っている。
私はマラソンも早起きもどちらもアウト。家を出る十分前まで寝ていたい。すっぴんでもいいなら三分前まで寝ていたい。三分あれば、顔を洗って、歯を磨きながら髪をとかせる。
平凡でありふれた朝が一番だ。
友達に紹介され、知的で美的なその姿に一目惚れしてしまった。
片想いだと毎夜胸を焦がしていたら、隼人に告白された。
「美里ちゃん、僕の彼女になってもらえませんか?」
「はいっ……」
両想いって素晴らしい。
心は晴天。
どんな時でも傍に居たいほど大好き。……でも、着いていけない事がひとつだけある。
それはマラソン。
映画館や図書館が似合う草食系のインドア派で文学部の私と趣味が合いそうに見えたのは錯覚? 初デートは博物館で『地球の構造と宇宙の成り立ち』だったのに。
隼人は毎朝五時に起きてクラシック音楽を聴きながら多摩川の土手を走っている。
私はマラソンも早起きもどちらもアウト。家を出る十分前まで寝ていたい。すっぴんでもいいなら三分前まで寝ていたい。三分あれば、顔を洗って、歯を磨きながら髪をとかせる。
平凡でありふれた朝が一番だ。
大体、用もないのに走る意味がわからない。
バス停にバスが止まっているのが見える。そういう時でしょ、走るのって。
「運転手さーん、待ってー!!」とか、叫んだりしながら。
私はそれでも走らずに次のバスを待つ、緩やかな性格。
それに都会のバスの運転手さんはきっちり時間通りに行こうとするから、走っても待ってくれない事が多い。
それが当たり前なんだけど。私が生まれ育った田んぼに囲まれた町では、手をあげればそこがバス停でなくても乗せてくれた。蛙でも飛び跳ねれば乗せてくれそうな親切心溢れる町だった。
そんな町で育った私が家電店で警報装置のような大音量の目覚まし時計を買い、朝五時に起きて、眠い目を擦りながら隼人と一緒に多摩川の土手を走った。
違う。一緒に、ではない……。
バス停にバスが止まっているのが見える。そういう時でしょ、走るのって。
「運転手さーん、待ってー!!」とか、叫んだりしながら。
私はそれでも走らずに次のバスを待つ、緩やかな性格。
それに都会のバスの運転手さんはきっちり時間通りに行こうとするから、走っても待ってくれない事が多い。
それが当たり前なんだけど。私が生まれ育った田んぼに囲まれた町では、手をあげればそこがバス停でなくても乗せてくれた。蛙でも飛び跳ねれば乗せてくれそうな親切心溢れる町だった。
そんな町で育った私が家電店で警報装置のような大音量の目覚まし時計を買い、朝五時に起きて、眠い目を擦りながら隼人と一緒に多摩川の土手を走った。
違う。一緒に、ではない……。
「俺、先行くから」
隼人はクラシック音楽が流れるイヤホンを耳に入れると、足の遅い私を置いて朝日の中、一人で颯爽と走っていった。
どこかで見たストレートな青春ドラマのワンシーンのように。
永遠に置いていかれそうな気分になって……、寂しさが息を切らして込み上げてきた……。
胸が苦しくなった。
台風が過ぎ去った後の水嵩が増した多摩川が私の気持ちをそうさせたんだ。隼人が悪いわけじゃない。
翌日、私は隼人がエントリーしている『都民マラソン2014』にエントリーした。開催日は五ヶ月後。
隼人の好きなものを私も好きになりたい。隼人と一緒に走って、健康的な汗を流したい。
目標というハードルを同じ高さに設定して私もそれを飛び越え、達成したい。
それから、大音量の目覚まし時計で毎朝五時に起きて多摩川の土手を走るようになった。
「俺、先行くから」
何日経っても同じ言葉が繰り返される。リピートされる壊れたカセットテープのよう。
隼人の耳に聴こえているクラシック音楽はきっと今日も変わりなく優雅なのだろう。聴きたいのはマラソンで乱れる私の呼吸音よりクラシック。
やっぱりマラソンなんて嫌い……。
バスも止まってないのに走る意味なんてない。
もし止まっていたとしても
「運転手さん、先行ってください。私、次でいいので」
と、ほどけてもいないスニーカーの靴紐を結ぶ仕草をするだろう。
そんな気分で立ち止まり俯くと、後ろから低音で少し鼻にかかった柔らかい声が響いた。
「一緒に走ろう」
「俺、先行くから」
何日経っても同じ言葉が繰り返される。リピートされる壊れたカセットテープのよう。
隼人の耳に聴こえているクラシック音楽はきっと今日も変わりなく優雅なのだろう。聴きたいのはマラソンで乱れる私の呼吸音よりクラシック。
やっぱりマラソンなんて嫌い……。
バスも止まってないのに走る意味なんてない。
もし止まっていたとしても
「運転手さん、先行ってください。私、次でいいので」
と、ほどけてもいないスニーカーの靴紐を結ぶ仕草をするだろう。
そんな気分で立ち止まり俯くと、後ろから低音で少し鼻にかかった柔らかい声が響いた。
「一緒に走ろう」
その声の持ち主は端正な顔立ちで、綿菓子のようにふんわり微笑んでいた。その微笑みが私の瞳の中でふんわり溶けた。
『ドクッ』
ひとつしかない鼓動が走り出した。
腕の振り方や地面の蹴り方、呼吸の仕方、水分補給まで優しく教えてくれる綿菓子のような人。
───小学生の頃、マラソン大会で最下位だった事もある私。
その時も多摩川の水嵩が増していた。台風が過ぎ去った後だったのかもしれない。
みんなの背中が遠く小さくなっていく、その寂しさは言葉にならない寂しさだった。
「おまえ、遅いな。あれで走ってたの?」
やっとゴールした直後、好きだった男子に笑われた。
一人が笑うと『皆、一斉に続け!!』というようにみんなが笑いだす。
その笑い声が辛かった。
笑いが伝染するのは面白い時、楽しい時がいいと思う。こんな風に伝染してほしくない。
傷つく人もいるんだから。
『ドクッ』
ひとつしかない鼓動が走り出した。
腕の振り方や地面の蹴り方、呼吸の仕方、水分補給まで優しく教えてくれる綿菓子のような人。
───小学生の頃、マラソン大会で最下位だった事もある私。
その時も多摩川の水嵩が増していた。台風が過ぎ去った後だったのかもしれない。
みんなの背中が遠く小さくなっていく、その寂しさは言葉にならない寂しさだった。
「おまえ、遅いな。あれで走ってたの?」
やっとゴールした直後、好きだった男子に笑われた。
一人が笑うと『皆、一斉に続け!!』というようにみんなが笑いだす。
その笑い声が辛かった。
笑いが伝染するのは面白い時、楽しい時がいいと思う。こんな風に伝染してほしくない。
傷つく人もいるんだから。
この作家の他の作品
表紙を見る
名探偵、赤沼光一
またもや殺人事件を解決へと導く
2017年11月23日*完結*
レビュー
ありがとうございました
月乃ミラ様
高山様
表紙を見る
『重なり合う、ふたつの傷』
子供の頃は泣けなかった
でも今は泣ける
あなたと出逢ったから
その涙は希望の涙か
それとも別れの涙か
今を生きている
あなたへ贈ります
玉置梨織(たまきりお)15歳
天野蒼太(あまのそうた)15歳
神田ルミ(かんだるみ)15歳
桜井零士(さくらいれいじ)19歳
「オレ、好きだな、君の声。鼻にかかったじゃれた声」
コンプレックスだった自分の声を好きになった瞬間。
*2014年9月9日完結*
どうぞよろしくお願いします
レビュー
ありがとうございました
mira!様
高山様
さいマサ様
小田真紗美様
シュレディンガーの猫様
こみあな様
表紙を見る
瀬名優人×小松結月
+友情出演 吉沢愛子
あの、国民的コーンスナックが
東京で買えなくなる。
残るは、あと一袋。
さてどうなる、
コーンスナックと恋の行方。
イケメンを超越した王子様。
私は瀬名先輩のことが、
好きで好きで、
どうしようもなくなりました。
2017年6月6日*完結*
レビュー
ありがとうございました
高山様
月乃ミラ様
小田真紗美様
英 蝶 眠様
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…