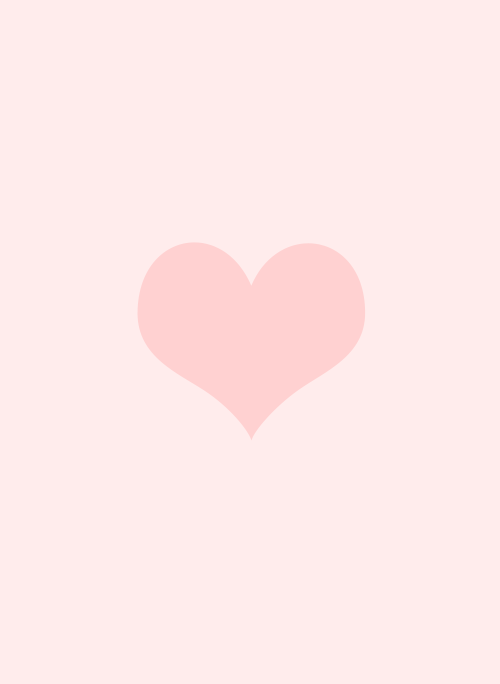花は、一番最初に送ってもらうグループだった。遅くなると家族が心配するからと、倉内の両親が気を使ってくれたのだ。
ずっとノンアルコールだったという倉内の父の車には、花と倉内、千恵と──何故かジャック。コウは、最後まで飲んでいくので居残りらしい。
「秋葉はサイコーでしたよ」と、助手席で話し続けるジャックをBGMに、花はどうにも朝からの疲れがどっと押し寄せて、うつらうつらしてしまった。
ぼんやりとたゆたう意識の中で、花は短い夢を見る。タロとフルールと倉内と自分がいて、ただ草原で遊ぶだけの楽しい夢。そうしたら、何故かいつの間にか倉内がタロになっていて、花はフルールになっていた。それでも、草むらの中で遊び続ける。やっぱり、ただ楽しい夢だった。
「……さん」と、軽く肩が揺らされる。
「花さん……ついたよ」
次の声ははっきり聞こえて、花ははっと目を開けた。ついでに頭を持ち上げる。気がつけば、隣の倉内の肩を借りていたようだ。
「す、すみません」
慌てて口元をぬぐう。よかった、よだれは出ていないと安堵する。
「いいのよ、疲れたんでしょ? ふふふ」と、千恵が倉内の横から顔を出して、にまにまと微笑んでいる。きっと寝顔を見られたのだろう。恥ずかしい花は、慌てて挨拶をして下りる動作に入った。
空っぽになったタッパーには、倉内家の料理の余り物が詰められていて、思ったほど軽くはならなかった。それを、倉内が抱えて一緒に降りてくれる。
明かりのついたままの玄関先で、花は振り返った。両手を出して、彼から風呂敷を受け取る。
「今日は楽しかったです、楓先輩」
「うん、楽しかった……楽しかったね、花さん」
言葉を噛み締めるように、倉内が言う。花は、言葉の重みの違いに気がついた。
花は、普通に言葉をしゃべる。だから、その言葉の重さを普段は考えない。言葉が苦手な倉内だからこそ、こうして感情を乗せた言葉を表すことが出来るのかもしれないと思った。
とは言っても、いきなり自分の言葉を変えられるはずもないのだが。
「何か楽しいものを見つけたら、私も楓先輩を誘いますね」
だが、少しは花も成長するのだ。いつまでも、倉内に誘われるばかりの人間ではない。大事な友達ということは、花から誘ったっていいのだ。
「た、楽しいものがなくても……つまらないことでもいいから、誘って」
そんな花に、倉内が一歩身を乗り出した。さすがにつまらないことでは誘えないと思ったが、花は彼もまた自分に誘われることを嬉しいと思っているのだと感じる。
「じゃあ、何でもないことでも、誘います」
つまらないことではなく、何でもないこと。ただの、普通の一日。ただの、ありふれた時間。
そんなささやかな時でも、きっと倉内と一緒なら楽しいに違いない。ただ、学校から一緒に帰る、そんな彼の誘いもまた、花は楽しかったのだから。
「うん、うん」
倉内は、言葉を噛み締める。彼にとって、それらの言葉はとても美味しい味がするのではないかと思えて、少し羨ましくなる。
花には味わえない、言葉の味。
「今日は、ありがとうございま……」
「花ー? 帰ったのか?」
最後のお別れの言葉は、中から父の声に被せられる。
「帰ってるー」
慌てて返事をして、じゃあと倉内に視線を向ける。
「挨拶……していく」
「えっ?」
なのに彼が視線を玄関の向こうに向けるので、花は焦った。夏の、風呂上りの父の姿は、ランニングと膝丈パンツだ。そんな家族の姿を見られるのは、少し恥ずかしい。
しかし、本人がせっかく出したやる気を削ぐわけにもいかず、花は玄関を開ける。
「た、ただいま」
小さくなりながら、花が風呂敷を抱えて中に入ると、父が玄関に歩いてきているところだった。
「こんばんは……」
「あ、ああ、こんばんは」
倉内の声が中に投げられた時、父の足がぴたっと一度止まる。
「きょ、今日は、素敵なお寿司を、わ、わざわざありがとうございました。ち、父も、母も、カナダに帰る従兄妹も……とても喜んでいました」
ボス犬に立ち向かう、若い犬を思わせる神妙で緊張した面持ちに、花まで緊張が伝染しそうになる。倉内が頑張っているのが、痛いくらいに伝わってくるのだ。
「あ、ああ、いや……うん、その辺は花が……なあ花?」
威厳を持って答えようとした父が失敗して、うなるように花に言葉を回す。ランニング姿では、威厳もへったくれも最初からないので、思わず花は吹いてしまったが。
「倉内のおば様から、おいしいものをおすそ分けしてもらったの。明日、食べようね」
重さの残る風呂敷を掲げて、父へアピール。「あ、それは、どうも」と、男子高校生に向けるのとは違う、妙な態度。
「あ、いえ、こちらこそ」と、倉内も頭を下げる。どこかで見た光景だなと思ったら、初めて倉内家を訪ねた時の自分と倉内母が、まさにこんな風だった。
そのまま男同士、微妙な空気を練り上げた後、「また、猫で何かあったら来るといい」と、父は逃げ出してしまった。猫に何かなくても、今のように倉内は来ているというのにと、花はまた笑ってしまう。
しかし、笑えないのは倉内だった。ふぅーっと大きく息を吐き出して肩の力を抜いたのだ。
オス同士の、縄張りの確認のような感覚は花には分からないが、それでも彼がやり遂げたのが分かる。
「そ、それじゃ、花さん……おやすみ」
「はい、お休みなさい、楓先輩」
やり遂げた男に、笑顔で軽く手を振って見送る。そんな彼女に、ほっとした笑みを返して、倉内は去っていった。
車が去る音を聞き終えた後、花は風呂敷を抱えて台所へと入る。母が冷蔵庫の中身を整理していた。父はもう、自室に戻ったのだろう。
「おみやげ、あるのよねー?」と、玄関の父との会話を聞いていたとしか思えない言葉と差し出される手。
「珍しいね、出てこないなんて」
「だって、お父さんが行ったもの……二人も出て行くのは大げさでしょ?」
ふふっと笑いながら母は風呂敷を受け取り、ささっとタッパーの中身を小さな容器に移し始める。
「クレープ皮の余りももらったの、いろいろ巻いておいしかったよ」
寿司飯の入っていた方には、折りたたんだそれ。母は、普段家で作らない食品にやったと小さく小躍りしていた。
「でも……猫はないわよねぇ」
いただきものを空けた冷蔵庫の中に詰め込みながら、花の母が思い出し笑いを始める。どうやら、玄関先の父の話のようだ。
「うん、あれはない。ランニング姿で、獣医の威厳をアピールしようとしてた」
花が同意すると、母の想像が膨らんでしまったのか、更にぶふっと笑う。
「複雑なのよ、お父さんも……ああ、おかしい。最近、花は倉内くんとばっかり遊ぶでしょ? 気になって気になってしょうがないの」
今日も夕食の時はと、花がいない間にひと悶着あったことを伝えられる。前回の写真の時もそうだったが、どうにも花の父は倉内にひっかかりを覚えているようだ。
「大事な、友達だから……楓先輩は、どんどん成長してて、よく助けてもらうようになって……ううん、そんなことは本当は関係なくて、一緒にいてすごく楽しいから、とても大切な友達になったの」
そのひっかかりを解く鍵になるとは思わないが、花は正直に自分の気持ちを言葉にしていた。いままでなかった、二人の関係を表す名前。親にも曖昧にしていたそれに、花はちゃんと名前を書いてから母に見せた。
「あら、そう?」
母は、少し首を傾げた後、「まあ、花にしてみれば上出来かもね」と歯を見せた。
お風呂につかって、今日のことを一通り思い出した後、花はパソコンをつけた。倉内のブログをチェックするが、今日はまだ更新がない。片付けで忙しいのかもしれない。
疲れていた花は、そのままバタンキューと眠ってしまう。夢なんか見る隙間もないほどの熟睡だった。
ブログは──翌朝変わっていた。
『昨日の従兄妹たちの送別会では、ご飯の時以外はフルールと一緒にいた。ずっと一緒にいたいけれど、人と猫の間には乗り越えられない壁がある。でも、そんなことはフルールには関係ない。少し僕の部屋で待ってもらった後に迎えに行ったら、やっぱり怒られた。お詫びにいっぱい撫でた。僕より撫でるのが上手な友達と二人で撫でた。ああ……昨夜はよく眠れなかった。眠い。でも、フルールが朝から乗っかって起こしてくれたから起きる。可愛い僕のフルール……いつまでも僕の傍にいて。それが、どんな名前の関係でもいいから』
ブログには、相変わらずフルール病が炸裂していたが、花の視線は一点に集中していた。
『僕より撫でるのが上手な友達』
おおと、花は感動した。これはきっと、自分のことなのだ、と。
初めて倉内のブログに登場した自分と『友達』という形容に、この日一日、とても楽しい気分で花は過ごしたのだった。
『終』
ずっとノンアルコールだったという倉内の父の車には、花と倉内、千恵と──何故かジャック。コウは、最後まで飲んでいくので居残りらしい。
「秋葉はサイコーでしたよ」と、助手席で話し続けるジャックをBGMに、花はどうにも朝からの疲れがどっと押し寄せて、うつらうつらしてしまった。
ぼんやりとたゆたう意識の中で、花は短い夢を見る。タロとフルールと倉内と自分がいて、ただ草原で遊ぶだけの楽しい夢。そうしたら、何故かいつの間にか倉内がタロになっていて、花はフルールになっていた。それでも、草むらの中で遊び続ける。やっぱり、ただ楽しい夢だった。
「……さん」と、軽く肩が揺らされる。
「花さん……ついたよ」
次の声ははっきり聞こえて、花ははっと目を開けた。ついでに頭を持ち上げる。気がつけば、隣の倉内の肩を借りていたようだ。
「す、すみません」
慌てて口元をぬぐう。よかった、よだれは出ていないと安堵する。
「いいのよ、疲れたんでしょ? ふふふ」と、千恵が倉内の横から顔を出して、にまにまと微笑んでいる。きっと寝顔を見られたのだろう。恥ずかしい花は、慌てて挨拶をして下りる動作に入った。
空っぽになったタッパーには、倉内家の料理の余り物が詰められていて、思ったほど軽くはならなかった。それを、倉内が抱えて一緒に降りてくれる。
明かりのついたままの玄関先で、花は振り返った。両手を出して、彼から風呂敷を受け取る。
「今日は楽しかったです、楓先輩」
「うん、楽しかった……楽しかったね、花さん」
言葉を噛み締めるように、倉内が言う。花は、言葉の重みの違いに気がついた。
花は、普通に言葉をしゃべる。だから、その言葉の重さを普段は考えない。言葉が苦手な倉内だからこそ、こうして感情を乗せた言葉を表すことが出来るのかもしれないと思った。
とは言っても、いきなり自分の言葉を変えられるはずもないのだが。
「何か楽しいものを見つけたら、私も楓先輩を誘いますね」
だが、少しは花も成長するのだ。いつまでも、倉内に誘われるばかりの人間ではない。大事な友達ということは、花から誘ったっていいのだ。
「た、楽しいものがなくても……つまらないことでもいいから、誘って」
そんな花に、倉内が一歩身を乗り出した。さすがにつまらないことでは誘えないと思ったが、花は彼もまた自分に誘われることを嬉しいと思っているのだと感じる。
「じゃあ、何でもないことでも、誘います」
つまらないことではなく、何でもないこと。ただの、普通の一日。ただの、ありふれた時間。
そんなささやかな時でも、きっと倉内と一緒なら楽しいに違いない。ただ、学校から一緒に帰る、そんな彼の誘いもまた、花は楽しかったのだから。
「うん、うん」
倉内は、言葉を噛み締める。彼にとって、それらの言葉はとても美味しい味がするのではないかと思えて、少し羨ましくなる。
花には味わえない、言葉の味。
「今日は、ありがとうございま……」
「花ー? 帰ったのか?」
最後のお別れの言葉は、中から父の声に被せられる。
「帰ってるー」
慌てて返事をして、じゃあと倉内に視線を向ける。
「挨拶……していく」
「えっ?」
なのに彼が視線を玄関の向こうに向けるので、花は焦った。夏の、風呂上りの父の姿は、ランニングと膝丈パンツだ。そんな家族の姿を見られるのは、少し恥ずかしい。
しかし、本人がせっかく出したやる気を削ぐわけにもいかず、花は玄関を開ける。
「た、ただいま」
小さくなりながら、花が風呂敷を抱えて中に入ると、父が玄関に歩いてきているところだった。
「こんばんは……」
「あ、ああ、こんばんは」
倉内の声が中に投げられた時、父の足がぴたっと一度止まる。
「きょ、今日は、素敵なお寿司を、わ、わざわざありがとうございました。ち、父も、母も、カナダに帰る従兄妹も……とても喜んでいました」
ボス犬に立ち向かう、若い犬を思わせる神妙で緊張した面持ちに、花まで緊張が伝染しそうになる。倉内が頑張っているのが、痛いくらいに伝わってくるのだ。
「あ、ああ、いや……うん、その辺は花が……なあ花?」
威厳を持って答えようとした父が失敗して、うなるように花に言葉を回す。ランニング姿では、威厳もへったくれも最初からないので、思わず花は吹いてしまったが。
「倉内のおば様から、おいしいものをおすそ分けしてもらったの。明日、食べようね」
重さの残る風呂敷を掲げて、父へアピール。「あ、それは、どうも」と、男子高校生に向けるのとは違う、妙な態度。
「あ、いえ、こちらこそ」と、倉内も頭を下げる。どこかで見た光景だなと思ったら、初めて倉内家を訪ねた時の自分と倉内母が、まさにこんな風だった。
そのまま男同士、微妙な空気を練り上げた後、「また、猫で何かあったら来るといい」と、父は逃げ出してしまった。猫に何かなくても、今のように倉内は来ているというのにと、花はまた笑ってしまう。
しかし、笑えないのは倉内だった。ふぅーっと大きく息を吐き出して肩の力を抜いたのだ。
オス同士の、縄張りの確認のような感覚は花には分からないが、それでも彼がやり遂げたのが分かる。
「そ、それじゃ、花さん……おやすみ」
「はい、お休みなさい、楓先輩」
やり遂げた男に、笑顔で軽く手を振って見送る。そんな彼女に、ほっとした笑みを返して、倉内は去っていった。
車が去る音を聞き終えた後、花は風呂敷を抱えて台所へと入る。母が冷蔵庫の中身を整理していた。父はもう、自室に戻ったのだろう。
「おみやげ、あるのよねー?」と、玄関の父との会話を聞いていたとしか思えない言葉と差し出される手。
「珍しいね、出てこないなんて」
「だって、お父さんが行ったもの……二人も出て行くのは大げさでしょ?」
ふふっと笑いながら母は風呂敷を受け取り、ささっとタッパーの中身を小さな容器に移し始める。
「クレープ皮の余りももらったの、いろいろ巻いておいしかったよ」
寿司飯の入っていた方には、折りたたんだそれ。母は、普段家で作らない食品にやったと小さく小躍りしていた。
「でも……猫はないわよねぇ」
いただきものを空けた冷蔵庫の中に詰め込みながら、花の母が思い出し笑いを始める。どうやら、玄関先の父の話のようだ。
「うん、あれはない。ランニング姿で、獣医の威厳をアピールしようとしてた」
花が同意すると、母の想像が膨らんでしまったのか、更にぶふっと笑う。
「複雑なのよ、お父さんも……ああ、おかしい。最近、花は倉内くんとばっかり遊ぶでしょ? 気になって気になってしょうがないの」
今日も夕食の時はと、花がいない間にひと悶着あったことを伝えられる。前回の写真の時もそうだったが、どうにも花の父は倉内にひっかかりを覚えているようだ。
「大事な、友達だから……楓先輩は、どんどん成長してて、よく助けてもらうようになって……ううん、そんなことは本当は関係なくて、一緒にいてすごく楽しいから、とても大切な友達になったの」
そのひっかかりを解く鍵になるとは思わないが、花は正直に自分の気持ちを言葉にしていた。いままでなかった、二人の関係を表す名前。親にも曖昧にしていたそれに、花はちゃんと名前を書いてから母に見せた。
「あら、そう?」
母は、少し首を傾げた後、「まあ、花にしてみれば上出来かもね」と歯を見せた。
お風呂につかって、今日のことを一通り思い出した後、花はパソコンをつけた。倉内のブログをチェックするが、今日はまだ更新がない。片付けで忙しいのかもしれない。
疲れていた花は、そのままバタンキューと眠ってしまう。夢なんか見る隙間もないほどの熟睡だった。
ブログは──翌朝変わっていた。
『昨日の従兄妹たちの送別会では、ご飯の時以外はフルールと一緒にいた。ずっと一緒にいたいけれど、人と猫の間には乗り越えられない壁がある。でも、そんなことはフルールには関係ない。少し僕の部屋で待ってもらった後に迎えに行ったら、やっぱり怒られた。お詫びにいっぱい撫でた。僕より撫でるのが上手な友達と二人で撫でた。ああ……昨夜はよく眠れなかった。眠い。でも、フルールが朝から乗っかって起こしてくれたから起きる。可愛い僕のフルール……いつまでも僕の傍にいて。それが、どんな名前の関係でもいいから』
ブログには、相変わらずフルール病が炸裂していたが、花の視線は一点に集中していた。
『僕より撫でるのが上手な友達』
おおと、花は感動した。これはきっと、自分のことなのだ、と。
初めて倉内のブログに登場した自分と『友達』という形容に、この日一日、とても楽しい気分で花は過ごしたのだった。
『終』