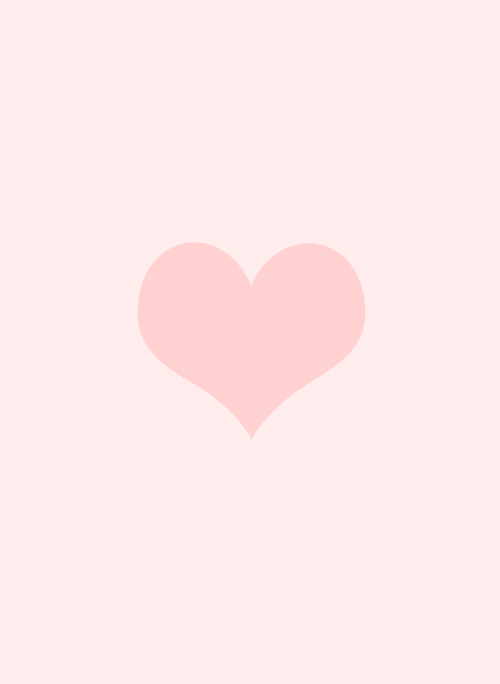勇二さんの言葉に、全員から笑みがこぼれる。
そして、それに反応するように、カランっとアイスコーヒーの氷が音をたてて崩れる。
そうだ…私と先生の恋は、世間的には『禁断の恋』だったんだよね。
皆にバレないように隠れながら恋をして、すごく必死だった。
会いたくても直ぐには会えなくて、デートもなかなか行けなかった。
電話も緊張しながらかけていたんだよね。
まだたった数ヶ月前のことなのに、すごく前に感じてしまう。
「本当、不思議な出会いよね。かっちゃん、伊緒ちゃんに感謝しなきゃ駄目よ?こんなおじさんを好きになってくれたんだから。」
「え?」
「それは俺も本当に感謝してます。あの頃は、まさか10も年上の俺を選んでくれるとは思っていませんでしたよ。付き合い始めの時なんて直ぐに飽きられるんじゃないかってビクビクしてましたし。ははは。」
「まぁそうだろうな。俺も同じ立場ならそう思うよ、あはははは。」
ちょっと、ちょっとちょっとちょっと待てい!!!
昔話に花を咲かせるのは全然良いけど、この会話はいただけない!!
「異議あり!!!」
3人が笑いあっている空間をぶち壊すように、大きな声と身振りで発言をする。
すると、私のあまりに突然の行動に驚いたのか、3人は目を丸くしながら私の方へと視線を向けた。
「ど、どうした?」
私の怒りのオーラを感じたのか、少し戸惑っている先生。
志帆さんと勇二さんも相当驚いているのか、口が半分開いている。
「…私が先生を選んだことに感謝?先生がおじさん?直ぐに飽きる?何ですかそれ。今の発言全てに異議ありです。」
あの初めて先生と一つになれた日にも思ったけど、やっぱり先生は私のことを解っていない。
いや、正確には解ってくれているんだけど、先生に対する気持ちの大きさだけは解っていない。
「私こそ、先生に感謝しなきゃいけないんです。こんな子供でリスクの高い私を選んでくれたことを。10歳も年上で色々な経験をしていて、それでもって魅力的な人が沢山周りに居る中で私なんかと付き合ってくれたことの方がよっぽど奇跡なんですよ。それに、先生に飽きることなんて一生無いです。先生以上に魅力ある人なんて知りません。だから…」
「伊緒。」
「え?」
勢いよく話す私を止めるように、先生の低い声が部屋に響く。
その声で我にかえり先生の方へと視線を向けると、顔を真っ赤にして照れている先生が目に入った。
「もういい、もう解ったから。」
「あ、え…す、すみません。」
その先生の反応で、どれだけ自分が恥ずかしいことを言っていたかが解る。
やってしまった…ついつい興奮してあんなことを…。
しかも、
「いやー、愛されてるわね、かっちゃん!!」
「本当だなぁ。相思相愛とは正にこのことをいうんだろうなぁ。」
この2人がいる前で……っっ!!!
恥ずかしさのあまり顔を伏せる私と先生。
そして、それをニヤニヤしながら見る志帆さんと勇二さん。
ううぅ…この2人、私達の反応みて楽しんでるっ!!
でも、今回は私が悪いから何も言えない。
いや、悪くなくても言い返せるわけじゃないんだけど。
「ふふ、あなた、今日は良い日ね。こんな幸せそうな二人が見れて。」
「あぁ、そうだな。」
「本当にかっちゃんが伊緒ちゃんと付き合ってくれて良かった!!じゃなかったら、私達は伊緒ちゃんに出会えなかったし、お店も続けられてなかったわ。」
「「え……?」」
志帆さんのまさかの発言に、下を向いていた顔を上げる。
さっきとは打って変わり、今度は私が驚いた顔をして志帆さんを見る。
「本当わね、あの夏頃、いつお店を閉めようかどうか2人で悩んでいたの。でも、伊緒ちゃんに会って、働いてくれるようになって、それからはいつ閉めるかなんて終わりのことばかり考えて悩んでいるのがバカらしくなってね。元気なうちは続けて行こうって2人で決めたのよ。だから、あの店を開けられるのも、このアップルパイを作れるのも、実は伊緒ちゃんのお陰なの。ふふ、知らなかったでしょ。」
「…し、らな、かったです……。」
「そりゃそうだな、言ってないんだから。」
「ふふふ、そうね。」
笑い合う2人を見る視界が少しずつ歪んでいく。
あ、どうしよう泣きそう…。
こんな楽しい雰囲気の時に泣きたくないのに、今にも涙が落ちてしまいそう。
「伊緒。」
膝の上に置いていた手に、先生の手が重なる。
「先生?」
「皆の分のアイスコーヒー入れてきてくれるか?あ、あと物置からティッシュ持ってきてくれ。場所解る?」
「はい、解ります。」
「ん、じゃぁ頼む。」
重ねられていた手が私の頭へと移動する。
ポンポンっと2回程頭を撫でて、それから先生は私に微笑みかけた。
「…アイスコーヒーのおかわり持ってきますね。」
その微笑みを合図に、視線をグラスに向ける。
全員分のグラスを回収し、一度それをキッチンに置いてから廊下の途中にある物置きへと向かう。
そして、廊下に出て3人の視界から外れた瞬間、1粒の涙が頬を伝っていった。
「…先生には敵わないなぁ。」
アイスコーヒーのおかわりも、ティッシュのお願いも、全部私の為にしてくれた先生の優しさ。
私が泣きたくないって思ったの、先生には解ったのかな。
じゃなかったら、先生の隣に新品に近いティッシュが置かれていたのに、わざわざティッシュ持ってきて欲しいなんて頼まないよね。
「…ふふふ。」
先生の不器用で暖かい優しさに、自然と笑みがこぼれる。
「いおー、場所わかるかー?」
「あ、はい、大丈夫です!!」
うん、もう大丈夫。
先生のお陰で笑っていられる。
「よし、行きますか。」
1人で小さく意気込みをしてから、3人の元へと向かう。
戻ってから食べたアップルパイは、甘みに混じって少しだけしょっぱく感じた。
ザ―――――ッッ……キュッ
「よし、これで終わりっと。」
時計が18時を指す頃、志帆さんと勇二さんが帰ることになり、先生は2人を家まで送っていった。
私は2人を家で見送り、使った皿の後片付け。
といってもそんなに沢山使ってないから直ぐに終わってしまった。
今さっきまでお菓子食べてたから晩御飯を作るのも早いし…うーん、やることないな。
部屋全体を見渡しながら、自分のやれることを探す。
が、志帆さん達が来る前に2人で掃除をしてしまったし、先程まで使っていた場所の掃除機はすでに済ませてある。
これは本格的に何もないのか。
部屋全体を見渡していた視線を、外へと向ける。
「あ、1つだけあった。」
そこで見つけた1つの仕事。
ベランダに干されたままの洗濯を取り込んで畳もう。
もしかしたら畳み方のこだわりとかあるかもしれないけど、それは後で直せばいいし。
何より、今何もせず座っているよりはいいだろう。
キッチンの電気を消し、ベランダへと移動する。
開けた窓からは外の生暖かい風が入ってきて、夏の匂いが鼻をかすめる。
この分だと、直ぐに猛暑になるだろう。
とゆうことは、喫茶店に来るお客さんも増える。
暑い中にいる人達にとって、涼しくて冷たい物が飲める喫茶店は救いの場所に見えることは多々ある。
それは寒い時も同様で、だから、夏や冬には自然とお客さんが増えてくるって勇二さん言ってた。
うーん、今でも十分忙しいのに、更に忙しくなったら回っていくのかな…。
あの喫茶店はコーヒーだけじゃなくてドルチェも人気だからな…志帆さんはドルチェ、勇二さんはドリンクに付きっ切りになるであろう。
とゆうことは、私がお出迎えと会計と運搬とヘルプでドリンクとドルチェ……いやいやいや、流石にこれは難しいんじゃないか?
やばい、これからのこと考えてたらぞっとしてきた。
「どうするかなぁ…。」
頭ではこれからのことを考えながら、取り込み終えた洗濯を1枚ずつ畳んでいく。
カチ、カチ、と時計の音だけが鳴り響くなか考えをまとめていく。
とりあえず明日2人に相談してみようか。
あ、いやまてよ…。
そういえば、帰り際に志帆さん達が…「おーい、伊緒さん?」
「――――っっ!!!?」
喫茶店のことでいっぱいだった頭の中が、一気に真っ白へと変わっていく。
「何俺のパンツ眺めながら考えてんの?」
「え?パン、ツ……?」
先生の言葉を飲み込めないまま、自分が手にしているものへと目をやる。
「っっ!!!!!」
そこにあったのは男性用の、先生の下着だった。
「あ、いや、これは、ちがくてっ!!」
男性用の下着なんてスーパーとかでよく見るから初めてという訳ではないが、先生の物となると話は別である。
どうしようどうしようどうしたらいいんだ!!!
このまま持っているのは変だし、変態だと思われる。
先生の顔面に投げつける?
いや、顔面は駄目だろう。
…違うな、投げつけることから間違っている気がする。
うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ良い案が出てこない!!!
「あの、先生、これは別に眺めてたわけではなくてっ」
「ぶはっ、あははははっ」
「え?…ちょ、何笑ってるんですか。」
「いや、そんなに焦らなくてもと思ってな。畳んでくれようとしてただけだろ?それくらい周りの状況見たら解るよ。あははははっ」
私のリアクションにお腹を抱えて笑う先生。
うん、これはあれだな、顔面に投げつけるが正解だった気がする。
今からでも遅くないな、よし投げよう。
「あ、おい、投げるなよ。」
「え。」
「投げつけてやるって顔してる。」
……こんなことまでお見通しとは。
さっきは嬉しくて感謝もしたけど、今は腹立たしさしかないな。
「先生のばか、もう畳んであげません。」
先回りされ投げるのは禁止されたので、床に下着を置き立ち上がる。
本当は畳んだものひっくり返して仕返ししようかと思ったけど、それは子供っぽすぎる気がするからね、やめる。
とりあえず洗面所にでも行って落ち着こう。
少しだけ拗ねてやる。
「伊緒、待って。」
立ち去ろうとした私の手を、先生が掴む。
さっきも感じた先生の温もりはやっぱり暖かいもので、触れられただけで安心してしまう。
「…何ですか。私怒ってるんですよ。」
でも、今は安心より怒りが勝っております。
本当は先生が帰ってきたらさっきのお礼を言おうと思ってたけど、そんなもの忘れました、捨てました。
「ごめん、からかいすぎた。」
「謝っても許しません。……今は。」
「ふはっ、その言い方だと、後では許してくれるの?」
「私の拗ねモードが切り替わったら許してあげます。」
わざとらしく、顔に空気を含み片側の頬を膨らませる。
子供っぽいけど、この顔が一番拗ねていると相手に伝えられるであろう。
「…なんだそれ、可愛いとしか思えないんだけど。」
「へ?」
「伊緒のそんな顔初めて見たなぁ。可愛い。」
そう言って笑いながら、先生は私の顔を両手で包み込む。
その行動と言葉の衝撃に、膨らませていた頬が一気にしぼんでいく。
やばいやばいやばい、このまま先生のペースに持っていかれたら拗ねモードがドキドキモードに切り替えられてしまう!!!
いやもう、半分位切り替えられてるんですけどねっ!!!
先生の手を振り払おうと腕に力を入れる。
「―――ぅわっ!!!」
でも、そんな私の考えを察知したのか、腕を上げようとした瞬間、力強く抱きしめられた。
「ごめん伊緒。もういじめないから許して。」
「……………。」
先生の低い声にドキドキしながら、揺らぎそうな気持ちを一生懸命怒りの方へと留める。
駄目、こんなことで許してたら先生を甘やかすことになるっ!!!
「…実はさ、俺が2人を送ってる間、伊緒が1人で泣いてるんじゃないかって心配してたんだ。」
「え?」
突然の発言に、留めていたはずの気持ちがどこかへ飛んでいきそうになる。
「さっき志帆さんの話し聞いて泣きそうになってただろ?だから、俺がいない間に泣いてるんじゃないかって。でも、帰ってきたらいつも通りの伊緒がいてさ…。何かそれがむしょうに嬉しくて、浮かれていじめすぎた。すまん。」
抱きしめられているから顔は見えないけど、お互いに鼓動が速くなっているのだけは解る。
先生も私も、すごくドキドキしている。
「…え、え、え、そんなこと…いやでも、何で1人で泣いてたら心配なんですか?」
ドキドキして、凄く動揺しながらも先生に問いかける。
すると、先生は抱きしめる力を少しだけ強めた。
「そりゃ、伊緒が泣いてたら…抱きしめて、隣に居てやりたいって思うからだよ。高校生の頃みたいに1人で泣くんじゃなくて、今は近くにいれるんだから…俺が居るところで泣いて欲しいんだよ。」
この作家の他の作品
表紙を見る
「ちょっと…先生待ってっ!!」
「…ん?なに……嫌?」
そう言いながら、又キスをする。
まだ答えてないのに……。
苦いコーヒーと先生の匂いが
漂うこの教官室でキスをする。
「もう一回してもいい?」
「いやいや、ここ学校!!」
はははっと笑いながら、
先生は又私にキスをする…。
\感想ノート・レビュー/
いつも励まされてます!!
僕ちみ様・すっチャン様・
遊哉様・ひか*様・狸様・
LOvE様・愛か様・
乙姫いちご様・たくくま様・
ペペロンえりか様・
あーさ5296様・しーCHAN様・
ことぎし。様・めがねチャン様・
れいな★様・みおあず様・
カズユキヨリ様・へにー様・
さてぃあ様・mehi様・
ぁぃく様・來雨様・
藤堂ありあ様・葵翼様・
りゃー♪様・スカイマリン様
感謝の気持ちでいっぱいです!
『先生と教官室2~新しい道~(完結)』
『先生と教官室3~沢山の初めて~(更新中)』
『先生と執事(完結)』
『先生と執事【続・短編】(完結)』
続編、別作品も是非読んでみて下さい!!
表紙を見る
「んっ…やっぱり無理…苦い。」
「じゃぁ俺が飲ませてやる。」
「えっっ!!ちょっ先生!!」
「バカ、大人しくしろ。」
「ーっっ!!!!!!」
そう言って私を抱きしめてくる
先生の身体からコーヒーの匂い
がして思わずキュンッとする。
「せ…んせ…。」
「……なんだ?」
そして、抱きしめられた後の
キスからはフワリとコーヒー
の苦味がして、いつも私を
大人の気分にさせてしまう。
もう何度私と先生はこの教官室で
抱きしめあいキスをしたのだろう。
この、大好きな教官室で
大好きな私だけの先生と……
『先生と教官室』の続編です。
『先生と教官室3~沢山の初めて~』
『先生と執事』
こちらも宜しくお願い致します!!
表紙を見る
私のお母さんは大手会社
の社長でもある、お嬢様
私のお父さんは高校の教師
でもある、お母さんの執事
麻椿(35)×雄輝(44)
私は、そんな2人の娘
冨田 永愛(12)
あれから数年後を書いた
短編の物語です(^O^)/!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…