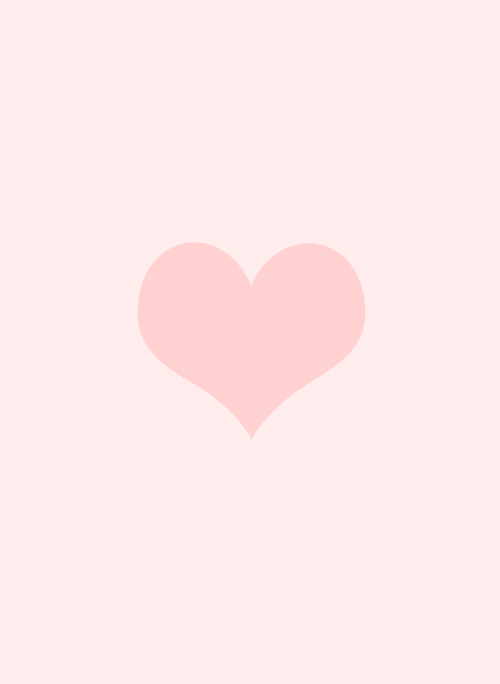カチ…カチ…と、時計の音が二人の空間に響き渡る。
そして、その音に同調するように自分の鼓動が速くなっていく。
この静かな時間、嫌だな…言ってしまったことを強く後悔してしまう。
緊張する、恥ずかしい、怖い。
もういっそこの空間から逃げてしまいたくなる。
「伊緒。」
「………はい。」
固まっていた空間が、先生の低い声によって崩されていく。
怖くて見られないけど、先生今どんな顔をしているのかな…。
「やべぇ、泣きそう。」
「…………え?」
え、ちょ、今、なんと?
泣きそう?先生が?
「え、先生何言って…。」
「いや、俺も自分で自分が良く解らん。でも、何だろうな凄く嬉しい気持ちなんだ。伊緒に色々してもらって俺は幸せ者だなぁって思ってたら、いつの間にか泣きそうになってた。」
「え…。」
「ははは、感極まって泣くとか俺も相当老けたなぁ。」
そう言って笑う先生の目には、確かに少しだけ涙が浮かんでいた。
嬉しいって、幸せだって、私の行動や言葉でそんな風に先生は思ってくれるんだね。
「せんせっ……。」
「うわっ」
床に座る先生の上に飛びつくように、思いっきり先生の胸へと飛び込んだ。
飛び込んだ先生の胸からは、私と同じくらい速い鼓動の音が聞こえる。
体温もいつもより高い気がする。
先生も私と同じように恥ずかしかったり緊張しているのかな。
「先生、もっと泣いてもいいんですよ?」
「あ?泣かねぇよ。男はそんなに簡単に泣いたりしないんですー。」
「何ですかそれ、さっきまでの可愛い先生はどこにいったんですか。」
「可愛いってなんだ、可愛いって。」
「そのままの意味です。涙目になってて、それはもう可愛かったですよ?ふふっ」
「よし、伊緒、覚悟しろ。歯くいしばれ。」
「え、きゃ、あはははははっちょ、こしょぐるの、反則…あははっっ」
さっきまでのぐちゃぐちゃした気持ちが、今では嘘のように消えてしまった。
先生と一緒に居られることがただただ嬉しくて、楽しい。
さっきの私の『お誘い』は先生にどう捉えられたか解らないけど、きっと気持ちは伝わってる。
先生は私のエスパーだもん、そうでしょ?
「せんせ…このままだとスーツ皺になりますよ?」
「あぁーそうだな。…それに、忘れてたけど腹も減ったし…ご飯食べようか。」
「ふふっ、そうですね。今準備するんで着替えてきて下さい。」
「あぁ。」
ひとしきり私をこしょぐって満足したのか、先生は素直に寝室へと着替えに向かう。
よし、私もご飯温めなおそうかな。
「あ、伊緒。」
「はい。」
「ただいま。…さっき、言い忘れてたからな。」
「……はい。お帰りなさい、先生。」
――――――――――――――………
「はぁー…癒されたぁ……。」
「へ?何か言いました?あ、コーヒーどうぞ。熱いですよ。」
「ありがと。いやー、飯食って風呂入るっていうことが自分一人と誰かとやるのとではこうも違いがあるんだなぁと思ってさ。何か今日はいつもの倍は癒された気がする。」
「あははっ、そうなんですか?」
「そうだよ。伊緒も一人暮らししてみたらきっと解る。」
「そうかもしれないですね。あ、私晩御飯の片付けしてるので何かあったら呼んで下さい。」
「あぁ、ありがとな。」
お風呂から出てソファーの上でまったりとしている先生。
私が淹れた珈琲を飲みながら新聞や本を読む姿を見ていると、不思議とそこの空間が学校の教官室に見えてくる。
先生、今も昔と変わらず珈琲ばっかり飲んでいるのかな。
いやでも、教官室の冷蔵庫って意外にオレンジジュースとかココアも入ってるんだよね。
進藤先生あたりが飲み物の種類増やしてそうだし。
…進藤先生、元気かな?
恵那との進展はどうなってるんだろう。
そろそろダブルデートもしたいし、恵那に連絡しなきゃだなぁ。
あ、そういえば…教官室といえば、先生ソファーで寝てたこともあったなぁ。
うーん、あの先生の寝顔は出来れば誰にも見られたくないんだけど、でも先生意外に無防備だし…。
「伊緒。」
「うえ?!…あ、何ですか?」
「…何考えてる?顔が険しいぞ。」
「あ、いやー大したことじゃないです。」
「…ふーん。まぁいいけど。」
私の返しに、こちらへと向けられていた視線が再び本へと戻っていく。
その姿を確認し、私の手も再び晩御飯の片付けへと取り掛かる。
やばい、今完全に気持ちがどっか飛んでたわ。
先生の視線にも全く気付かなかったし…。
「なぁ、伊緒…。」
先生の呼びかけに、再び取り掛かっていた片付けの手を止める。
あれ、先生本読み始めたと思ったのに。
珈琲のおかわりか何かかな?
「どうかしましたか?」
キッチンから先生がいたリビングへと移動し、ソファーへと近づく。
すると、先生は開いていた本をゆっくりと閉じ、私の方へと顔を向けた。
「ん、こっちおいで。」
「へ?」
「早く。」
いつになく真剣な先生の目が私を襲う。
声だって低めだし、何、何なの…そんな不意打ちずるい。
「でも、まだ片付け終わってない…。」
「明日の朝やるからいいよ。それより、今は伊緒とひっついてたい。だから早くおいで。」
「――――――っっ」
有無を言わせないといったような口調で話す先生は、私に両手を広げておいでと言う。
どうしよう、久し振りの『おいで』の破壊力が半端じゃないんですけど…。
先生の言葉に応えるように、ゆっくりと広げられた手の中に入る。
そして、そのまま先生の身体に自分の体重を預けるようにして寄りかかってみた。
「…先生、凄い暖かいですね。」
「まぁさっきまで風呂に入ってたからな。」
先生より先にお風呂に入った私の身体が、先生の熱によってもう一度深く温められていく。
人の体温はやっぱり心地がいいなぁ…。
それとも、これは先生の体温だからこんなに気持ちがいいのかな…?
さっきまで広げられていた手は、今度は何かを包みこむようにして私に触れた。
「なぁ、伊緒さん。」
「ふふっ、何ですか?急に改まって。」
さっきまではあんなに俺様だったのに、今度はすごく申し訳なさそうに話してくる先生が面白い。
学校では特定の人以外の前ではあんまり表情を変えないから、もしその人達が先生のこんな姿みたら凄く驚くんだろうな。
やばい、少し見てみたい気がする。
どうしよう、これは恵那と文化祭にでも乗り込もうかな。
「おい伊緒、今何か良くないこと考えてるだろ。」
「え?いやいやいや、そんなことはないですよ?って、それより先生の方こそ私に言いたいことあるんじゃないですか?」
「あ、あぁ…。」
ん?抱きしめられる力が少しだけ強くなった?
何だろう、この歯切れの悪い感じ…もしかしてあんまり良くない話しなのかな。
今日起きた学校での問題事?
え、それとも別れ話?
いやいやいや、こんな抱きしめ方しといてそれはないだろ、どんだけ鬼畜だよ。
「先生?どうしました?」
「あー…いや、その…キス…」
「え?キス?」
「キス、して欲しいな…って思って…。」
何だと、このエロバカ教師め。
さっきから言うのをためらってたのはキスのおねだりかい。
心配した私の気持ちと時間を返せ。
「伊緒?おい?」
「紛らわしい。」
「え?」
「先生が深刻そうな顔したから重大なことかと思ったんです。心配して損しました。とゆうことで離して下さい、夕飯の片付けしてきます。」
本当は申し訳なさそうな態度でおねだりしてきて可愛いなとか思ったけど、毎度こんなおねだりの仕方されたら心配疲れしてしまう。
なので、少しお仕置きをしてみたいと思います。
「先生、湯冷めするといけないので早いところ布団に入った方がいいですよ。私も片付けだけしたらお邪魔しますね。」
抱きしめられていた手を私の身体から離し、身体をキッチンの方へと方向転換させる。
どうしようかな、どれくらい放置したらお仕置きになるだろうか。
それとも、片付けと称して先生が眠るまで近づかないでおいてやろうか。
うむ、とりあえず今すぐ離れて片付けながら考えるとするかな。
「じゃぁ先生、お休みなさい。」
私の冷めた発言に驚いたのか、おねだりを断られて怒っているのか、先生は今何も言わないで顔を伏せてしまっている。
まぁやりすぎ位が先生にとっては丁度いいお仕置きになるだろう。
さて、キッチンに向かいますか…グイッ
「え?」
私、今何か、引っ張られて………。
「キッチンになんか行かせる訳ないだろ。」
あ――……や、やばい予感しかしない……。
キッチンへと向かうはずだった身体は、先生の力によってソファーの上へと再び投げ出されてしまった。
目の前に広がるのは先生の少し怒った顔と明るい電気の光。
この光景懐かしいなぁ…まるで教官室でみた時みたいだ。
あぁ、そういえばあの時も先生に引っ張られてソファーの上に投げ出されたんだっけな。
「何するんですか、先生。」
でも、私はあの時みたいに先生に免疫が無い訳じゃない。
ここ数年でこのシチュエーションにも少しは慣れて、余裕だって出来てきているのだ。
「何って、押し倒したんだけど?」
「だから、何でですか?私片付けがしたいので、重要な話しじゃないならどいて下さい。」
「いやだ。」
「……何で。」
やばい、先生の反応が子供っぽくて可愛くなってきたぞ。
放置できるのか危うくなってきたぞ。
「…俺の中では、伊緒とのキスは重要なことに入るんだよ。だからどかない。」
「え……。」
「伊緒、キスしてくれないのか?」
「―――――っっ!!!」
なんなんだその不意打ち&甘え方わぁぁぁぁぁぁぁあ!!!!!
私のお仕置きをしようという意気込みを意図も簡単に打ち砕きおって!!
憎い、憎いぞ甲田先生!!!
「伊緒?」
押し倒された身体に力が入る。
うぅ、どうしても自分からのキスはめちゃくちゃ緊張してしまう。
いつも先生からしてくれるし、逆に私は先生からのキスを待っているばかりで自分からしてみようなんて思わないからな…。
「…一回だけですよ。」
そう言って自分の身体を少し持ち上げ、先生の服を引っ張り身体を引き寄せることでお互いの距離を詰める。
そしてそのまま、唇と唇が触れ合うくらいの優しいキスをした。
身体だけじゃなくて、唇も熱い。
服を掴む手にも更に力が入る。
「…はい、しましたよキス。」
ゆっくりと唇を離し、平然を装った風に身体をソファーへと戻す。
今はドキドキした素振りなんて見せてあげない。
見せて…あげない……と、いいたい所なんだけど、顔が赤くなっちゃいそうだから今すぐにでもキッチンに行きたい。
だから早く私の上からどいて下さい先生。
「先生?」
「…足りない。」
「はい?」
「もう一回。」
「え、何い…んんっ」
押し倒されている身体に先生の身体が覆いかぶさる。
そして、噛みつくように先生は私にキスをした。
さっきの触れるようなキスとは全く違う、深い深いキス。
お、おねだりなんてしなくても、最初っから先生がキスすれば良かったじゃないですかぁぁぁぁ!!!
先生からのキスを阻止することが出来ず、されるがままにキスを受け入れるしかない私。
いつまで経ってもキスの時の息継ぎが解らない私にとって、今の先生は凶器でしかない。
叩いてもビクともしないし、声を出したくても口が塞がれていて出来ない。
キスへのドキドキとあいまって、そろそろ苦しくなってきた……。
「せん…っっせ、もうくる…んっっ!!」
私は先生以外の男の人を知らないけど、きっと先生はキスが上手いと思う。
私が口を開くタイミングを見逃さずに唇を重ねてくるし、不快に思ったことだって一度もない。
むしろ先生とのキスは心地がよくて……あぁどうしよう、頭がボーっとしてきた…。
「伊緒、もっと……。」
「え、せ……」
長いキスが終わったと思ったら、今度は首筋へと唇があてられキスをされる。
そして、それと同時に服の中に先生の手が入ってきて、私の素肌へと触れた。
時折耳にかかる先生の吐息が熱くて、顔だけじゃなくて耳まで火照っていく。
いや、むしろもう全身が火照っている気がする。
「伊緒……」
私をじっと見る先生の目に、思わず吸い込まれそうになる。
さっきまでの勢いが急に消え、ただ私をじっと見つめる先生。
少し息が上がって真剣な顔…あー、かっこいいなぁ
「伊緒、俺のこと殴れ。それか、今すぐどこかに逃げろ。」
……………はい?
この作家の他の作品
表紙を見る
「ちょっと…先生待ってっ!!」
「…ん?なに……嫌?」
そう言いながら、又キスをする。
まだ答えてないのに……。
苦いコーヒーと先生の匂いが
漂うこの教官室でキスをする。
「もう一回してもいい?」
「いやいや、ここ学校!!」
はははっと笑いながら、
先生は又私にキスをする…。
\感想ノート・レビュー/
いつも励まされてます!!
僕ちみ様・すっチャン様・
遊哉様・ひか*様・狸様・
LOvE様・愛か様・
乙姫いちご様・たくくま様・
ペペロンえりか様・
あーさ5296様・しーCHAN様・
ことぎし。様・めがねチャン様・
れいな★様・みおあず様・
カズユキヨリ様・へにー様・
さてぃあ様・mehi様・
ぁぃく様・來雨様・
藤堂ありあ様・葵翼様・
りゃー♪様・スカイマリン様
感謝の気持ちでいっぱいです!
『先生と教官室2~新しい道~(完結)』
『先生と教官室3~沢山の初めて~(更新中)』
『先生と執事(完結)』
『先生と執事【続・短編】(完結)』
続編、別作品も是非読んでみて下さい!!
表紙を見る
「んっ…やっぱり無理…苦い。」
「じゃぁ俺が飲ませてやる。」
「えっっ!!ちょっ先生!!」
「バカ、大人しくしろ。」
「ーっっ!!!!!!」
そう言って私を抱きしめてくる
先生の身体からコーヒーの匂い
がして思わずキュンッとする。
「せ…んせ…。」
「……なんだ?」
そして、抱きしめられた後の
キスからはフワリとコーヒー
の苦味がして、いつも私を
大人の気分にさせてしまう。
もう何度私と先生はこの教官室で
抱きしめあいキスをしたのだろう。
この、大好きな教官室で
大好きな私だけの先生と……
『先生と教官室』の続編です。
『先生と教官室3~沢山の初めて~』
『先生と執事』
こちらも宜しくお願い致します!!
表紙を見る
私のお母さんは大手会社
の社長でもある、お嬢様
私のお父さんは高校の教師
でもある、お母さんの執事
麻椿(35)×雄輝(44)
私は、そんな2人の娘
冨田 永愛(12)
あれから数年後を書いた
短編の物語です(^O^)/!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…