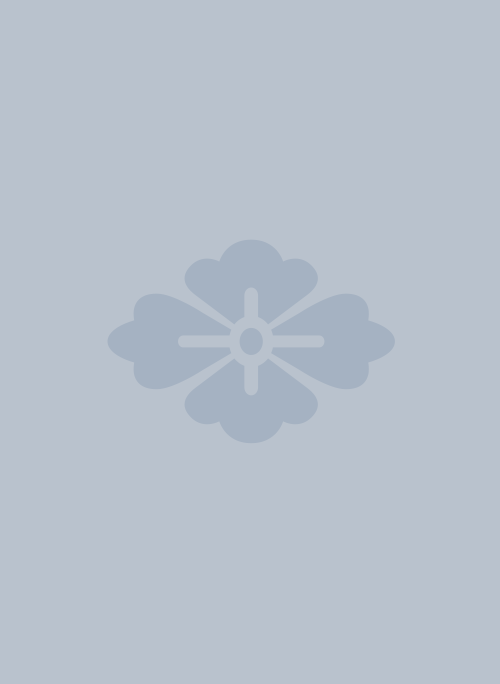「危ない!!」
龍馬を助けに行こうとした薫子の手を、とっさに武市が引っ張る。
「!」
「……ちっ!」
子供のような者が、薫子に刃を向けていたのだ。このままいては危険だ。
「さあ、行くぞ!」
「待って!龍馬さんが……!」
「グズグズしている暇はない!くるんだ!!」
「あっ……!」
武市は強引に薫子の腕を掴み、逃げるために走り出す。
後ろからは龍馬が、早くいけーー! と叫ぶ声と、刃が啄む音が聞こえる。
それを振り切るように走り続ける。
「武市さん!武市さん……!あっ……!」
大人の脚と子供の脚とでは速さも違う。足を縺れさせながら、薫子が何度も転びそうになる。
その度に、背後から迫る刺客の影が迫ってくる。
武市は追いつかれないように、薫子を引きずるようにして、連れて走った。
ある程度走って行くと、磐谷へと出る。
武市はその岩場の間に薫子を押し込める。
「ここに入っていろ…!」
「あっ…!」
「ほら!もっと奥に入れ……!お前なら入れるはずだ!」
「わ、私よりも龍馬さんが…!助けないと!」
「何を言っている!お前が行っても役にはたたん!!」
「たつ、たたないの問題ではありません!龍馬さんを助けないと……!」
「少しは黙っていろっ!!!」
「!」
「……僕だって龍馬のことは心配でたまらん。だが、あいつを信じている。だから、大丈夫だ。」
「……武市さん。」
伸ばされた手が優しく、薫子の頭をポンポンと撫でる。
それだけでも、龍馬が大丈夫なのだと安心が出来る。
しかし、次の瞬間にその期待は裏切りものとなる。
「うわっ!!」
「武市さん!?」
一瞬にして武市が消えてしまう。
おずおずと覗いて見ると、あの刺客が武市を岩場にたたき付けていた。
刃が喉元に充てられ、握っていた刀も足で動かせられなくなっていた。
「!」
「……まったく、上手く隠れるならば、声をもっと潜めるべきだな。」
子供のなりをしているが、その力は大人のものだ。
このままではやられてしまう……。
「それはもっともなことだな。だが、そんななりをしているが、お前は何者だ?大人にしては、滑稽だがな?」
「……言ってくれる。私はただの影武者としてだけに、育てられた者だ。こんなところで役に立つとはな。」
「子供の影武者とは……また、手の込んだことをしたものだな……。」
「我ら会津藩は幕府のためなら、命だけでなく自らの身体さえ差し出すのだ。」
「それは忠義なことだな…。それで、お前が相手をするのか?」
「そうだ。その前に邪魔なお前には消えてもらう。」
「………薫子……。」
刀も身体の自由を奪われた今、武市にはどうすることも出来ない。
後は、薫子次第だ。
「薫子……、聞いているか……? お前が潜んでいる岩場の間に、例の刀を包んで隠してある……。」
真っすぐと目の前にいる、鬼のお面を見つめながら、悟られないように薫子に、【白菊一】の在りかを教える。
薫子は言われた場所から、刀を包んであるものを見つける。
こうなってしまっては、武市と自分が助かる道は一つだけだ。
「うっ、うっ……!」
「僕はもうダメらしい………。」
「ううっ……!うっ……!」
音を出すのを堪えて泣く薫子の啜り泣きを聞きながら、振り上げられる刃を見つめる。
月明かりに照らされて、刃先が白く光る。
後は、もう………。
ジャリ……。
「……!」
振り上げられた刃が止まる。何かを見つめているようだ。促されるように、その方向を見ると、【白菊一】を手にした薫子がこちらへと、歩いて来ていた。
「………!!」
敵を見据えた薫子の目付きが一瞬にして変わり、辺り一面が血の海となった。
「…………。」
「うわっーーーーん!!うわっーーーん!!」
緊張の糸が切れたかのように、泣き出す薫子の声が山中に響き渡る。
「嫌い!嫌い!!こんな力があるから、皆死んじゃうんだ!!うわっーーーん!!」
泣きじゃくる薫子をただ、見ているしかなかった。
自分よりも大きな刀を握り、血まみれになって泣く姿はまるで狼のようだ。
武市は薫子が泣き止むまで、それを見ていた。
しばらくしてから、武市は薫子から【白菊一】を取った。
この刀はまだ幼い子供には早すぎたのだ……。
何を考えて、こんな者を幼い娘に託したのかは分からないが、人間の世界で生きて行くには【猫人族】という事実も、今日のことも忘れなければならない。
武市はまだ泣いている薫子を連れて、近くの川へと連れて行った。
「うっううっ……。」
「いつまでも泣いていないで、これで顔を拭きなさい。」
川の水に浸した手ぬぐいを薫子に差し出す。
「うっ……うっ……。」
「そんな顔をしていては、龍馬に会った時にびっくりされますよ?」
薫子はそれを受け取り、血で汚れた顔を拭う。
武市は着ていた羽織りを脱いで薫子に着せる。着物は真っ赤に染め上がっていて、洗っても、もう落ちないであろう。
「うっ……うっ……。」
「いつまで泣いているつもりですか?貴女は勝ったのですから、もう泣くのはやめなさい。」
「うっ……。」
「殺さなければ、殺されるだけです。それがこの世の道理です。」
「………ううっ。」
「君はもうここには置いてはおけません。刀を握った人間は、村人として生きられないのです。」
武市は立ち上がり、幼い薫子を見下ろす。
「人間の女として生きるか、再び刀を握って戦う道を選ぶか、それは君が選びなさい。そして、刀の道を選ぶ時には、必ず貴女を今度は養女ではなく、仲間として受け入れましょう。」
「………。」
「それまで、この刀にはここでまた、眠っていてもらいます。」
二度と目を覚ますことがないよう祈りつつ、武市は刀に重しを付けて、川の底へと沈めた。
薫子はただそれをじっと眺めていた。
「……さあ、行きますよ。龍馬が待っている。」
「はい……。」
二人が来た道を戻ろうとすると、龍馬の声が聞こえてくる。
「おーーい!武市ーー!薫子ちゃーーん!!」
両手をブンブンと振りながら、龍馬が駆けてくる。どうやら無事だったらしい。
「龍馬…!」
「龍馬さん…?龍馬さーーん!」
薫子は龍馬を目掛けて走り出した。
「うわっ!薫子ちゃん!?」
「龍馬さん 無事でよかったです!」
「……武市ーー!!薫子ちゃんがワシの名前を呼んだぜよー!!」
驚いたように龍馬が武市に向かって叫ぶ。今まで一度も呼んだことがなかったのだから当然のことだ。
「薫子ちゃん!もう一度ワシの名前を呼んでみるぜよ!」
「龍馬さん!」
「もう一度!」
「龍馬さん!」
「……嬉しいのは分かるが龍馬、みっともないぞ。」
「じゃが武市!ワシは嬉しくてたまらんぜよ!!」
穏やかに笑う武市とニコニコしながら、薫子と手を繋ぐ龍馬。
そして、人を殺したとは思えない無邪気さで笑う薫子。
これから運命が別つことになる三人を、朝日が優しく包み込んだ。
ーー数年後。
京の町に【花町街】という場所がある。
夜になると、綺麗に身を着飾った舞妓達がやって来る客人をもてなし、ひと時の楽しみを味あうのだ。
ここ【島原】もその一つである。
夜になると女を目当てに来る客が後を絶つことはない。一番上の【大夫】(最上級の遊女)から、一番下っ端の【新造】(見習い妹各の遊女)まで、休む暇もなく足を運び続ける。
そんな中、一人の芸妓が自分の妹各の者を捜し歩いていた。
「【白鳴】!白鳴ーー!」
「【明美】姐さん どうかなさいましたか?」
白鳴と同じ見習いの娘が尋ねてきた。
「白鳴は?白鳴を知らぬか?」
「白鳴でしたら、裏庭にいましたよ?」
「裏庭に……?」
急いで裏庭へと行くと、白鳴がたくさんの食器を一人で洗っていた。
「白鳴!」
別の場所から同じ見習いの格好をした者がやって来る。
「なんですか?」
「これも洗っていてちょうだい。」
「えっ……?」
「あと、あそこの台所も綺麗にしておくのよ!いいわね?」
「………。」
「返事は?」
「……はい。」
「本当、生意気な子……。」
吐き捨てるように言うと、その者は中へと入って行った。
白鳴は他の者とは違い、途中から入って来た娘だ。だから、同じ妹各でも皆より、下にみられていたのだ。
他の者達はそんな白鳴が、自分達と同じように扱われるのが気に入らないのだ。
明美は他の娘達がいなくなるのを確認してから、外へと出て白鳴に近寄る。
すると、食器を洗っていた白鳴が不意に、手を挙げて、指先に伝う雫を見つめていた。
雫が月明かりに照らされて、墜ちていく様もとても綺麗だ。
「白鳴…。」
「あ、明美姐さん!!」
慌てて振り返り、前掛けで手を拭う白鳴。
今まで明美には何も言わずにここにいたのだ。姉各の芸妓に従わないのは、もってのほかだ。白鳴は明美に怒られるのを覚悟していた。
「……今までここにいたのか?」
「はい……。」
「……これを全部お前が片付けていたのか?」
「はい……。」
明美は洗った食器を手に取って見る。おそらく、もっとたくさんの物を一人でこなしているに違いない。
「なるほど……。最近、お前が私の前に姿を見せないのは、このためか…。他には何をさせられている?」
「………。」
「黙っていないで言え。稽古も出来ぬほど、他に何をさせられている?」
「……洗濯や炊事、甘露梅作りなどをやっています……。」
「じゃあ、お前がほとんど雑用をやっていると言うことか?」
「はい。」
「そうか……。なら、仕方ないな。今日はもういい。明日の早朝に、また裏庭へ来なさい。」
「え……?」
「もうすぐ、昇格の試験がある。その試験に通れば、お前は位を授かり、一人前の芸妓となれるのだ。こんなことをしていては、芸妓にはなれん。」
「…………。」
「分かったら、さっさと早朝に間に合うように、仕事を済ませてしまいなさい。」
「わかりました。」
早朝というのは、皆が仕事をし終え、寝静まる時だ。この時ばかりは邪魔が入ることなく、稽古が出来るのだ。
日中は他の者達も起きてくるため、白鳴が稽古をするのならこの時しかない。
白鳴は早朝に間に合うように、押し付けられた仕事をこなすのであった。
勝手場の掃除から洗濯までこなし、繕い物を終える頃には、夜明け前となっていた。
夜も更けた帳となる時刻。
慌ただしかった足音も今は聞こえない。
少しの間眠っていた白鳴は目を覚まし、皆がいないことを確認すると、こっそりと抜け出し、日中に皆が使っている稽古場へとやって来る。
見つかるとまずいので、足元を照らすのは月明かりのみである。
立ち位置に立つと白鳴は、腰から扇子を取り出し、バッとそれを広げた。
月明かりに照らされて、踊る様はまるで月から舞い降りた天女のようだ。
日中は稽古が出来ないため、この時刻に白鳴は稽古をしていたのだ。
一通り踊り終えると、窓から月明かりが見えた。
そして、拍手が聞こえてくる。
「……!」
「……やはり、お前だったのか。」
「明美姐さん……!」
「毎夜、いなくなっていることは知っていた。稽古を目的として言ったが、この分では問題がないだろうな。」
「そう言って頂けると嬉しいです。」
「ところで、お前の舞いは独特だな。何処で覚えたのだ?」
「自分で作りました。」
「なんと……まあ。で、どんな意味の舞いだ。」
「月明かり、桜、……すべてに生きる女の舞いです。」
「なるほど、してその扇は?それも独自の動きか?」
「はい。……刀を現しています。全てを無に帰す刀です。」
「!!」
明美は慌ててそれを白鳴の手から取り上げた。
「明美姐さん……?!」
「その舞いはやめよ!!芸妓が名誉ある刀の舞いをしてはならぬ!」
「!」
「………してはならぬのじゃ…。」
「………。」
物苦しそうに言う明美。何かを隠しているようだが、それは白鳴には分からない。
「……とにかく、その舞いは誰にも見せてはならぬ。良いな?別の舞いを私が教えてやるから、お前はそれを踊りなさい。」
「……はい。」
明美はその踊りが、白鳴の運命を狂わすことになるのを恐れたのだ。
数年前に、武市から託され血まみれになっていた、哀れな子供……。
女として生きるために、狂われた運命を封じるために……。
それを今更、壊すわけにはいかないのだ。
明美は立ち位置に立つと、【白鳴】となった娘を見据える。
「……行くわよ。」
「はい。」
いつの間にか芽生えた愛情……。
出来ればこのまま、何も起こらないようにと祈った……。
白鳴はいつものように仕事をこなし、試験の日が近くなるにつれて、明美と共に座敷に上がることも多くなっていた。
もちろん、お客の相手をするわけではない。側で三味線を弾いたり、琴を奏でたりして、その場の雰囲気を盛り上げるのだ。
白鳴は他よりも笛を吹くのが上手かった。いつものように、笛を奏でていると、ふいに目の前が暗くなる。
「……?」
顔を上げて見ると、そこには今までお酒を呑んでいた者が、白鳴の前に立ち見下ろしていた。
みるからにかなり酔っている。
「……なんでしょうか?」
「お前、新造か…?」
「……そうですが、何か?」
「見かけない顔だが、身体付きは良さそうだ。お前、俺の相手をしろ。」
「お言葉ですが、私はまだ位を持っておりませんので、お客様のお相手をすることは出来ません。」
「生意気な。俺はこう見えても立派な侍なんだぞ?その俺が相手をしてやるって言ってんだ、素直に喜んだらどうだ? どうせ、もうすぐ水上げだろうが、早いか遅いかの違いだけだ。文句を言わずに来い!!」
「!!」
手を掴まれ強引に表へと出される。
「白鳴!」
とっさに明美も止めに入ろうとするが、それよりも早くに、白鳴は近くにあった煎れたての熱燗を、その男にぶっかけた。
「やめて下さい!!」
「……っっ!!」
「ああっーー!!なんてことを!!」
その場にいた姉各の者達が悲鳴を上げ、その場は騒然となってしまう。
明美はとっさに白鳴を自分の後ろへと避難をさせるが、その場から動けずにいた。
「大丈夫でございますか!?火傷はされておられませんか!?」
「何をしているのお前達!さっさと、水を持ってきな!!」
「は、はい…!」
妹各の者達がバタバタと廊下を走って行く。姉各の者達は、その男の着物を手ぬぐいで拭いていく。
「………っっ!!この女!こっちへ来い!!」
「!」
男は怒りまかせに、白鳴に手を出そうとする。
「お止め下さい!!」
すかさず明美が間に立つ。
「なんだ?俺に意見しようってんのか?退け!!」
「明美!」
「……どきませぬ!この娘は私の妹でございます!!それに、この者はそう出来ないと申したはずです!場をお慎み下さいませ!!」
「この女……、俺に意見をするとはいい度胸じゃねえか…。殺されてえのか!!」
「明美!!」
周りで悲鳴を上げる芸妓達。男はますます怒りをおぼえ、明美の胸倉につかみ掛かる。
「お客様!お止め下さい!!相手なら私がいたします!!」
「明美!早く謝って……!」
「白鳴!!なんてことをしたんだい!!今からでも、お相手をすると言いなさい!!」
「お客様!どうかお許し下さい…!!」
皆必死になって男をなだめようとする。本当に殺されてしまう芸妓だっているのだ。早く収集を付けないと、本当にまずいことになってしまう。
中には泣き出す者までいるが、白鳴と明美は決して意思を曲げずに、相手を睨みつけていた。
「……っ!」
絶対にこびないと悟ったのか、男の顔色が変わる。
「……なるほど、いい目をしている。こんな女を斬るのは勿体ないが、俺を侮辱する者は許せん…!この者を庭に引っ立てろ!!」
「!!」
周りにいた男の仲間が、二人の脇を抱え表へと連れだしてしまう。
「何事でございますか!?」
騒ぎを聞き付けた店の主である大夫が、他の女達を引き連れてやって来る。
「うるせー!退け!!この無礼な女共を斬って晒し首にしてやる!!」
「それは失礼をいたしました。が、しかし、そのようなことは酒の席で起きたこと。そのような者を斬っても、名が汚れるだけですわ。」
「なんだと!この俺様に説教するきか!?」
「ここは京の都を管理する島原です!侮辱が許せぬのなら、きちんと手順をお踏みになって頂きたい!!」
「なんだと!?こいつらもやっちまえ!!」
一勢に男達が襲い掛かってくる。しかし、主が手軽に男達を薙ぎ倒して行く。
「ぐっ……!!」
男達も酒が回り過ぎて、上手く身体がついていかないようだ。
あっという間にやられてしまい、玄関の外へと出されてしまう。
しかも、運が悪いことに見回りの兵士達に見つかり、追い回されるはめとなってしまった。
なんとも情けない姿である。
一方、事の一件は重大なことであり、客の気分と妹各のしつけを怠ったとして、明美は謹慎処分となり、白鳴は土間に出されて、また下働きとなってしまった。
着物を着替えて、せっせと炊事と甘露梅作りに励むのであった。
「白鳴ちゃん。」
「……?」
訪ねて来たのは、同じ妹各の者である。とくに何をするでないので、普通に接していた。
「……実はお菓子がきれてしもうてな。あったら、欲しいんやけど……。」
手にはお客様用の小鉢が握られており、白鳴とは違い、綺麗な手をしていた。
「……戸棚にあると思う。ちょっと待って。」
戸棚を開けてお菓子がないかを確かめる。
「……これ、全部白鳴ちゃんが漬けとるん?」
山のような梅を見て言っているのだろう。
「そう……。……あ、ないわ。お菓子きれてるみたい。」
「えっ!ど、どうしよう…!必要なのに……。」
そんなこと白鳴に言われても困る。オロオロと困った仕草をする。これも、ちゃんと稽古をされている証だ。
稽古をしたいが、今の白鳴にそんな余裕はない。
「……分かった。私が後で買っておく。」
「本当!?」
「うん。」
「ありがとう!じゃあ 私この後稽古だから、これよろしくね!!」
嬉しそうにして、小鉢を置いて出て行った。
「……稽古か……。」
置かれた小鉢を手にし、行った方向を見つめる。
今頃、皆自分達の姉各の者に稽古をつけてもらい、練習に励んでいるのだろう。
それに比べ、自分は……、
「…………。」
誰も白鳴に声をかける者も、庇う者もいない。
ただ、虚しく鍋の蒸気だけが返事をしていた……。
白鳴は約束通りに、お菓子を買うために町へと出ていた。
他にも買い物があったので、少し遅くなってしまい、荷物の重さがズッシリと白鳴の腕にのしかかる。
町へ出たのは、いつ以来だっただろうか……。
久しく出た町はとても賑やかだった。
川の近くまで来ると、薄紅の花びらが白鳴の目の前を横切る。
「……?」
上を見上げると桜の花が満開に咲いていた。薄紅色をした花びらが、風に誘われて雪のように、舞い散っていく。
「…………。」
白鳴はそれをしばらくの間眺めると、誰も近くにいないことを確かめ、川原へと降り、桜を後ろにして足元を流れる川を見つめる。
風が白鳴の髪の間を優しく吹き抜ける。
白鳴は襷を外すと、扇子を取り出し、あの舞いを踊り出す。
桜の花びらがまるでそれに合わせるかのように、ヒラリとヒラリと舞い落ちる。
そこへ、一人の青年が通り、足を止めた。
「………?」
一人の女の人が桜の木の下で踊っていた。歳は青年とそう変わらないぐらいなのに、まるで桜の使いのような、そんな感覚がした。
回りの音が聞こえなくなり、その舞いだけが青年の眼を釘付けにする。
ふいに、踊りが止まった。女がこちらに気づいたからだった。
女はこちらを見たが、それ以上の反応は見せずに、荷物を抱え川原から上がって行ってしまう。
「……待って!」
「!」
青年が女の手を掴んだ。女は驚いた顔をしていたが、ちょっと赤い顔をしていた。
「君、この近くの娘?」
「……!」
掴まれた手を振りほどこうとするが、青年が離さないように、しっかりと握っていた。
ナンパと思ったのだろうか、少し警戒しているような感じだった。
「どうなの……?」
「……そうです。」
「そっか…。」
掴まれた手が互いの熱で、汗ばみはじめていた。
「あの、離してもらってもいいですか?」
「……じゃあ、最後に質問してもいい?」
「……?」
「僕の名前は【沖田総司】。」
「……。」
「君の名前は?」
「……………。」
パアッと二人の間を風が駆け抜けて行く。
ヒラヒラと互いの間を、桜の花びらが舞う。
「!」
一瞬の隙をついて、白鳴は青年の手を振りほどいき、走って行って見えなくなってしまっていた。
沖田はそれを黙って見送っていた……。
「はぁはぁ……!」
この作家の他の作品
表紙を見る
愛することが罪なの………?
生まれながらに不運を背負い、故郷である長州藩を守るために、愛する男に刃をむけるしかなかった女【高杉薫】(月)。
散り行く運命にひたすら走り続け、愛する女と新撰組を守るために戦い抜いた男【沖田総司】。
彼らはなぜ出会い、愛し合うのか……?
彼らの運命と恋の物語。
ここから始まる………。
†読んだら感想など貰えたら嬉しいです†
表紙を見る
汝、影となり世の月となりー。
我、汝の光となり世を照らすー。
時は平安時代から幕末期まで、あらゆる運命と愛、そして時代に翻弄されながらも、自らの宿命に挑む者達がいたー!
幕末超大作!
【新撰組物語】。
いざ、開幕!
†平安時代から幕末まで描くので、かなり長い物語になります。
†幕末期になると 有名な幕末志士達が出てきます。
沖田総司/土方歳三/近藤勇/坂本龍馬/武市半平太/中岡慎太郎/岡田以蔵/等…。
†感想などもらなえたら嬉しいです。
では、物語をお楽しみ下さい。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…