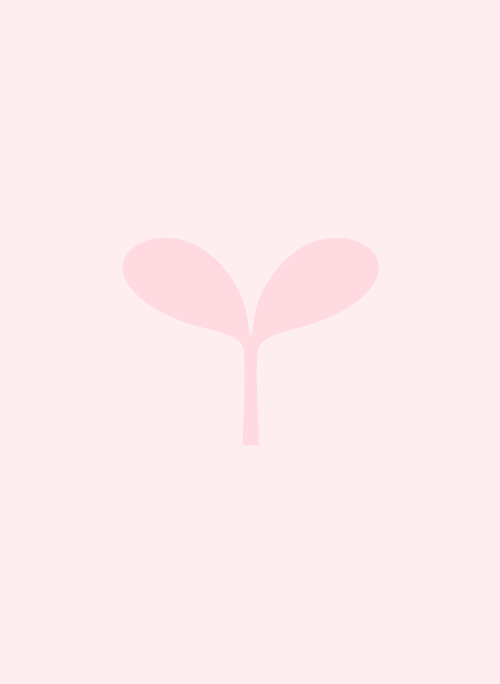『卒業式』
校門の前に、看板が置いてあった。
どことなく哀愁を漂わせているのは、学校全体か、それとも…。
朝の10時、看板の上にポツポツ降ってくる水。
「…ぁ」
女はその光景を見て、反射的に呟いた。
幸い、卒業生が入場してきたところなので、その呟きは音楽と拍手に掻き消された。
(雨が…先輩の、卒業式なのに…)
拍手の手を止めず、卒業生の列に体を向けている女。
その女が視線だけ上にあげ、降り始めた雨を見つめていたなど、いったい誰が気付こうか。
そして眉を下げて悲しそうな顔をしているなど、誰が気付こうか。
女の憂いを帯びた瞳には、いったい“なに”が映っているのだろうか。
それはきっと、女にしか分からない…。
「三組の入場です」
その言葉に女はハッとして、卒業生が入ってくる入り口に目を向けた。
瞳だけが忙しなく動き、そして最後には、一人に向けられた。
悲しそうな顔は、一転して笑顔に変わった。
卒業式が終わった後の高校の正門前。
花を持った卒業生の男と、在校生の女が二人でいた。
「先に行って、待ってるから」
すぐに高校の事だと、女は気付いた。
「これ…うちの学校は、第二ボタンとか駄目だからね…」
渡されたのは、ハンカチだった。
(知ってる…これ、先輩のお気に入りの…)
「…あり、がとう…ござっいますっ…‼」
何故かは分からない。
“想い”が…“涙”が、溢れて止まらなかった―――
【 その他 】
――好きになっても、言えない
けれど、ふとした時に口が動いて――
『生涯の伴侶』
朝の7時、あたしは今日も、貴方に会う為に学校へ行く。
「ばーか、それはyだよ。xは…」
チャイムと共に、あたしと彼の机を向かい合わせにする。
英語の授業の後の休み時間なら英語の予習をするように、今は数学の予習をしていた。
「お前、xとyを逆に覚えてたら、高校受験受かんねーぞ?」
悪戯っぽく笑う彼に、薄紅色になった頬を隠すように机に突っ伏した。
「うぅー…数学だけじゃなくて英語も絶対無理だよぉ」
「お前さ…ローマ字も打てないよな」
一瞬だけ自分の体が大きく震えたことが分かった。
「ひ、人には誰だって苦手な物があるの!!」
完璧な人なんていない、と言いかけてやめた。
…いるじゃないか、目の前に。
料理以外は何でも出来る、完璧な人が。
「確かに俺も…料理は無理だな…」
あたしの大好きな彼は、苦笑しながら言った。
「………そだね…」
「おい!!ちょっとくらいフォローしろよ!!」
一瞬なにかを考え込んだあたしは、瞳に憂いを宿していた。
彼の「おい!!」にハッとした時には、チャイムが鳴っていた。
国語の後の休み時間、つまり今は国語の予習の時間。
「…あれ?ひとみってどう書くんだったっけ?」
「え、なにいきなり?目の横に児童の童だよ?」
「あぁ、そっか!!あんま使わないとすぐ忘れるんだよなぁ」
彼の言うことは尤もなことだった。
使わないと誰だってすぐに忘れてしまう。
ずっと会っていなければ、その人の事も…じゃぁいつか、あたしの事も…?
続きます
あたしは、自分でも知らず知らずのうちに呟いていた。
「ずっと傍で、料理を作りたい…ずっと、勉強を教えて欲しいよ…」
目を見開いた彼の表情を見て、あたしはハッとした。
頬が一気に染まっていく…鮮やかな紅色に。
そしてまるで狙ったかのようなタイミングで、チャイムが鳴った。
次の授業が終わっても給食の時間だから予習はしないし、班の当番は配膳である。
これなら、意識すれば今日は関わらずに済む。
幸い四時間授業なので、学活が終われば走って帰ればいい。
そして給食が終わり、学活も終わったその時だった。
「さようなら」の掛け声と共に、教室を飛び出そうとした。
そう、飛び出そうとしたあたしの腕を、彼は掴んだ。
周りに学校の生徒どころか近所の方々、つまり人が誰もいない状況。
二人きりになってしまい、しかも腕を掴まれたまま…。
逃げることは出来ない。
なんせ、相手は男である。
女の自分が、男に力で勝てるはずがない、身長差だってあるのだ。
「………あ、の…」
恐る恐る彼の背中に声をかけてみたら、彼は体の向きを180度変え、自分と向き合う。
そこから出てきた言葉は、思いもよらない言葉だった。
真剣な表情をしながら、あたしに向かって言った。
「好きだ」
今度はあたしが、目を見開く番だった。
彼はあたしをからかってるのだろうか。
そんな疑問が心の中に生じた。
「君の人生を、俺にください」
中学3年生にして、生涯を誓い合った二人だった。
この二人に、神の御加護が有らんことを―――
『引っ越し』
少女は両手に荷物を持って、横断歩道の前に佇んでいた。
「お、重い…いや、早く帰ってご飯作らないと!!」
少女の母は仕事先で怪我をした。
箱を抱えて階段を下りていた少女の母。
その後ろに、箱を抱えずに蹴って運んでいる男の人がいた。
少女の母を避けるように方向転換を試みた男の人。
しかし、階段で落ちたその箱の行き先には…少女の母がいた。
少女の母の体、悪く言えば「いつ死ぬか分からない」だが、軽く言えば「別にどこも悪くない」である。
自分の家族を心配する者が、「別にどこも悪くない」と思えるだろうか。
答えは「思えない」だ。
それに少女の母は今、右腕が使えない。
その“事実”が有る限り、少女の家族(少女と少女の母以外には父だけだが)は全員「いつ死ぬか分からない」の方の考えなのである。
なので、少女は母親の身を案じていた。
「あ、青になった…」
ふぅ…と息を吐いて、少女は歩き始めた。
横断歩道を過ぎた時だった。
右手にあった荷物(エコバック三つ)の重さが消えたのだ。
少女は思わず右を見た。
柔らかく微笑んだ少年に、少女は目を奪われた。
「少しは軽くなった?」
微笑んだままそういう少年に、少女は「は、はい!!」と言った。
心の中では、少し軽くなったどころかかなり軽くなったよと呟いていたが、少年にそれを言う勇気を少女は持ち合わせていない。
家に着くまでの会話は、少年の道を聞く質問に「右に曲がります」などと答えるだけだった。
「あれ、ここなんだ」
「へ?あ、はい」
いきなり話しかけられて驚いたのか、声が裏返った少女に少年は言った。
「実は昨日、ほら、見えるよね?あそこに引っ越してきたんだ。あ、お袋がいる。ごめん、ここに置いておくよ」
そして少年は自らの家族の元へ駆けていった。
「……そっか、また…会えるんだ…」
薄く浮かんだ笑顔と、頬に浮かんだ桃色。
今日も太陽は沈んで行きます―――
『クラス替え』
「ねぇねぇ、こっちの人と…こっちの人!!どっちの方が好き!?」
数ページ違うところに写っている二人の男。
「…別に、どっちでもいいと思うけど」
「またまたぁー!!…で、どっち!?」
女が二人、その部屋にはいた。
机に頬杖を突いて、雑誌に全く興味を示さない女と、雑誌の二人の男のどっちが好きかと聞いている少女。
少女は女の部屋に雑誌を片手によく押しかけてくる。
雑誌の男の中から二人を選び、女に「どっちが好き!?」と聞くのだ。
それも決まって木曜日に。
ここまで来ると、もう女と少女の関係性が分かってくる。
そう、少女は女の妹だ。
「…どっちでもいいって、いつも言ってると思うんだけど」
女はうんざりとした表情を隠すことなく顔に出している。
対して少女は眉を寄せて、頬を膨らませて「えー!!つまんなーい!!」という言葉が聞こえてきそうな顔をしていた。
「あたしこそいつも言ってると思うけど、なんでお姉ちゃんはそんなに男に興味がないの!?」
女は、少女の「もう高校生でしょ!?」という言葉を軽く受け流した。
「…じゃぁ逆に聞くけど、なんでそんなに男に興味があるの?」
「勿論、格好良いから!!」
即答だった。
女は隠すことなく、溜め息を吐いた。
「明日は私、高校の始業式なの。明後日の入学式で一年生をどう迎えるかとか聞いてくるのよ」
少女は「だから?」という顔で女を見つめた。
そんな少女に、女は容赦なく言葉を放った。
「邪魔なの。寝れないの。出てけ雑誌馬鹿」
少女は「雑誌馬鹿!?」と叫んだ。
そしてすぐ、「雑誌馬鹿…雑誌馬鹿…雑誌馬鹿…」と呟きながら出て行った。
女は漸く煩いのが出て行ったと思った。
しかし、生まれてしまった“寂しい”という気持ち。
誰もいない、たった一人のこの部屋は、とても広く感じた。
続きます
朝、小鳥も鳥も煩いくらいに鳴いていた。
目覚ましの丁度6分前に、女は目を覚ました。
自然に目を覚ましたら、普通はスッキリした気持ちで起きるはずなのに、女は不機嫌そうな顔で起き上がった。
「…鳥、煩い」
女からしてみれば、鳥の鳴き声に無理やり起こされたようなものなのだろう。
酷く苛立っている女は、もうすっかり覚めた目で目覚ましを見た。
目覚ましの5分前を表示しているアナログ時計の針。
次の瞬間、目覚ましは仕事をする前に仕事をキャンセルされた。
何故だろう、女の不機嫌さに一層拍車が掛かったような気がした。
準備を終えてすぐに玄関に行き、女は靴を履いて鞄を持ち、リボンがずれていないか確認してから家を出た。
自分とは無縁の“友達”や“恋人”を持っている人達が、校門を次々に潜っていく。
少女の顔に、憂いが浮かんでは沈んでいった。
人付き合いが苦手な自分は、小学校でも中学校でも、高校ですらも友達を作ることが出来なかった。
友達を作ることが出来なかったのだ、恋人なんて作れるわけがない。
下駄箱で自分の名前を探すと、2年1組のところにあった。
女は前のドアから2年1組の教室へ入り、黒板に貼られた紙を一瞥して自分の席に向かい座った。
横に鞄を掛けて移動の声が掛けられるまで本を取り出し読んでいた。
そんな時、男に声を掛けられた。
「おはよう!!これから宜しくね!!」
その男は女の隣の席に座り、机の横に鞄を掛けて女に話し掛けていた。
返事を返すのは礼儀だと思っている女は、男に「…宜しく」と言った。
その言葉のどこで嬉しがれるのか、男は嬉しそうに「うん、宜しく!!」と言いながら握手を求めてきた。
久しぶりに同年代の人に触れた女は、男の手から感じる温もりについ微笑んだ。
本当に長い間、誰からも掛けられることのなかった「おはよう」という言葉。
手を離しても、まだ残っている男の手の温もりを、女は感じていた―――
【 その他(悲恋) 】
――好きすぎて、辛すぎて、切なくて
勇気のない自分に、涙を流した――
『見つめているだけ』
“好き、好き、大好き”
そんな言葉に憧れていた頃のあたしは、もういない。
何故なら、恋という言葉を、言葉の意味を…知ってしまったから。
「さようなら」
彼女はチャンスを見つけては頭を軽く下げ、彼に挨拶をした。
運が良ければ、彼は頭を下げ返してくれるか、「さようなら」と返してくれた。
だからと言って、彼女が朝の「おはよう」を言えるはずがない。
休み時間に彼と話すことも出来ない、なんの接点もない。
ただ、ただただ、授業中に彼の後ろ姿を見つめ、休み時間に彼を盗み見るだけ…。
給食で彼が給食当番になったら、彼女はいつもより多く配膳をした。
相談する相手なんかいない、何故そんなに気になるか、理由がわかっていても、言う相手もいない。
いたとしても、彼女は言う勇気がなく、話を焦らすだけ。
そして最終的には諦め“また、言う機会を失った…”と落ち込む。
今までだって気になる人はいたはずだった。
だけど何故か彼だけを、ただ彼だけを気にしていた。
なんで…と戸惑っている彼女は、話すことも出来ない彼との距離が、苦しかった。
彼は滅多に異性と関わることはない。
だから、異性と関わっているところを見ると、胸になにか熱いものが込み上げてきて、苦しかった。
その苦しみから抜けようと、漸く決心し、もう関わらないと決め、挨拶をやめた。
しかし、挨拶をしないで帰っていく彼を見ると、やはり悲しさは込み上げてくるものである。
彼女は自身の眉が下がっていることに気付かなかった。
視線は帰っていく彼の後ろ姿を捉えたまま…。
この想いを、時間は解決してくれるのだろうか―――
この作家の他の作品
表紙を見る
僕達は、どこまでも行こうよ
例え唯一会えるこの日が雨だったとしても
大丈夫…だって、心は繋がっているから
会えなくても、君は僕の傍にいるでしょ?
星願シリーズは
『星達』『星に』『願う』
の順にシリーズになっております
『願う』はまだ公開しておりません(*^^*)
表紙を見る
僕達は、どこまでも行こうよ
あの星が導くままに…
君と一緒なら、僕はどこまでも行けるんだ
例え僕達が星になってもまた会えるよね?
星願シリーズは
『星達』『星に』『願う』
の順にシリーズになっております
『願う』はまだ公開しておりません(*^^*)
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…