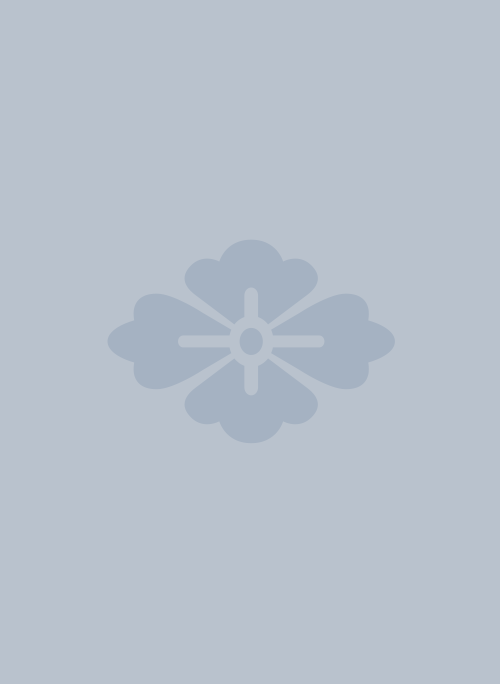やっぱり、このヒト……!
危険な、ホストの紫音なんだ……っ!
ヒトの真剣な心をもてあそぶなんて!
「何がおかしいのよ!」
今や、背中を丸めてげらげらと笑っている紫音をどついて、わたしは、くるり、と後ろを向いた。
気のあるふりして落っことすなんて!
『好き』だって、紫音はだれにでも、簡単に言うにちがいない。
わたしは、先輩に言うのに、ものすごく勇気が入ったのに。
「……も、帰るっ!」
「ま、待てよ。
家までは、送るって……!」
まだ笑いながら、追って来る紫音を振り切って、歩いて帰ろうと二、三歩進んだ時。
前からやってくるヒトを見つけて立ちすくんだ。
「お……お父さん……」
そういえば。
気がつけば、帰らなくてはいけない時間を……門限をだいぶ過ぎて……いた。
だいぶあちこち、わたしを探して歩き回っていたらしい。
汗だくで、ぼろぼろになっている。
父さんは、わたしを見つけると「春陽……っ!」と叫んで走ってきた。
危険な、ホストの紫音なんだ……っ!
ヒトの真剣な心をもてあそぶなんて!
「何がおかしいのよ!」
今や、背中を丸めてげらげらと笑っている紫音をどついて、わたしは、くるり、と後ろを向いた。
気のあるふりして落っことすなんて!
『好き』だって、紫音はだれにでも、簡単に言うにちがいない。
わたしは、先輩に言うのに、ものすごく勇気が入ったのに。
「……も、帰るっ!」
「ま、待てよ。
家までは、送るって……!」
まだ笑いながら、追って来る紫音を振り切って、歩いて帰ろうと二、三歩進んだ時。
前からやってくるヒトを見つけて立ちすくんだ。
「お……お父さん……」
そういえば。
気がつけば、帰らなくてはいけない時間を……門限をだいぶ過ぎて……いた。
だいぶあちこち、わたしを探して歩き回っていたらしい。
汗だくで、ぼろぼろになっている。
父さんは、わたしを見つけると「春陽……っ!」と叫んで走ってきた。