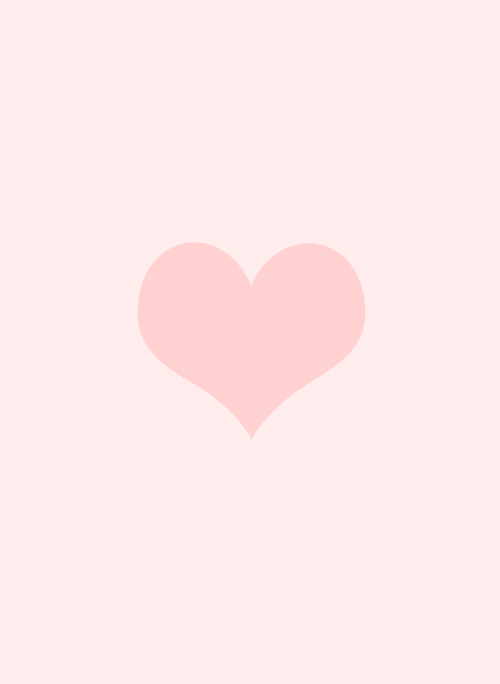「二人ともいってらっしゃい。気をつけてね。」
「うん、行ってきます。」
「行ってきまーす。」
私達が見えなくなるまでお母さんは手を降っていてくれる。
その姿を瞬輝と二人で見届けてから、学校へと向きをかえる。
なんだろう。
確かにいつもと変わらないはず。
何も心配する事はないはずなのに、胸がざわついてる。
「姉ちゃん、どしたの?」
「うんん…何でもない。」
もうすぐ予定日だからなのかな。
お母さんの方が不安なはずなのに、私がこんなんじゃ駄目だよね。
とりあえず落ちつこう。
私が焦ったって何も変わらないし。
「瞬輝、お互い出来るだけ早く帰ろうね。」
「……ん、わかった。」
お母さんの妊娠が解ってから、前より仲良くなれた私達姉弟。
前は私が何を言っても反抗してきたのに、今はぶっきらぼうながら頷いてくれる。
瞬輝は素直じゃないからたまに周りに誤解されちゃうけど、本当は凄く優しいんだ。
何気に色々見ていて、いつもさり気なく助けてくれる。
「…なに?何か顔についてる?」
「んーん、なんにもついてない。」
「……あっそ」
まぁ素直じゃない所は可愛げがなくてムカつくけどね。
『救いの着信音<麻椿side>』
永愛と瞬輝が家をでてから一時間後、洗濯を干しているといつもより身体が重いのを感じた。
まぁ臨月となれば身体が重いのも当たり前かと、休憩をとる事もなく全ての洗濯物を干し終える。
妊娠が解った時はあんなに暑かったのになぁ…。
今は顔にあたる風がこんなにも冷たい。
みんな学校寒くないかなぁ。
先生は職員室に暖房あるから大丈夫だろうけど。
小学校と中学校はあってストーブだろうし、教室は寒いだろうな。
「ゴホッゴホッ…」
あ、ちょっと外にいすぎたかな。
先生に怒られちゃう。
寒い外から暖かい部屋に入る。
すると、身体が一気に温まってゆく。
ん?でも温まりすぎているような気も…。
「ゴホッ……ゴホッ」
朝から体調はあまりよくないとは思っていたけど、何かおかしい。
そういえば永愛にも心配されたっけ…。
洗濯カゴを置きに行こうと洗面所へ向かうと、そこには鏡に映る自分の姿があった。
…なんか、顔赤い?
これは熱を測った方がいいかもしれない。
「ふぅ……。」
予定日が近いからかな。
なんかもの凄く不安になってきた。
ピピピ……
「ん…あ、体温計…。」
だんだん重くなる身体に耐えかねてソファーに寝転がっていると、脇に挟んでいた体温計が音をたてた。
身体を起こす事なくそれを取り出すと、驚きの数字がでていた。
「…38度…かぁ…」
妊娠中の風邪はとても危ないと聞いた事がある。
どうしよう先生に連絡するべきかな。
でも、そんな事したら飛んで帰ってきちゃうだろうし。
「…寝てれば治るよね。」
全ての家事を後へと回し、ソファーの上で毛布を掛けてから目を閉じた。
身体の外側は寒いのに、内側がすごく熱い。
早く寝て体調を整えようにも、身体がダルくて思うように寝つけない。
今は一人分じゃない身体が悲鳴を上げているような気がする。
苦しい。
熱い。
助けて。
そう言って赤ちゃんが泣いているようで。
いくら我慢強い子でも、やっぱり辛いよね。
大人の私でもこんなに辛いのだから。
「ゴホッゴホッ…」
でも、どうしたらいいのか解らない。
薬局で売っているような風邪薬は飲めないし、病院から出されている薬は貧血を抑えるもので意味がない。
本当は病院に行くのが一番いいんだけど…。
当たり前のように、今の状況では一人で行けるわけがない。
自分から先生に連絡する勇気もないし、まして子供達に助けを求めるわけにはいかない。
考えれば考えるほど、答えはどんどん遠のいていく。
どうしよう…。
このままじゃ赤ちゃんが死んでしまうかもしれない。
風邪で身体が痛めつけられていくのと同時に、心も痛められているよう。
小さかった不安は確実に大きくなっている。
誰かからの連絡を待ちわびるように必死で携帯電話を握りしめる。
身体中から流れ落ちる汗は急激に私の体温を奪い、さらに風邪を悪化させていく。
意識が少しずつ薄れていこうとしたとき、握りしめている携帯が振動しているように感じた。
メールとは違うバイブの仕方。
…これは、電話?
一刻も早く助けを求めようと、ディスプレイを見る間もなく携帯を耳へとあてる。
すると、電話の向こうからは聞きなれた声が聞こえた。
「…お嬢様?あれ、繋がっていますか?」
「う…えだ…?」
聞きなれた声の主は、小さいころから高校生まで私のお世話をしてくれた執事の上田だった。
「えっ…お嬢様?どうかなされたんですか?」
先生の声もそうだけど、小さいころから聞いていた上田の声はすごく安心する。
風邪で弱っている今なんかは聞くだけで涙が出そうになる。
「た…すけて…上田…っっ」
「え?あの…」
「お願、い……赤ちゃんが…」
「お嬢様!!?大丈夫ですか??……お嬢様っ?!」
手から滑り落ちた携帯から上田の声が聞こえる。
必死に携帯を拾おうにも、すでに身体が動かない。
「うえだ……」
助けを求める事ができた安心感からか、私の意識は真っ暗なものへと変わっていった。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
「ちょっと…先生待ってっ!!」
「…ん?なに……嫌?」
そう言いながら、又キスをする。
まだ答えてないのに……。
苦いコーヒーと先生の匂いが
漂うこの教官室でキスをする。
「もう一回してもいい?」
「いやいや、ここ学校!!」
はははっと笑いながら、
先生は又私にキスをする…。
\感想ノート・レビュー/
いつも励まされてます!!
僕ちみ様・すっチャン様・
遊哉様・ひか*様・狸様・
LOvE様・愛か様・
乙姫いちご様・たくくま様・
ペペロンえりか様・
あーさ5296様・しーCHAN様・
ことぎし。様・めがねチャン様・
れいな★様・みおあず様・
カズユキヨリ様・へにー様・
さてぃあ様・mehi様・
ぁぃく様・來雨様・
藤堂ありあ様・葵翼様・
りゃー♪様・スカイマリン様
感謝の気持ちでいっぱいです!
『先生と教官室2~新しい道~(完結)』
『先生と教官室3~沢山の初めて~(更新中)』
『先生と執事(完結)』
『先生と執事【続・短編】(完結)』
続編、別作品も是非読んでみて下さい!!
表紙を見る
「先生、できましたよっ!!」
「あ、伊緒。お前また敬語使っただろ。
それに名前じゃなくて先生って…」
「あ…それはー…」
私のしまったという顔に、先生は
不敵な笑みを少しずつ浮かべる。
「次言ったらおしおきって言ったよな?」
そして、その笑みは甘さと恐怖を交えて
確実に私へと襲いかかろうとする。
「ちょ、ちょっと待って先生!!変な事
したらオムライスあげませんからねっ!」
「うぐっっ……それは…」
新しく始まった、先生との関係。
甘くて、温かくて、安心して、でもたまに
苦しいことも悲しいこともあって……。
「ふふっ、食べましょうか。せーんせっ」
「……おぅ。」
それでも最高に幸せだと思える日々が今、
ゆっくりと幕を開ける―――…
表紙を見る
「んっ…やっぱり無理…苦い。」
「じゃぁ俺が飲ませてやる。」
「えっっ!!ちょっ先生!!」
「バカ、大人しくしろ。」
「ーっっ!!!!!!」
そう言って私を抱きしめてくる
先生の身体からコーヒーの匂い
がして思わずキュンッとする。
「せ…んせ…。」
「……なんだ?」
そして、抱きしめられた後の
キスからはフワリとコーヒー
の苦味がして、いつも私を
大人の気分にさせてしまう。
もう何度私と先生はこの教官室で
抱きしめあいキスをしたのだろう。
この、大好きな教官室で
大好きな私だけの先生と……
『先生と教官室』の続編です。
『先生と教官室3~沢山の初めて~』
『先生と執事』
こちらも宜しくお願い致します!!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…