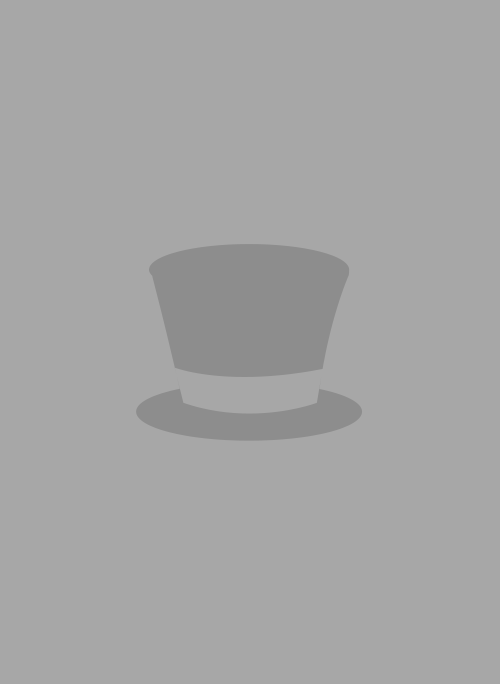女性宮家の創設に関して百家争鳴の様相だ。
だが、この問題を男女同権の観点から論じる人が、特に女性に多いのが気になる。
どうも「女性天皇」と「女系天皇」を混同しているようだ。
皇室典範という現在の法律では皇位を継承できるのは「男系の男子」のみとされている。
一方歴史上女性の天皇は8人(二人は二度即位しているので10代)存在する。
だから皇太子の娘である愛子さまが天皇になれないのはおかしい、女性差別だという論がある。
最初に確認しておくが、愛子さまは「男系」の皇族である。
男系というのは「実の父親が男系男子の皇族」という意味である。だが愛子さま本人は女性なので「男系の女子」になる。
従って男系ではあるが「男子」ではないので現在の皇室典範を改正しないと即位はできない。
過去の女性天皇は、後継ぎがまだ若すぎるとかの理由で一時のつなぎとして即位した人がほとんどで、その次の皇位は従兄弟や遠縁の甥にあたる「男系男子の皇族」に譲位するか、引き継がせている。
唯一、元明天皇だけは自分の子供に皇位を継がせている。次の代の元正天皇はその娘で女帝が2代続いた。
ただし、元明天皇の夫は「草壁の皇子」という皇族である。だから元正天皇は母から皇位を継いだが、父親が男系男子の皇族だし、その後皇位を弟に譲っているので、「男系男子による皇位継承」という原則は崩れた事はない。
だが、この問題を男女同権の観点から論じる人が、特に女性に多いのが気になる。
どうも「女性天皇」と「女系天皇」を混同しているようだ。
皇室典範という現在の法律では皇位を継承できるのは「男系の男子」のみとされている。
一方歴史上女性の天皇は8人(二人は二度即位しているので10代)存在する。
だから皇太子の娘である愛子さまが天皇になれないのはおかしい、女性差別だという論がある。
最初に確認しておくが、愛子さまは「男系」の皇族である。
男系というのは「実の父親が男系男子の皇族」という意味である。だが愛子さま本人は女性なので「男系の女子」になる。
従って男系ではあるが「男子」ではないので現在の皇室典範を改正しないと即位はできない。
過去の女性天皇は、後継ぎがまだ若すぎるとかの理由で一時のつなぎとして即位した人がほとんどで、その次の皇位は従兄弟や遠縁の甥にあたる「男系男子の皇族」に譲位するか、引き継がせている。
唯一、元明天皇だけは自分の子供に皇位を継がせている。次の代の元正天皇はその娘で女帝が2代続いた。
ただし、元明天皇の夫は「草壁の皇子」という皇族である。だから元正天皇は母から皇位を継いだが、父親が男系男子の皇族だし、その後皇位を弟に譲っているので、「男系男子による皇位継承」という原則は崩れた事はない。