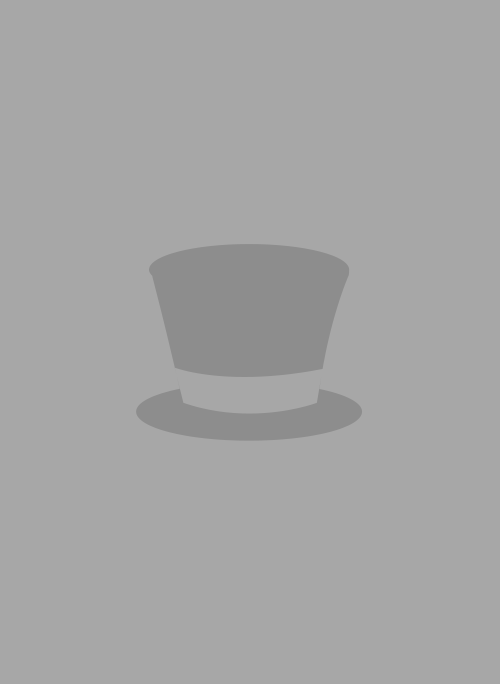内閣府が「国内総生産(GDP)ギャップ」という数字を発表した。
この中で日本経済は「年間15兆円の需要不足」に陥っていて、これがデフレの一因だとされている。
しかしこの「需要不足」という言葉、そもそもおかしいのではないだろうか?
経済というのは、まず需要が先に発生して、そこに供給する企業なり個人が現れて、それから市場が生まれるものであるはずだ。
需要が足りないという現象は本来あり得ないはずではないのか?
内閣府が言う「需要不足」とはつまりは「企業がせっかく生産しているのに物やサービスが売れない」という話だろう。
しかしそれは「消費者が必要としていない製品やサービスを企業が作っている」という事になるのではないのか?
これでは政権交代の意味がない。
2009年の衆議院選挙で自民党が大敗して民主党に政権交代した理由、原因はいろいろあるだろうが、一つには自民党はブルジョワ政党なので「生産者目線」だったからだ。
生産者、つまり企業とか農家とか、物やサービスを作る側、売る側の都合ばかり考えて買う側の事を真剣に検討してくれない。
買う側とは同時に雇われている労働者でもあるから、あの時の民主党への雪崩現象は「消費者、労働者軽視の自民党はもう嫌だ!」という有権者の意思表示という面もあったはず。
相変わらず「需要不足」などという言葉を平気で使って、それに違和感すら覚えないというのなら、民主党と自民党ではこの点に関しては何も違いがない事になる。
この中で日本経済は「年間15兆円の需要不足」に陥っていて、これがデフレの一因だとされている。
しかしこの「需要不足」という言葉、そもそもおかしいのではないだろうか?
経済というのは、まず需要が先に発生して、そこに供給する企業なり個人が現れて、それから市場が生まれるものであるはずだ。
需要が足りないという現象は本来あり得ないはずではないのか?
内閣府が言う「需要不足」とはつまりは「企業がせっかく生産しているのに物やサービスが売れない」という話だろう。
しかしそれは「消費者が必要としていない製品やサービスを企業が作っている」という事になるのではないのか?
これでは政権交代の意味がない。
2009年の衆議院選挙で自民党が大敗して民主党に政権交代した理由、原因はいろいろあるだろうが、一つには自民党はブルジョワ政党なので「生産者目線」だったからだ。
生産者、つまり企業とか農家とか、物やサービスを作る側、売る側の都合ばかり考えて買う側の事を真剣に検討してくれない。
買う側とは同時に雇われている労働者でもあるから、あの時の民主党への雪崩現象は「消費者、労働者軽視の自民党はもう嫌だ!」という有権者の意思表示という面もあったはず。
相変わらず「需要不足」などという言葉を平気で使って、それに違和感すら覚えないというのなら、民主党と自民党ではこの点に関しては何も違いがない事になる。