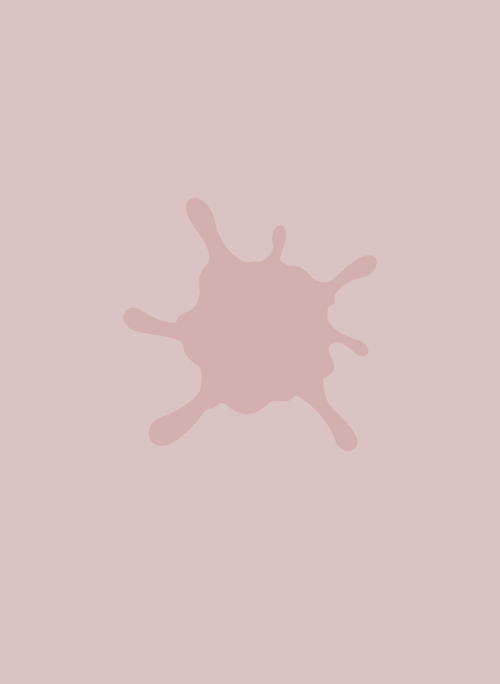「雛、みーつけた」
勢いを止めたのは、鬼。
心臓を握りつぶされたような感覚が襲ってくる。苦しい。痛い。
ペタンとその場に尻餅をついた。恐怖の対象を目に映しながら必死に心の中の私が悲鳴を上げ、助けを呼ぶ。
「ぁ……ぁぁ……」
肝心の外の私は枯れた声しか上げることができない。
それどころか体は後ずさりを始め、押し入れの中へと舞い戻る。
「あれ?何か怯えてる?」
不思議そうに首を傾げる柊様は私の後を追うように両の手をついて近づいてくる。
静かな息遣いだけが二人の間に聞こえた。
まだ近くなる。まだ。まだ。
ギュッと目を瞑る私の耳のすぐ傍で鬼が囁いた。
「怯えなくていいよ。遊びに負けたら、貰うだけだから」
「ひ、ぁ……何、を……?」
「……雛の右腕」
鬼は嘲笑い、私の右腕に……
手を、置いた。
ススッと袖をたくし上げ、線をなぞるかのように触れる。ゆるりと二の腕に向かってくる。
「ひ、ひ、柊様っ、じょ、冗談ですよね?」
仕切りにぶつかる口内の歯のせいで喋りにくいのを堪えて声を押し出した。
「んーーん。最近流行ってるんでしょ?見つかったら鬼にならないで罰ゲームってやつ」
「で、でも……っ」
流行っている。確かに流行っている。近所の幼い子供達が舌足らずに『罰ゲーム』と言っていた。
けれど、じゃれあう程度の罰で腕を……なんて事は……。
「ほっそい腕」
声にハッとすればついに柊様の腕は肩口に到達していた。
冷たい。怖い。嫌だ。
「や、だ……いや……や」
「この屋敷でのルールは薺。腕、貰うね?」
「いっ……やぁぁぁぁぁぁぁぁ!」
--
仲良しの同い年の雛。その雛は、村の掟に選ばれてしまった。
掟に選ばれたのは雛なのだから僕が干渉してはいけないのは重々承知だった。
けれど、どうしても気になって雛が連れて行かれた後、僕は村の書物庫に来ていた。
書物庫は何年も使われていないようで埃だらけになっていて、思わず息を吸い込んで咳き込んでしまう。
着物の袖で口元を覆いつつ、村の歴史に関する書物を探した。
『村の周辺について』
『災害について』
『出生と死亡者』
……
……
「『村の歴史』……これだ」
並んだ書物の中から選びとり、埃が舞うのも構わずにパラパラと捲って目を通していく。
「……?」
おかしい。
確かに此処には歴史が、村で起こった事が並べられている。なのに。
「……ない」
歴史なのに掟が出来たことも、ある事も示唆されていない。
この書物じゃない……?
そう思ったけど、一通り見た限りでは他に目ぼしい物はなかった。
「……椿」
「っ、あ、すみません直ぐに出ます!」
いつの間にか立っていた書物庫の所有者に謝り飛び出すように出る。書物庫自体は立ち入り自由な筈なのに、突拍子もなく声を掛けられた故の対応だった。
それでも丁度いい。と直接聞いてみる。
「あの、村の掟って……?」
無意識に控えめになる僕に対して、書物庫の所有者は眉を下げて申し訳なさそうに言う。
「すまないな椿。それに関しては言えないんだ」
言えない。知らないんじゃなくて言えない。
どうして?
そもそも僕は村の偉い人の顔なんて知らないし、見た事もない。そんな存在に対する掟って何だ?
いや、それ以前に僕が知る呼ばれた数人の中で、帰ってきた人は……
誰一人としていなかった。
「っ、雛!」
とにかく走った。足が草木で傷つこうとも走った。
初めから、初めから引き止めるべきだったんだ。
事の重要さに、関係ないと今まで見て無ぬ振りをした自分を今更ながらに呪った。もう遅い。
雛は僕の幼馴染で大切な、大切な女の子なんだ。
小さい頃から楽しい時も嬉しい時も悲しい時も一緒だった。そんな雛が居なくなるなんて考えるだけで息が出来なくなる。
だから、助けたい。
だから、ここにいる。
森の中に隠れるかのように佇む古い屋敷。
古くはあるが老朽化等は進んではおらず、手入れもそれなりに行き届いているようにも見えた。
それでも、不気味さがある屋敷。
この場所は、村の誰もが知っている偉い人の屋敷で、幼い頃から言い聞かされてきた“絶対に踏み込んではいけない場所”
只単に偉い人の家だからと言うだけだったとは思うが、そんな場に僕は今足を踏み入れようとしていた。
風が木々を揺らし、葉を舞い散らせる。ヒラリヒラリ、僕の手元に。
「雛……」
一歩、踏み出す。
彼女を想えば不安ばかりが駆け巡り、幼い頃の言い付けも今簡単に破った。
無事である事を祈るばかりだった。それしか出来ない。
門を潜るとそこはちょっとした庭。松の木もあれば小さな池もある。濁りを見せた池だが鯉だって泳いでいる。
辺りに視線を移しながらも進む足は前へ前へ。入り口へ。
そうして立ち止まる大きな引き戸の扉の前。鍵が掛かっていれば別の場所を探すしかないが……
「!」
だが、そんな心配も無用。思いの外扉は簡単に開いた。音もなく、誰もいなく。
僕にとっては誰も居ない方が好都合だった。だって、行ってはいけない場所に来ていて、無断で門を潜っていたのだから。
リスクを背負っても尚、軋む床に足を置いた。
時。
「いや!来な、いで!来ないでください!!」
叫び声が家全体に行き届いた。
「っ!?」
真に迫った声に両肩を跳ね上げ、喉を詰まらせる。温かみのない空間が酷く気持ち悪い。
今のは甲高い女の子の声だった。そう、女の子の……
「ひ、な?」
聞き間違えようなんてなかった。
喉の中の水分は一気に枯渇し、体温は低下へ向かって行く。痛む。冷える。
雛を昔から見てきた僕は異常事態が起きていると直感した。雛はどれだけ驚いても喉の奥から叫ぶような声を上げる事は一度としてなかった。只の一度も。
「っ雛!」
体温が最下層まで到達した時、僕は名を呼び長く歪んだ音を立てる廊下を駆け出していた。
ギィギィ。ギィギィ。
耳障りな音がこびりついて離れない。
この作家の他の作品
表紙を見る
それは依存だと誰かが言った。
それは恋ではないと彼が否定した。
ただ、その行為に溺れるだけ。
-----
以前書いていた話を加筆修正して新しく書き直しています。
途中まで大まかな流れは変わらないのですが、後半は追加エピソードと展開に変化があります。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…