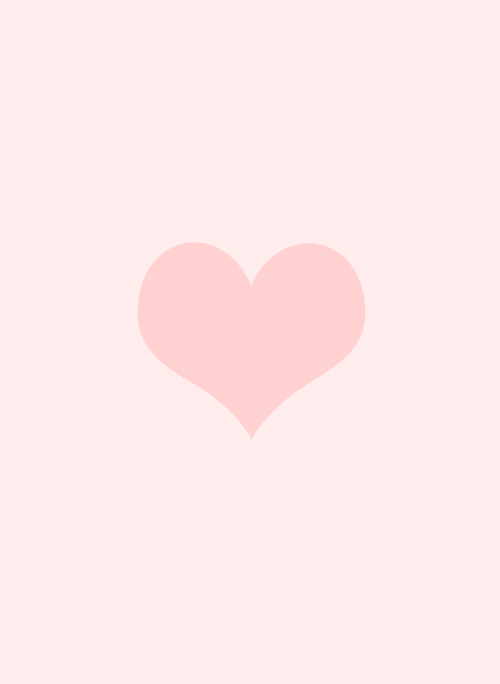「ん…せん…せ…」
眠る伊緒の頭をなでると、少し笑いながら俺を呼んだ。
俺のせいでこんなにも辛い思いをしたのに、それでも俺の事を考えてくれてるのか?
「ふふ、かわいいわね。」
「はい。」
志帆さん達がいなかったら今すぐにでも抱きしめたい。
それほどに、伊緒が愛おしいと思えた。
「大切にしてあげなさい。もう泣かせるんじゃないぞ?」
「もちろんです。」
ずっと俺の隣にいてほしいから。
だから、約束するよ。
お前が泣かないように、一人で寂しい思いをしないように、俺が守るって。
「…伊緒、帰ろう。」
頭にのせていた手を、身体へと移動させる。
起こそうと思ったけど、やっぱりやめよう。
今はこのまま寝かせといてやりたい。
きっと、俺の顔見たら辛くなるだろうし。
伊緒が起きないように、そっと抱き上げる。
そしてそのまま出口へと歩きだそうとした瞬間、伊緒の目が開いた気がした。
「…せんせ?」
「伊緒…目覚め…」
「ごめ…んなさ…ぃ…」
俺の言葉を遮って聞こえてきたのは、予想外の言葉だった。
薄く開いた目は、再び少しずつ閉じていった。
閉じられた目からは、一筋の涙が流れてゆく…。
なぁ伊緒、今お前はどんな夢を見ているんだ?
もしかして、夢の中でも俺の事考えてくれてるのか?
「かっちゃん、もっと素直になりなさいね。」
両手が塞がっている俺の代わりに、後ろから歩いてきた志帆さんが伊緒の涙を拭いてくれた。
「ずっと一緒にいたいんでしょ?だったら、大人ぶるのはやめなさい。」
「志帆さん…。」
何も言っていないのに、志帆さんは全てを理解してくれている。
もちろん、勇二さんも。
二人は優しく笑いながら大切な事を沢山教えてくれる。
教師をやっている俺だけど、二人に教わる事はまだまだありそうだ。
「また近いうちにいらっしゃい。そうね、今度は二人揃ってよ。」
「はい。約束します…。」
笑いかけてくれる志帆さんに軽く会釈し、勇二さんが開けてくれている扉から外へと出る。
「じゃあ失礼します。」
「あぁ、また。」
二人に見送られ外へと出ると、薄暗かった空は真っ暗へと変わっていた。
それでも、春に比べたら大分日が長くなったな。
そう思いながら見上げる空には、珍しく沢山の星が輝いている。
一つ一つはとても小さいのに、あれだけ集まればなんと明るいのだろう。
「伊緒、今日は星が綺麗だよ。」
前まではイルミネーションや星など光物には興味がなかった俺。
だけど、俺とは逆に光物が好きな伊緒。
きっと一緒にいるうちに影響されて好きになったのかな。
今はこんなにも星に感動してるなんて。
それに気づけなかった今までが勿体無くも感じるな。
「……帰るか。」
今度は二人でこの夜空を見よう。
そうだな、伊緒が淹れてくれる美味しいコーヒーを飲みながらなんて幸せだろうな。
「ん……」
ふわふわと身体が揺れる感覚。
微かに感じる光と音楽。
さっきまでは感じなかったものが、少しずつハッキリと伝わってくる。
その不思議な感覚に閉じていた目を開ける。
すると、そこには見覚えのあるものが映っていた。
…ここどこだっけ。
私、何してたんだっけ?
寝起きで頭がボーっとして何も考えれない。
頭がスッキリするまでもう一度寝ようかな…。
そう思いながら、薄く開いた目をもう一度閉じてみる。
目を閉じるとそこは真っ暗で、当たり前のように何も見えない。
さっきまで夢の中だった私は、目を閉じると今すぐにでも、もう一度夢の中へと戻れそうになる。
もう少し。
あとほんの少しで深い夢の中…。
そう思っていた私の頭の上に、なにか暖かいものが優しく触れた。
「伊緒…って、まだ寝てるかぁ…。」
微かな夢と現実が入り乱れる。
今の声は、もしかして先生?
それとも、私の夢の中の声?
「……伊緒。」
もう一度、私の名前を呼ぶ声。
それと、私の頭に触れ、撫でている暖かいもの。
それは、まぎれもない先生の大きな手。
私の大好きな、先生の手…。
もう一度寝ようと閉じた目を、ゆっくりと開ける。
「伊緒?」
「せんせ…」
さっきより明確に動きだした頭は、今いる場所をハッキリと認識した。
目を閉じても開いても変わらない暗さに、微かに聞こえる音楽。
私と少し距離を置いて隣に座っている先生。
身体には、椅子と私を固定するベルト。
ここは、間違いなく先生の車の中。
でも、確か私はあの喫茶店にいたはず。
先生が迎えにきてくれて、車まで運んでくれたのかな…?
「おはよう、伊緒。よく眠れた?」
そう言って私の顔を覗き込む先生は、少しニヤッと笑っていた。
「…先生のいじわる。」
きっと、ずっと寝ていた私の事をからかっているのだろう。
先生の言葉に頬を膨らませながら窓の外を見ると、そこは私の家の近くのコンビニを映していた。
時刻は夜の九時を指していて、まだ帰らなければいけない時間には達していない。
それなのに家の近くまで来てくれたのは、きっと先生なりの優しさなのかな…。
「伊緒、怒った?」
「…怒ってませんよ。」
窓からは視線を戻さずに、先生の言葉に答えた。
なんだか、今先生を見ると泣いちゃう気がするから。
「じゃぁ、なんで泣きそうなんだ?俺に怒ってるからじゃないの?」
「っっ!!!!!」
先生は私のエスパーで、考えてる事は何でもお見通し。
そんな事はずっと前から知ってるよ。
でも凄いね、顔も見ないで私の思っている事が解っちゃうなんて。
何もかもかなわないよ、先生には……。
「伊緒、ちゃんと話そう。思ってる事全部言っていいから。」
一度離れた先生の手が、もう一度私の頭へと触れた。
その手は優しくて暖かくて、まるでさっきいれてもらったココアのように心に沁みこんできた。
止まったはずの涙が、再び溢れ出してくる。
「……怖かったです。知らない場所で一人にされて。」
「うん、そうだよな。」
「男の人に触られた時だって、ずっと先生に助けてほしくて…。なのに、先生はずっと怒ってるから、だから…」
そこまで言った瞬間、先生は私を後ろから抱きしめた。
まるで壊れ物を扱うように優しく、そっと触れる程度に。
「ごめん、ごめんな伊緒…。」
抱きしめながら私に謝る先生は、クーラーのせいか少し冷たく感じる。
でも、伝わってくる確かな温もりは、少しずつ私の心をあっためていく。
ずっと求めていた先生の温もりだと、私に実感させてくれている。
この作家の他の作品
表紙を見る
「ちょっと…先生待ってっ!!」
「…ん?なに……嫌?」
そう言いながら、又キスをする。
まだ答えてないのに……。
苦いコーヒーと先生の匂いが
漂うこの教官室でキスをする。
「もう一回してもいい?」
「いやいや、ここ学校!!」
はははっと笑いながら、
先生は又私にキスをする…。
\感想ノート・レビュー/
いつも励まされてます!!
僕ちみ様・すっチャン様・
遊哉様・ひか*様・狸様・
LOvE様・愛か様・
乙姫いちご様・たくくま様・
ペペロンえりか様・
あーさ5296様・しーCHAN様・
ことぎし。様・めがねチャン様・
れいな★様・みおあず様・
カズユキヨリ様・へにー様・
さてぃあ様・mehi様・
ぁぃく様・來雨様・
藤堂ありあ様・葵翼様・
りゃー♪様・スカイマリン様
感謝の気持ちでいっぱいです!
『先生と教官室2~新しい道~(完結)』
『先生と教官室3~沢山の初めて~(更新中)』
『先生と執事(完結)』
『先生と執事【続・短編】(完結)』
続編、別作品も是非読んでみて下さい!!
表紙を見る
「先生、できましたよっ!!」
「あ、伊緒。お前また敬語使っただろ。
それに名前じゃなくて先生って…」
「あ…それはー…」
私のしまったという顔に、先生は
不敵な笑みを少しずつ浮かべる。
「次言ったらおしおきって言ったよな?」
そして、その笑みは甘さと恐怖を交えて
確実に私へと襲いかかろうとする。
「ちょ、ちょっと待って先生!!変な事
したらオムライスあげませんからねっ!」
「うぐっっ……それは…」
新しく始まった、先生との関係。
甘くて、温かくて、安心して、でもたまに
苦しいことも悲しいこともあって……。
「ふふっ、食べましょうか。せーんせっ」
「……おぅ。」
それでも最高に幸せだと思える日々が今、
ゆっくりと幕を開ける―――…
表紙を見る
私のお母さんは大手会社
の社長でもある、お嬢様
私のお父さんは高校の教師
でもある、お母さんの執事
麻椿(35)×雄輝(44)
私は、そんな2人の娘
冨田 永愛(12)
あれから数年後を書いた
短編の物語です(^O^)/!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…