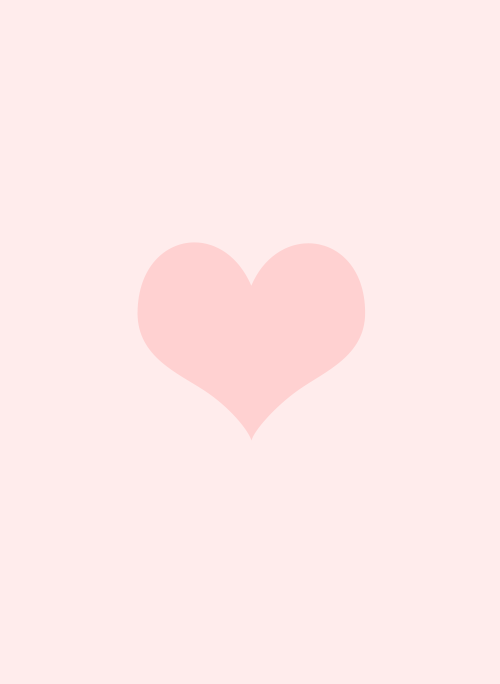「うわー…大丈夫か?」
「いたそーっ」
「やっちゃったな…」
さっきまでの大歓声は少しずつ同情の声へと変わっていき、誰もがその子に注目した。
あの子どうしたんだろう、起き上がってこずに地面を向いたまま…。
「…先生、1位で決まりだね。」
「う…ん…。」
不本意だけど仕方ないのかな…これが勝負の世界だもんね…。
みんなが1位の子に注目している、その時、先生がその子の前を通過しようとした。
でも、次の瞬間…ズッッザ―――――ッッッッ!!!!!!!
「ぬおおおおおおっっ!!!!!」
「……。」
「……。」
「「……………。」」
………え?せんせい?
「ぷっ…」
「「「アッハハハ!!!!!」」」
「先生何やってんのー!!?」
「オヤジ―っ!!」
グラウンドが笑いの渦で包まれていく。
1位争いの二人が並んで転ぶって、ある意味奇跡だもんね。
「いってぇぇ…って、ふはっお前も大丈夫か?」
「あ、俺は…」
先生達がそうこうしている間に、後ろからきた選手達が次々と二人を抜いていった。
「先生速く走れよ!!ドベになっちゃうぞ!!」
どこかの男子生徒がそう叫ぶと、先生は転んでしまった男子生徒の肩に手を置いた。
「うるっせぇ!!足つって走れねぇの!!だから今からこいつに運んでもらおうかなって。」
「え…おれ…?」
「頼むよー、な?」
「…解りました。」
9位中7位までが埋まっている中、残り数mの所からまさかの二人三脚もどきが始まった。
先生と男子生徒が、肩を組みながらゴールへ。
結局先にゴールテープを切ったのは男子生徒で、先生はドべだった。
「え!!俺の方が早くなかった!!?」
そんな発言にグラウンドはまたもや大爆笑で、800mリレーは大盛り上がりのまま幕を閉じていった。
『只今からお昼休憩とします。午後の部開始予定時刻は…』
「あっはっはっ!!甲田先生散々だったけど面白かったね、伊緒。」
「………。」
先生の嘘つき。
「…伊緒?」
「っっあ、ごめん。えーっと、お昼行こっか。」
「…うん?」
ブー…ブー…ブー…
「っと恵那ごめん、ちょっと待って。」
ポケットに入っている携帯に手をやると、メール受信の文字が浮かび上がっていた。
メールの相手は、もちろん先生。
「…恵那、どうやら急いだほうがいいみたい。」
「あー…そういや無いと困るとか言ってたよね。」
メールに書かれていた文は、短いけれど強力なものだった。
『俺達のジャージは?』
絵文字もなければ、顔文字もない。
これはなんか怖いんだけど…早くいかなきゃ怒られそうだな。
「ご飯、教官室持ってこうか。」
「うん。」
メールを見た私達は、それから足早に教室へと向かい、途中でジュースを買ってから教官室へとダッシュした。
コンコンッ
午前の部終了後、教官室のソファーで寝転がっていると誰かがドアをノックした。
「はーいって、おぉどうした?」
「甲田先生…。」
ドアを開けると、そこにはさっきの男子生徒の姿があった。
転んだせいかティーシャツがそこらじゅう砂だらけだ。
「さっきは…ほんと、ありがとうございました。」
顔を赤くしながら俺に頭を下げるこいつが可愛くて、なんだか胸の奥がジーンとする。
きっと、俺の所にくるのめちゃくちゃ勇気いったよな。
でもきちんと伝えにきてくれて…お前めちゃくちゃ良い奴だな。
「ちょっと待ってろ。」
「え…?」
普段はこんな事しないけど、今日だけは特別に。
教官室の中に入っていき、冷蔵庫からオレンジジュースの紙パックを取り出した。
「俺こそ運んでくれてありがとなっ!!これご褒美!!」
「!!!!…でも、先生は…」
「はい終わり!!もう今回の事はこのジュースで貸し借りなしなっ。だから俺が足つった事も忘れてくれよ?」
「……ふはっ、了解っす。ごちそう様です。」
「おぅ、じゃーな!!」
それから俺に失礼しますと頭を下げてから、男子生徒は友達の所へと走っていった。
片手に俺が上げたオレンジジュースを持ち、友達と楽しそうに笑いながら歩いていった姿を見て、すごく安心した。
楽しいはずの体育祭が嫌な思い出で終わらなくてよかった。
あの笑顔なら、あいつはもう大丈夫そうだな。
「せーんせっ、大丈夫ですか?」
「うわっっ!!」
教官室に戻ろうとドアに手をかけた瞬間、頬に何か冷たいものがあてられて動きを止められた。
「傑作でしたよー、先生のこけた姿!!」
「なっ、お前ら…。」
俺の後ろに表れたのは、ジュースをもった伊緒に、ケラケラと笑う横井。
俺がさっきメールしたせいか、二人とも少し息をきらしていた。
…もしかして走ったのか?
「恵那、先に教官室入ってて。」
「え?」
「先生、ちょっといいですか?」
「お、おぉ。」
なんか伊緒のオーラが…え、怒ってんのか?
俺、怒らせるようなことでもしたっけ…。
「来てください。」
それから俺はただ伊緒に引っ張られるがままに校舎裏へと歩いていった。
お互い、一言も発しないまま。
ただひたすらついていった。
もしかして、これはマズイ状況なのかもしれない。
俺いきなりフラれるとか?
まさかそんなこと…「先生。」
「っっあ、はい?」
さっきまで黙っていた伊緒の声に驚きながらも顔を見ると、目に沢山涙を溜めながら俺を見ている姿が映った。
「伊…」
「バカ、先生のバカ!!」
突然の事で何も理解出来てない俺の胸に、伊緒がとびついてくる。
ぎゅうっと俺の背中へと回された手は震えていて、でもとても力強く俺を抱きしめてくれていた。
「優しすぎるよ…先生。」
「え?」
俺の胸で泣いている伊緒は、もしかして俺の為に泣いてくれているのだろうか。
「全部嘘ですよね?ジャージも、リレーも…。」
「伊緒?」
ジャージを握りしめている手の力が、少し強くなった気がした。
「私達が不安にならないように、わざと長袖のジャージなんか着たんですよね?じゃなかったら、こんな暑い日におかしいですし…。
それにリレーだって、先生はわざとコケた。あの子が我慢してるのが見えて…だから足をつったフリして自分に視線がくるようにした。そうですよね?」
いつからこんなに大人になったのだろう。
自分の事で泣いてばかりの伊緒が、今では俺の為に泣いてくれているだなんて。
伊緒があまりに必死にに抱きついてくれるから、何だか包み込まれている気持ちになってくる。
「はぁー…全部気づいてたのか?」
「…当たり前です。」
事実、伊緒が言った事は全て正解で誤魔化す事はできなかった。
かっこつけたつもりが、何か俺かっこわるいな…。
「嘘ついてごめんな。」
伊緒の頭に手を置いて謝ると、伊緒は頭を横へと振った。
「…嬉しかったです、本当に。先生の私達への優しさも、あの子への優しさも全部。あの時の先生の姿は一位でゴールする姿よりもかっこよくて…感動しました。」
「…っっ」
「えへへ、また一つ先生の事好きになっちゃいました。」
「……伊緒のバカ。」
俺の顔を見上げて笑う姿がめちゃくちゃ可愛いくて、俺は力強く伊緒を抱きしめ返した。
愛おしくてたまらなくて、出来ることならずっとひっついていたい。
ずっと二人で一緒にいたいな。
どんな俺でも伊緒は理解してくれて、見ていてくれる。
いつも隣にいてくれる。
そのことがまた俺を幸せにさせてくれる。
「先生?」
「ん?なに?」
「ふふ、今日は良くできましたっ!!」
…まるで母親に誉められた子供のような俺。
その一言が嬉しくて、頑張って良かったと思える。
「…伊緒、好きだよ。」
「えぇっ!!?」
「ふはっ、良い反応。」
それから少しの間だけひっついていた俺達は、その後教官室に戻り四人で昼食を食べて過ごした。
横井と並んで座っている進藤先生はどこか新鮮で、見ていて面白い。
普段は一緒に居れないぶん、今日の二人はいつもより距離が近い気がするし。
「いつかWデートしたいなぁ。」
「うふふ、そうだね。」
ましてや横井と伊緒がこんな会話するなんて思ってもいなかったからな。
本当に良かったな、この二人が上手くいってくれてさ。
まぁ、まだ付き合ってはいないんだけど。
「ちょっと甲田先生?何ニヤニヤしてるんですか?気持ち悪いですよ。」
「なっっ!!!!」
お前と横井の幸せに微笑んでいたのに、お前というやつは…!!
「あ、甲田先生どうせ伊緒の事考えてだんでしょ!!」
あれ、横井までそんなこと言うのか?
…案外この二人、性格似てるんじゃないか?
「先生…?」
横井の言葉に、伊緒までが俺の顔を真っ赤にしながら見てくる。
なんだこの状況、3対1じゃないか。
「ちょ、まてお前ら…」
「キングオブ変態ですね、甲田先生。」
待て待て待て!!!!なんだそれっっ!!!!
この作家の他の作品
表紙を見る
「ちょっと…先生待ってっ!!」
「…ん?なに……嫌?」
そう言いながら、又キスをする。
まだ答えてないのに……。
苦いコーヒーと先生の匂いが
漂うこの教官室でキスをする。
「もう一回してもいい?」
「いやいや、ここ学校!!」
はははっと笑いながら、
先生は又私にキスをする…。
\感想ノート・レビュー/
いつも励まされてます!!
僕ちみ様・すっチャン様・
遊哉様・ひか*様・狸様・
LOvE様・愛か様・
乙姫いちご様・たくくま様・
ペペロンえりか様・
あーさ5296様・しーCHAN様・
ことぎし。様・めがねチャン様・
れいな★様・みおあず様・
カズユキヨリ様・へにー様・
さてぃあ様・mehi様・
ぁぃく様・來雨様・
藤堂ありあ様・葵翼様・
りゃー♪様・スカイマリン様
感謝の気持ちでいっぱいです!
『先生と教官室2~新しい道~(完結)』
『先生と教官室3~沢山の初めて~(更新中)』
『先生と執事(完結)』
『先生と執事【続・短編】(完結)』
続編、別作品も是非読んでみて下さい!!
表紙を見る
「先生、できましたよっ!!」
「あ、伊緒。お前また敬語使っただろ。
それに名前じゃなくて先生って…」
「あ…それはー…」
私のしまったという顔に、先生は
不敵な笑みを少しずつ浮かべる。
「次言ったらおしおきって言ったよな?」
そして、その笑みは甘さと恐怖を交えて
確実に私へと襲いかかろうとする。
「ちょ、ちょっと待って先生!!変な事
したらオムライスあげませんからねっ!」
「うぐっっ……それは…」
新しく始まった、先生との関係。
甘くて、温かくて、安心して、でもたまに
苦しいことも悲しいこともあって……。
「ふふっ、食べましょうか。せーんせっ」
「……おぅ。」
それでも最高に幸せだと思える日々が今、
ゆっくりと幕を開ける―――…
表紙を見る
私のお母さんは大手会社
の社長でもある、お嬢様
私のお父さんは高校の教師
でもある、お母さんの執事
麻椿(35)×雄輝(44)
私は、そんな2人の娘
冨田 永愛(12)
あれから数年後を書いた
短編の物語です(^O^)/!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…