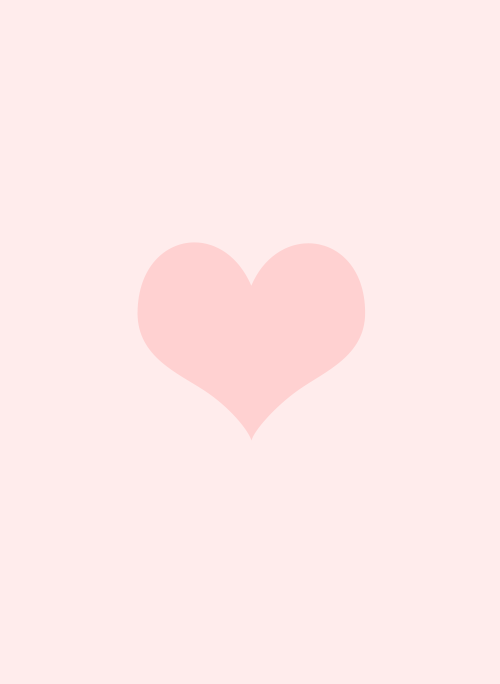付き合いたての頃とは違う感情が襲ってくる。
あの頃は抱きしめただけでも十分だったのに。
最近はやたら伊緒が足りない。
触れたくてたまらないのに、触れるのは怖い。
伊緒を壊してしまうような気がして…。
あいつはどんな気持ちで俺に触れてくるんだろうか。
今日だってそんなに嫌そうな感じではなかったし…。
俺はどこまで伊緒に近づいていいんだ?
どこまでの俺なら許してくれる?
こういう時、大人の自分を少し恨む。
もし俺が伊緒と同じくらいの年齢だったら、もっと自由に恋愛ができたんじゃないかなって。
みんなの前で手を繋ぐ事もできるだろうし、デートも堂々とできるんだよな。
好きな時に触れたいだけ触れて…。
「はぁ……」
失敗を許される年齢が懐かしい。
大人のようでまだまだ子供なあの年代。
責任も重荷もあってないようなもの。
今では考えられないあの頃がこんなに恋しいなんて、どうかしてるな…。
いつもは寝る前に伊緒にメールをするが、今日はやめておこうと思った。
きっとあいつ色々悩んでるだろうから。
今日はそっとしておくのが一番だろう。
少し開いていたカーテンから、曇った夜空がよく見えた。
明日の部活はどんな顔して行こうか。
少し引き締めないとまずいかな。
伊緒の顔見てニヤけたりでもしたらマズイだろうし。
「ふっ……」
きっとあいつも一緒の事考えてるだろうな。
そう思うと明日逢うのが楽しみになってきたかも。
真っ赤になって必死でキスマークを隠してる伊緒の姿。
やっべぇ早く見たい。
寝るはずだったのに、完璧に目が覚めてしまった俺は、ためていた仕事を手に取りリビングへと足を向けた。
春の清々しい風。
晴れた日の気持ちいい太陽。
何もかもが爽やかで気持ちいい。
ただ一つを除いては…だけど。
「帰りたい…今すぐ帰りたい。」
恵那のテンションの低さが半端ない。
確かに昨日の今日で進藤先生の顔を見るのはしんどいよね…。
でも、お互いの気持ちを知っている私にとっては少し複雑なところ。
大丈夫だよって言ってあげたいけど、進藤先生の気持ちを知らない恵那にとっては気休めにしかならないだろうし…。
「とりあえず教室いこ?進藤先生の顔見ないようにすれば何とかなるよ。」
「うん…頑張る…。」
早く両想いって気づいてくれればいいんだけど…。
そしたら毎日が楽しくて教室に行くのも嬉しくなるはずなのに。
「今日は時間割り変更があるので、前に書いときますから皆さん気をつけて下さい。では以上で終わります。」
朝のチャイムがなってから、たった10分で終わってしまう進藤先生の話し。
本当に無駄がないというか何というか…。
「あ、それと…片瀬さんと横井さんは放課後に教官室へ日誌持ってきて下さい。」
…は?
「なんで私と恵那…?」
日誌って今まで活用されてたの?
絶対何も書かれてないただの紙だよね…?
しかもそれを体育委員でもない私達が持ってくの?
とてつもない不信感から進藤先生を見ると、少し眉を下げて寂しそうな顔をしていた。
あぁそうゆうことか、とその時確信した。
進藤先生の視線の先にいるのは、うつむいたままの恵那の姿。
きっと、進藤先生は恵那と話すために私達を呼び出したんだね。
「恵那、日誌書かない?」
「え?でも今まで書いたことないじゃん…。」
「うん知ってる。でも、だからだよ。」
今まで書いたことのないのは私達だけじゃない。
みんなが書いたことのないこの日誌。
それは誰からも興味をもたれない。
だから書こうと提案したんだ。
「今の恵那の気持ち書きなよ。声に出すより字で表した方が思ってる事きちんと伝えれるよ。」
「伊緒……。」
「もし昨日と同じ事を進藤先生が恵那にしたら、私が殴りに行く。だから、もう一回頑張ってみよ?」
お願い諦めないで。
まだ答えはでてないんだよ。
握りしめていた日誌を、恵那はゆっくりと受け取ってくれた。
「伊緒が味方なら大丈夫だね!!」
そう言って笑った恵那は、日誌とにらめっこを始めた。
頑張れ、恵那。
応援してるからね!!
真剣に日誌に気持ちを書く恵那の姿を見ていると、嬉しくもなるし不安にもなる。
もしうまくいかなかったら…って。
好きとか嫌いじゃなくて、教師だからとか大人だからっていう立場の問題が邪魔するんじゃないかなって思ってしまう。
本当はありえない立場同士の恋だもん。
うまくいくほうが奇跡に近い。
「よし、書けた!!」
「……じゃあ放課後行こっか。」
「うん、頑張るよ。」
何だか、少し不安になってきてしまった…。
先生と私は運が良かったんだよね。
出逢った場所もタイミングも。
たまたま運が良かったから両思いになれたんだ。
感謝しなければいけない事なんだよね。
先生が先生でいてくれた事や、この学校を進めてくれた周りの人達に…。
「失礼します…進藤先生、日誌持ってきました。」
放課後、進藤先生に言われた通りに教官室に来た私達。
少し控えめな恵那の挨拶で部屋の中へと入った私達を迎えたのは、いつもの二人だった。
「二人とも有り難うございます。」
そう言って歩み寄ってきた進藤先生は、さっきと変わらず悲しい顔をしていた。
そして、恵那は今日一度も進藤先生の顔をみようとしない。
「横井さん、少し話しませんか?」
「………はい。」
恵那の緊張が全身から伝わってくる。
さっきまで日誌を握りしめていた手は、今はスカートの裾を握りしめていた。
「いってらっしゃい、恵那。」
「うん、ありがと…」
小声で励ました私に、恵那は笑顔を見せてくれた。
この作家の他の作品
表紙を見る
「ちょっと…先生待ってっ!!」
「…ん?なに……嫌?」
そう言いながら、又キスをする。
まだ答えてないのに……。
苦いコーヒーと先生の匂いが
漂うこの教官室でキスをする。
「もう一回してもいい?」
「いやいや、ここ学校!!」
はははっと笑いながら、
先生は又私にキスをする…。
\感想ノート・レビュー/
いつも励まされてます!!
僕ちみ様・すっチャン様・
遊哉様・ひか*様・狸様・
LOvE様・愛か様・
乙姫いちご様・たくくま様・
ペペロンえりか様・
あーさ5296様・しーCHAN様・
ことぎし。様・めがねチャン様・
れいな★様・みおあず様・
カズユキヨリ様・へにー様・
さてぃあ様・mehi様・
ぁぃく様・來雨様・
藤堂ありあ様・葵翼様・
りゃー♪様・スカイマリン様
感謝の気持ちでいっぱいです!
『先生と教官室2~新しい道~(完結)』
『先生と教官室3~沢山の初めて~(更新中)』
『先生と執事(完結)』
『先生と執事【続・短編】(完結)』
続編、別作品も是非読んでみて下さい!!
表紙を見る
「先生、できましたよっ!!」
「あ、伊緒。お前また敬語使っただろ。
それに名前じゃなくて先生って…」
「あ…それはー…」
私のしまったという顔に、先生は
不敵な笑みを少しずつ浮かべる。
「次言ったらおしおきって言ったよな?」
そして、その笑みは甘さと恐怖を交えて
確実に私へと襲いかかろうとする。
「ちょ、ちょっと待って先生!!変な事
したらオムライスあげませんからねっ!」
「うぐっっ……それは…」
新しく始まった、先生との関係。
甘くて、温かくて、安心して、でもたまに
苦しいことも悲しいこともあって……。
「ふふっ、食べましょうか。せーんせっ」
「……おぅ。」
それでも最高に幸せだと思える日々が今、
ゆっくりと幕を開ける―――…
表紙を見る
私のお母さんは大手会社
の社長でもある、お嬢様
私のお父さんは高校の教師
でもある、お母さんの執事
麻椿(35)×雄輝(44)
私は、そんな2人の娘
冨田 永愛(12)
あれから数年後を書いた
短編の物語です(^O^)/!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…