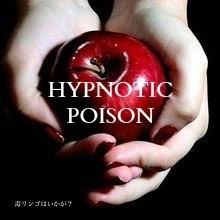「とにかく、俺はお前がやったとは思わん。お前の毛髪が落ちていたのは真犯人の企みだろう。お前をはめるために」
俺を……?
周は鉄格子を掴むと、俺をじっと見つめてきた。
熱い視線だった。
この前言い合いをしたときの温度のない視線じゃない。
俺の知ってる―――まっすぐで熱い視線。
「ヒロ。待ってろ。俺が必ずお前の無実を証明してみせる。俺がお前を助けてやる」
「周―――……」
俺は鉄格子を握っていた周の手にそっと自分の手を重ねた。
「言ったろ?俺はお前を生涯守りぬくと」
周の手が俺の手をしっかりと握り返してくる。
視線と同じだけ熱い温度で、そこから周の爽やかでどこか甘さを含んだ香りが漂ってきた。
いつになく真剣に見つめられて、俺はその視線をしっかりと受け止めるよう目を開いた。
「ヒロ」
周の顔が近づいてきて、鉄格子のすぐ向こう側にあった。周の香りが一段と近くに感じて、それだけで胸が熱くなる。
「周……」俺も周の手を握ったまま、顔を近づける。
鉄格子を隔てて、俺たちは口付けを交わした。
「ヒロ。愛してる。だから待ってろ」
唇を通して、周の気持ちが流れ込んできた。