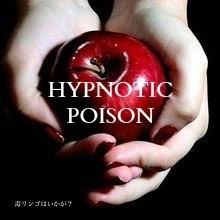どうしてこんなときに気付いてしまったんだろう。
いや、俺はきっと認めることが怖かったんだ。
平凡な日常を望んでいて、それこそが唯一の道であると信じていた俺は―――
周の世界に踏み出すことを怖がって―――目を逸らしていた。
だけど周はいつだって真正面から俺を受け止めてくれた。
平凡で何の撮り得もない俺を―――
あいつは
受け入れてくれた―――
自分の信念を曲げずに信じた道にひたすらまっすぐ進み続けるあいつ。
それがどんなに間違っていようと、倫理に反していようと、神の道徳に反していようと―――
あいつはいつでも進み続ける。
終点のない円の線のように。
俺はそんなアイツの生き方が眩しくて―――羨ましくて、かっこよくて
とてつもなく憧れた。