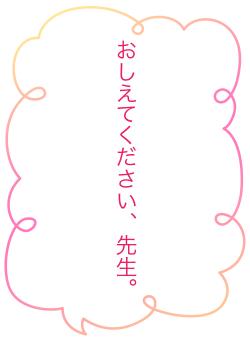ドドドドド……と、心臓が急速に音を立て始めた。さっきまで不気味なくらい冷静だったのに、突然スイッチが押されたかのようだった。
「ちち、おや……」
言われたことをそのまま呟く。
予想の範囲内だったにもかかわらず、その事実を受け入れることに時間がかかった。
「そう、ですか……」
そう言葉を紡ぐことで精一杯だった。
「マリー、髪を……染めているのかい?目は……カラコン?」
「髪は、スプレーで……洗えば、取れます」
「そうか」
カイヴァントさんは、切なげに、でも嬉しそうに言った。
あたしにとっては忌々しいこの色も、カイヴァントさんにとっては違うのかもしれない。
「カイヴァントさん、あの……」
「ヘンリーと、せめてそう呼んでくれないか」
カイヴァントさんは目を伏せて、そう言った。
「で、では……ヘンリー、さん」
あたしの記憶に、父親は陰も形もない。
きっと、あたしが物心つくよりも前に別れたんだろう。
“あんたのせいで”と母親はさんざん言っていたけど、幼いあたしに何の責任があったって言うんだろう。