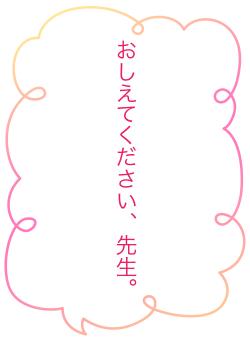名刺は画家らしく、シンプルだが綺麗な色彩の水彩画のようなデザインだ。
ヘンリック・カイヴァントの文字と連絡先が印刷されている。そして、空白にはどう見ても手書きの携帯電話番号が書かれていた。
「水川、真梨です」
「志摩蓮斗といいます」
名刺も持っていない一介の高校生であるあたしたちは、形にせずそう名乗る。
「蓮斗くん、だね。それから……」
カイヴァントさんはそう言って、蓮を見てからあたしの方へ目を向けた。
淡い空色の瞳と目が合う。あたしと同じ色。ただし、あたしは今カラコンをつけていて黒色だけど。
「マリーと、呼んでも良いかな」
「え……?」
そんな呼ばれ方、したことがなかった。つい、口からは戸惑いの音が漏れる。
「昔、私は君のことをそう呼んでいた」
カイヴァントさんがそう言った瞬間、部屋の空気が震えた気がした。
蓮があたしの手をぎゅっと握ってくれて、実際に震えているのは自分自身だと気がついた。
「もう、察しているかもしれないが……私は、マリーの実の父親だ」