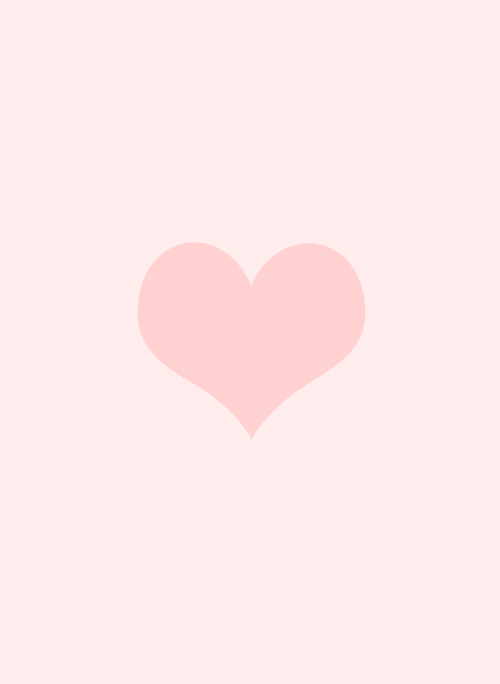この作家の他の作品
表紙を見る
「ちょっと…先生待ってっ!!」
「…ん?なに……嫌?」
そう言いながら、又キスをする。
まだ答えてないのに……。
苦いコーヒーと先生の匂いが
漂うこの教官室でキスをする。
「もう一回してもいい?」
「いやいや、ここ学校!!」
はははっと笑いながら、
先生は又私にキスをする…。
\感想ノート・レビュー/
いつも励まされてます!!
僕ちみ様・すっチャン様・
遊哉様・ひか*様・狸様・
LOvE様・愛か様・
乙姫いちご様・たくくま様・
ペペロンえりか様・
あーさ5296様・しーCHAN様・
ことぎし。様・めがねチャン様・
れいな★様・みおあず様・
カズユキヨリ様・へにー様・
さてぃあ様・mehi様・
ぁぃく様・來雨様・
藤堂ありあ様・葵翼様・
りゃー♪様・スカイマリン様
感謝の気持ちでいっぱいです!
『先生と教官室2~新しい道~(完結)』
『先生と教官室3~沢山の初めて~(更新中)』
『先生と執事(完結)』
『先生と執事【続・短編】(完結)』
続編、別作品も是非読んでみて下さい!!
表紙を見る
「先生、できましたよっ!!」
「あ、伊緒。お前また敬語使っただろ。
それに名前じゃなくて先生って…」
「あ…それはー…」
私のしまったという顔に、先生は
不敵な笑みを少しずつ浮かべる。
「次言ったらおしおきって言ったよな?」
そして、その笑みは甘さと恐怖を交えて
確実に私へと襲いかかろうとする。
「ちょ、ちょっと待って先生!!変な事
したらオムライスあげませんからねっ!」
「うぐっっ……それは…」
新しく始まった、先生との関係。
甘くて、温かくて、安心して、でもたまに
苦しいことも悲しいこともあって……。
「ふふっ、食べましょうか。せーんせっ」
「……おぅ。」
それでも最高に幸せだと思える日々が今、
ゆっくりと幕を開ける―――…
表紙を見る
「んっ…やっぱり無理…苦い。」
「じゃぁ俺が飲ませてやる。」
「えっっ!!ちょっ先生!!」
「バカ、大人しくしろ。」
「ーっっ!!!!!!」
そう言って私を抱きしめてくる
先生の身体からコーヒーの匂い
がして思わずキュンッとする。
「せ…んせ…。」
「……なんだ?」
そして、抱きしめられた後の
キスからはフワリとコーヒー
の苦味がして、いつも私を
大人の気分にさせてしまう。
もう何度私と先生はこの教官室で
抱きしめあいキスをしたのだろう。
この、大好きな教官室で
大好きな私だけの先生と……
『先生と教官室』の続編です。
『先生と教官室3~沢山の初めて~』
『先生と執事』
こちらも宜しくお願い致します!!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
この作品をシェア
先生と執事
を読み込んでいます