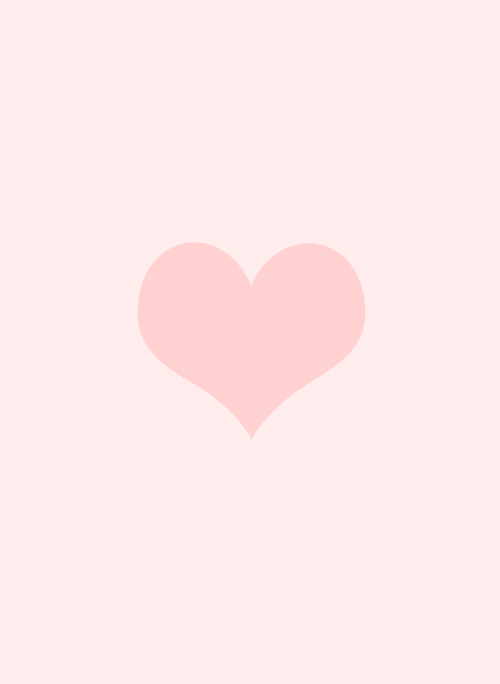黒い声をだしたかのように思われる先生は、強く抱きしめている手の力をゆっくりと緩めていく。
そして、私の顔を覗き込んでニヤッと笑った。
「…お嬢様、私にかなうとお思いですか?」
「!!!!!!?」
あ、あれ!!?
今まで先生モードだったのに!!
なんでいきなり執事モードになってんの!!?
「私はあなたより何歳も年上なんですよ?」
「…あ、はい。知ってます。」
「大人の知識は豊富なほうだと思いますが…どうしましょうか。」
えっと…私は何をどうしたらよいのでしょうか。
大人の知識って…なんですか?
何事ですか?
え、先生何をしようとしてるんですか?
「大人の知識…とは?」
そう言いながら、覗き込む先生の顔から少しそらす。
近すぎて先生の顔を直視できない。
恥ずかしすぎるし、執事の時の先生のオーラはさっきとまでとは違いすぎて正直戸惑う。
「では…実践してみましょうか?」
じ…っせん?
今、実践とおっしゃりました?
それは何かとまずい気が……!!!
「ちょ、先生まっ…!!」
グイッ
「お嬢様、私は待つのが嫌いな性分なんです。ですから…もう待ちません。」
「なっ!!せ…っっ!!!」
後頭部を力強く引き寄せ、先生は私の唇に自分のを重ねた。
「ん…っっせ…!!」
何度も繰り返される激しさに、身体がとけそうになる。
唇…熱い。
後頭部に回された力強い手も、抱き締める手も。
全てが熱い…。
「…麻椿。」
「ん…。」
キスの合間から聞こえる先生の声は、やたらと私をドキドキさせた。
実践って…なんて激しい。
「はい、ここまで…です。」
唇を離した先生は、ポンッと私の肩を押して身体を離す。
激しかったキスに息をあげながらも先生を見ると、先生の息もあがっているように見えた。
それに、顔なんか真っ赤…。
「ん?」
むむむ…これは、もしかして…。
下を向いたまま動かない先生の顔に手をあてると、私の体温よりはるかに高い温度を感じた。
「ちょっと先生!!熱が…っ!!」
そうだった。
あんな余裕そうな顔してたけど、先生は酷い熱を出してたんだ…。
「お嬢…さま…。」
「え?あ、先生!?」
そのまま、先生は上を向く事がないまま私の方へと倒れてしまった。
「ふぅ…これでよし。」
薄い水色のフカフカのベッド。
とても優しい匂いがするアロマ。
そして、薄暗い部屋。
きっと寝るのに最適な環境だろう。
「…上田、手伝ってくれてありがとう。」
「いえ、私の方こそ手伝わせてしまって…。」
申し訳なさそうに私を見る上田が、何故か笑っているようにも見えた。
「…お嬢様、雄輝と仲直りできたのですね。」
「え…あ、えぇ。」
仲直りってのとはまた違う感じがするけどね。
「じゃあこれからも雄輝が執事で宜しいですか…?」
「…………。」
「お嬢様?」
「上田、あなたにお願いがあるの。」
これからの私と先生の人生をかけた、大切なお願いが……。
「あのね……。」
―――――――………
「…本当によろしいのですか?」
「えぇ、これが一番いいのよ。」
「そうですか…では、かしこまりました。」
「ありがとう…。」
それから、私にお辞儀をした上田を見送り、そのままベッドへと足を向けた。
寝たいわけじゃない。
ただ近くに居たいだけ。
執事であり、先生である私の大切な人のもとに。
「せんせ…。」
「んっ…うぅ…」
苦しそう。
熱のせいで身体が熱いのか、先生は布団を脱ぎたがる。
そして私はそれを見ては直すの繰り返し。
これ以上酷くなられたらどうしていいか解らないから…。
だから、今私ができる全てを先生にやってあげるんだ。
「ごめんね…先生。」
眠っている先生の頭をそっと撫でる。
サラサラの髪に長いまつげ、火照った頬がよくあっている。
きっと、熱なんて出ていなかったら綺麗な寝顔なのだろう。
今の寝顔はあまりに苦しそうで綺麗なんて言ってられない。
綺麗よりも心配がうわまってしまうから。
「ん……っっ」
「えっ、先生?どしたの?苦しい?」
「っはぁ…はぁ…」
私が頭を撫でていると、先生は突然声をあげながら苦しみだした。
どうしよう…私どうしたら…。
眠っている先生の頭をそっと撫でる。
サラサラの髪に長いまつげ、火照った頬がよくあっている。
きっと、熱なんて出ていなかったら綺麗な寝顔なのだろう。
今の寝顔はあまりに苦しそうで綺麗なんて言ってられない。
綺麗よりも心配がうわまってしまうから。
「ん……っっ」
「えっ、先生?どしたの?苦しい?」
「っはぁ…はぁ…」
私が頭を撫でていると、先生は突然声をあげながら苦しみだした。
どうしよう…私どうしたら…。
ガタッ
「あ……。」
そうだ、薬…。
さっき上田が起きたら飲ませて欲しいと置いていった解熱剤が私の視界に入った。
これのんだら…楽にはなるかな?
「……できるかな。」
置かれていたコップと薬に手を伸ばし、ゆっくりと薬を口の中へ。
そして、当たり前のように水を飲む。
というより、水を口の中へと含んだ。
よし、準備万端……。
先生の顔の横に手を置き顔を近づける。
そして、そのまま唇を重ねて薬を飲ませてみる。
けど、初めてだから上手くいくはずもなく…。
「…ふんっっ?!!!」
なんと、苦戦してる最中に先生が起きてしまったではないか。
そして次の瞬間、ゴクン…という音と共に先生の目も見開いていった。
まぁ不幸中の幸いといいますか…無事薬は飲んでくれたよ。
「お嬢様…?もしかして…。」
この作家の他の作品
表紙を見る
「ちょっと…先生待ってっ!!」
「…ん?なに……嫌?」
そう言いながら、又キスをする。
まだ答えてないのに……。
苦いコーヒーと先生の匂いが
漂うこの教官室でキスをする。
「もう一回してもいい?」
「いやいや、ここ学校!!」
はははっと笑いながら、
先生は又私にキスをする…。
\感想ノート・レビュー/
いつも励まされてます!!
僕ちみ様・すっチャン様・
遊哉様・ひか*様・狸様・
LOvE様・愛か様・
乙姫いちご様・たくくま様・
ペペロンえりか様・
あーさ5296様・しーCHAN様・
ことぎし。様・めがねチャン様・
れいな★様・みおあず様・
カズユキヨリ様・へにー様・
さてぃあ様・mehi様・
ぁぃく様・來雨様・
藤堂ありあ様・葵翼様・
りゃー♪様・スカイマリン様
感謝の気持ちでいっぱいです!
『先生と教官室2~新しい道~(完結)』
『先生と教官室3~沢山の初めて~(更新中)』
『先生と執事(完結)』
『先生と執事【続・短編】(完結)』
続編、別作品も是非読んでみて下さい!!
表紙を見る
「先生、できましたよっ!!」
「あ、伊緒。お前また敬語使っただろ。
それに名前じゃなくて先生って…」
「あ…それはー…」
私のしまったという顔に、先生は
不敵な笑みを少しずつ浮かべる。
「次言ったらおしおきって言ったよな?」
そして、その笑みは甘さと恐怖を交えて
確実に私へと襲いかかろうとする。
「ちょ、ちょっと待って先生!!変な事
したらオムライスあげませんからねっ!」
「うぐっっ……それは…」
新しく始まった、先生との関係。
甘くて、温かくて、安心して、でもたまに
苦しいことも悲しいこともあって……。
「ふふっ、食べましょうか。せーんせっ」
「……おぅ。」
それでも最高に幸せだと思える日々が今、
ゆっくりと幕を開ける―――…
表紙を見る
「んっ…やっぱり無理…苦い。」
「じゃぁ俺が飲ませてやる。」
「えっっ!!ちょっ先生!!」
「バカ、大人しくしろ。」
「ーっっ!!!!!!」
そう言って私を抱きしめてくる
先生の身体からコーヒーの匂い
がして思わずキュンッとする。
「せ…んせ…。」
「……なんだ?」
そして、抱きしめられた後の
キスからはフワリとコーヒー
の苦味がして、いつも私を
大人の気分にさせてしまう。
もう何度私と先生はこの教官室で
抱きしめあいキスをしたのだろう。
この、大好きな教官室で
大好きな私だけの先生と……
『先生と教官室』の続編です。
『先生と教官室3~沢山の初めて~』
『先生と執事』
こちらも宜しくお願い致します!!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…