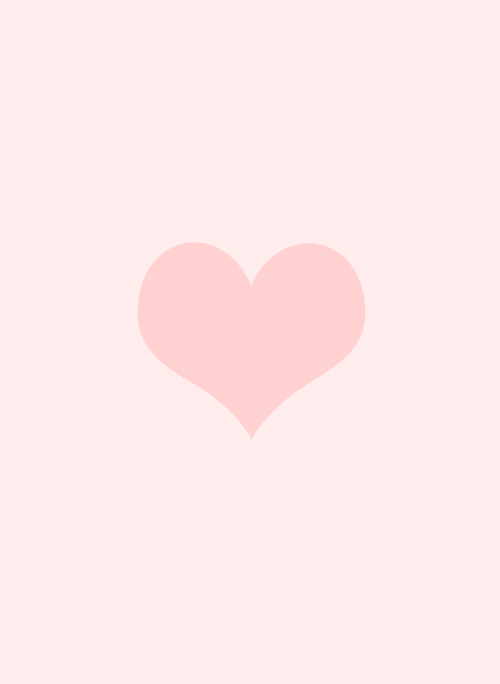―――――――――……
ガチャ
「ただい…」
「お帰りなさいませ。」
「……何をやってるんですか?」
「見ての通りお迎えですが?」
「っそうじゃなくてっ!!」
やっとの思いでついた家の扉を開けると、そこにはいつものように笑顔の先生が立っていた。
「どうなされました?早くお部屋に入りませんと身体が冷えますよ。」
…意味が解らない。
先生の言葉も行動も何もかも。
授業にでれなくなるほど辛いんでしょ?
本当は酷い熱なんでしょ?
何でそんな辛い状況でも無理に笑って私の面倒をみようとするのよ…。
「弱みをみせないのはどっち…?」
「え?」
持っていた鞄を力強く握りしめる。
「先生、風邪ひいてるんでしょ?辛いんでしょ?だったら正直に言えばいいじゃないですか。」
「………。」
「私には弱みを見せろとか言うのに自分は隠すんですか?そんなのおかしいじゃないですか!!!」
笑っていた先生の顔は、私の言葉を聞いていくにつれてどんどん消えていった。
そして、今までこんなに怒った姿を家のものに見せた事がない為か、仕事をしていたメイド達が足を止めて私達を見つめた。
「…お嬢様。」
笑顔が消えた先生は、静かに私のもとへと歩みを寄せてきた。
その声に反応してメイド達は再び仕事を始める。
「私はあなた様の執事という存在です。」
「…だから何ですか?」
「私はあなた様のお世話をするのが仕事なんです。私情を挟む事はできません。ですので、私の事は気にせず普段通りお過ごし下さいませ…。」
……何をいいだすかと思ったら…仕事?気にするな?
何なのよそれ…。
「それは上田からの教えなの?」
「いえ、そうゆうわけでは…。」
とゆう事は先生の考えなんだ…。
握っていた鞄から手を離し、脱力していく。
「…もういいです。」
「え?お嬢様?」
「冨田さん。」
「…なんでしょうか。」
近づいてきてた先生に、私からもう一歩だけ近づくと、とても近い距離だった。
驚いてる先生の顔を下から見上げるというのはまた新鮮だ。
さっきと顔色一つ、声のトーンすら変えずに、私は先生へ残酷な一言を言い放った。
「あなたをクビにします。」
「………今なんと?」
「冨田さん、今までありがとうございました。
あなたの仕事は今日で終わりです。」
聞こえるか聞こえないかの声でそう呟き、私は部屋へと逃げるように走り出した。
先生の返事を聞かなかったのは、何て言われるか怖かったから。
その場にいる事すら、今の私にはできなかった。
ガチャッ、ガタガタ…
「もぉやだ……。」
鍵を閉めた扉の前にずるずると座り込んだ瞬間、一気に涙が頬を伝う。
そんな、まるで子供みたいに泣きじゃくる自分の姿に絶望を覚えながらも、止める事ができない。
泣かないと決めたのに、涙はあわないはずなのに…。
流れる涙の冷たさが身体を冷やしていく感じがする。
「…ひっく…っっ。」
自分がどうしたいのか、どうされたいのか。
この感情も、何とも言えない孤独感も…何もかも解らない。
どうしてしまったのだろうか…。
止まる事をしらない涙を拭うと、制服の袖がベタベタになっていた。
これは私なんだろうか…。
こんなに泣くなんて…私はいつからこんなに弱くなってしまった?
コンコンッ
「!!!?」
もたれていた扉から響いてくるノックの音に、思わず身体が反応してしまう。
いったい誰だろうか。
もしかして…先生?
確かに、いきなりクビと言われても納得できないだろう。
…でも、今は冷静に対応できる自信は無いに等しい。
「お嬢様、少しよろしいですか?」
「!!!…上田??」
「はい、そうでございます。開けていただけますか?」
「ちょ、ちょっと待って。今開けるから。」
頬につたっている涙を全て拭い、鍵と扉を開けた。
「…どうしたの?」
「ちょっと用事がありましてね、どうでしょうか私とティータイムというのも。たまには新鮮でいいんじゃありませんか?」
いきなりの訪問に驚いている私を無視して話し始める上田に更に驚きが隠せない。
でも、持っているティータイムセットを指差し、いたずらっぽく笑う上田からは安心感が漂ってくる。
昔からこの人からは何ともいえないものを感じるんだよなぁ。
「お嬢様?お嫌ですか?」
「あ…えっと…。」
そういえば初めてだ…上田とティータイムなんて。
今まで一人で飲むのが当たり前だと思ってたし。
新鮮か…そう言われればそうかもしれない。
「…そうね。お願いしようかしら。」
「かしこまりました。失礼いたします。」
久しぶりだ。
上田と一緒の空間にいるのは…。
なんだか懐かしいな、この感じ。
カチャ
「どうぞ。」
いれられた紅茶からとても良い匂いがする。
この香りは…。
「アップルティーでございます。」
「アップルティー…。」
これまた懐かしいな。
最近はストレートが多かったし。
「そういえば、初めてお飲みになったのもアップルティーでしたね。」
「えっ、そうなの!?」
「はい、そうですよ。」
アップルティーが特別好きな訳じゃないんだけど……そうだったんだ。
何か、上田に少し敗北感。
「あなたは私より私の事を知ってるのね。」
「それはそうでございます。
なんといっても、あなた様がお産まれになってからずっとお仕えしてきたのですから。」
「…………。」
お仕えしてきたか…。
その言葉は今の私には少し残酷かもしれない。
いつか先生にもそう言われる日が来るんだと思うと、胸が締め付けられるようになるんだ。
「上田。」
飲んでいた紅茶を一度置き、ソファにもたれる。
すると、少しだけ眠気を感じた。
「どうなされました?」
私の眠そうな表情を見てか、上田も紅茶を置き、こちらをじっと見てきた。
「私は…いつからこうなってしまったのかな。」
「……え?」
「なんで…なんで私はこんなに弱いんだろう…。」
もたれていた身体をズルズルと倒していき、ソファの上に寝転がる。
眠いからかな、どんどん弱音がでてきてしまう…。
上田の驚いた顔を見ると言ってはいけないとは思うんだけどね……。
この作家の他の作品
表紙を見る
「ちょっと…先生待ってっ!!」
「…ん?なに……嫌?」
そう言いながら、又キスをする。
まだ答えてないのに……。
苦いコーヒーと先生の匂いが
漂うこの教官室でキスをする。
「もう一回してもいい?」
「いやいや、ここ学校!!」
はははっと笑いながら、
先生は又私にキスをする…。
\感想ノート・レビュー/
いつも励まされてます!!
僕ちみ様・すっチャン様・
遊哉様・ひか*様・狸様・
LOvE様・愛か様・
乙姫いちご様・たくくま様・
ペペロンえりか様・
あーさ5296様・しーCHAN様・
ことぎし。様・めがねチャン様・
れいな★様・みおあず様・
カズユキヨリ様・へにー様・
さてぃあ様・mehi様・
ぁぃく様・來雨様・
藤堂ありあ様・葵翼様・
りゃー♪様・スカイマリン様
感謝の気持ちでいっぱいです!
『先生と教官室2~新しい道~(完結)』
『先生と教官室3~沢山の初めて~(更新中)』
『先生と執事(完結)』
『先生と執事【続・短編】(完結)』
続編、別作品も是非読んでみて下さい!!
表紙を見る
「先生、できましたよっ!!」
「あ、伊緒。お前また敬語使っただろ。
それに名前じゃなくて先生って…」
「あ…それはー…」
私のしまったという顔に、先生は
不敵な笑みを少しずつ浮かべる。
「次言ったらおしおきって言ったよな?」
そして、その笑みは甘さと恐怖を交えて
確実に私へと襲いかかろうとする。
「ちょ、ちょっと待って先生!!変な事
したらオムライスあげませんからねっ!」
「うぐっっ……それは…」
新しく始まった、先生との関係。
甘くて、温かくて、安心して、でもたまに
苦しいことも悲しいこともあって……。
「ふふっ、食べましょうか。せーんせっ」
「……おぅ。」
それでも最高に幸せだと思える日々が今、
ゆっくりと幕を開ける―――…
表紙を見る
「んっ…やっぱり無理…苦い。」
「じゃぁ俺が飲ませてやる。」
「えっっ!!ちょっ先生!!」
「バカ、大人しくしろ。」
「ーっっ!!!!!!」
そう言って私を抱きしめてくる
先生の身体からコーヒーの匂い
がして思わずキュンッとする。
「せ…んせ…。」
「……なんだ?」
そして、抱きしめられた後の
キスからはフワリとコーヒー
の苦味がして、いつも私を
大人の気分にさせてしまう。
もう何度私と先生はこの教官室で
抱きしめあいキスをしたのだろう。
この、大好きな教官室で
大好きな私だけの先生と……
『先生と教官室』の続編です。
『先生と教官室3~沢山の初めて~』
『先生と執事』
こちらも宜しくお願い致します!!
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…