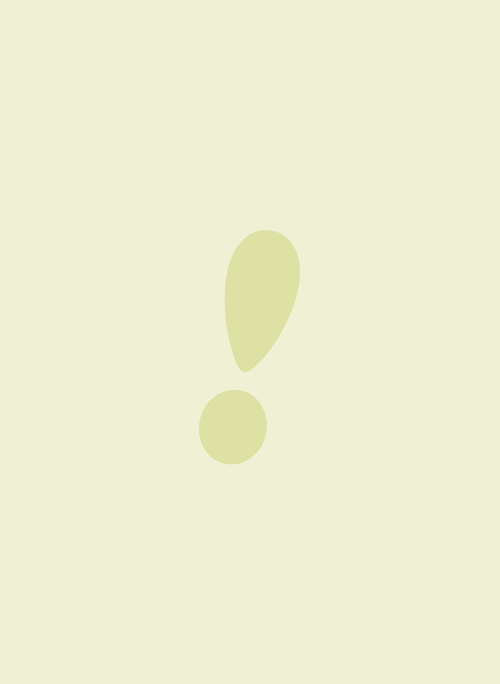空気の乾燥した都会の街中。
夜中の3時。
片側二車線の道路でブレーキ音とその後に鈍い音が響く。
ドンッ、と。
それから響く悲鳴。
慌しく集まる人の波。
携帯で電話する人。
わたしの目の前で彼は車にひかれてしまった。
ただわたしは立ち止まり、そのまま立ち尽くしていた。
3日間、慌しく終わった。
環境の変化がめまぐるしい。
わたしの恋人であった白木潤一はわたしの目の前で26歳の若さで亡くなった。
「璃那ちゃん、大丈夫??」
自分の方が大丈夫じゃないんじゃない??って聞きたいくらい目を腫らした潤一のお母さんが葬儀の後にわたしに話しかけてきた。
「はい…。おばさんは大丈夫ですか??」
「うん…どうにか。本当に潤一…いなくなったのね。」
そんなこと百も承知だよ。
わたしだって信じたくはないけど…。
「おばさん、たまにまた遊びに行ってもいいですか??」
「もちろんよ。遊びに来て。潤一も喜ぶし。」
潤一も喜ぶ…か。
死後に喜ぶって感情、あるんだろうか。
つーかわたし、いつになく冷静だな…。
「はい、それでは失礼します。」
深く頭を下げてわたしは葬儀場を去った。
まだ実感がわかない。
ただ現実にはわたしの携帯にあの日以来、潤一から連絡が来ることはない。
当たり前なんだろうけどおかしいんだ。
いつものように
<今から行っていい??>
とかメールが来る気しかしなくって。
潤一…どうして潤一が…。
飲酒運転だった。
潤一をはねた男は。
しかも18歳の免許取り立ての未成年。
スピードが出てたせいでほぼ即死だったらしい。
恨んでも恨みきれない。
道の反対にいた飲み会帰りのわたしを連れに来てくれてた時だった。
歩き始めてたわたしは駆け寄ることが出来ず、立ち尽くした。
人が集まり始めてようやく近づき、それが本当に潤一だと実感した。
洋一の体からはすごい量の血が流れてて、発狂して叫ぶわたしを知らない人が止めた。
24歳にして恋人と死別。
しかも目の前で。
普通に体験する人、あんまりいないよね??
でもそれが何でわたしに体験させるんだろう。
最初のうちは流れてたニュース。
でも3日ともたてばまた新しい事件や事故が起き、人々は忘れていく。
悔しい。
どうして潤一を選んだんだろう。
わたしがあの場所にいなければ、潤一だって行かなければよかったのに…。
いい人に限って早く逝ってしまうってよく聞くけど、本当だな。
「璃那、大丈夫??」
家に帰るとアパートの下の車の中から出てきた4人。
友達が数人待っててくれた。
仲良しだった愛と雪子と拓也と尚樹。
みんな喪服姿で葬儀帰り。
潤一とは大学のサークルが同じだったことからみんなも葬儀に出てくれてた。
部屋に入れ、アルバムをみんなで広げた。
「潤一、まじこの顔変!!」
夏のキャンプのときの写真でスイカを食べながらカメラ目線の潤一を指差して笑った。
「潤一くん、ホントおもしろい人だったよね。」
「バカっ、そんな言い方するなよ!!」
「あ…──っ。」
過去の人って言い方のこと??
わたしだってもう受け入れてるからいいのに…。
気をつかわせてるなって思った。
「大丈夫だよ…。」
そう言って笑い、次のページを開いた。
そこにはわたしと潤一の2ショット。
そういえば今から2年半前の22歳の夏くらいに付き合い出したっけ。
この写真、付き合った日の。
照れて写る2人の姿。
周りに冷やかされたから。
「やめろって、まじそういうの。ガキどもが。」
「ほんとやめてください…。」
そう言いながらも写った写真。
「璃那…。」
涙がやっぱり流れてしまってた。
そんなわたしを抱きしめる愛と雪子。
すすり泣く声が2DKのわたしの部屋に響いた。
しばらく4人はいてくれて、夜の8時過ぎくらいに帰って行った。
「璃那、俺明日も来るから。」
そう言う拓也。
拓也は高校から一緒の仲のいい友だち。
「ん。無理はしないでいいからね?」
「無理してまで来るわけねーじゃん。」
アハハと笑い飛ばしながら言う拓也。
やっぱり気つかってくれてる。
嬉しいけどやっぱり申し訳ないや。
送った後に部屋に戻ると見たままで片付けてないアルバム。
また開いた。
2人っきりでクリスマスパーティーしたときの写真、ディズニーランドに行ったときの写真、USJに行ったときの写真、スノボに行ったときの写真。
全部笑ってる。
「潤一…。」
心にクギが刺さってるよう。
痛い…。
会いたい…。
このクギ、抜いて。
そう思ったときだった。
「よっ。」
アルバムの上に……潤一があぐらをかいて手を挙げ、突然現れた。
「じ、潤一!?え…──」
「なーに泣いてんだよ、このバカ。」
そう言うと横に座りわたしをギュッと抱きしめた。
震える手で潤一を触る。
いつもの…潤一。
体温だって…。
そして自分のほっぺをつねる。
「いた…──っ」
「何やってんだよ。つーかお前まだ信じてねーの??」
信じられるわけがない。
だって…さっきまで葬儀があってて、みんなで泣いてて…
「ま、そのうち慣れるだろ。」
あっけらかんと言う潤一。
いやいや──…。
「どうして?だって…潤一は…」
するとちょっと離れてわたしの頬を触りながら
「うん、死んだよ。でもまぁ、戻ってきたんだわ。アハハ。多分っつーか絶対お前しか触れねーし、俺と話せねーんだけどな。ってことでよろしく。」
そして潤一の唇がわたしの唇に触れた。
暖かい。
前と同じやわらかい唇。
ホントに死んだんだよね?
死んだって今言ったし、そうだよね?
意味がわか…──
バタッ。
「おい、璃那!!」
そう叫ぶ潤一の声も聞こえるわけがなく、睡眠不足、栄養不足も加勢して驚きすぎでわたしは倒れた。